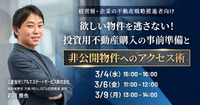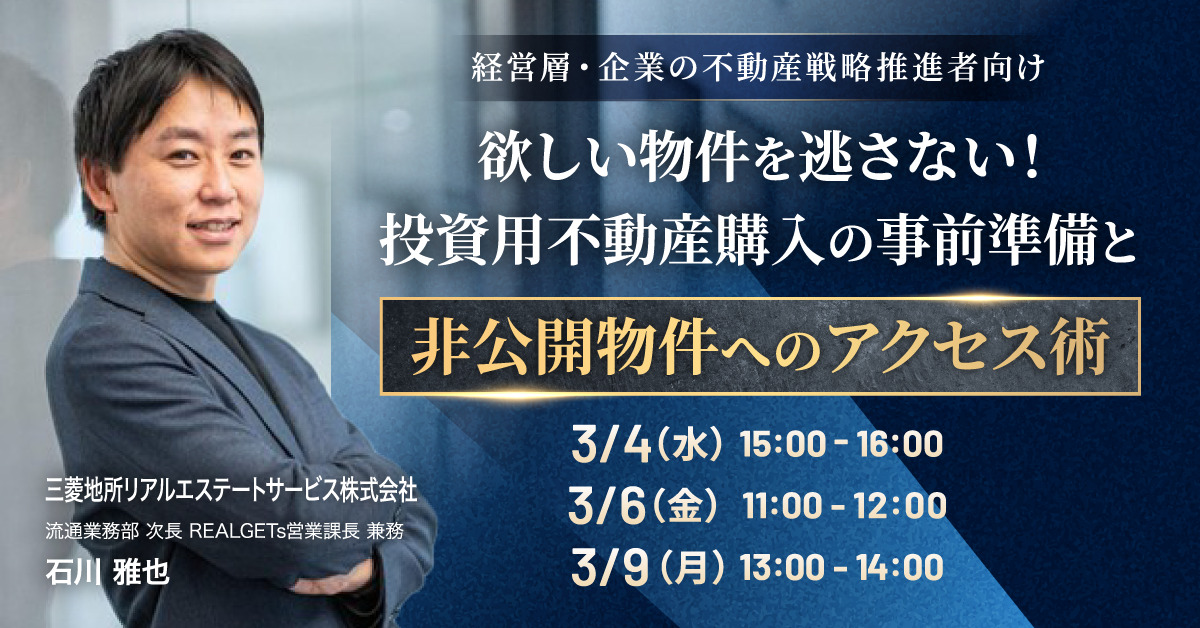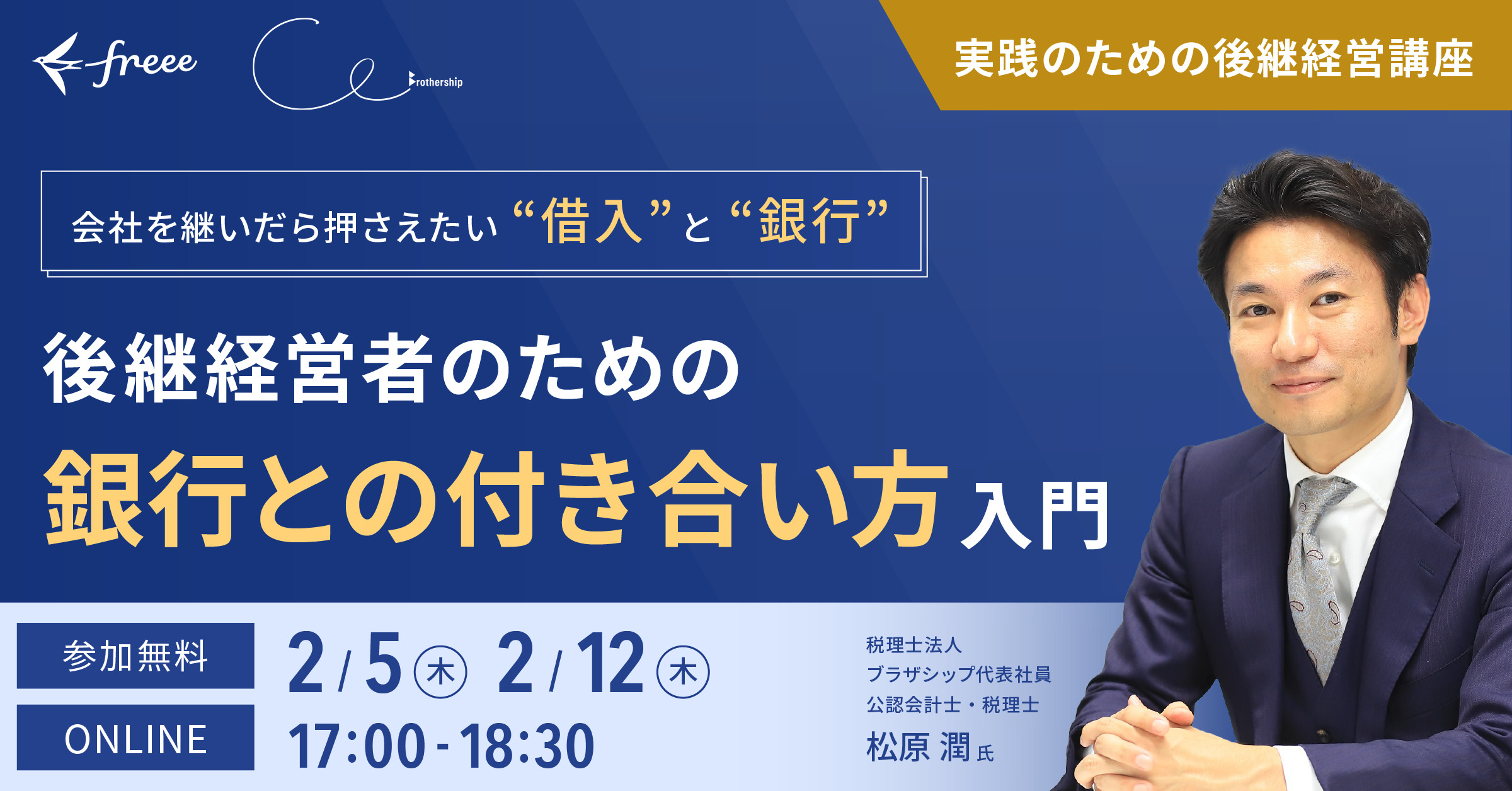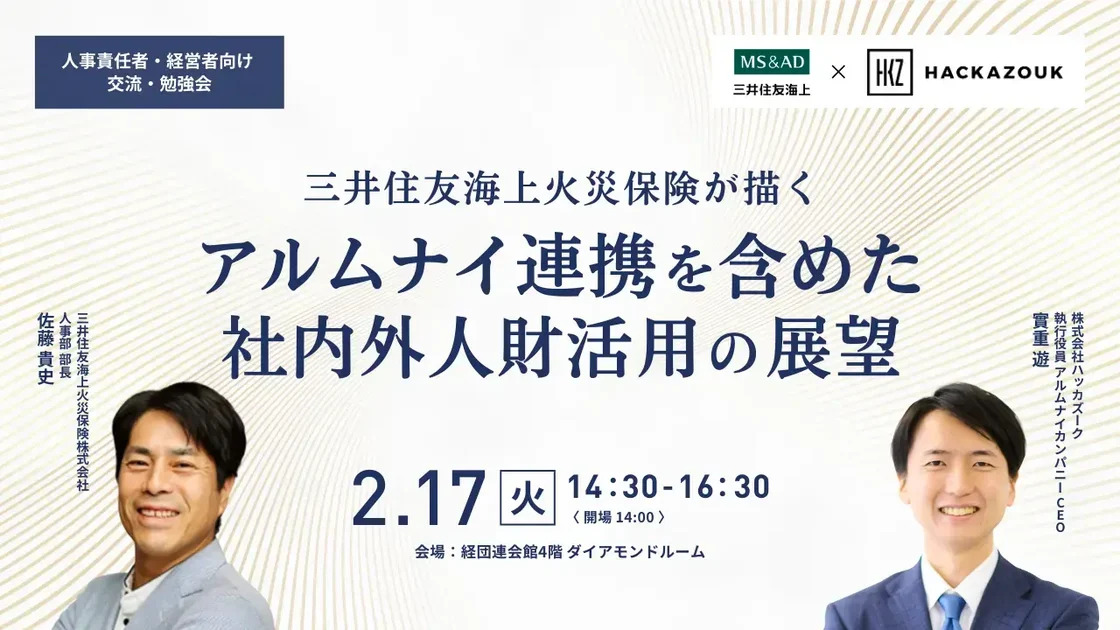公開日 /-create_datetime-/
過去最高を更新した2021年度の企業の内部留保

2021年度の企業の内部留保が、金融・保険業をのぞく全業種で初めて500兆円を超え、10年連続で過去最高を更新したことが、法人企業統計(財務省)によって示されました。
原材料費や輸送コストの高騰、急激な円安で企業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しているはずですが、はたして企業は“もうかっている”のでしょうか。
前年度比6.6%増の516兆4,750億円
財務省が9月1日に発表した法人企業統計によると、2021年度の企業の内部留保は前年度比6.6%増の516兆4,750億円となり、2017年以来の高い伸び率となりました。
業種別で好調だったのが製造業で、前年よりも10.9%増となり、非製造業でも4.4%増の伸び率となっています。一方、企業規模別では資本金10億円以上の大企業が5.9%増でしたが、1,000万円未満の中小企業では3.6%減となっています。
大企業の製造業は、行動制限が解除され、経済活動が再開したことが業績アップにつながり、さらに円安の恩恵も受けて内部留保を確保できたようです。しかし、その割に賃金水準が低く抑えられているのは、なぜなのでしょうか。
企業が溜め込んだ最終利益
その謎を解き明かすには、内部留保とはどういうことなのかを知っておく必要があります。会社は、売り上げから経費や税金を引いて当期純利益として計上しますが、その利益額によって株主への配当額が決まります。
つまり、配当金も含めて払うべきものを払った後の純利益、簡単にいえば、企業が溜め込んだ最終利益が、内部留保となります。給与所得者であれば、家賃や光熱費、税金、生活費を差し引いた余剰分を貯蓄に回すこともできますが、企業の内部留保は、必ずしも現金として残っているわけではありません。
企業の損益には、含み益や含み損、減価償却費や売掛金などがあり、貸借対照表における純資産の部の利益剰余金が、帳簿上の企業の最終利益である「内部留保」となるわけです。
景気動向に連動する内部留保
とはいえ、内部留保は企業が事業で貯めた利益であり、いざという時に企業を支える大切な資産です。内部留保がいくらあるかは、会社の強さを示すバロメーターでもあります。
労働者の立場からは、「そんなにもうかっているのなら、いくらかでも賃上げに回してほしい」と思うことでしょう。しかし、経営者の立場からは「少しでも多く内部留保を貯めこみ、将来に備えたい」という思惑があります。
いずれにしても、景気が上向けば企業の蓄えも増え、景気が悪くなれば蓄えを吐き出すことになり、内部留保も少なくなります。
ですから、2021年度の企業の内部留保が、500兆円を超えて10年連続で過去最高を更新したことだけをみれば、表面上は景気が上向きと判断できるのです。
景気へのマイナス要因ばかりが目につく現状
しかし、本当に景気が上昇傾向にあるのかといえば、誰もが首をかしげるのではないでしょうか。たしかに、新型コロナウイルスの感染予防対策としての行動制限が解除され、経済活動を再開する動きが加速しています。
でも足元をみれば、コロナショックともいわれる経済への打撃は想像以上に大きく、ロシアのウクライナへの軍事侵攻、そしてエネルギー価格や輸送コストの高騰によるインフレ懸念、さらに急激な円安など、景気へのマイナス要因ばかりが目につきます。
現実問題として、企業の内部留保は過去最高となりましたが、その割には設備投資や人件費が増えているわけではありません。景気が上向きと実感できるのは、賃金アップと事業拡大に向けた設備投資への積極的な姿勢です。現状をみる限り、それはまだまだ先のことになりそうです。
まとめ
賃金が上がらなければ消費が冷え込み、景気はますます悪化することになります。内部留保という名の企業の資産が、10年連続で過去最高を更新しようとも賃上げにつながらない要因がどこにあるのか、ビジネスパーソンは見極める必要があるのではないでしょうか。
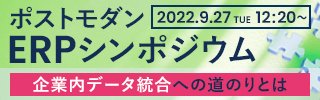
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -
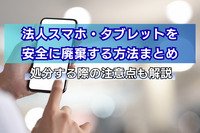
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由
ニュース -

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表
ニュース -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -

ファイル共有のセキュリティ対策と統制
ニュース -

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -
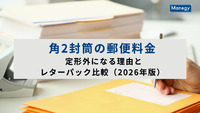
角2封筒の郵便料金|定形外になる理由とレターパック比較(2026年版)
ニュース