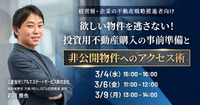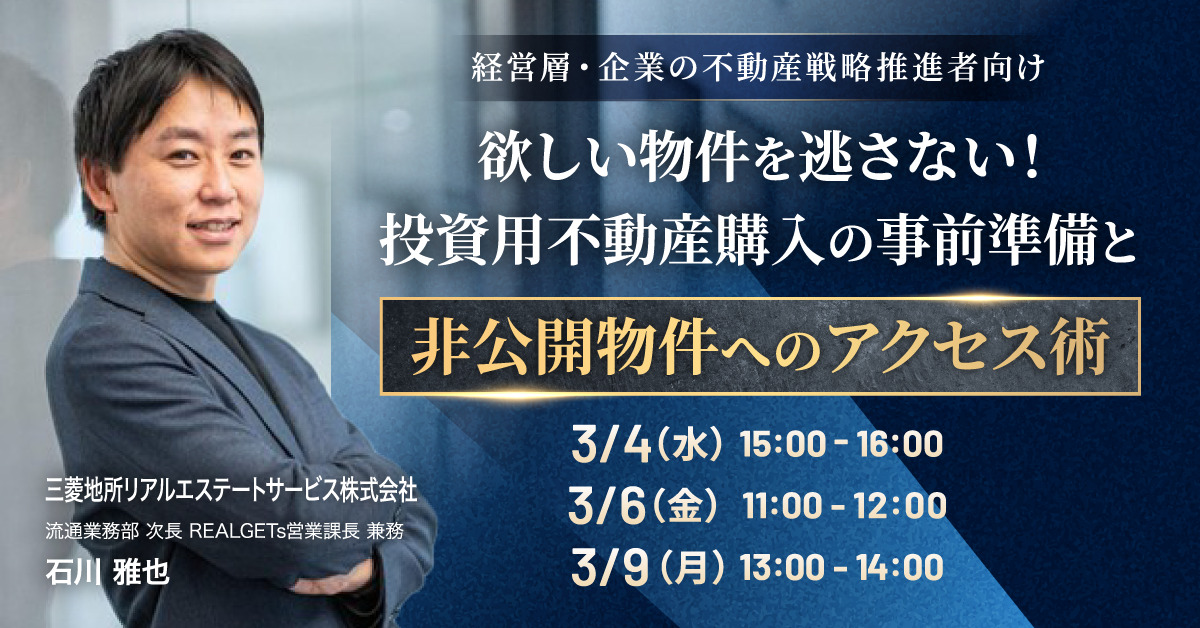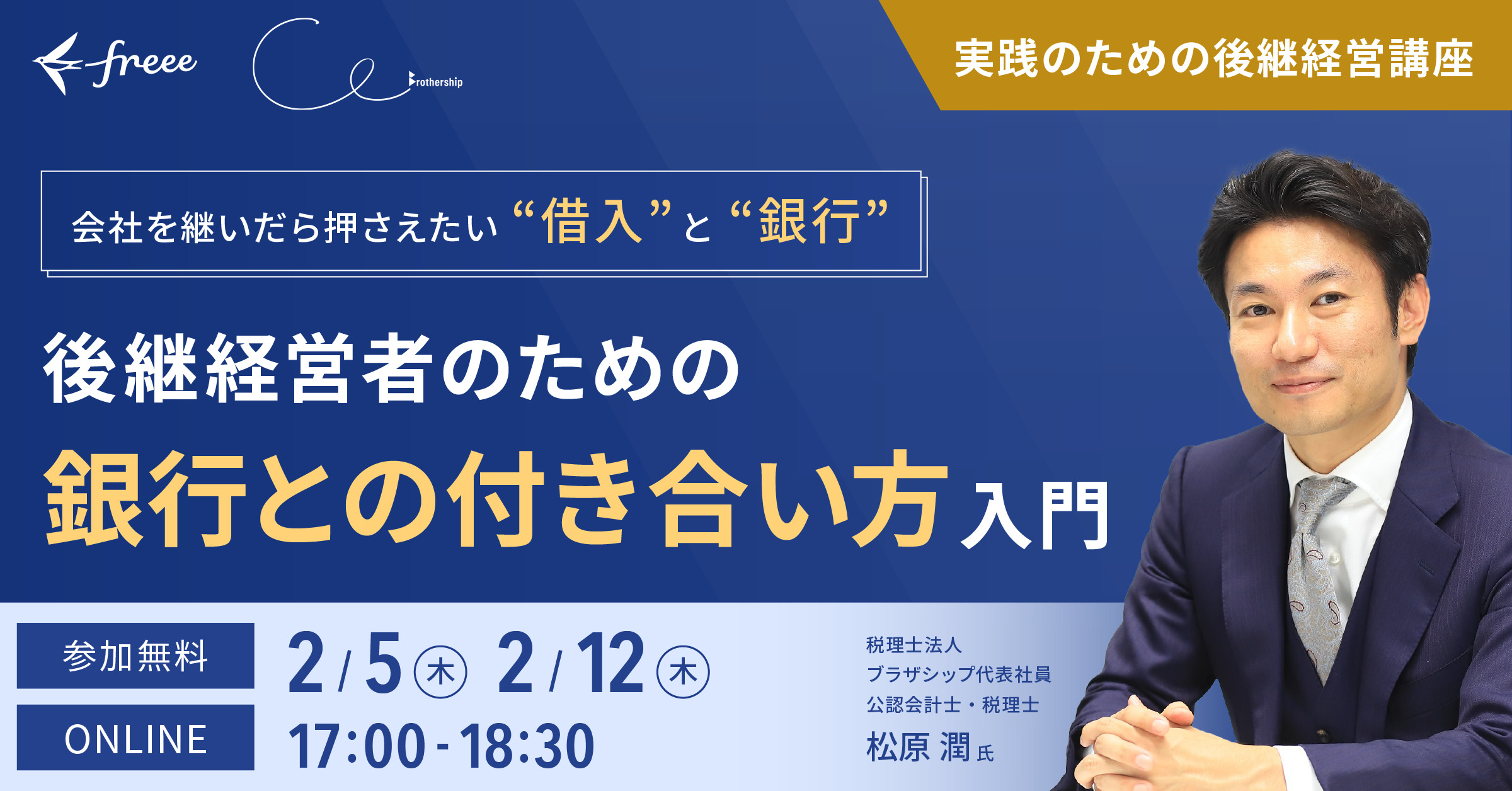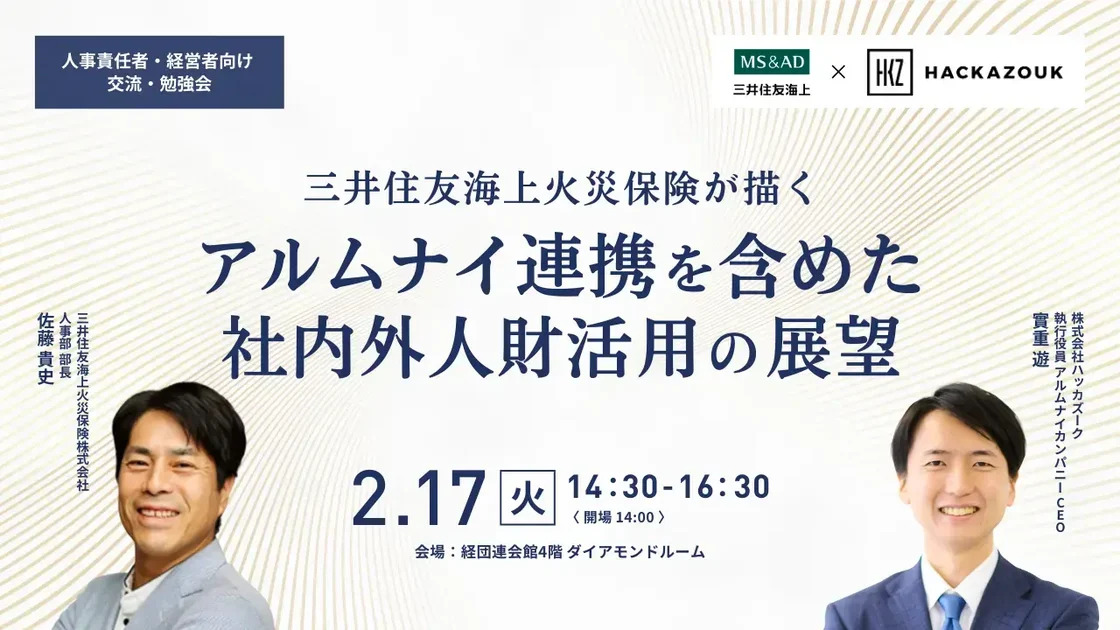公開日 /-create_datetime-/
もしも行政処分を受けたら?企業にとっての影響と対応策を検証する
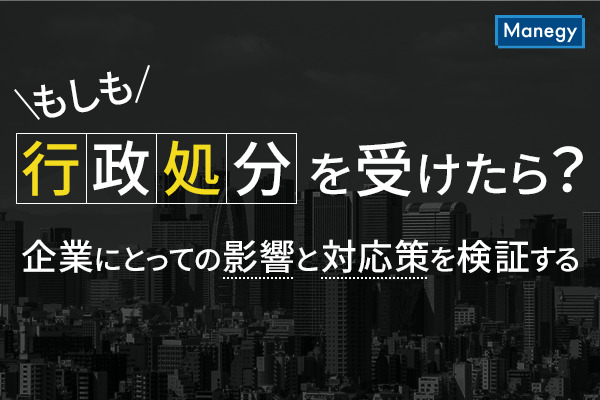
2022年6月、消費者庁は大手回転ずしチェーンに対して、景品表示法違反を認めて行政処分を行いました。
また11月には関東財務局が、大手暗号資産(仮想通貨)取引業者に対して、資金決済に関する法律違反で業務停止の行政処分を行いました。
こうした事例では、経営に対するダメージはもとより、社会的なイメージの低下や、取引先に対する信頼性の低下を招き、経営危機にまで発展する可能性があります。
今回の記事では「もしも行政処分を受けたら?」というテーマで、行政処分の概要と、処分を受けた場合の対応策などについて解説します。
行政処分とは?
行政処分の身近な例としては、運転免許の取り消し処分や飲食店の営業停止処分などが挙げられます。こうした処分には法的な強制力が伴います。行政機関は強制力をもたない行政指導を行うこともありますが、それでも改善されない場合は、やはり行政処分に移行することが一般的です。
行政処分には三つの種類があり、それぞれ監督省庁や自治体により行使されます。その概要は以下の通りです。
●指示処分
主に法令に違反した企業などを対象に、違反に相当する内容の改善を求めるために行われます。
●営業停止処分
不正な営業を続けていた企業などに対して、数日間から1年以内の期間を定めて発効される行政処分です。営業停止処分を受けると公告されるため、違法行為が社会的に知られることになります。
●免許取消処分
運転免許以外にも、企業や飲食店などに交付されるさまざまな免許に対して、その権利を取り消すという非常に重い処分です。
行政処分には懲罰的なイメージがありますが、なかには「旅館の経営許可」や「農地の権利移動許可」のように、前向きな認可も含まれています。ただしこの記事では、行政による罰則に絞って解説を進めます。
行政処分を受けた企業の具体的事例
最初に紹介したように、行政処分を受けた大手回転ずしチェーンでは、実際には準備していない商品を「おとり広告」によって宣伝・集客し、別な商品を提供するという悪質な営業を行っていました。
これに対して消費者庁と公正取引委員会は、業務改善を求める措置命令を行いました。措置命令とは、営業停止などの直接的な処分ではないものの、業務改善と再発防止策が徹底されない場合は、より具体的な行政処分に移行する可能性がある処分です。
さらにこの回転ずしチェーンでは、以前にも複数回にわたって食中毒による営業停止処分を受けてきました。今回のチェーン全体に対する行政処分には、飲食・物販業界に対する警告と、一般消費者に対する注意喚起という二つの目的があると考えられます。
一方の大手暗号資産取引業者は、海外に拠点をもつ親会社の経営悪化が明らかになり、経営者による不正な資金流用などの疑いも認められたため、完全に営業を停止しました。
そのため、当該取引業者の国内法人に対して、業務停止命令と業務改善命令との二つの行政処分が行われたのです。
行政処分を受けた企業がするべきこと
行政処分を受けた場合には、その対象になった違反や違法行為について、適正な状態にまで改善する必要があります。そのため、まずは企業であれば社内の調査を実施して、改善すべき部分を適切に把握しなければなりません。
その上で、通常は監督省庁や自治体に対して業務改善計画書を提出します。場合によっては業務改善計画が完了するまでの間、一定期間ごとに実施状況を報告することもあります。
業務改善が適正に行われたと認定されれば、行政処分が解除されます。
行政処分による最悪の結末
このように、もしも行政処分を受けた場合には、業務改善を徹底すれば処分自体は解除されます。しかし、行政処分を受けたことが周囲に波紋を広げる可能性があることを忘れてはいけません。
行政処分の内容にもよりますが、そのことが顧客や取引先、金融機関などに伝わると間違いなくイメージは低下します。最悪の場合、取引の停止、融資の停止などにより経営を続けられなくなるかもしれません。
また最近は企業のコンプライアンスが重視されているため、行政処分を受けたことが知られると、コンプライアンスの意識が低い企業と見なされることになるでしょう。
その結果、経営状況の悪化を招くだけでなく、人材採用などにも悪影響を与えることが考えられます。
このような行政処分による影響を払拭できない場合、最悪のシナリオとして考えられるのは倒産に至ることです。企業にとっては絶対に避けたい結末です。
まとめ
コンプライアンスも扱う法務が業務に活かせる資料はこちら(無料)
本来行うべき健全な営業を続けていれば、企業が行政処分を受けることはまずありません。つまり、行政処分を受けるということは、その企業や個人事業主が悪質な経営を行っており、社会に対する責任を放棄している証拠なのです。
行政処分を受けた場合、消費者庁のホームページに該当する企業などが公告されることがあります。健全なビジネスを行う上では、こうした情報も常に確認しておき、違法性が高い企業との取引を避けることも重要です。
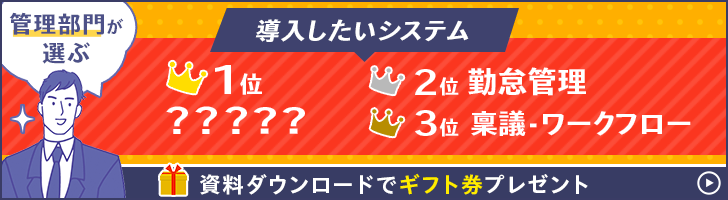
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説
ニュース -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
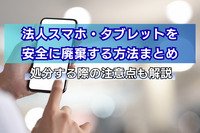
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説
ニュース -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -
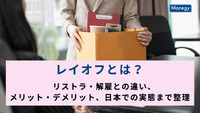
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
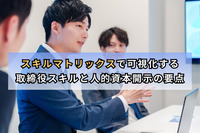
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース