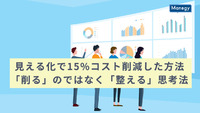公開日 /-create_datetime-/
平成30年分以後の給与所得の源泉徴収票の項目が変更!どこが変わった?

企業で勤務していると、年に1度受け取ることになるのが源泉徴収票。社外に対する収入証明書として用いることもあるでしょうが、その源泉徴収票の表記が、一部変更になっているのをご存知でしょうか。
今回の変更は、税制のしくみが変更になったことに伴いますが、具体的にはどのような表記変更が行われたのでしょうか。背景と合わせて見ていきましょう。
源泉徴収票が作成される意味をおさらい
源泉徴収票は、年末調整の対象となる従業員ごとに会社が2通ずつ作成し、1通は税務署へ提出、もう1通は従業員に交付するものです。
特に請求していなくても配布され、人によっては特に使うこともないので、作成される意味などについて、意識していない方もいるでしょう。
源泉徴収票が作成されるのは、年末調整が無事に完了したことを示すためです。年末調整完了の控えと言えます。
そもそも年末調整が必要になるのは、毎月の給与から天引きされている「所得税」があくまで仮の数字だからです。会社員は、受け取る毎月の給与からは、「所得税」が源泉徴収という形であらかじめ天引きされていますが、この額は実は「仮」なのです。
1ヶ月の給与に対する額として計算されていますが、実際には年間単位でみると、ボーナスが支給されたり、新たな控除が追加されたりして、納めるべき所得税額に変動が生じることが多いのです。
そのため、従業員ごとの年単位での所得税額を確定させ、もし源泉徴収で引かれすぎていれば、その額を払い戻し、足りなければ追加徴収をする。これらのプロセスが「年末調整」というわけです。
源泉徴収によって納めすぎになっている所得税は、税務署に確定申告を行うことで「還付金」として払い戻しを受けることが原則的な扱いです。しかし、日本国内においては会社勤めの社会人が多く、還付金に関する申請を一人ひとり受け付けていては、税務署の処理能力を超えてパンクしてしまいます。そこで、申請者や税務署の省力化の観点から、会社勤めの人々に関する税務処理は、その会社がいわば、毎月の源泉徴収や毎年暮れの年末調整によって、まとめて「代行」するかたちを採用しているのです。
(ただし、年間10万円以上の医療費控除を受ける場合や、初年度の住宅ローン控除を受ける場合、年間2000万円以上の給与を受け取っている場合、複数の勤務先から給与を受け取っている場合等は、たとえ会社員でも年末調整の対象外であり、例外として確定申告を行わなければなりません。)
このようにしておこなわれた年末調整の結果を、従業員へフィードバック書類が源泉徴収票です。源泉徴収票は、年末調整が完了した翌年明け頃に、会社の経理部などが作成し、各従業員へ交付されます。
源泉徴収票の変更点
源泉徴収票の仕様については、2016年度(平成28年度)に、大きな変更がありました。A6サイズからA5サイズへと2倍の大きさになり、横向き(横長)から、縦向き(縦長)に変わっています。
さらに、2018年(平成30年)5月にも、源泉徴収票の新しい様式について、国税庁から発表がありました。2016年度に比べると、いわば「マイナーチェンジ」といえる変化かもしれませんが、変更点は次の通りです。いずれも、A5サイズの新源泉徴収票において、「上半分」の欄にあたります。
<所得控除欄>
従来は「控除対象配偶者の有無」と表記してあったものが、『(源泉)控除対象配偶者の有無』と変更されています。
また、そのすぐ右にある「配偶者特別控除の額」との表記は『配偶者(特別)控除の額』と変更されました。
<配偶者情報欄>
従来は「控除対象配偶者」と書かれていたものが『(源泉・特別)控除対象配偶者』と変更されています。
なぜ源泉徴収票の内容が変更されたのか
まず、『配偶者(特別)控除の額』という変更は、2018年度から、従業員の給与所得の額に応じて、配偶者控除ならびに配偶者特別控除の適用される額がいずれも変動する可能性が生じるようになったことを受けてのものです。
配偶者控除と配偶者特別控除の双方の意味を持たせて『配偶者(特別)控除』と表記されるようになりました。
また、2018年度から「源泉控除対象配偶者」「控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という3種の配偶者概念が登場するようになり、制度が複雑になっています。
「源泉控除対象配偶者」は、年収1120万円以下の従業員の配偶者が年収150万円以下の場合に該当し、38万円の控除枠が設けられます。いわゆる「扶養」に該当します。
「控除対象配偶者」に該当するのは、年収1220万円以下の従業員の配偶者が年収103万円以下の場合です。配偶者控除が適用されます。従来は、従業員の年収上限は設けられていませんでしたが、2018年から「1220万円以下」という上限が設定されています。
「同一生計配偶者」は、年収103万円以下の配偶者がいる従業員に適用されます。従業員の年収上限はありません。
今回の源泉徴収票での『(源泉・特別)控除対象配偶者』という新表記には、「源泉控除対象配偶者」と「控除対象配偶者」が含まれています。さらに「配偶者控除」に加えて「配偶者特別控除」の対象という意味も込められているのです。
まとめ
今回の源泉徴収票の表記変更は、2016年に行われた形式の大幅変更に比べると、ほとんど目立たないかもしれません。しかし、項目表記の変更より、配偶者控除制度が改正となったことを確認しておく必要があります。特に控除の適用対象の方は、注意しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
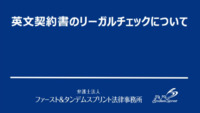
英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -
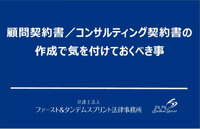
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -
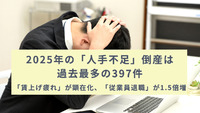
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増
ニュース -

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論
ニュース -
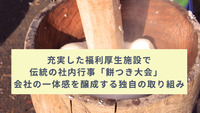
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み
ニュース -
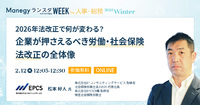
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】
ニュース -

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
ニュース -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -
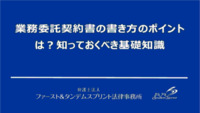
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
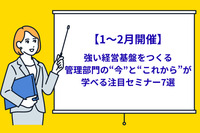
【1〜2月開催】強い経営基盤をつくる管理部門の“今”と“これから”が学べる注目セミナー7選
ニュース -
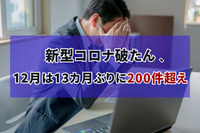
新型コロナ破たん、12月は13カ月ぶりに200件超え
ニュース -
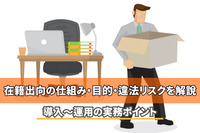
在籍出向の仕組み・目的・違法リスクを解説|導入〜運用の実務ポイント
ニュース -

従業員サーベイの動向ー定期実施は5割弱、そのうち年1回以上の実施が8割超ー
ニュース -

【累計視聴者92,000人突破!】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』2月に開催決定!
ニュース