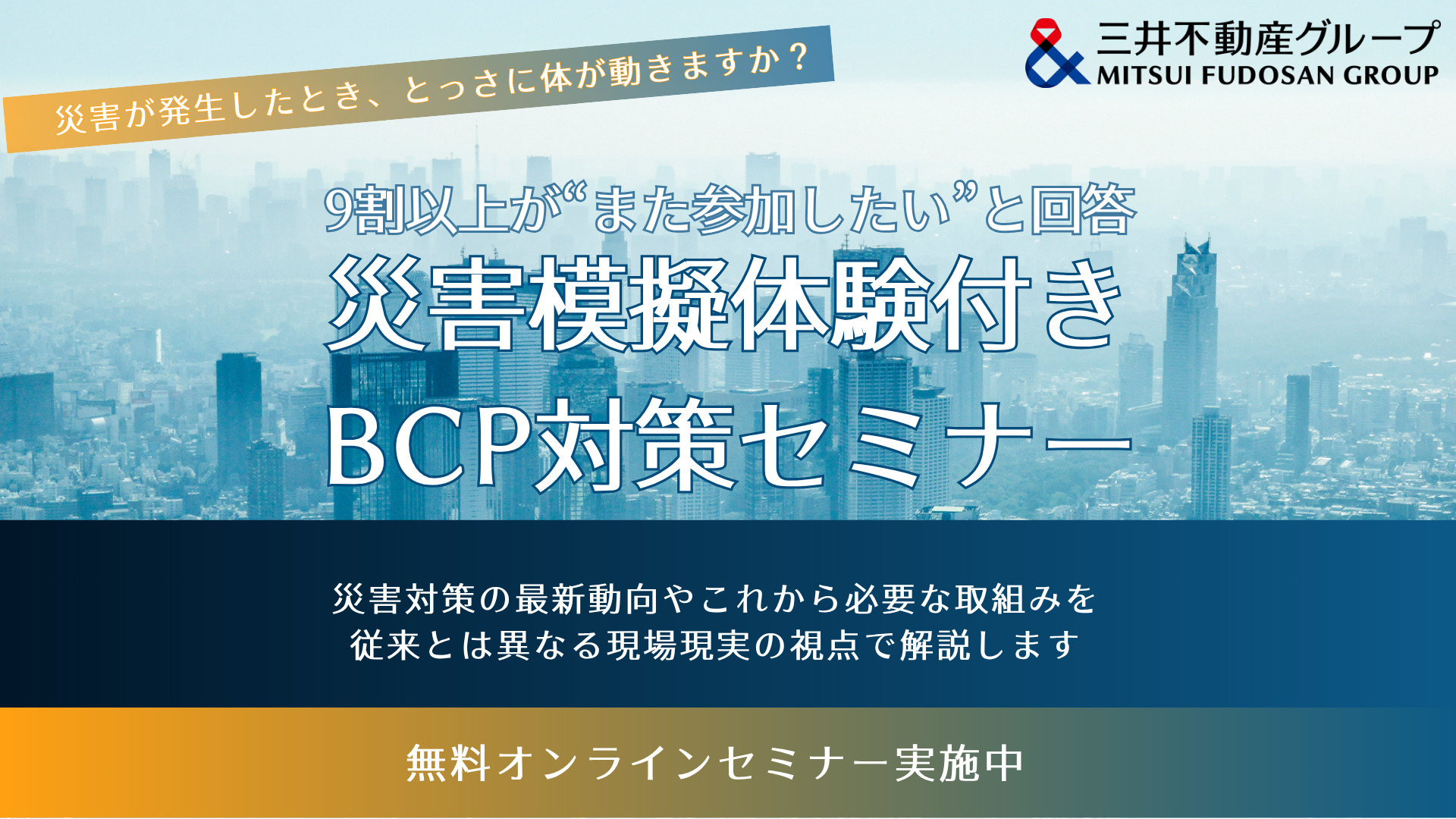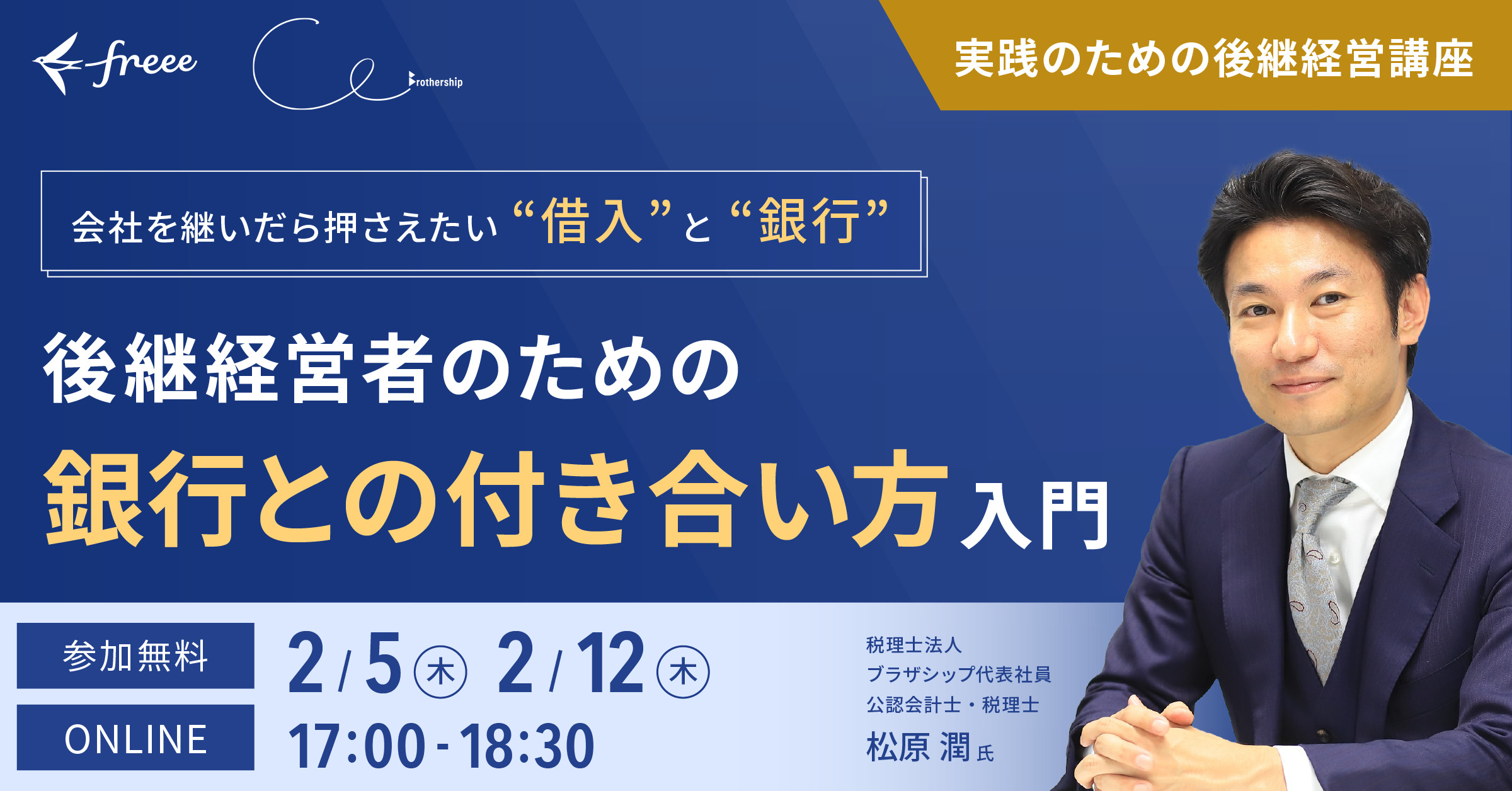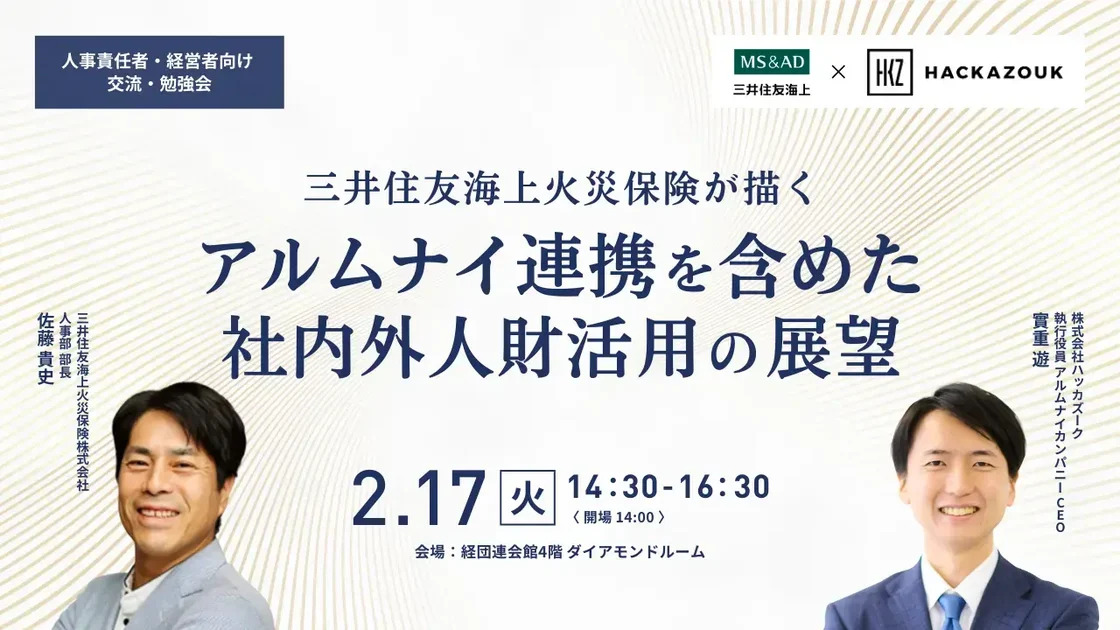公開日 /-create_datetime-/
社員のやる気アップ、企業の業績もアップ、社員持株制度のメリットとは?
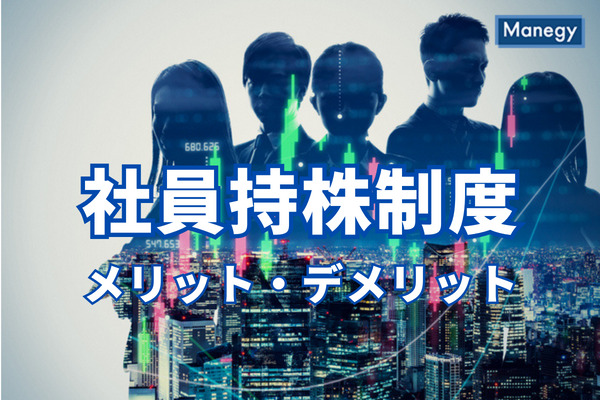
企業が従業員から会員を募り、共同購入で自社の株式を売買する投資方法を「社員持株制度(持株制度)」と呼びます。社員の福利厚生の一つでもあり、国内上場企業のほとんどがこの制度を導入しています。
社員にとっては簡単に資産形成ができるほか、利益を生み出せるというメリットがあり、一方の企業側にも、経営安定化や社員のモチベーションアップなどのメリットがあります。この記事では持株制度の概要と、制度を活用するメリットについて解説します。
目次【本記事の内容】
持株制度の仕組み
持株制度の基本は、社員が自社の株式を購入して株主になることです。一般的には「従業員持株会(持株会)」の会員になり、毎月の給与などから原資を拠出します。その会員の原資をまとめ、実際には持株会が自社の株式を共同購入する仕組みです。
具体的な持株制度の利用方法
より具体的に、制度の仕組みを見てみましょう。まず制度を利用するには、持株会に加入する必要があります。会員になると、毎月の給与などから一定の掛け金が天引きされます。これが株式を購入する原資になるのです。
持株会は会員の原資をもとに、自社の株式を購入します。会員は株式を保有している間、会社が利益を上げれば配当金を得られます。また、ほとんどの企業では配当以外にも、会員に奨励金を支給しています。株式が値上がりしたタイミングで売却すれば、当然利益を得ることも可能です。
持株制度の運営方法
持株会は組合形態で設立することが多く、株式の管理は組合内で行う場合と、外部の証券会社などに委託する場合との二つのパターンがあります。
自社株を購入するという性質上、インサイダー取引を防止するため、売却する場合には上司や担当部門への事前申請を求められます。さらに会社によっては、売却回数やタイミングに制限を設けることもあります。
持株制度のメリット
持株制度には、利用する社員側にも、企業の側にも多くのメリットがあります。その中から、それぞれに主なメリットを紹介しましょう。
社員側のメリット
持株制度の目玉は、奨励金が出されることでしょう。奨励金とは、企業側が株式購入時に一定の金額を上乗せしてくれる仕組みです。通常は購入金額の5~10%の場合が多く、その分だけ多く社員は株式を購入できるのです。
まとまった資金がなくても投資ができる点も、社員にとっては魅力の一つでしょう。さらに毎月の掛け金は株式という形で、いわば積立式の資産になります。奨励金と合わせれば、低金利の貯蓄に回すよりも、ずっと効率的な資産形成が可能です。
企業側のメリット
企業にとっては、多くの社員が持株制度に参加することが、安定的で長期的な株主の確保につながります。自社株を保有している状態になるため、敵対的買収の防止という点でも有効です。
また、多くの企業が福利厚生の一環として実施しているように、持株制度は社員のモチベーションアップにもなります。業績が上がれば配当金も増える可能性があるので、さらにやる気アップにつながります。福利厚生が整っていて社員を大切にする企業は、顧客や取引先からも信頼を得やすくなるでしょう。
持株制度のデメリット
次に、持株制度を利用する上での注意点と、デメリットについても確認しておきましょう。
社員側のデメリット
一般的な株式投資と異なり、持株制度では自由なタイミングでの売買ができません。株式は定期購入になるため、値下がりしたタイミングを狙って購入するように、投資のテクニックを使うことができないのです。
また、売却する場合にはある程度まとまった株式が必要になり、証券会社に個人で口座を開設する手続きにもかなりの時間がかかります。株価の変動に合わせた投資は、持株制度ではできないということです。
もう一つ注意すべき点は、資産形成と収入が自社に集中することから、万が一業績不振で会社が倒産すると、仕事だけでなく資産も失う可能性があることです。リスクの分散という観点から考えると、別の資産形成と併用したほうがよいかもしれません。
企業側のデメリット
社員のモチベーションを保つためにも、企業には安定的に持株制度で配当を続けることが求められます。そのためには常に業績をアップする必要があります。
しかも、やむを得ない事情で業績が下がった場合でも、無配当を続けることはできません。持株制度が上場企業に多いという理由は、こうした点にあるのです。
まとめ
低金利時代の資産形成として、社員持株制度は魅力的な仕組みだと言えるでしょう。売買のタイミングを計ることはできませんが、奨励金による上乗せも可能で、安定的に資産を増やすことができます。
一方で企業側にとっても、従業員のモチベーションアップが業績アップにつながり、経営基盤を強化できる可能性もあります。ただし安定した配当を続けるためには、業績に左右されにくい仕組みを整える必要があります。持株制度の導入に関しては、事前の設計と計画が重要だと言えるでしょう。
■併せて読みたい関連ニュース
仕事に対するモチベーションが上がる1位は?
発言者のモチベーションをググッと上げる3つの秘訣とは!?
企業によっては最重要課題、社員のモチベーションを上げていくためには
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

「叱る・注意する」が怖くなる前に ─ ハラスメントを防ぐ“信頼ベース”の関係づくり
ニュース -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -

日本のダイバーシティの針はどちらに振れるのか ―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―
ニュース -
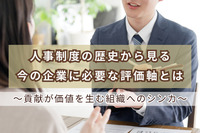
人事制度の歴史から見る今の企業に必要な評価軸とは ~貢献が価値を生む組織へのシンカ~
ニュース -
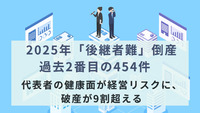
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える
ニュース -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

事業用不動産のコスト削減ガイド
おすすめ資料 -

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~
ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>
ニュース -
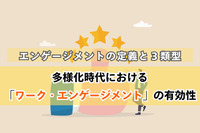
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース