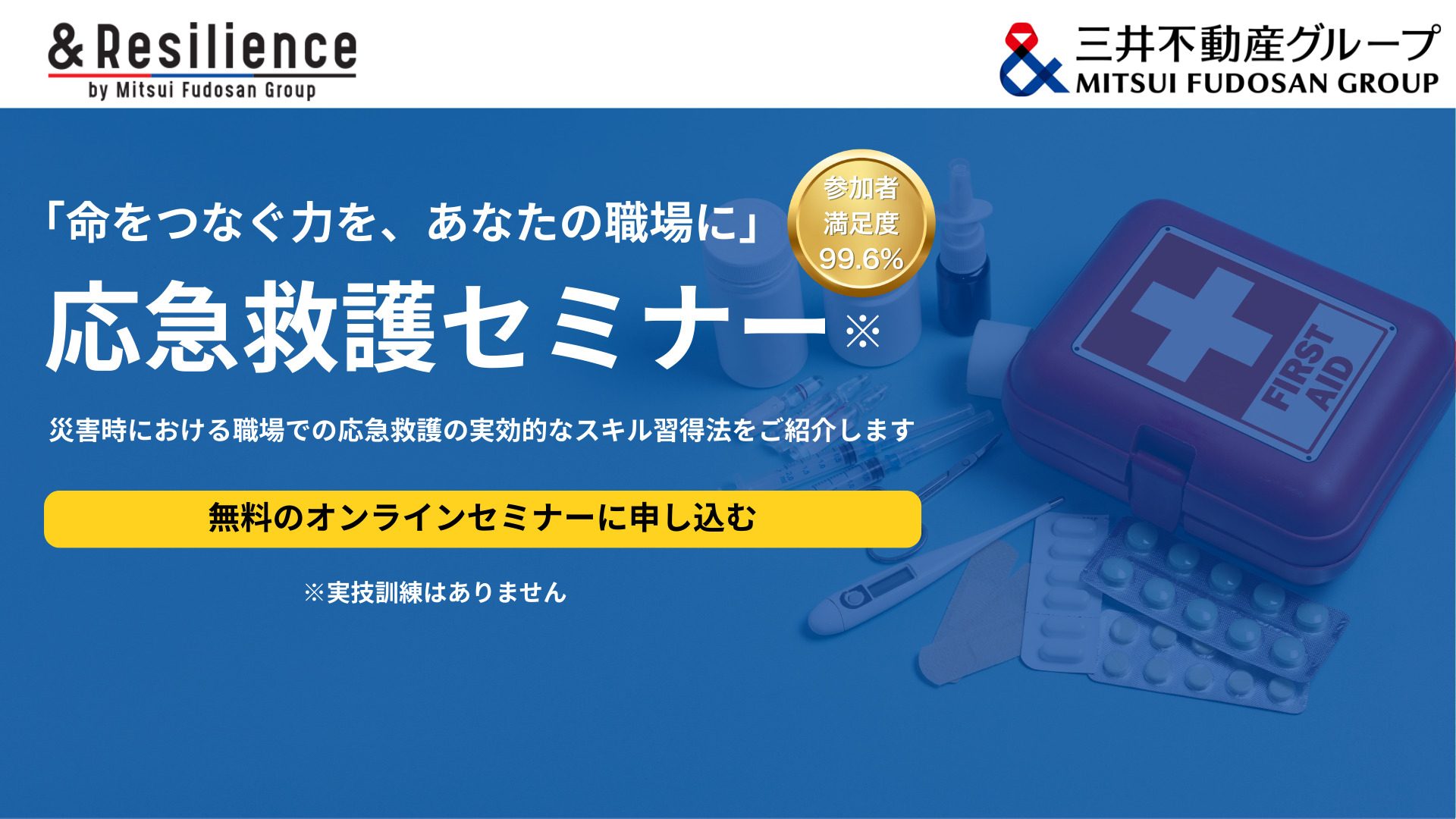公開日 /-create_datetime-/
勘定科目「減価償却累計額」とは?減価償却費との違いや仕訳例を解説
「減価償却累計額」とは簿記の勘定科目の一つで、固定資産の仕訳時に用いる勘定科目です。経理に不慣れな方は「どのように使う勘定科目だろう」「減価償却費と何が違うのだろう」と迷ってしまうかもしれません。
「減価償却累計額」は「減価償却費」と似ていますが、性質は異なり、表示される財務諸表が違います。
この記事では、減価償却累計額の概要や減価償却費との違い、仕訳例を解説します。 注意すべきポイントも解説しますので、減価償累計額の扱いに悩んでいる方は参考にしてください。
目次【本記事の内容】
減価償却累計額とは、固定資産の減価償却費を集計する勘定科目
減価償却累計額とは、固定資産の減価償却を集計する勘定科目で、資産の取得から現時点までの減価償却費を合計した金額のことです。
資産の状態を把握して管理しやすくなるメリットがあり、取得価額から差し引けば、現在の資産価値もわかります。
また減価償却が終了している場合は、経年劣化によりメンテナンスが生じやすくなり、そうした支出も予測しやすくなるでしょう。
減価償却とは?耐用年数に応じて資産を配分する会計処理
減価償却累計額で集計する「減価償却」とは、「時間の経過によって資産価値が次第に減っていく」という考え方で行われる会計処理のことです。
建物や機械装置、車両といった資産は、使用していくうちに劣化して価値が下がります。 このような性質から、高額な資産を購入した場合は、購入費用の全額を一度に経費にせず、分割して少しずつ計上するルールがあるのです。
購入費用を何年かで少しずつ経費にするのが「減価償却」で、分割されたお金は「減価償却費」として当期の「費用」に計上されます。
「減価償却累計額」と「減価償却費」の3つの違い
情報キャッチアップも効率化的に!経理向け資料ダウンロードはこちら(無料)
「減価償却累計額」と「減価償却費」は言葉が似ていて混同しやすい勘定項目といえます。 両者の大きな違いである以下の3つについて解説します。
・【勘定科目】減価償却累計額は「資産」、減価償却費は「費用」
・【財務諸表】減価償却累計額は「貸借対照表」、減価償却費は「損益計算書」
・【計上範囲】減価償却累計額は「取得から現在」、減価償却費は「当期1年」
【勘定科目】減価償却累計額は「資産」、減価償却費は「費用」
「減価償却累計額」と「減価償却費」は、勘定科目の区分が違います。
減価償却累計額は「資産」の勘定科目のひとつで、資産を取得してから現在までの減価償却費の累計をあらわします。
「資産」とは、会社が所有する資源のことです。 減価償却累計額は、「資産」の勘定科目で、累計額の分だけ資産価値を減少させます。
一方、減価償却費は「費用」の勘定科目です。 「費用」は事業を行うための支出をあらわします。 減価償却によって算出された分を「費用」として経費計上し、損益のマイナスをあらわすのが減価償却費です。
【財務諸表】減価償却累計額は「貸借対照表」、減価償却費は「損益計算書」
先ほど「減価償却累計額」は「資産」、「減価償却費」は「費用」の勘定科目であることを説明しました。
「資産」と「費用」の違いがあることから、「減価償却累計額」と「減価償却費」は記載する財務諸表が異なります。
というのも勘定科目は、「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループに分けられ、それぞれ記載する財務諸表は以下のようになるからです。
・貸借対照表:「資産」「負債」「純資産」
・損益計算書:「収益」「費用」
そのため「資産」に分類される減価償却累計額は「貸借対照表」に、「費用」に分類される減価償却費は「損益計算書」に記載されるのです。
【計上範囲】減価償却累計額は「取得から現在」、減価償却費は「当期1年」
「減価償却累計額」と「減価償却費」は計上する範囲も異なります。 「減価償却累計額」は名前のとおり累計額なので、資産を取得してから現在までの資産価値の減少分を合計した金額です。 つまり「減価償却累計額」は、資産取得から現在までが計上範囲になります。
一方、「減価償却費」は1年間に減少した資産価値を「費用」として計上するので、計上範囲は当期1年です。
たとえば、3年前に取得した資産を年10万円ずつ減価償却した場合、3年目の減価償却累計額は30万円、減価償却費は当期分の10万円のみを記載します。
減価償却費の計算・仕訳で知っておくべきこと3つ
減価償却累計額を集計するには、減価償却費を算出する必要があります。 そこでここからは、減価償却費を計算・仕訳する上で知っておくべき以下3つのことを紹介します。
減価償却費の関連用語
「定額法」と「定率法」2種類の計算方法
「直接法」と「間接法」2種類の記帳方法
減価償却費の関連用語
減価償却費を理解するうえで重要な用語を把握しておきましょう。 知っておくべき関連用語は、下表のとおりです。
「定額法」と「定率法」2種類の計算方法
減価償却の方法は「定額法」「定率法」の2種類で、特徴や計算式、対象となる固定資産は下表のとおりです。
固定資産の種類に応じて、どちらの計算方法を利用するかは決められています。 しかし機械設備、車両運搬具、工具器具備品は、定額法と定率法のどちらかを任意で選択可能です。
「直接法」と「間接法」2種類の記帳方法
減価償却の仕訳には、「直接法(直接控除法)」と「間接法(間接控除法)」の2種類の方法があります。
各仕訳方法の内容とメリット・デメリット、対象となる資産は下表のとおりです。
なお上記のとおり、直接法と間接法は任意に選ぶことはできず、無形固定資産は直接法、有形固定資産は間接法と定められているので注意しましょう。
減価償却累計額の仕訳例
ここからは、仕訳方法について以下の3つの事例を使ってわかりやすく解説します。
200万円の車両を購入した
200万円の車両を購入し、100万円で売却した
200万円の車両を購入し、100万円減価償却した時点で除去した
200万円の車両を購入した
事業用の車両を200万円で購入した場合の仕訳例を紹介します。
200万円の車両を購入し、決算時に35万円減価償却する場合の仕訳は下表のとおりです。
200万円の車両を購入し、100万円で売却した
事業用の車両を200万円で購入し、100万円で売却した場合の仕訳例を紹介します。
▼売却益が生じる場合
200万円の車両を購入し、減価償却累計額が140万円積み上がった時点で100万円で売却する場合の仕訳は、下表のとおりです。
▼売却損が生じる場合
200万円で購入した車両を100万円で売却する際に、減価償却累計額が70万円だった場合、30万円の売却損が生じます。
仕訳例は下表のとおりです。
200万円の車両を購入し、100万円減価償却した時点で除去した
除去とは、資産を使用することを中止し、帳簿から除く会計処理のことです。
固定資産は課税対象なので、使用していない場合は除却することで節税につながります。
200万円の車両を購入し、100万円減価償却した時点で除去する場合の仕訳は下表のとおりです。
なお、減価償却が終わった後に除去する場合は、固定資産は簿価1円と扱われるため、除却損は資産の取得価額から1円を差し引いた金額になります。
仕訳は下表のとおりです。
減価償却累計額で気をつけるべきポイント3つ
情報キャッチアップも効率化的に!経理向け資料ダウンロードはこちら(無料)
本章では、減価償却累計額の仕訳時に気をつけるべき3つのポイントを解説します。
・減価償却累計額は減価償却費を「間接法」で仕訳する際に使用する
・減価償却累計額を無形固定資産に使わない
・減価償却累計額がどの固定資産に該当するのか把握する
減価償却累計額は減価償却費を「間接法」で仕訳する際に使用する
前章で解説したとおり、固定資産の減価償却費には「直接法」と「間接法」2種類の記帳方法があり、減価償却累計額は減価償却費を「間接法」で仕訳する際に使用します。このとき、減価償却累計額を記載するのは「貸方」です。
貸方の金額欄にはこれまで積み上げた減価償却費の合計を記載し、この仕訳を見れば現時点の償却済み金額を把握できます。
減価償却累計額を無形固定資産に使わない
繰り返しになりますが、減価償却累計額は間接法に用いる勘定科目です。間接法は有形固定資産を対象とします。
無形固定資産には間接法が適用されないため、減価償却累計額は無形固定資産の仕訳には使いません。
これは、有形固定資産と無形固定資産の性質の違いが影響しています。 有形固定資産は時間経過によって価値が減少しますが、無形固定資産は価値が減少しません。 時間が経っても価値が変化しないので、取替や更新、修繕の必要がないのです。
減価償却累計額は将来の修繕や更新資金の目安になる一方で、無形固定資産は修繕が必要ないため用いる意義が少ないといえます。
減価償却累計額がどの固定資産に該当するのか把握する
勘定科目に減価償却累計額を用いる場合、集計している減価償却費がどの固定資産に該当するか把握する必要があります。
減価償却累計額は、固定資産の管理に必要不可欠で、申告や税額の計上時や処分時などに使用されます。 各資産の状況を正確に把握することで、税額の計上ミスや思わぬ売却損の発生といったリスクを軽減できるはずです。
固定資産は減価償却累計額と合わせて固定資産台帳で管理し、保有する資産の取得から現在までの状況を把握できるようにしましょう。
減価償却累計額・減価償却費のよくある質問
減価償却には、計算や仕訳のほかに理解しにくい点がいくつかあります。 その中でも「減価償却が終わった資産はどうなる?」「中古の資産はどう処理する?」という2つのよくある疑問にお答えします。
減価償却が終わった資産はどうなる?
固定資産は減価償却が終わっても変わらず使用できますが、課税対象なので税金の負担は生じます。
耐用年数が過ぎて減価償却費を計上する必要がなくなると、「費用」が減るため帳簿上の利益は増加します。
利益が増えれば税額も増えてしまうので、注意が必要です。 節税したい場合は、減価償却が終わった後に資産の売却や除去を検討しましょう。
中古の資産はどう処理する?
中古の資産であっても、購入価格が10万円を超える場合は減価償却が必要です。
中古資産の耐用年数は、通常の法定耐用年数に当てはまらないこともあります。その場合には、資産を取得した人が自身で使用可能な年数を見積もるのが一般的です。
年数の見積もりが難しい場合、「簡便法」という下表の計算式を使用します。
経過期間の1年未満の端数は月数に直して計算し、最終計算結果の1年未満の月数は切り捨てです。 最終結果の耐用年数が2年より短い場合は、2年とします。
まとめ:減価償却累計額を理解し、資産を正しく仕訳しよう
情報キャッチアップも効率化的に!経理向け資料ダウンロードはこちら(無料)
簿記の勘定科目「減価償却累計額」について解説しました。
減価償却累計額は、固定資産の減価償却費を集計する「資産」の勘定科目です。
間接法で減価償却費を仕訳する際に使用され、減価償却費の合計が把握できるメリットがあります。
一方で、資産の現在の価値がすぐに確認できないデメリットもあります。
減価償却累計額を理解し、適切に使えるようにしましょう。
以下のページでは、クラウド会計や会計システムの各社サービスを一覧にしています。 会計業務の効率化を考えている方は、ぜひ確認してみてください。
■参考サイト
勘定科目を一覧表で解説!経費の科目や経理に役立つ仕訳のコツも紹介
勘定科目「租税公課(公租公課)」とは?経費にできる租税公課の種類
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
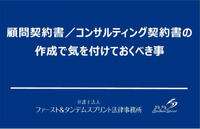
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -
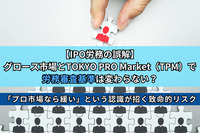
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース