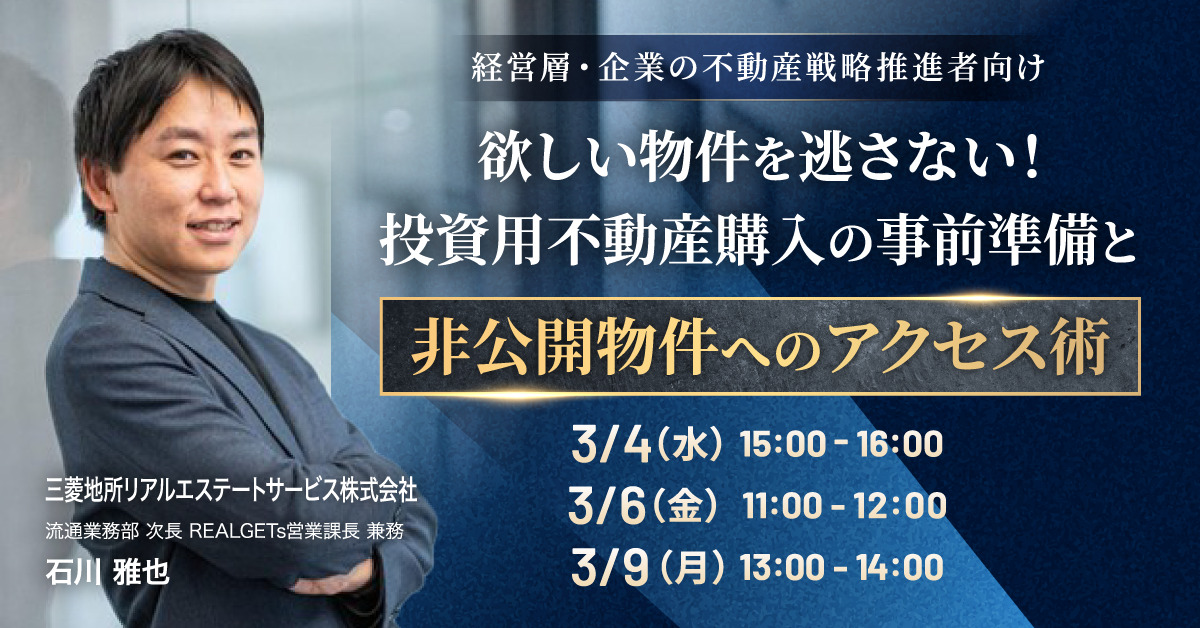公開日 /-create_datetime-/

仕事によるストレスや過労によって従業員が死亡する「過労死」は、よく聞く言葉ですが、その定義や厚生労働省に認定される基準があるのをご存じでしょうか?
万が一にも、「業務が原因で従業員が倒れた…」などの事態が起こった際には、労務や法務をつかさどる管理部門として適切に対処しなければなりません。
今回は管理部門や経営者が知っておくべき、過労死について紹介します。
過労死とは
厚生労働省によると、過労死等とは「業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡。業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡。死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害。」のことをいいます。
代表的な病気としては、くも膜下出血や心筋梗塞などが挙げられます。また、過労による精神障害を原因とする「過労自殺」も過労死として認定されます。
過労死は医学用語ではなく、2014年に制定された「過労死等防止対策推進法」で初めて法律上で定義されました。それまでは、労働者災害補償保険法で、業務上の死亡として補償を定めていましたが、明確な定義は存在しませんでした。
過労死が起こりやすい業種・職種
平成29年度「過労死等の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患に関する過労死等の請求件数は840件で、前年度比で15件増加しました。そのうち、認定され補償支給が決定した件数は253件で、前年度比7件の減少でした。
業種別にみると、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」「建設業」の順で請求件数が多く、肉体労働中心の仕事が、過労死が起こりやすい業種であることがわかります。
また、職種でみると、「輸送・機械運転従事者」「販売従事者」「専門的・技術的職業従事者」の順で請求件数が多く、肉体労働の中でもトラック運転手や営業・販売職などの職種で過労死が起こりやすいようです。
一方、平成29年度の精神障害に関する過労死等の請求件数は1,732件で前年度比146件増加しました。そのうち、認定され支給が決定した件数は、506件で前年度比8件の増加でした。
業種別でみると、「医療,福祉」「製造業」「卸売業,小売業」の順に請求件数が多く、精神障害に関しては、医療・福祉従事者、なかでも社会保険・社会福祉・介護事業の過労死請求が多いことがわかります。
職種別でみると、「専門的・技術的職業従事者」「事務従事者」、「販売従事者」の順に請求件数が多く、一般事務従事者や営業職、商品販売などの職種が、業務の精神的負担が大きいことがわかります。
上記に該当する会社の方は、自身の会社で過労死等の事件が起きないよう、社員の労働環境により一層注意が必要です。
過労死の認定基準について
過労死として認定される、主な疾患である脳梗塞や心筋梗塞は、主に加齢、食生活、生活環境などによる諸要因や遺伝などの要因により、徐々に悪化し発症しますが、仕事が主な原因となり発症した場合を過労死とみなします。
脳や心臓疾患による過労死とみなす認定要件には、①異常な出来事②短期間の過重業務③長期間の過重業務の3つがあり、総合的に「業務上」か「業務外」で起こった疾患か判定します。
①異常な出来事
発症直前から前日まで、「通常業務遂行過程において遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったか、また、気温の上昇や低下等の作業環境の変化※₂」があったかどうかで異常な出来事にあたるか判断されます。
業務中、重大な事故や人身事故に巻き込まれる、またその救護活動や事後処理により身体的負荷を受ける、熱中症などがこれにあたります。
②短期間の過重業務
発症前から約1週間程度に、「日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事※₂」をしたかで短期の過重業務にあたるか判断されます。
労働時間や拘束時間、出張業務、深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務などから負荷程度を評価されるようです。
③長期間の過重業務
発症前から約6ヶ月程度に、「著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した」かで、長期間の過重業務か判断されます。
具体的には、1ヶ月あたり45時間から100時間を超える時間外労働が認められる場合、その長さによって、「業務と発症の関連性が徐々に強まる~関連性が強い」と評価されます。
一方、精神障害の労災認定基準は、①精神障害を発病している②精神障害の発病前、約6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる③業務以外の要因により発病したとは認められないという3つすべてを満たすことが必要です。
業務による強い心理的負荷とは、具体的に強姦やわいせつ行為などのハラスメントを受けた場合や、ひどいいじめや嫌がらせを受けた場合、月に100から160時間を超える長時間労働があった場合などがあります。
このような業務上の強い心理的負荷により、精神障害を発病したと認められる場合に労災認定されるのです。
まとめ
過労死は、どのような業態にも起こりうる死亡事故です。経営者や管理部門のみなさんは、今一度、自社に過労死発生のリスクがないか見直しを行い、労務上のコンプライアンスを遵守した会社づくりを行っていただけたらと思います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -
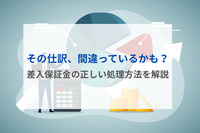
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース