公開日 /-create_datetime-/
採用管理のサービス一覧
採用管理システムを導入することで、採用プロセスの効率化、適性のある人材の採用、人事部門の業務負担軽減が可能になります。これにより、企業全体の生産性の向上や成果の向上、採用コストの削減が期待できます。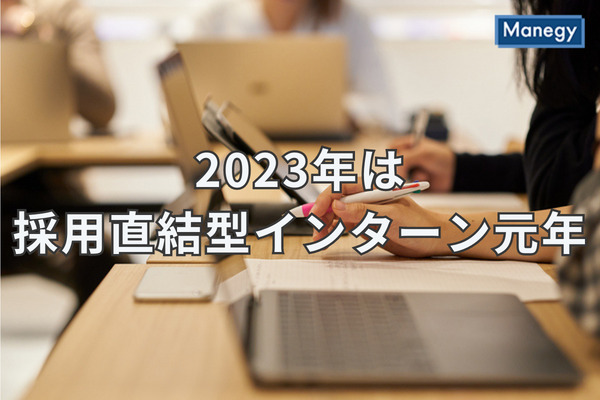
先日、就職情報大手の民間企業が、2025年卒の学生1,000人以上を対象にアンケート調査*を実施し、「(1日だけの仕事体験を含めて)インターンに参加したい」との回答割合は9割を超え、「少しでも興味があれば参加したい」との回答も6割を超えました。
つまり、新卒者向けのインターン参加を巡って、学生の間で「質より量」という状況が生まれつつあるのです。
こうした状況の背景にあるのが、2025年から始まる採用直結型インターンの実施です。今回はこの点について掘り下げて解説します。
*【調査概要】
調査対象:キャリタス就活会員のうち2025年3月卒業予定の全国の大学3年生・大学院修士課程1年生
回答者数:1,124人(文系809人、理系・学部生 206人、理系・大学院生109人)
調査方法:インターネット
調査期間:2023年5月18日~ 31日
目次【本記事の内容】
そもそもインターン(インターンシップ)とは、企業が学生に就業体験の場を提供する制度のことです。実際に学生が就職活動を始める前に実施され、参加を通して、学生は業種・職種への適性の確認を行ったり、参加先企業の組織風土・文化を理解したりできます。
また、企業で実際に働いている人から話を聞けるので、企業のホームページやパンフレットからではわからない、多面的な業界・企業の情報を得ることも可能です。
かつて企業側にとってインターンは、優秀な人材の青田買いという性格をもっていました。しかし、2018年9月3日に当時の経団連会長が「それまでの就活ルールを2020年の学生を最後に取りやめる」と発表したことで、その風向きが変わりました。経団連は1997年以降、経済界における就活ルールを事実上取り仕切っていたわけですが、この2018年における一連の動きにより、経済界だけでなく、政府や大学が就活ルール作りに直接介入するようになったわけです。
当時、インターンとは名ばかりで、会社説明会のような内容のインターンや採用選考会のようなインターンなど、「職業体験をして適性・企業風土を見極める」という本来の目的が果たされていないケースが多数ありました。こうした状況を受け、政府側は「採用につながるインターンに対する禁止要請」を3者の協議(産学協議会)に提出し、これがルール化されたのです。
ここでいう禁止要請とは、インターンの開催そのものを禁止するのではなく、インターンで得た学生の情報を、新卒者採用の際に用いてはならない、という内容です。このルールにより、採用とは関係のないインターンは開催しても問題ないものの、採用直結型のインターンは禁止されることになったわけです。
ただ、「禁止されることになった」といっても、法制度で厳格に禁止されたわけではなく、あくまで「要請」にとどまるものです。そのため実際は、事実上「インターン→採用」という状況が続いていた面が多分にありました。 そうなると「禁止といわれているのに、採用直結型インターンが行われている」などと、学生を混乱させる事態になってしまいます。
そこで産学協議会としては、採用直結型インターンを禁止するのではなく、「明確なガイドラインを設けた上で、認める形にする」という方針を固めます。これが2022年4月のことであり、その後三省(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)もその内容に合意し、新たなルールが2025年卒業予定者から適用されるようになったのです。
この結果、「いつから企業は採用活動を開始できるか」などを定めたいわゆる就活ルールは事実上形骸化し、2025年卒からは「3年の夏にインターンに参加することから就活はスタート」という形態がスタンダードになります。
ただし、インターンに参加した学生の情報を採用活動に用いるには、いくつか条件があります。
・就業体験を含む内容であること。
・5日以上の期間で行うこと。
・実施期間の半分以上が就業体験できる内容であること。
・実際に現場で就労している社員が指導・フィードバックをすること。
・夏休みなど学生が長期休暇中に行うこと。
その上で、この条件を満たすインターンは、「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」(大学3、4年生を対象とし、マッチング制度向上、評価材料の取得を目的に実施する)と、「高度専門型インターンシップ」(主に大学院生を対象とし、2カ月以上にわたって実施。学生の専門技術を活かし、より向上させることが目的)と位置づけられています。
1日だけ実施される「オープン・カンパニー」や、参加者に対して社会人としての一般的な教育を行う「キャリア教育」などはインターンとして認められない、とされています。
新ルールの適用により、2025年卒の学生は希望に合った就活を成功させるために、3年の夏から一斉にインターンに参加する必要性が生じました。とくに大手企業は、優秀な学生を早めに確保するためにインターンを積極的に実施します。
学生はそこに何とか参加したいわけですが、インターンは指導を伴うため、希望者全員を参加させることはできません。「インターンのための選考」「インターンのためのエントリーシートによる書類審査」などを通して、企業側がふるいにかけるのが通例です。
現在、インターン参加の倍率が100倍に達することも当たり前の状況となっています。
こうなるとインターンは、「自分の適性に合っているかを試す場」などではなく、完全に就活の場となります。
つまり、事実上、大学3年の夏休みから本格的な就活がスタートするわけです。企業側は学生の自社に対する志望度を測り、優先度の低い学生をふるいにかけるため、インターンに参加するための提出課題を増やす傾向もあります。
採用直結型インターンが正式に解禁されたことで、インターンの位置づけが大きく変わります。学生にとって、採用直結型インターンに参加して高評価を得ることは就職活動そのものであり、ここで採用に至らなかった学生が、従来通りの公募型(新卒対象)の就職活動をスタートさせるという状況になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
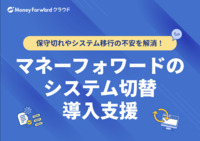
マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!

【中堅社員の意識調査】成長実感が低いほど、離職意向が高まる傾向

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営
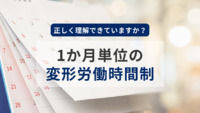
1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

採用を「運」から「設計」へ変える――役割貢献制度で実現する、ミスマッチゼロの要件定義とは?
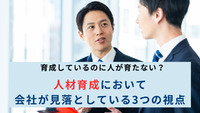
育成しているのに人が育たない?人材育成において会社が見落としている3つの視点

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説

【中堅社員の意識調査】管理職志向のない中堅社員、管理職を打診されたら8.3%が「承諾」、25.1%は「辞退」

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
公開日 /-create_datetime-/