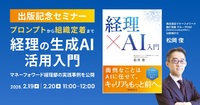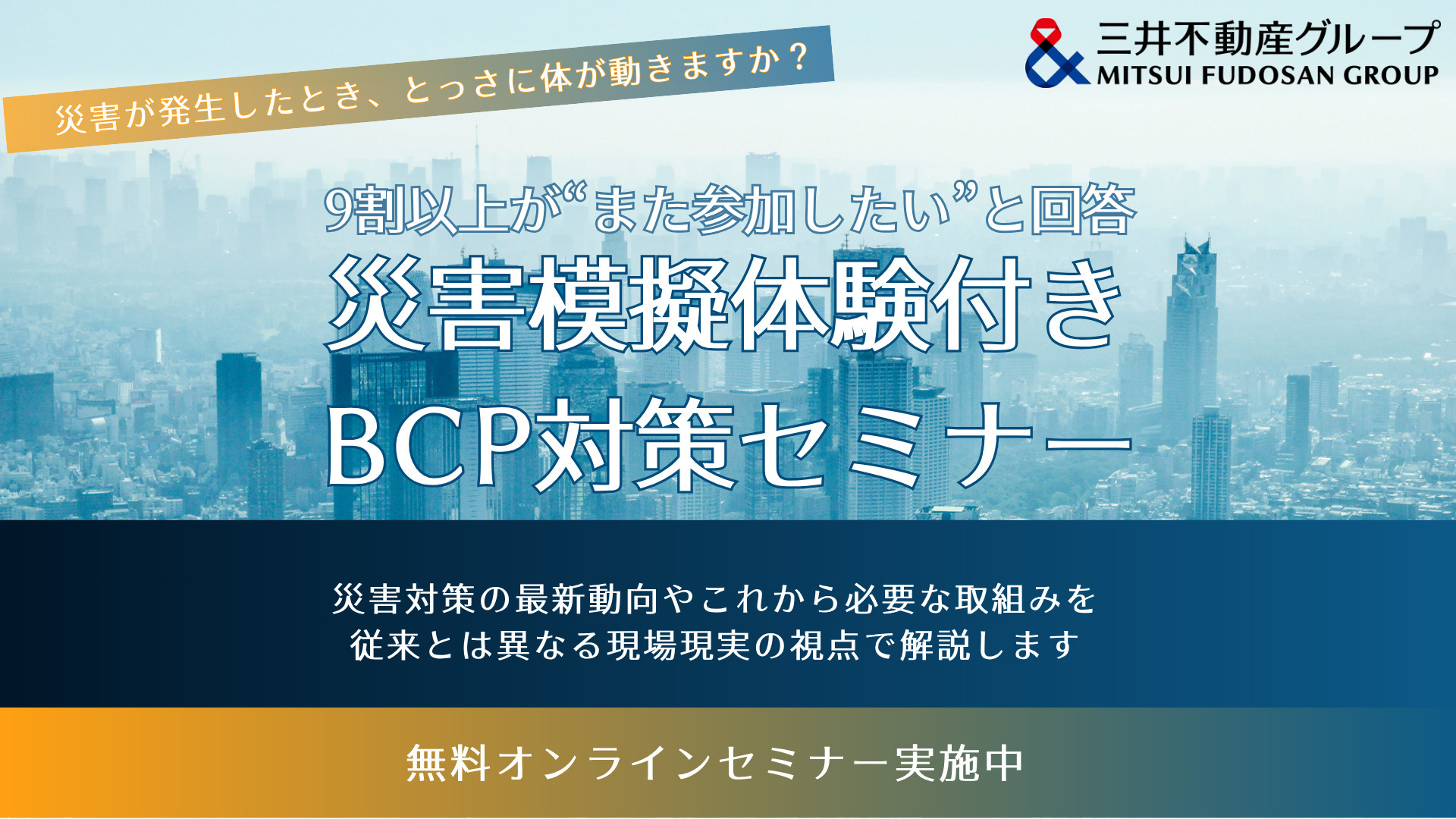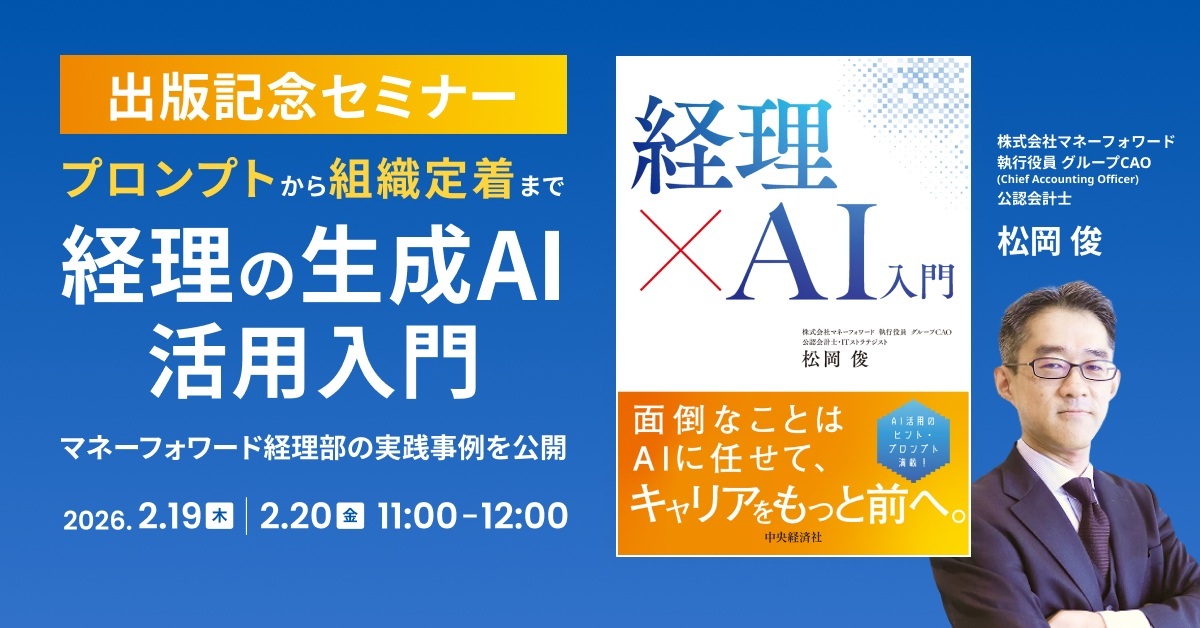公開日 /-create_datetime-/
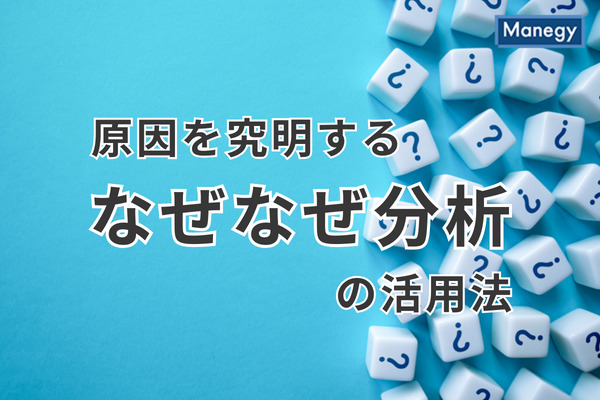
日本を代表する自動車メーカー、トヨタが考案した「なぜなぜ分析」は、現在さまざまな業界で活用されています。しかし、ただなぜを繰り返すだけでは効果は得られません。なぜなぜ分析は、正しく使って初めて結果が出るものなのです。
目次【本記事の内容】
なぜなぜ分析の進め方
なぜなぜ分析は、ビジネスで生じる問題を特定し、根本的な原因を探る分析手法です。「なぜ? 」という問いかけを繰り返すことにより、問題の原因を追究するという、一見シンプルなやり方ですが、多くの現場で効果が実証されています。
なぜなぜ分析は、大きく分けて以下の三つの手順で問題の原因を追究します。
1)5W1Hなどで具体的に課題を定義する
2)「なぜ?」と繰り返す、根本的な原因を見つける
3)原因を特定し、解決策を考える
たとえばある工場で、不良品が出荷されたと仮定しましょう。この課題に対して、最初の「なぜ?」を問いかけると、「出荷検査でチェックできなかったから」という答えがでてきました。
その答えに対して再び「なぜ?」を問いかけると、今度は「マニュアルにある項目が一つとばされていたから」という具体的な答えが提示されました。
もちろんここで終わりではなく、一般的にはこの過程を5回ほど繰り返し、改善につながる答えを見つけることが推奨されています。
なぜなぜ分析で陥りやすいポイント
ところが、「なぜ? 」と答えを5回繰り返せば自然と解決策が見つかるほど、現実は単純なものではありません。トヨタの元祖なぜなぜ分析にも、5回というルールはないそうです。実際には確かな答えが見つかるまで、なぜなぜを繰り返すことが必要なのです。
なぜなぜ分析とは、過程を規定の回数繰り返すことが目的ではなく、最終的に具体的な改善案を導き出さなければなりません。そのためには、「なぜ?」に対する答えを具体的にする必要があります。
また、「社員のやる気が上がらないのはなぜ? 」もしくは「業績が伸びないのはなぜ? 」のように、初めに考える課題に具体性がない場合は、何度「なぜ? 」を繰り返してもあいまいな結論になってしまいます。
なぜなぜ分析では、はじめに解決したい問題を明確にすることが重要です。
意味のあるなぜなぜ分析のために
正しい活用法を知らないと、なぜなぜ分析を何回繰り返しても時間の無駄です。なぜなぜ分析で結果を出すために、以下のポイントを参考にしてください。
・はじめに課題を具体的に定義する
・原因を個人の責任として特定しない
・複数の課題を一本化して分析しない
・個人の感情や感想を排除して、客観的に考える
・解決不可能な原因で結論づけない
このような点を意識しながら、1回の「なぜ?」によって、さらに深く原因を追究し、最終的には具体的で実行可能な改善策を見つけることが、なぜなぜ分析が目指すべき目標です。上手に活用を続ければ、なぜなぜ分析そのものが進歩するのではないでしょうか。
まとめ
業務上の問題に「なぜ?」と問いかけることにより、それを系統立てたシステムとして活用するのがなぜなぜ分析です。ただし上手に使うためには、課題の決め方と答えの出し方に注意する必要があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

文書管理データ戦略:法人セキュリティの決定版
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
ニュース -
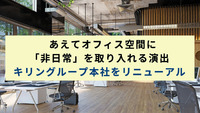
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル
ニュース -

従業員の副業における注意点|企業が知っておきたいリスクと対応策
ニュース -

ファイル共有規程ひな形|禁止事項と運用術
ニュース