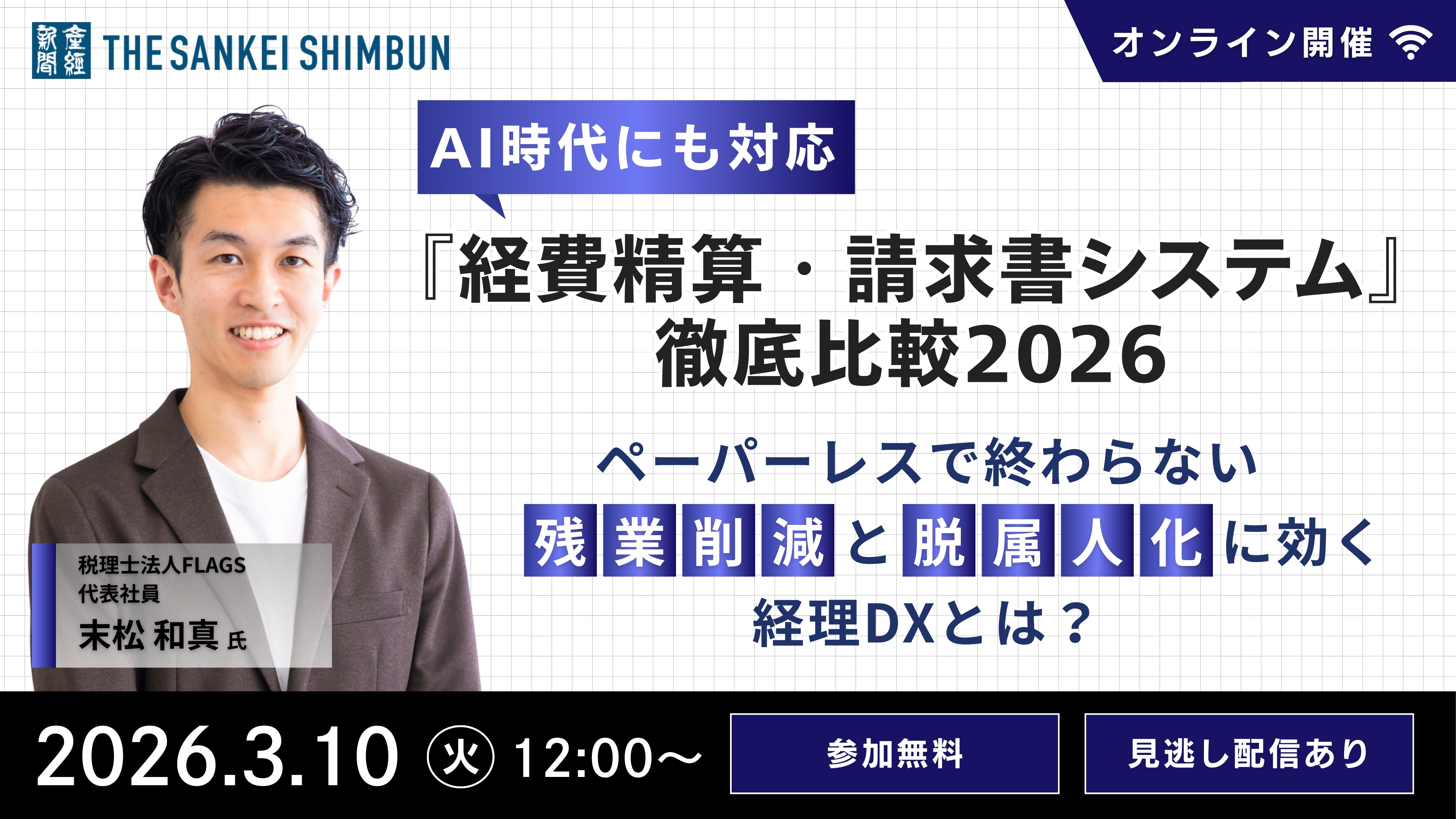公開日 /-create_datetime-/
デジタル化時代に対応するためのオンラインストレージ導入ガイド

目次【本記事の内容】
オンラインストレージとは何か
オンラインストレージとは、具体的に言えば、「クラウドストレージ」とも称され、データをインターネット上のサーバーに保存するサービスのことを指します。
これにより、データを自分だけのパソコンやモバイルデバイスに頼ることなく、どこからでも手軽にアクセスして取り出すことが可能となります。
情報が古代の紙などの物理的な媒体からデジタル化され、コンピュータのハードディスクなどへと保存されるようになった現代、更にその一歩を進めてデータはネット上に保管される時代が到来しています。
オンラインストレージの定義
オンラインストレージの定義とは、インターネットを通じて、ユーザーが自身の各種ファイルやデータをサーバー上に保存、管理できる場所やサービスを指します。
専用のソフトウェアを利用することで、各デバイスからデータをアップロード、ダウンロードを行ったり、共有したりすることが可能です。これにより、物理的なストレージ媒体を持ち歩く必要が無くなるだけでなく、端末の故障や紛失からもデータを守ることができます。
また、複数人でデータを同時に扱う、共有する場合にも利便性があります。そのため、ビジネスの現場だけでなくプライベートの使用においてもオンラインストレージが欠かせない存在となってきています。
オンラインストレージの利点
オンラインストレージの利点は、何と言ってもその利便性と安全性です。データはインターネットがつながる場所であれば、どこからでもアクセス可能です。
また、データの自動バックアップ機能が付いているサービスも存在します。これによりデータの紛失リスクを低減でき、端末が故障した場合でもデータを安全に保つことが可能です。
さらに、多数のユーザーが一つのファイルに同時に作業することも可能なので、リモートワークやグループ作業を効率的に進めることができるでしょう。一方で、ストレージの容量を自在に増減できるので、必要に応じたスペースを確保できる利点もあります。
オンラインストレージの欠点
オンラインストレージの欠点として挙げられるのは、まずインターネット接続が必要であることです。ネット環境が整っていない場所ではデータにアクセスできません。
また、セキュリティ面も大きな課題です。パスワードが漏洩した場合や、サーバーが不正アクセスに遭った場合、個人情報や大切なデータが第三者に渡るリスクもあるのです。
このため、どのサービスを選択し利用するのかは、信頼性やセキュリティ強度が問われます。また、データを大量に保管していると料金が高くなることもあるでしょう。
大量のデータを一括でアップロード、ダウンロードする際は、時間がかかりますので、計画的な運用が求められます。
なぜオンラインストレージを導入するのか
デジタル化が進む現代では、私たちの周りに存在する情報が増えつつあります。その大半がデジタルデータとして存在しており、それらを適切に管理していくことが求められています。
しかし、情報量の増加により従来のデータ管理方法では対応が難しくなってきています。ここで注目されているのが、オンラインストレージです。ではなぜオンラインストレージを導入するのか、その理由を説明していきます。
デジタル化時代のデータ管理の課題
一昔前までは、ほとんどの情報が紙媒体で管理されていましたが、今日では大量の情報をパソコンやスマートフォンで一元管理するデジタルデータが増えています。
しかし、これには新たな課題が付きまとうのです。つまり、大量のデータを安全に保存しつつ、必要なときにすぐにアクセスできる状況を作ることができるかという問題です。
さらに、データの消失やセキュリティリスク、アクセス権限の設定など、管理面でも難しさが増してきています。それらの課題を解消するためにも、オンラインストレージの導入が求められています。
導入のメリットとデメリット
オンラインストレージ導入の最大のメリットは、以前述べた課題の解消でしょう。すなわち、大量のデータを安全に保存し、必要なときにすぐにアクセスできる環境を整えることができます。
さらに、クラウド上であればデバイスに問わずアクセス可能であり、データの共有も容易になります。
ただし、情報を第三者のサーバーに預けることになり、そのセキュリティに依存することになるため、デメリットも無視できません。また、長期的視点では費用面も考慮する必要があります。
ビジネスへのインパクト
ビジネスの観点では、オンラインストレージは大きなインパクトをもたらすでしょう。一つは「生産性の向上」です。データの簡単な共有や遠隔地からのアクセスが可能となることで、作業効率を大幅に向上させることができるでしょう。
また、データ紛失のリスクを軽減し、セキュリティも強化されるので、ビジネス運営上のリスクも低減されます。しかし、上述したようなデメリットによるリスクも存在します。
そのため、導入を検討する際には、そのメリットとデメリットを十分に比較検討することが重要です。
人気のオンラインストレージサービスを比較
現代社会においてデータ管理は絶対に避けて通れない道です。それを可能にするのが、オンラインストレージサービスです。しかも、それぞれのサービスはユーザビリティ、セキュリティ、容量などの観点から、異なる特徴を持つのです。
本記事では、グローバルに愛用されている3大オンラインストレージ、Google Drive、Dropbox、そしてOneDriveを比較し、その特徴と評価を深掘りしていきます。
Google Driveの特徴と評価
Google Driveは、Google社が提供するオンラインストレージであり、無料プランでは15GBまでのデータ保存が可能です。拡大性と利便性を兼ね備え、Googleのアプリケーション群との連携も容易な点が一番の魅力でしょう。
特にGmailやGoogle Photosとのシームレスな連携は注目で、写真やメールなどを手間なくバックアップできます。ほかにもGoogle Docs、Sheets、Slides等と連携し、編集形成したドキュメントはDrive上で直接共有できるのです。
評価の点では、上記の機能の高さから一般ユーザーだけでなく、チームでの利用にも好評です。ただ、無料プランの15GBは日常生活をデジタル化するとあっという間に埋まります。
大量のデータを保存したい場合は、追加容量へのアップグレードを検討する必要があるでしょう。
Dropboxの特徴と評価
Dropboxは、単なるデータ保存場所以上の機能を提供しており、同期フォルダとしても使用可能です。
親しみやすいUI・UXとシンプルな操作方法が特徴で、初めてオンラインストレージを利用する人にもお薦めでしょう。無料プランでは2GBまでのデータ保存が可能となります。
評価の面では、データ同期の速度や安定性が評価されています。仕事で使用するのに適していると言えるでしょう。ただし、他サービスと比べて無料で使用できる容量が少ないという点がデメリットで、大量データのバックアップには向いていません。
OneDriveの特徴と評価
OneDriveは、Microsoftが運営するオンラインストレージで、Windowsとの連携性が特徴です。特にOffice系のアプリケーション(Word、Excel、PowerPointなど)との深い連携ができるため、ビジネス利用に適しています。
また、無料プランでは5GBまでのデータ保存が可能です。
評価の観点では、WindowsユーザーやOfficeを使用するユーザーからは高評価を受けています。
ただし、他のOSやアプリケーションを主に使用するユーザーにとっては、他のストレージサービスと比べてメリットを感じにくい部分もあるのです。
オンラインストレージ導入の手順とコスト
近年、企業のデータ管理にオンラインストレージの導入が進んでいます。セキュリティの強化、データの管理効率の向上、災害時のデータ復元など、オンラインストレージ導入のメリットは多岐に渡ります。
しかし、成功した導入のためには準備や手順の理解、コストの計算が必要となります。以下、その詳細を紐解いていきましょう。
導入前の準備と注意点
まず、オンラインストレージの導入前にはしっかりとした準備が求められます。データの種類や容量、利用者の数や利用状況を把握し、どの種類のオンラインストレージが最も適しているかを検討することが重要です。
また、セキュリティ面においても、例えばパスワードの設定や暗号化のオプションの有無など、自社のニーズに合ったものを選択することが求められます。
導入前の準備としては、データのバックアップも欠かせません。万が一のデータ消失時でも直ちに対応できるよう準備しておくべきでしょう。
さらに、移行計画とその実行のためにはIT部門のスタッフや外部のIT専門家の助けを借りることも必要になるでしょう。
導入手順と必要なリソース
オンラインストレージの導入手順は大きく分けて、選定、設定、移行の3つのステップに分けられます。選定では、以前の準備で特定したニーズに基づき、最適なストレージを選びます。
設定では、アクセス権やセキュリティ設定などを施し、ストレージを導入可能な状態にします。移行では、データを新たなストレージに移す作業を行います。
導入に必要となるリソースは、主に時間と人材、そして費用です。時間と人材は、移行作業や設定作業に必要となるもので、十分な専門知識をもつ人間が必要となるでしょう。
そして費用は、ストレージの導入費用や運用コスト、問題が発生した際の対応コストなどを考える必要があります。
導入コストとROIの検討
オンラインストレージの導入コストは、提供サービスのプラン、データ量、利用者数により大きく変動します。保守・運用費用や故障時の対応コストも含め、予算設定を怠らないよう気をつけましょう。
また、これらのコスト対策としてROI(投資回収期間)の検討は重要です。ストレージの導入を通じてどれほど効率化やコスト削減が図れるかを計算し、導入による経済効果を確認することが求められます。導入コストを回収出来る時間を意識し、長期的な視点で計画を立てる事が肝要です。
導入後の運用と管理方法
導入後の運用と管理方法は、システムのパフォーマンスを最大限に引き出すための不可欠な工程です。
新たに導入されたシステムが完全に組織内で活用されるためには、適切な運用と管理が必要であります。
それらの方法は、データの保管と整理方法、不正アクセスからの保護策、適切な運用のためのポリシー作成の3つの観点から考えます。
データの保管と整理方法
データの保管と整理は、ビジネスの要となる部分であります。まず、保管方法について、データの保存場所は重要な設定となります。外部のクラウドサービスを利用するのか、社内のサーバーを利用するのかは存外に重要です。
次に、整理方法です。ここでは、データ構造の設計が重要となります。検索性や再利用性を重視した設計にすることで、データの使いやすさが向上し、ビジネスの効率化を実現します。
不正アクセスからの保護策
不正アクセスから自社のシステムやデータを守るための保護策は、セキュリティ対策の一部です。最も基本的な手段として、パスワードの管理が挙げられます。強固なパスワードを設定し、定期的に変更することで、不正アクセスを防ぐことが可能になります。
さらに、防火壁やセキュリティソフトを用いて、外部からの不正アクセスを遮断します。最新のパッチやアップデートをこまめに適用して、システムの脆弱性を減らすことも重要な対策となります。
適切な運用のためのポリシー作成
適切な運用のためには、ポリシーの作成が必要であります。このポリシーは、システムの利用に関する明確なガイドラインやルールを示すものです。
ユーザーの権限管理、ログイン時間、使用可能な機能やサービス、データのアクセスと使用方法についてのルールなど、システムの適切な利用を保証するための具体的な指示が必要となります。
また、システムの変更や更新に伴う情報の共有、問題発生時の対応や報告ルールも明記します。このポリシーによって、システムの運用と管理がスムーズに行えるようになります。
オンラインストレージの法律や規制への対応
昨今のデジタル化の進展とともに、オンラインストレージの使用率が増加しています。
企業や個人が情報を容易に保存し、共有できるツールとして利便性は高いのですが、それと同時に様々な法律や規制への対応も必要となりました。
法律や規制の詳細と、それらにどのように対応すべきかを以下の3つの視点から解説します。
個人情報保護法(GDPR)との関連
2018年に実施されたEUの個人情報保護法(GDPR)は、ユーザーのプライバシー保護制度を大きく変えました。個人情報を扱うオンラインストレージは、この法律に厳しく規制されます。
企業はユーザーの同意を得ること、データの保管方法と管理に関する明確な基準を設けること、さらには問題が発生した際の報告義務を負う必要があります。ユーザーから見れば、個人情報の正確性、アクセス権、削除権などの権利を保証されています。
これらの新しい義務と権利は、セキュリティ体制を見直すだけでなく、ユーザー保護を旨としたビジネスモデルを検討するきっかけともなります。
著作権とオンラインストレージ
オンラインストレージで著作物を共有することは著作権に直接関連します。著作権者の許可なく著作物をアップロードすることは違法とされます。
また、オンラインストレージを使用して違法に著作物を共有・配布する行為も取り締まられます。企業や個人は、被著作権者からの訴訟の危険を避けるため、常に著作権法を遵守することが求められます。
一方、オンラインストレージサービス提供者側も、ユーザーが法を犯すことを防ぐための対策を講じる責任があります。
クラウドストレージの法規制と企業の対応
クラウドストレージは、個人情報保護法や著作権法だけでなく、サイバーセキュリティ法の対象にもなります。企業は自社の情報を安全に保つため、データ保管先国の法律や規制を考慮する必要があります。
また、特に重要な情報を扱う場合、自社内でのクラウド運用規範を設け、従業員教育を実施することで、法規制への対応と情報漏洩リスクの低減を図るべきです。
さらに、企業はデータ転送や保存に際しての暗号化、ユーザー認証、アクセスログの管理など、セキュリティ対策も重視すべきです。
まとめ:オンラインストレージの選び方と導入のコツ
今日の情報量は飛躍的に増加しており、それを保存するための手段としてオンラインストレージが注目されています。
フリーソフトから有料版まで様々なオンラインストレージが存在しますが、ニーズに応じて最適なものを選び、スムーズに導入し続けていくための重要なポイントをまとめていきます。また、事例を通じて具体的な成功のポイントを紐解いてまいります。
ニーズに合わせたベストなストレージの選択
オンラインストレージを選ぶ際、まずは自分自身のニーズを明確にすることが求められます。購入前に必要な容量や機能などを絞り込み、それに見合ったプランを選ぶことが大切です。
たとえば、一人で使用するか、複数人で共有するかでも選ぶべきオンラインストレージは異なります。また、安全性や使いやすさも重要な要素です。一般的な業務用途であれば、データの保管先が法令等に準拠しているか確認することが必要となります。
これらのニーズに合わせて、一つ一つのオンラインストレージの特性を把握し比較していくことが求められます。
スムーズな導入と継続的な運用のために
オンラインストレージの選択が決まったら、次にスムーズな導入とその継続的な運用のための戦略を立てる必要があります。導入の前に運用のポリシーを明確にし、それに基づくルール作りが重要となります。
また、導入にあたっては従業員一人ひとりが問題なく使えるよう教育やトレーニングが必要でしょう。
その後の運用面では、データのバックアップ体制やセキュリティ対策、また万が一の障害時の対応策などを事前に準備することで、スムーズにオンラインストレージを継続して使用することができます。
導入成功のポイントとケーススタディ
オンラインストレージ導入の成功のポイントとしては、前述の適切な選択とスムーズな導入が挙げられますが、それを具体的にするための具体的な事例を挙げて考察してみましょう。
たとえば、ある企業が導入した際、ユーザーニーズをデータに基づいて把握し、それに合ったストレージを導入した事例があります。
この結果、従業員たちが効率よくストレージを使いこなし、業務効率のアップにつながりました。このような成功事例から学ぶべきは、やはりニーズに合わせた導入と適切な教育が成功の鍵となるということです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営
ニュース -
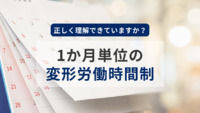
1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?
ニュース -
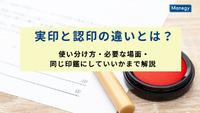
実印と認印の違いとは?使い分け方・必要な場面・同じ印鑑にしていいかまで解説
ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説
ニュース -

採用を「運」から「設計」へ変える――役割貢献制度で実現する、ミスマッチゼロの要件定義とは?
ニュース -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

生成AI導入の鍵はデータ整備|RAG精度を高める運用設計の極意
ニュース -
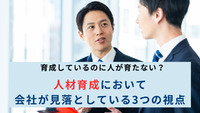
育成しているのに人が育たない?人材育成において会社が見落としている3つの視点
ニュース -

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説
ニュース -
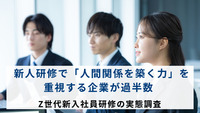
新人研修で「人間関係を築く力」を重視する企業が過半数 Z世代新入社員研修の実態調査
ニュース -

契約書のコンプライアンスチェックとは? 独禁法・2026年施行「取適法」・反社条項の論点とAI活用
ニュース