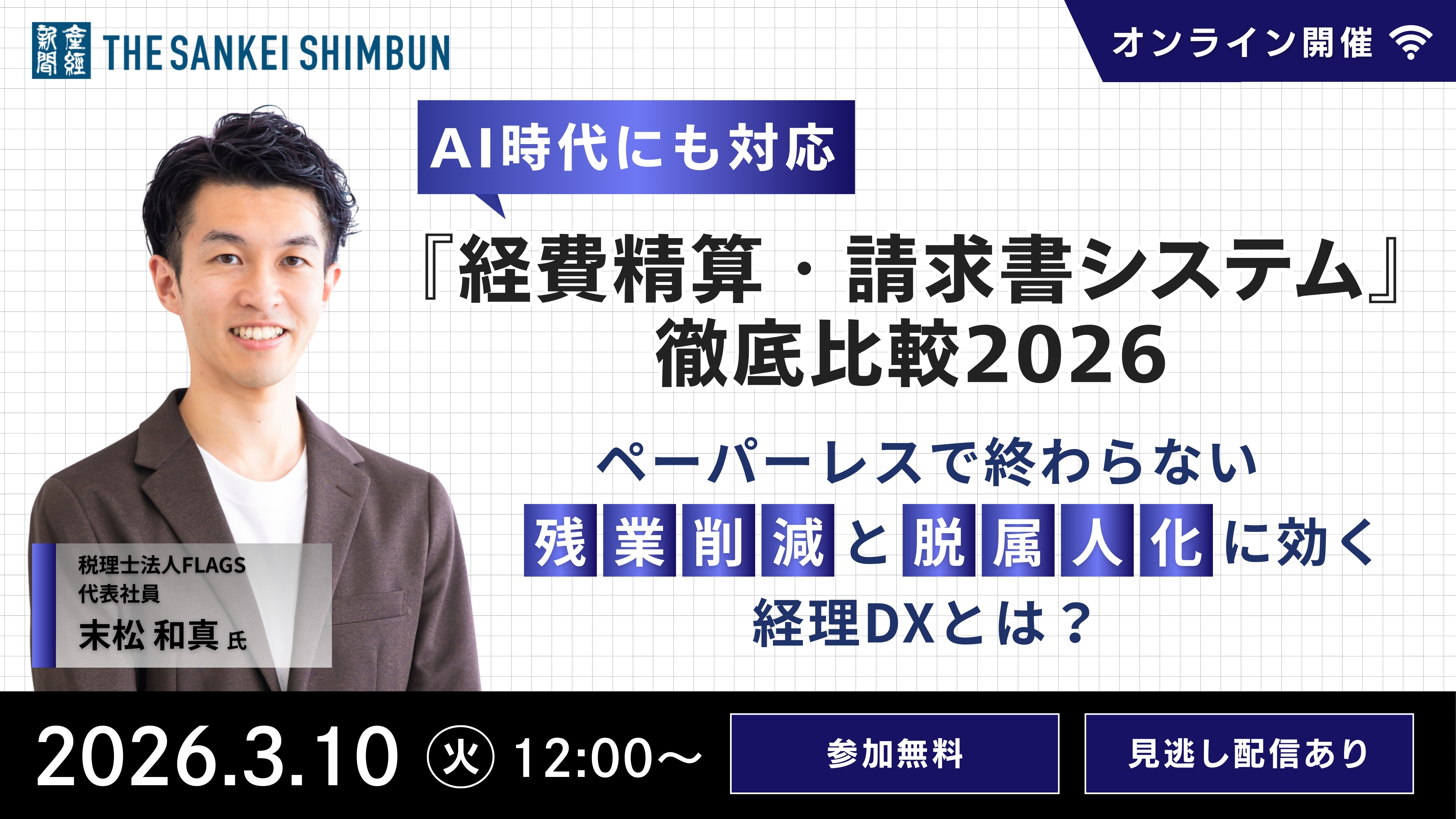公開日 /-create_datetime-/
高すぎるモチベーションは問題?学習意欲を最適な状態に保つ方法とは
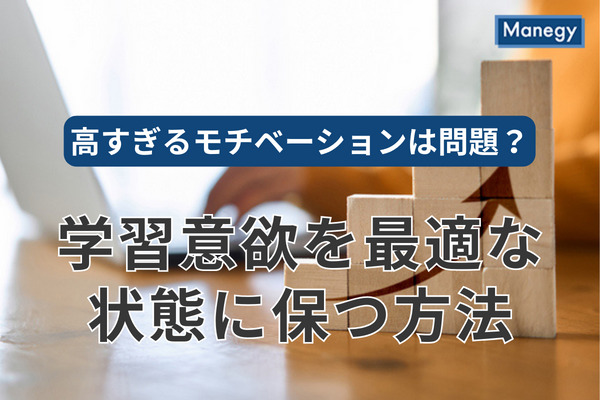
近年、リスキリングの浸透などに伴い、社会人が学習を行う機会も増えてきました。忙しい中で勉強時間を確保するには、モチベーションを高く維持する必要があるでしょう。
一方で学習意欲が高すぎると逆に成果が上がりにくくなるというデータもあることをご存じでしょうか?
本記事では学習のモチベーションと学習成果の関係や適切な緊張状態などについてご紹介します。
学習意欲の変化と動機付け
何かを学ぶ際の学習意欲やモチベーションは、些細なことで大きく変化します。たとえば、毎日勉強を続けていたのに、1日空いてしまっただけで急にやる気が下がり、それ以降勉強をやめてしまうといったケースもあります。一方で、同僚の資格取得や成功の話を聞き、急に勉強を始める気になるという経験をしたことがある人もいることでしょう。
また、学習意欲を高い状態でキープすることは非常に難しいのも事実です。一度やる気になっても、時間が経てば次第にモチベーションは低下していってしまいます。
定期的に動機付けを行い、好奇心や向上心を刺激することが長期的なモチベーション維持においては非常に重要です。
ヤーキーズ・ドットソンの法則から見る最適な緊張状態
学習意欲やモチベーションは高いに越したことはないのですが、高ければ高いほどいいのかといわれれば、実はそうではありません。適度なレベルでモチベーションを維持していくことが大切なのです。動機付けのレベル(学習意欲)と、成果の関係を表したものに「ヤーキーズ・ドットソンの法則」というものがあります。
ヤーキーズ・ドットソンの法則の法則によれば、物事を行う上で極端に意欲が低かったり、緊張感がなかったりすると最大限のパフォーマンスは発揮されません。また逆に、極度に高い緊張感がある状態でもやる気やパフォーマンスが下がってしまうといわれています。
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格試験を考えている社会人を例にとって考えてみましょう。
「毎日3ページくらい参考書を読むだけでいいか」と考えている、意欲の低い人が試験に受かりにくいのは想像にかたくないと思います。
一方で、事前知識のない人が「3日間の勉強で3級に合格する」「3級を飛ばして1級に一発で合格する」など、難しい目標を立ててしまうと、良い結果を得にくいのです。これは、モチベーションによって実行が難しい計画を立ててしまったり、必要以上にプレッシャーを感じたりするためだと考えられています。
学習意欲が低すぎる場合の注意点
学習意欲が低すぎる場合、集中力の欠如による勉強効率の低下が成果の出ない主な原因です。「なぜこれを学習する必要があるのか?」など、最終的な目標から見直すことでモチベーションの向上を図りましょう。
学習意欲が高すぎる場合の注意点
学習意欲が高すぎるケースでは、勉強によって「結果が出せるかな」と不安を感じやすくなったり、うまくいかなかった際の焦燥感が強くなったりすることでパフォーマンスが低下します。“適度”なストレッチ目標をもつということは学習において非常に大切でしょう。
モチベーションを適切なレベルで維持していくために
ヤーキーズ・ドットソンの法則を参考に、「学習意欲やモチベーションには最適な範囲がある」という結論を導きました。それでは、モチベーションを最適な範囲で保つにはどうすればよいのでしょうか?
以下に、適切なモチベーションを維持するための対策をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
いきなり高すぎる目標を設定しない
学習意欲が高い人が陥りがちな失敗傾向の1つに「いきなり高い目標を設定する」というものがあります。たとえば、Webデザインの勉強を始めたばかりなのに「副業で1件100万円の案件を獲得する」という目標を掲げるといったようなことです。
目標が高いことは決して悪いことではありません。しかし、自分の力量に見合わない目標だけを掲げると成長を実感することが難しく、結果として学習成果も低調なものになってしまう傾向にあります。
程よい緊張感や学習意欲を継続させるためには、「現在の自分が少し努力したら達成できる目標」を設定する必要があります。そのためには、まず自分の現状を正しく理解する必要があるでしょう。
学んだことを実践できる機会を設ける
学習した内容を実践する機会を設けるのも大切です。
勉強していることに関する仕事を社内で回してもらってもいいですし、会社から副業が認められているのなら、クラウドソーシングで安い案件を請け負うこともできます。 実践によって学習内容の定着が確認を実感することができれば、モチベーションの低下を防ぐことができるでしょう。
まとめ
近年、社会人の学習が注目されるようになってきましたが、学習内容を効果的に定着させるためには、適度なモチベーションを維持する必要があるとされています。モチベーションが低すぎる場合はもちろん、高すぎる場合でもパフォーマンスが低下する傾向があるとわかっているからです。
適切な目標を定める、学習内容を実践できる場を設けるなどを意識して、最大の学習成果を発揮できる範囲でモチベーションを維持することを心がけましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -
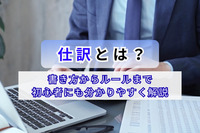
仕訳とは? 書き方からルールまで初心者にも分かりやすく解説
ニュース -

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説
ニュース -
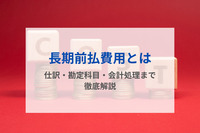
長期前払費用とは|仕訳・勘定科目・会計処理まで徹底解説
ニュース -
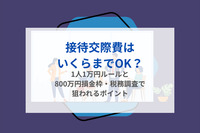
接待交際費はいくらまでOK?1人1万円ルールと800万円損金枠・税務調査で狙われるポイント
ニュース -
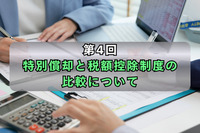
第4回 特別償却と税額控除制度の比較について
ニュース -
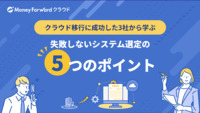
クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント
おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に
ニュース -

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応
ニュース -

税制適格ストックオプションとは?メリットや要件、導入時・会計時の注意点
ニュース -
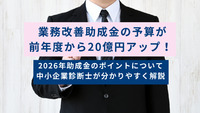
業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説
ニュース -
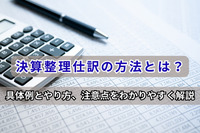
決算整理仕訳の方法とは?具体例とやり方、注意点をわかりやすく解説
ニュース