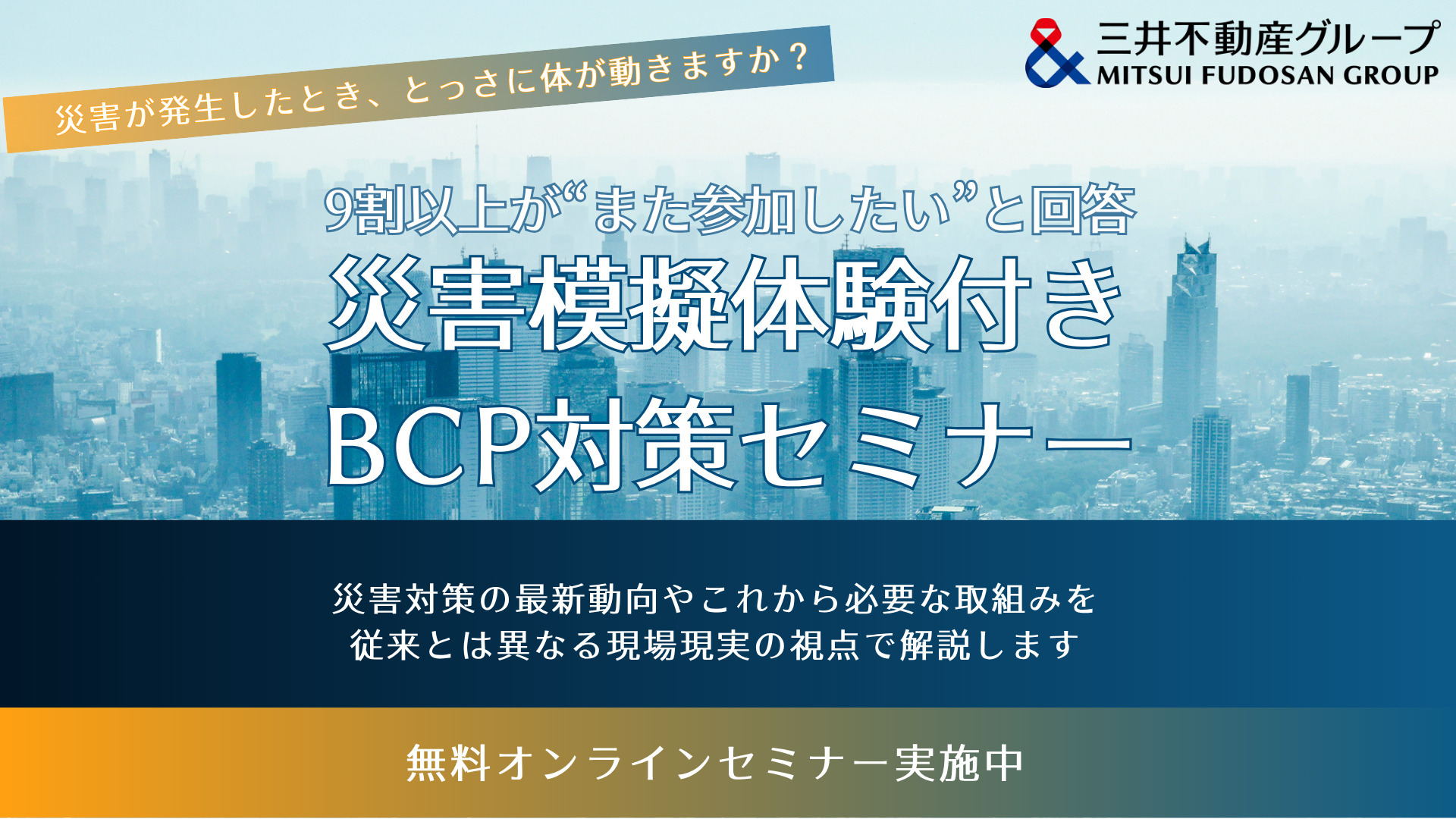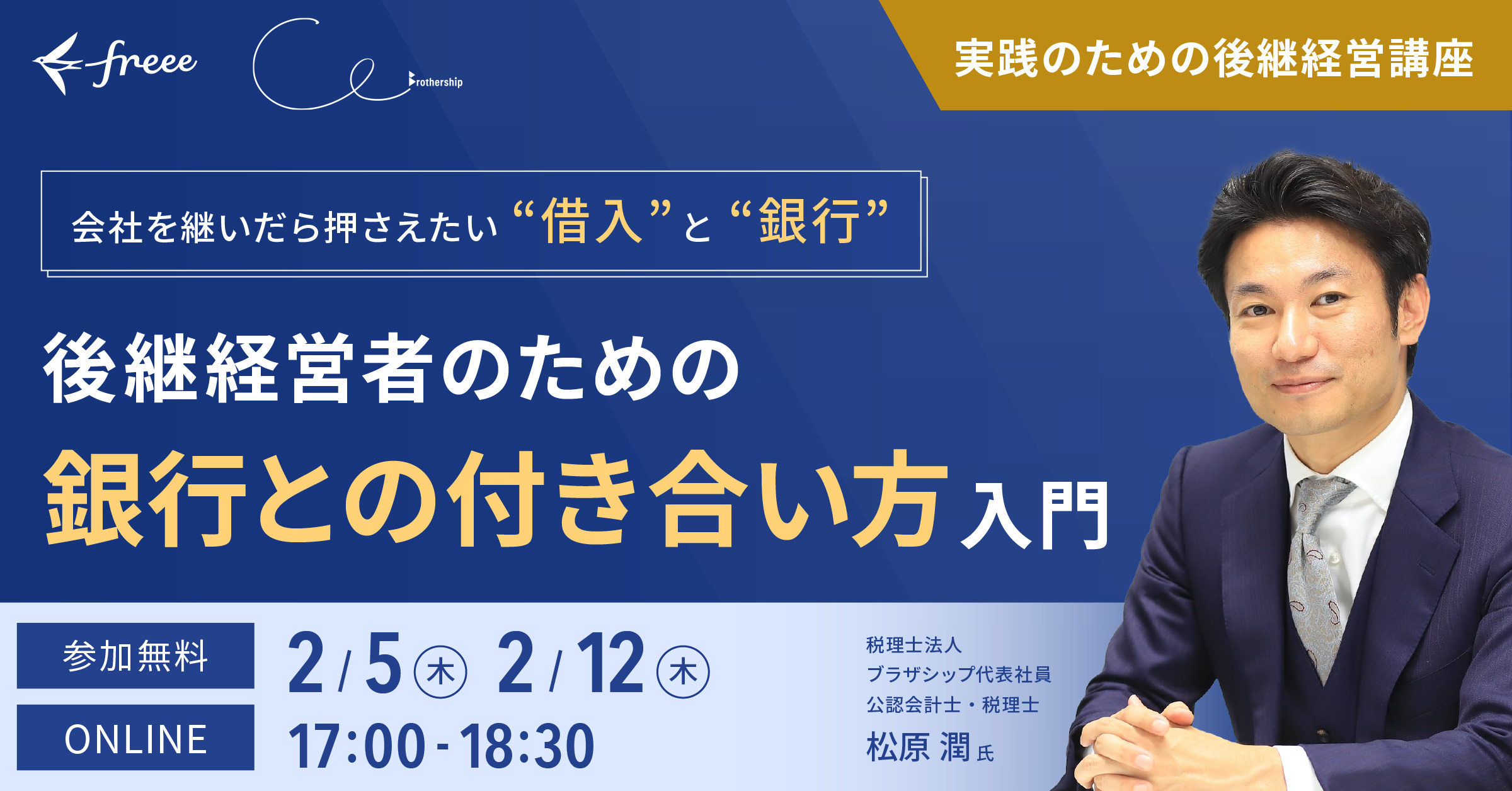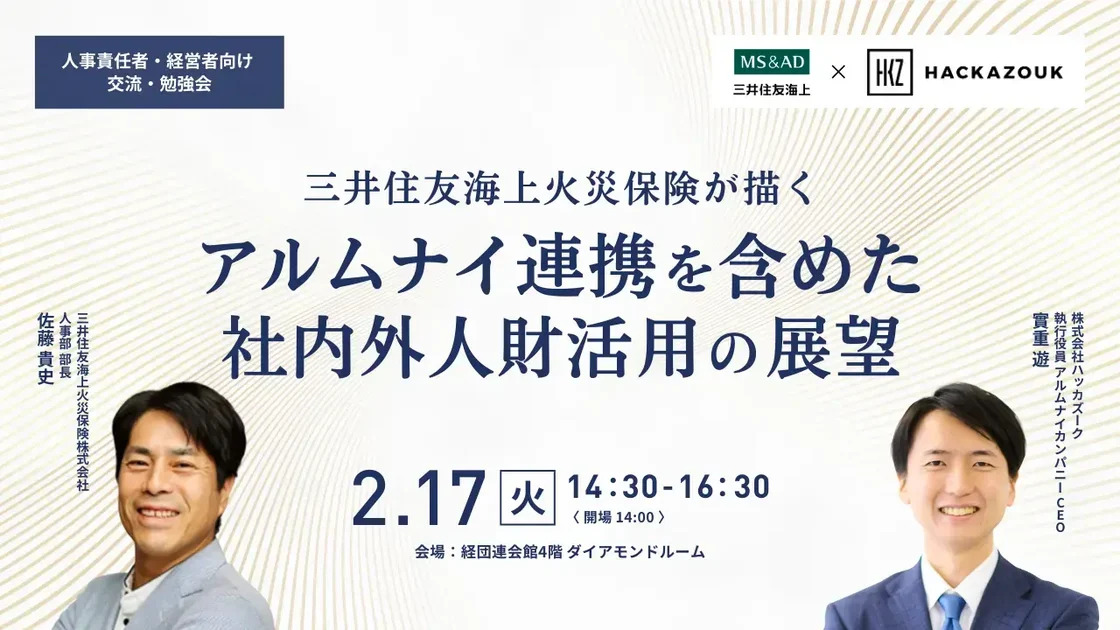公開日 /-create_datetime-/
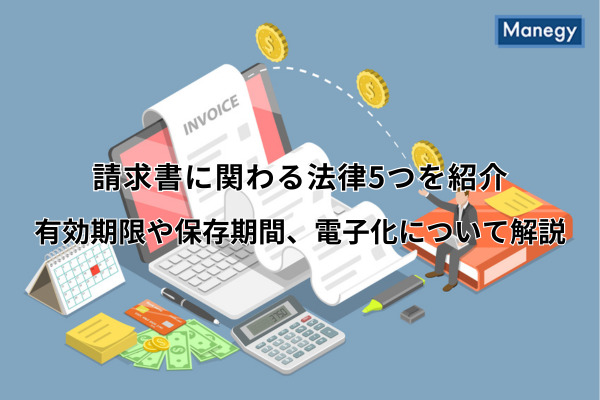
ビジネスで使用される「請求書」ですが、請求書に関する法律について、完全に理解せずに取り扱っている方も多いでしょう。
普段請求書を作成する際にも、以下のように感じることもあります。
「有効期限はあるのか」
「どれくらい保管すればいいのか」
この記事では、請求書に関係する法律を紹介し、有効期限や保存期間、電子化についてもあわせて解説していきます。
今までなんとなく作成していた請求書のルールを知ることで、請求書の発行や管理の業務を効率化できるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次【本記事の内容】
請求書に関する知っておきたい5つの法律
請求書は売買や契約などの取引において、金銭の支払いや受け取りを証明する重要な書類です。
ビジネス上で重要な役割の請求書には、以下の5つの法律が関係します。
●民法
●消費税法
●法人税法
●所得税法
●電子帳簿保存法
請求書に関する法律を知ることで、法的なトラブルを解決できるかもしれませんので、ぜひお読みください。
1.民法|請求書の有効期限についての法律
民法には、請求書の有効期限について書かれています。
改正民法第百六十六条(再検討の消滅時効)の一項一号には、有効期限が以下のように記載されています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
民法において請求書は「債権」と捉えられており、有効期限は5年間となります。
有効期限以上の期間が経ってしまうと、請求書は法的効力を失ってしまいます。
請求書の発行から5年以上支払いがされていない場合は、支払わなくてもよいと法律上定められているのです。
取引先とのトラブルを避けるためにも、請求書の有効期限はしっかりと把握しておく必要があります。
2.消費税法|仕入税控除についての法律
消費税法は、請求書と税徴収に関して記載されています。
特に消費税法で注目したいのは、仕入税額控除についてです。
仕入税額控除は、仕入に対してかかる消費税を差し引くことを指します。
消費税は商品やサービスの取引に対して税が課せられるため「仕入」と「売上」に対して、税金を支払うこととなります。
参考:消費税法(昭和六十三年法律第百八号)|e-Gov法令検索
取引先から請求書が届かない場合、本来支払う必要のない仕入分の消費税も払わなくてはいけなくなります。
仕入税額控除を利用する際に、請求書が必要になるのです。
取引先に損失を与えないためにも、請求書は必ず発行するようにしましょう。
3.法人税法|法人の請求書保存についての法律
法人税法は、会社の請求書の保存期間について記されている法律です。
法人税法によって、確定申告の提出期限の翌日から7年間は請求書の保存が必要だと定められています。
参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法|国税庁
請求書の起算日は作成日ではなく、確定申告の翌日から数えます。
たとえば、2023年度に発行された請求書は、確定申告の提出期限の翌日である2024年3月16日から7年間の保存が必要です。
また、欠損金の繰越控除を利用する場合は、保存期間が7年から10年に延長されます。
欠損金の繰越控除とは、各事業年度の赤字分を翌年の利益から控除する仕組みで、利用することで、法人税の負担を軽減できます。
自社の営業利益によって保存期間が変わるという点にも注意が必要です。
4.所得税法|個人事業主・フリーランスの請求書保存についての法律
所得税法は、個人事業主やフリーランスの請求書の保存期間に関する法律です。
所得税法第六十三条によると、個人事業主やフリーランスも、会社と同様に、発行したり受け取ったりした請求書を保存しなければなりません。
参考:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)|e-Gov法令検索
請求書の保存期間は、確定申告の提出期限から5年間です。
ただし、消費税課税事業者の場合は、法人と同様の7年間となります。
起算日についても法人と同様で、確定申告の提出期限の翌日から5~7年間の保管が必要です。
2023年度に発行された請求書は、2024年3月16日を起算日として保管しましょう。
請求書が多くあって場所を取るからといって捨ててしまうと、法律違反になってしまいます。
5.電子帳簿保存法|電子データで作成した請求書についての法律
電子帳簿保存法は、電子データで作成した請求書に関する法律です。
法人や個人、事業規模に関係なく、請求書を保存する義務のある人全員が対象となっています。
電子帳簿保存法は以下の3つの保存法に分け、それぞれの保存方法ごとにルールを定めています。
●電子帳簿保存
●スキャナ保存
●電子取引データ保存
電子帳簿保存は、自社で電子データで作成された帳簿を、社内で保存することを指します。
スキャナ保存は紙で発行された書類をスキャンし、電子データで保存することです。
電子取引データ保存は、電子データで受領した書類を、自社内で保存することを指します。
保存方法ごとに対象となる書類が異なりますが、請求書はすべての電子帳簿保存法の対象となります。
請求書の電子データ化に関する法律の変更内容
2022年1月に電子帳簿保存法は改正され、電子化を促すために要件の緩和が進められました。
具体的な変更点は以下のとおりです。
●電子データの保存方法の変更について
●タイムスタンプ付与の変更について
●税務署長からの承認手続きの変更について
電子帳簿保存法の変化に対応できるように詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
電子データの保存方法の変更について
2024年1月以降、請求書を電子データで受け取った際、電子データのまま保存しなくてはいけません。
取引先から電子データで請求書をもらった場合、プリントアウトし、紙で保存していた企業も多いでしょうが、今後は電子データのまま保存できる方法を整える必要があります。
ただし、やむを得ない場合のみ2024年以降も紙に出力して保存してもよいことになっています。
タイムスタンプ付与の変更について
従来「3営業日」以内に付与しなければならなかったタイムスタンプですが、改正により「2ヶ月と概ね7営業日以内」まで大幅に延長されました。
タイムスタンプとは、付与された時間に電子データがあったことを証明する、電子版のハンコを指します。
タイムスタンプを押すことで、データの改ざんがないことを証明できるのです。
取引先の請求書を電子データで受け取る体制が整いやすくなったため、電子データでの発行もしやすくなりました。
税務署長からの承認手続きの変更について
従来、電子データの請求書を保存する場合、事前に税務署長の承認が必要でしたが、改正により事前承認が不要とされました。
事業者にとっても事務作業の負担がかかる作業であったため、電子データでの取引への対応が取りやすくなりました。
従来以上に電子データでの請求書発行が簡単になり、請求書発行にかかる負担を軽減できるのです。
請求書について法律の観点から知っておきたいこと3選
法律の観点から知っておきたいことについて、以下の3つを解説します。
●法律上の発行義務はない
●有効期限がある
●保存期間がある
請求書の効果や性質を知っておくことで、適切に作成や管理ができるようになりますので、参考にしてみてください。
法律上の発行義務はない
請求書の発行は法律上義務付けられていません。
法的な効力はありますが、発行しなくても罰せられることはありません。
ただし、義務がないからといって業務負担の軽減のために請求書の発行をしないのはやめましょう。
発行する側に義務はなくとも、受け取る側にとっては大きな問題となってしまうためです。
消費税法における「仕入税額控除制度」を利用する際に請求書を必要とするため、請求書が発行されない場合、消費税を二重に払わなくてはいけなくなります。
取引先との不要なトラブルを避けるためにも、請求書は発行するようにしましょう。
また、発行するタイミングについては下記の記事で詳しく紹介しますので、参考にしてみてください。
有効期限がある
請求書には5年の有効期限が定められています。
2020年の民法改正までは債権の有効期限は2年と定められていましたが、現在では5年まで延長されています。
ただし、2020年4月1日以前に作成された請求書の有効期限は2年までなので、気を付けましょう。
請求書に有効期限が認められている理由は、民法において請求書は「債権の一種」とみなされるためです。
何かしらの事情で取引先から支払いがなかった場合でも、請求書を発行しておくことで、債権を行使できます。
リスクヘッジのためにも、請求書は発行しておくようにしましょう。
また、実際に支払いが行われない場合は、内容証明郵便による支払い催促を先方に送ることで、有効期限を6ヶ月延長できます。
参考:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
内容証明郵便は郵便局の制度のひとつで、どのような内容の文書が誰に送られたのかを証明できます。
保存期間がある
個人事業主やフリーランスの方は一年間の課税売上が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
また、インボイス発行事業者に登録した場合も課税事業者となるため注意が必要です。
請求書を作成したほうがよい法律上の理由2つ
請求書を作成したほうがよい法律上の理由を2つご紹介します。
●契約上のリスクヘッジのため
●仕入税額控除の適用のため
理由を具体的に把握することで、請求書作成でトラブルが起きないよう意識的に取り組めるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。
契約上のリスクヘッジのため
請求書は、契約上のリスクヘッジのために重要な役割を果たします。契約は口約束だけではなく、書面で証拠を残すことが大切です。
とくに金銭のやりとりが発生する場合は、金額や支払い期日などを明確に記載した請求書を発行することで、取引先との契約や税務調査の際に生じるトラブルを避けられます。
たとえば、正しく請求書を発行していない場合、帳簿と実際の金額が合わず、架空請求を疑われる可能性があります。
万が一トラブルが生じてしまい、自社に損失が生じる際には、法律にのっとった解決方法ができるのです。
請求書は、法的な根拠のある有力な証拠となるため、必ず発行するようにしましょう。
仕入税額控除の適用のため
請求書は仕入税額控除の適用のために必要です。
課税事業者は消費税法にもとづいて消費税を納める義務がありますが、仕入税額控除を受けられます。
しかし、仕入税額控除を受けるためには、仕入先から正式な請求書を受け取る必要があります。
たとえば、自社から100万円分の仕入れをしている取引先がその商品を120万円で販売している場合、取引先の売上の120万円にかかる消費税は以下のとおりです。
120万円×10%(消費税率)=12万円
自社では100万円分の売上が発生しているため、消費税は以下のとおりになります。
100万円×10%(消費税率)=10万円
仕入税額控除を利用すると、自社で支払っている消費税が控除されるため、取引先の支払う消費税は以下のとおりになります。
12万円ー10万円=2万円
請求書が発行されないと、取引先は自社の売上分の消費税も負担しなければなりません。
取引先へ迷惑をかけないためにも、請求書の発行をおすすめします。
請求書と各書類との法律的な違い
ビジネスで使用する書類には、請求書のほかにも以下の3つがあります。
●見積書
●領収書
●支払通知書
各書類の請求書との法律的な違いについて解説しますので、ビジネスで必要な書類について理解したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
見積書
見積書は、売買契約を結ぶ前に商品やサービスの内容や価格を提示するものです。
見積書には法的効力はありませんが、商慣習として発行されています。
しかし、見積書は契約の申し込みとみなされることもあるのです。
たとえば、見積書を提示し相手が同意した場合、契約が成立して見積書が契約書の代わりとなります。
見積書を作成する際には、内容や価格が明確であることや、有効期限やキャンセル条件などを記載することが重要です。
領収書
領収書は、売買契約の代金を受け取ったことを証明する文書です。
以下の4項目が記載されていることで法的効力を持ちます。
●発行日時
●金額
●但し書き
●発行者名
参考:No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁
経費精算を行う際に使用される領収書ですが、上記が記載されていればレシートでも代用可能です。
ただし、企業によっては、レシートが不可となっている場合もあります。
領収書は請求書とは異なり、支払いを確認するための書類なので、請求書の代わりになるものではありません。
支払通知書
支払通知書は、売買契約の代金を支払ったことを通知する文書です。
請求書は受注者から発注者へ発行されるものですが、支払通知書は発注者から受注者へ「支払いを行う」と通知する役割があります。
支払通知書は請求書と同じく法的効力を持ち、請求書の代わりとして用いることが可能です。
支払通知書は発行義務はありませんが、相手から請求された場合や、自分で記録したい場合に発行します。
請求書を発行できない場合は、先方へ支払通知書の発行を依頼するのもひとつの手段です。
請求書の作成で法律的に記載したほうがよい項目
請求書の作成で法律的に記載したほうがよい項目を、以下の9つ紹介します。
●題目
●発行者
●請求先(宛名)
●取引内容
●請求金額
●発行年月日
●振込先
●支払期日
●インボイス制度で必要となる記載項目
上記の項目は、消費税法や民法などの法令にもとづくものです。
請求書の作成で法律的に記載したほうがよい項目を把握しておくことで、正しい請求書を作成し、取引先との信頼関係を築けるでしょう。
適法な請求書の要件や必要事項を詳しく知りたい方は、国税庁のサイトでも確認できます。
1.題目
題目とは、請求書の一番上に記載する文言です。
基本的には「請求書」と記載することが一般的です。
しかし、再発行した場合は、最初に発行したものと区別できるよう「請求書(再発行)」と記載しましょう。
同じ内容の請求書が重複して発行されている場合は、税務調査でトラブルになる可能性もあるためです。
2.発行者
発行者とは、請求書を発行する側の名称や氏名です。
法人の場合は法人名を、個人事業主やフリーランスであれば個人名を、屋号とあわせて記載します。
住所や電話番号は必須ではないため、記載する必要はありませんが、連絡先として記載しておくと便利です。
法人の場合は部署名や担当者名を記載するケースもあります。
3.請求先(宛名)
請求先とは、請求書を受け取る側の名称や氏名です。
発行者と同様に、取引先の部署名や屋号もあわせて記載しましょう。
法人宛てに送る際は「御中」や「様」の使い分けについても注意が必要です。
「御中」は法人や団体に対して、「様」は個人に対して使います。
「御中」と「様」は併用できないため「○○社 △△部 御中」や、「○○社 △△部 ××様」と記載するようにしましょう。
4.取引内容
取引内容とは、商品やサービスの詳細を記載する項目です。
以下の項目を具体的に記載します。
●商品名
●数量
●単価
●金額
項目が多い場合は、数量を「一式」とまとめる方法もあります。
ただし、内容が具体的に分からなくなってしまうため、ある程度の信頼関係が構築されている取引先以外は、正確な数字を記載しましょう。
5.請求金額
請求金額とは、取引内容の合計金額を記載する項目です。
消費税を含めた税込金額で記載することが必要です。
また、区分記載請求書や的確請求書では、消費税の税率ごとに合計した金額を明記する必要があります。
たとえば、請求額が10,000円の場合は以下のように記載しましょう。
請求金額 10,000円(8%対象 5,000円 10%対象 5,000円)
上記のように記載することで、請求金額におけるトラブルを減らせます。
6.取引年月日
取引年月日とは、商品やサービスの売買を行った年月日を記載する項目です。
請求書の発行日ではないため、注意が必要です。
たとえば、4月15日に取引が完了し、請求書を4月30日に作成する場合は以下のとおりになります。
●取引年月日:4月15日
●請求書の発行日:4月30日
日付によって消費税額が変わる際、取引年月日が消費税の課税時期を決める基準となるため重要な項目となります。
また、日付の記載時は「2023年4月15日」や「2023/4/15」など、年月日の書き方についても統一性を持たせると、取引先も見やすくなります。
7.振込先
振込先とは、支払いを受け取る銀行口座を記載する項目です。
主に以下の内容を明確に記載します。
●銀行名
●支店名
●口座番号
●口座名義
支払いの際に振り込み間違いやトラブルを防ぐためです。
振込手数料の負担者も明記しておくとよいでしょう。
8.支払期日
支払期日とは、支払いを完了させるべき日付を記載する項目です。
支払期日を設定することで未払いや支払遅れなどのトラブルを防ぐ効果もあります。
支払期日の設定については、取引先と事前に合意しておくことが重要です。
支払方法や遅延利息なども明記することで、より支払われる可能性が高くなります。
9.インボイス制度で必要になる記載項目
2023年10月に導入されるインボイス制度にあわせて、請求書の必要な記載項目が変わります。
インボイス制度で必要になる記載項目は以下のとおりです。
適切な請求書を発行しないと適格請求書として認められないため、記載項目に注意して作成しましょう。
インボイス制度で必要になる記載項目を確認しておくことで、開始後に備えられます。
まとめ
請求書には、法律上の発行義務はありません。
しかし、取引先との契約上のリスクヘッジや、仕入額控除を利用するためにも必ず発行しましょう。
また、法律には請求書の有効期限や保存期間についても定められています。
それぞれに関する法律を理解し、正しい対応をしていく必要があります。
目まぐるしく変わる法律の中での請求書の発行や保存業務は、人的なコストのかかる作業です。
また、トラブルを回避するために、正確性も求められます。
正確な請求書作成や請求書に関するトラブルでお困りの方は、請求書発行システムの導入を検討してみてください。
時間や労力を削減し、請求書の作成・保存が容易に行えるようになります。
電子帳簿保存法の要件を満たした保存方法や、インボイス制度に合わせた要件の作成も可能です。
マネジーでは複数社の請求書発行システムの資料を用意していますので、導入を検討している方は下記から請求してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -
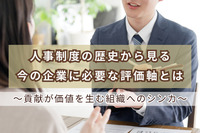
人事制度の歴史から見る今の企業に必要な評価軸とは ~貢献が価値を生む組織へのシンカ~
ニュース -
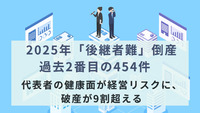
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える
ニュース -

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~
ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>
ニュース -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -
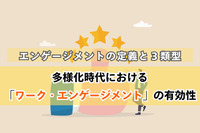
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
ニュース -
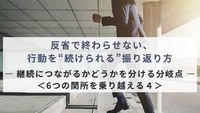
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース