公開日 /-create_datetime-/
管理部門・士業の学びに役立つ『Manegy Learning』
キャリアアップ・スキルアップのために実務能力アップや資格取得を目指しませんか? 管理部門・士業の学びはManegy Leaningで完結!サイトはこちら>>
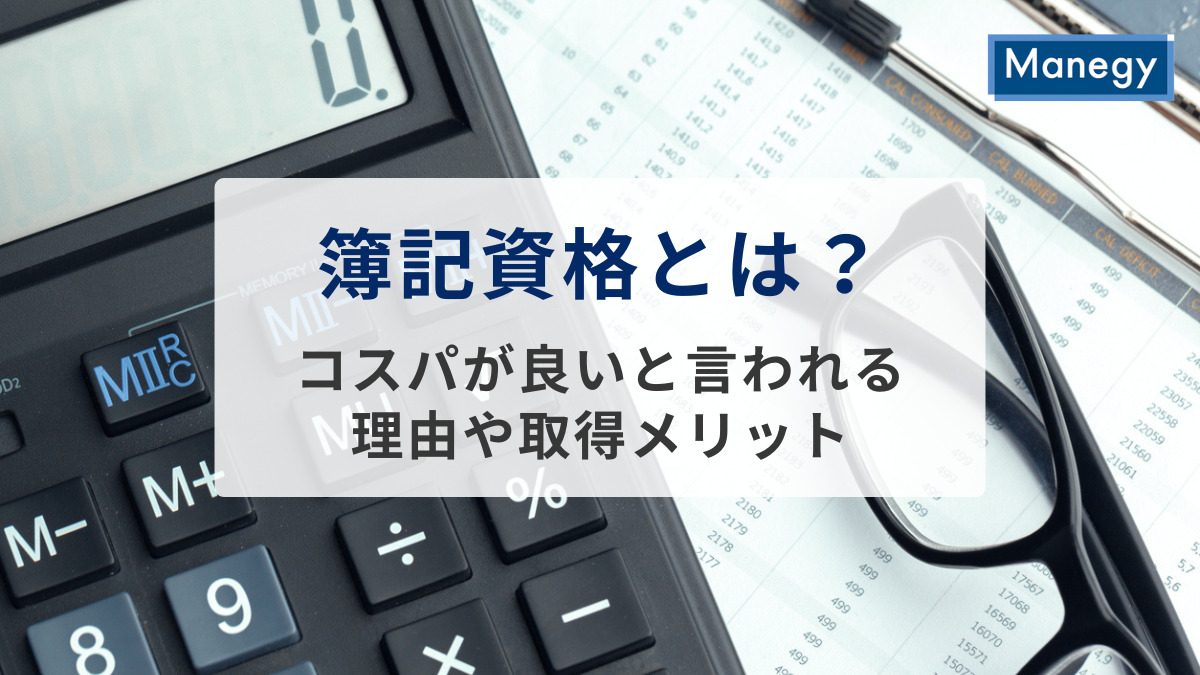
東京商工会議所によれば、簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能であり、この習得度を測るのが、日商簿記検定試験、と定義されています。
簿記資格には主に以下の3種類があり、それぞれ試験の特徴や対象者が異なります。
最も知名度が高く、企業での評価も高いです。3級から1級までの段階があり、経理・財務職を目指すなら2級以上の取得が推奨されます。
内容としては、3級は商業簿記、2級は3級以上に高度な商業簿記の知識と工業簿記、1級は商業簿記・工業簿記、プラスアルファ会計学や原価計算といった構成です。
企業実務向けの資格で、初級から上級まで幅広いレベルがあります。上級合格者は税理士試験の受験資格を得ることができます。
主に高校生向けの資格です。商業高校などでの学習に組み込まれており、将来的に日商簿記や全経簿記へステップアップしやすい傾向があります。
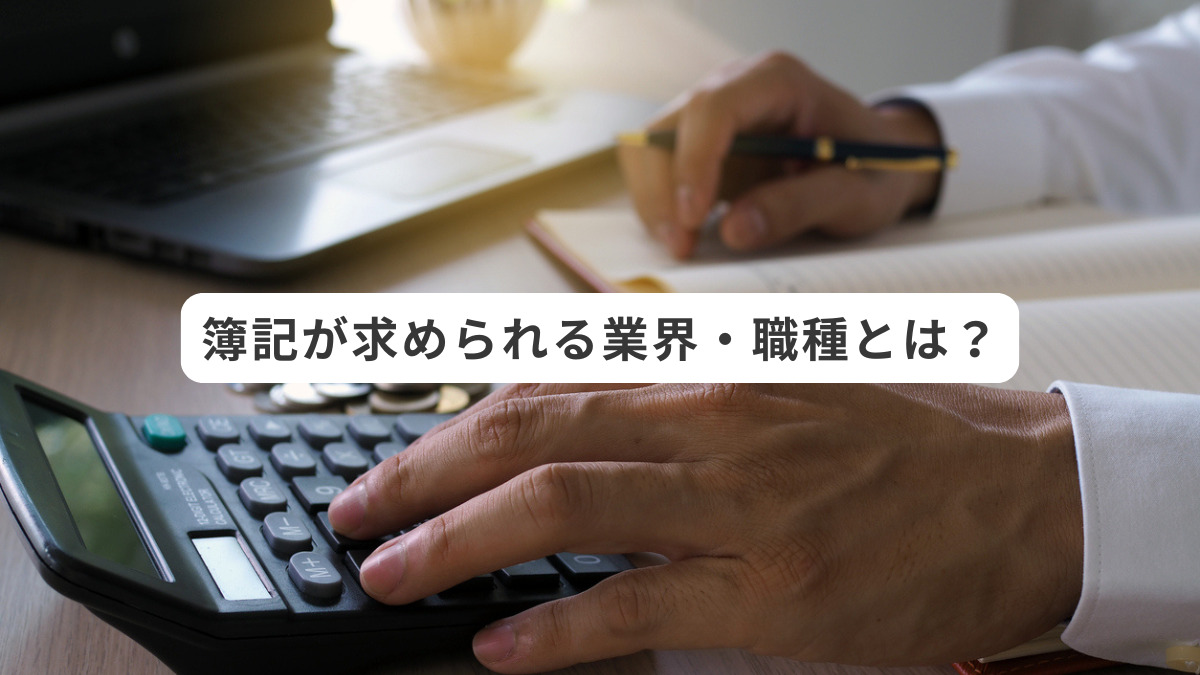
簿記の知識は、経理・財務職をはじめ、幅広い業界・職種で求められます。
企業のお金の流れを管理する重要なポジションで、就職や転職時には簿記2級以上を取得していると評価に繋がることもあります。
企業の利益やコストを理解し、戦略的な提案を行うために簿記の知識が役立ちます。
自身の事業の会計管理や確定申告に簿記の知識が不可欠です。
企業の財務諸表を正しく読み解くスキルとして活用できます。
簿記はどの業界でも活かせる普遍的なスキルのため、キャリアアップやスキル向上を考える人にとって、コストパフォーマンスの高い資格といえます。
複式簿記と単式簿記は、それぞれ独自の会計手法であり、ビジネスの規模や法的要件に応じて使い分けられます。以下に主な違いを説明します。
複式簿記
複式簿記は、企業の財務状況をより詳細に把握するための会計システムです。この方法では、取引ごとに少なくとも二つの勘定科目が関連し、一方が借方(デビット)、もう一方が貸方(クレジット)として記録されます。これにより、資産、負債、資本、収益、費用の各科目が正確に管理され、会計のバランスが保たれます。
・二重記帳
各取引は借方と貸方の両方に記録されるため、会計の精度が向上します。
・財務報告
損益計算書、貸借対照表など、詳細な財務報告が可能です。
・管理会計
企業の経営分析や意思決定に役立つ情報を提供します。
単式簿記
単式簿記は、主に小規模企業や個人事業主が利用するより簡単な会計システムです。この方法では、取引を一つの勘定科目にのみ記録し、主に収入と支出の流れを追跡します。
・単一記帳
取引が一方の勘定のみに記録されるため、記帳は簡単ですが、情報は限定的です。
・財務報告の制限
貸借対照表のような複雑な報告書は作成されず、主に現金出納帳が用いられます。
・簡易管理
資金の流れの基本的な追跡には適していますが、複雑な財務分析には向きません。
用途による選択
・大企業や中規模企業
法律や規制で複式簿記が要求されることが多く、財務の透明性や精度を高めるために適しています。
・小規模企業や個人事業
単式簿記で十分な場合が多く、運用の手軽さが求められる場合に適しています。
適切な会計方法の選択は、ビジネスの規模、業界の要件、および管理上の必要性によって異なります。
【簿記3級】
試験合格率 :30~50%
勉強時間目安:合計100時間程度
勉強時間が1日に3~4時間であれば1か月程度で学べる範囲
受験料 :<2024年3月31日までの受験分>2,850円(10%消費税込金額)
<2024年4月1日からの受験分>3,300円(10%消費税込金額)
※事務手数料550円(10%消費税込)が別途発生します。
【簿記2級】
試験合格率 :20~30%
勉強時間目安:独学なら250~350時間程度、通学・通信講座で150~250時間程度
簿記2級からは簿記3級にはない工業簿記が科目に追加されるため、簿記3級として簿記2級の難易度は上がります。
期間は4~6か月程度必要となり、簿記3級よりもしっかり勉強に取り掛かる必要がある。
受験料 :<2024年3月31日までの受験分>4,720円(10%消費税込金額)
<2024年4月1日からの受験分>5,500円(10%消費税込金額)
※事務手数料550円(10%消費税込)が別途発生します。
【簿記1級】
試験合格率 :10%程度
勉強時間目安:独学なら1,000~2,000時間、通学・通信講座でも500~800時間程度
簿記1級は簿記2級に会計学や原価計算が追加されるため、難易度がさらに上がる。
期間は10カ月以上が必要となり、勉強を始めた翌年の試験を受験することがおすすめ。
受験料 :7,850円(税込)
※事務手数料550円(10%消費税込)が別途発生します。
一般的には簿記2級以上が取得できていると評価につながりやすいとされています。 またスケジュールについて、3級と2級は年3回試験がありますが、1級のみ年1回の試験開催です。
では本題である、“簿記資格はコスパが良い”と言われる理由について解説します。 ビジネス上では、会社員であればスキルの向上やキャリアアップのチャンスになり、自営業でも経営に必要な知識であることが大きな理由です。 また、投資や日常生活でも活かせるなど、1つの知識で様々な物事に活かせることが「コスパが良い」とされるわけだと言えます。
得られることとして、具体的には、
などのメリットがあります。
加えて、企業によっては資格手当もあるため、思わぬ臨時収入を得られる可能性もあります。 自社に資格手当が適用されているか不明な方は、自社の就業規則の賃金規定を確認してみてください。
「簿記は経理が取得する資格」というイメージも強いですが、実際簿記2級以上を保有しているか否かで、就職・転職時に経理ポジションで応募できる領域が変わります。 特に実務未経験で経理を志望する場合は、簿記2級以上を取得しておくことが望ましいでしょう。

| 実施日 | 試験実施級 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 第170回 2025年6月8日(日) | 1級・2級・3級 | 7月上旬~7月下旬 |
| 第171回 2025年11月16日(日) | 1級・2級・3級 | 12月中旬~1月中旬 |
| 第172回 2026年2月22日(日) | 2級・3級 | 3月中旬~4月中旬 |
2025年度試験日程カレンダー | 商工会議所の検定試験
※各商工会議所によって申込開始日や合格発表日は異なります。
詳細は、試験実施団体の日本商工会議所でご確認ください。
日商簿記にて受験停止期間を設けることは発表されています。
以下の該当期間で受験はできないため、注意が必要です。
【対象期間】
■2024年度
・2024年4月1日(月)~4月13日(土)
・2024年6月3日(月)~6月12日(水)
・2024年11月11日(月)~11月20日(水)
・2025年2月17日(月)~2月26日(水)
※お申し込みは随時可能
対象期間外での日程で受験日を検討しましょう。
日商簿記検定試験(2級・3級)ネット試験について | 商工会議所の検定試験
簿記の知識は、企業の財務状況を管理し、適切な会計処理を行う上で不可欠です。特に日商簿記2級以上を取得していると、実務での即戦力として評価されやすくなります。また、決算業務や税務申告など、より高度な業務に携わるための基礎知識としても役立ちます。
経理・財務以外にも、総務・人事・経営企画といった管理部門でも簿記の知識は重宝されます。企業のコスト管理や予算策定に関与する業務では、簿記の知識があることで、データを正確に読み解き、意思決定に活かすことができます。
簿記資格を持っていると、未経験から経理職に転職する際に業務に関する知識が備わっていると評価されることもあります。特に簿記2級以上は多くの求人で応募条件として設定されています。また、管理職を目指す際にも、財務知識を持つことはプラス評価につながります。
企業によっては、簿記資格の取得者に対して資格手当を支給しているケースがあります。特に、経理・財務職の募集要項では、簿記2級以上を取得していることで毎月の給与に手当が加算されることも。自身の会社の就業規則や賃金規定を確認し、活用できる制度がないかチェックしてみましょう。
以上、簿記資格のコスパについての解説でした。
簿記は、経理だけでなく、様々な仕事・職種、延いては日常生活でも活かせる資格です。 比較的良心的な値段でここまでのメリットが得られるので、是非コスパ最強の簿記資格に挑戦してみてください!
MS-Japanが運営するマネジーは、資格取得の応援も行っており、普段から安価なKIYOラーニングの『スタディング』のサービスを、マネジーの会員は更にお得な特別価格で利用できます。
簿記資格のプランもありますので、気になる方は是非詳細をご確認ください。
また、すぐに転職を検討している方に限らず、情報収集をしたい方にもご提供できる内容もありますので、是非MS-Japanのエージェントサービスもご活用ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

英文契約書のリーガルチェックについて

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
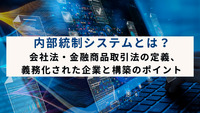
内部統制システムとは?会社法・金融商品取引法の定義、義務化された企業と構築のポイント
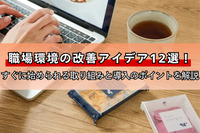
職場環境の改善アイデア12選!すぐに始められる取り組みと導入のポイントを解説

PPAPのリスクは取引停止|加害者にならないための廃止論

働く女性の7割超が「サイレント退職」 妊活・出産・育児とキャリアの両立、職場に相談できず
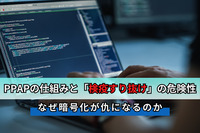
PPAPの仕組みと「検疫すり抜け」の危険性|なぜ暗号化が仇になるのか

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
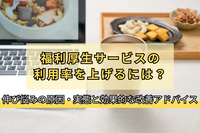
福利厚生サービスの利用率を上げるには?伸び悩みの原因・実態と効果的な改善アドバイス
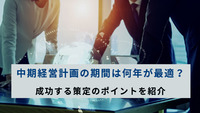
中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

DX導入後8割が「作業増えた」と回答 中小企業におけるDX推進、課題浮き彫り

「スポーツエールカンパニー」に1635団体認定 イベントや部活など健康経営の取り組み評価
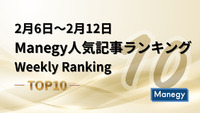
2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
公開日 /-create_datetime-/