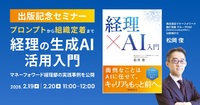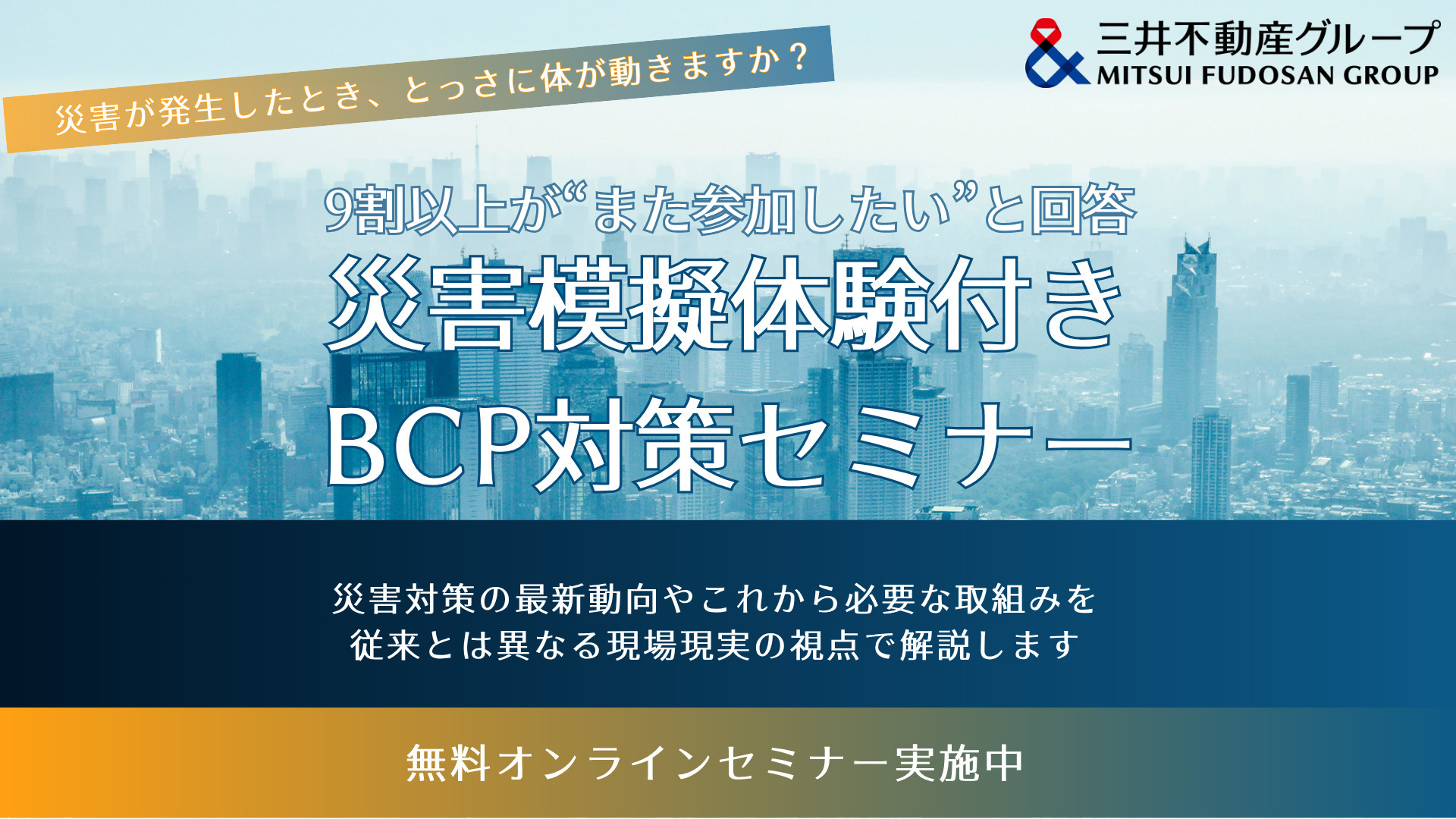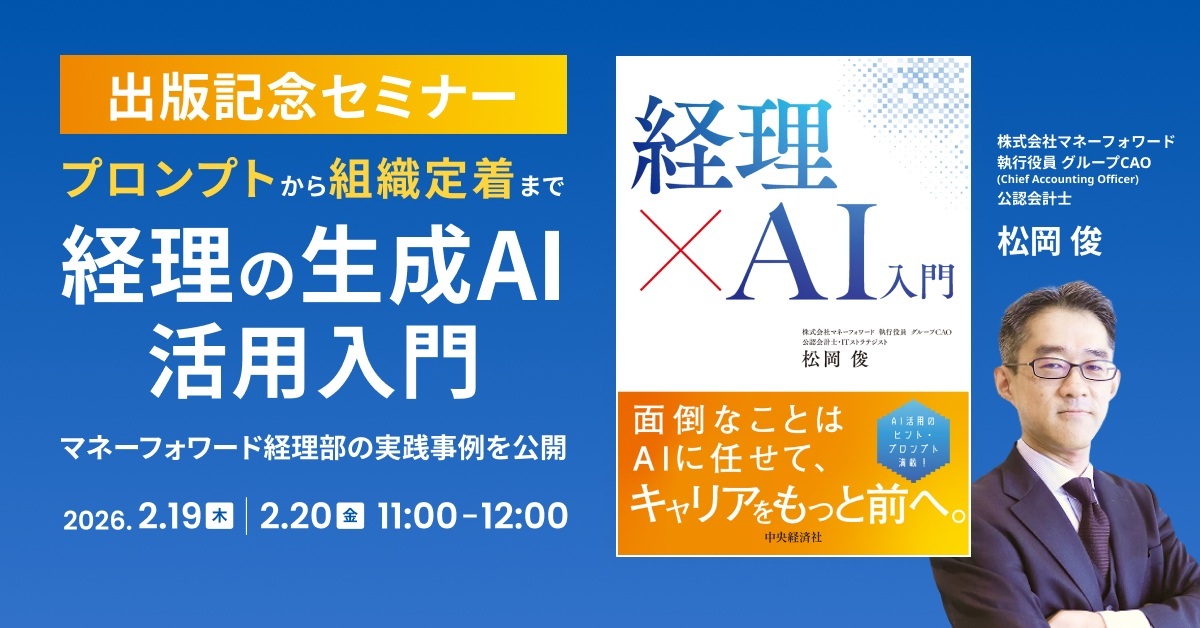公開日 /-create_datetime-/
GW「憲法記念日」特集!憲法と法律の違いを説明できますか? 憲法の基本を“こっそり”おさらい
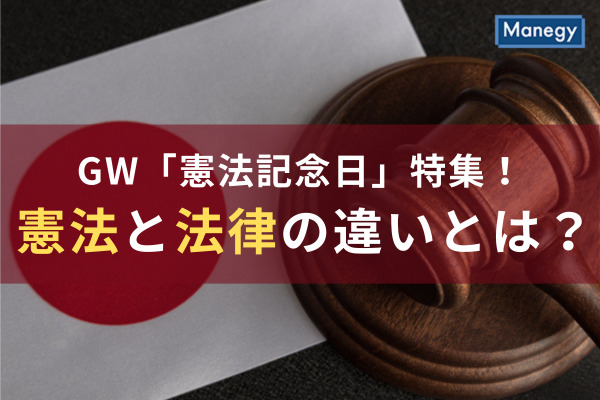
5月3日は「憲法記念日」です。ゴールデンウイーク半ばであり、連休のうちの一日としてあまり意識しない人も多いかもしれませんが、社会人としてはできれば“どのような日” なのか、知っておきたいところです。
ちなみに「憲法」はどういうものかは、小学校や中学校の社会科の授業で教わっていますが、大人になると忘れてしまっているものですよね。改めて、「憲法」って何? 「法律」や「条例」「規則」との違いは? この記事では、「何となくわかっているような、でも、きちんと説明するのは自信がないかも…」と感じている人でも「なるほど!」と理解できるように、憲法について解説していきます。
「憲法記念日」とは
5月3日の「憲法記念日」は、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日として、国民の祝日に定められています。 日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されました。憲法記念日は、その施行を記念したものです。
そもそも「憲法」とは? 法律・条例・規則との違いもひと言で解説
「憲法」とはひと言で言うと「国の基本的なルールを定めている最高法規」です。法規とは、法律や規則のことです。補足すると、憲法はその国の政治の仕組みや国民の権利などを規定している基本的な法文書であり、一般的に立法府(日本では国会)によって制定されます。“国の最高法規”ということはつまり、憲法に反する法律は作れないということです。
一方、「法律」「条例」「規則」はひと言で説明すると、以下のとおりです。
法律
憲法に基づいて国会で制定される、日常生活に関わるルール
条例
地方公共団体が制定する自治立法で、議会により制定され、その区域内で適用されるルール
規則
地方公共団体が制定する自治立法で、議会の議決を経ず、地方公共団体の長や委員会が制定できるその区域内のルール
このように、憲法・法律・条例・規則の4つの言葉は一見似ていますが、制定する機関や適用される範囲などは異なります。
では、次にそれぞれをもう少し詳しく解説していきましょう。
憲法・法律・条例・規則の特徴をそれぞれ理解しよう
憲法とは
憲法は国家の最高法規であり、国のあり方を決めた基本的なルールです。大きな特徴は、「国家権力を制限して、国民の権利や自由を保障する」ものとなります。
日本国憲法には「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の三原則があり、なかでも「基本的人権の尊重」は重視されています。その背景には、第二次世界大戦の経験をもとに、国家が人権を侵害しないように“人権の保障を守る憲法”を作ることが求められた経緯があります。
では、「国家権力を制限して、国民の権利や自由を保障する」とは、具体的にどういうことでしょうか? わかりやすく言うと、国民の権利や自由を守るために「国がやってはいけないことややるべきこと」について定められている、ということです。
「憲法=国民が制限されている(国民に課している)ルール」と勘違いされがちですが、そうではなく、国家権力が制限されています。 また、憲法は主に以下を定めています。
・政治体制の定義…憲法は国家の政治体制を規定し、行政機関の権限や責任を明確にしています。
・基本的人権の尊重…憲法は国民の基本的人権や自由を保障し、国家権力の乱用から国民を守ります。
・法の支配の確立…憲法は法の支配の原則を確立し、政府の権限の乱用を防止します。
国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、国民の権利を守ろうとすることを「立憲主義」といいます。
なお、国民の権利を守る憲法が簡単に変えられてしまうのは、国民にとって不利なことです。そのため立憲主義の国では、憲法の改正には厳しい手続が必要であり、憲法は他の法規よりも優先されます。
法律とは
法律は、国会の議決を経て制定される国のルールです。憲法に基づいて制定されるため、憲法に違反する内容の法律を制定することはできません。 憲法は国家権力を制限する=「国にルールを課す」ものですが、法律は「国民にルールを課す」ことで国民自身の自由や安全を守ります。
また、日本において憲法は1つしかありませんが、法律は「民法」「刑法」「地方自治法」など複数あります。社会秩序の維持、公共の利益の保護、個人の権利の保障などが、法律の主な役割です。
条例とは
条例とは、地方公共団体の区域内において適用される自治立法です。地方自治法に基づいて地方議会により制定され、国の法令に違反しない範囲で定められます。 条例で定める事項は例えば、地方公共団体の休日、都道府県や市町村の議会の議員定数、定例会の回数、職員の定数など、多岐にわたります。
条例はその違反者に対して、罰則を制定できます。罰則は、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金・拘留・科料・没収、5万円以下の過料を規定することができます。
規則とは
規則も、条例と同様に地方公共団体が制定する自治立法です。国の法令に違反しない範囲で地方公共団体の長や委員会が定めるもので、議会の議決を経ずに制定できる点が条例との大きな違いです。 規則も、違反者に対して罰則を制定することができますが、その内容は5万円以下の過料のみです。
以上が、憲法・法律・条例・規則のそれぞれの特徴です。
まとめ
いかがでしたか? 憲法・法律・条例・規則は、管理部門で働く皆さんが業務上で関わる機会が比較的多いものです。しかし、それぞれの違いをいざ説明しようとすると、意外と言葉に詰まってしまう人もいるのではないでしょうか。
それぞれの内容を理解しておくと、対応すべき事柄がわかりやすくなり、関係各所へのアナウンスなどもしやすくなるかもしれません。ぜひ、これらの知識を仕事に生かしてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -
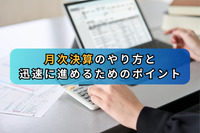
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -
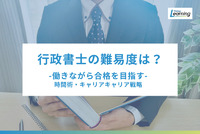
行政書士の難易度は「管理部門での実務経験」で変わる? 働きながら合格を目指す時間術とキャリア戦略
ニュース -

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。
ニュース -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】
ニュース -
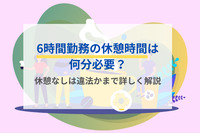
6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説
ニュース -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

文書管理データ戦略:法人セキュリティの決定版
ニュース