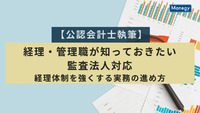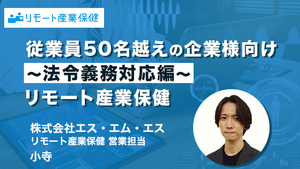公開日 /-create_datetime-/

2019年通常国会へ法案提出が見込まれている、企業にパワハラ防止措置を義務付ける関連法案だが、企業側はどう受け止め、義務化への対応策はどうなっているのだろうか。パワハラ対策は、大企業では増加傾向にあるものの、従業員99人以下の中小企業となると3割以下と低調だ。
しかし、労働局に寄せられる相談では「いじめ・嫌がらせ」が72,000件を超え、6年連続でパワハラ関連の相談がトップを占めている。パワハラによるマイナスは、従業員だけでない。生産性の低下や優秀な人材が流出するなど、経営者にとっても大きな損失となる。
したがって、パワハラのない職場環境をつくることは、労使双方にとってメリットがあるが、経営者側にとっては、「指導」と「パワハラ」の線引きが明確ではないといった懸念もあるようだ。
さて、各企業のパワハラ対策への取組状況だが、株式会社アドバンテッジ リスク マネジメントの調査によると、パワハラ対策を実施していると回答したのは全体で79.9%、2,000名以上の企業・団体となると、9割以上が既に対策を講じているという結果だ。
ところが、実施しているパワハラ対策の実効性については、「十分である」「概ね十分である」「やや不十分」「不十分」がそれぞれ4割弱で、既に取り組んでいるパワハラ防止対策では“不十分”ということが浮き彫りになった。
パワハラ対策が「十分である」理由としては、「できることはやり尽くした」という回答が多く、「不十分である」理由として、「対策の形骸化」や「実態が見えないことへの懸念」が挙げられている。
また、パワハラ防止措置の義務化に対しては、7割弱が「賛成」(68.7%)と回答し、「反対」(4.1%)を大きく上回り、「どちらでもない」が27.2%となっている。
パワハラ防止措置義務化に「賛成」する理由としては、「国による共通指針の明確化」や「意識の浸透」を期待する回答が多く、「反対」する理由としては、必要な指導がおろそかになるなど「パワハラへの過剰反応」や「画一的な指針策定」に対する懸念が挙げられている。
パワハラ防止措置の義務化によって、部下とのコミュニケーションの取り方にも影響が出ることが予想されるため、部課長などの管理職にとっては、難しい時代となるが、パワハラ問題は、コミュニケーション欠如に起因することが多く、部下との信頼関係を築き上げることが、何よりの防止策となるのではないだろうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -
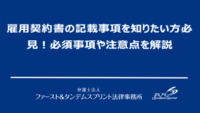
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

事業用不動産のコスト削減ガイド
おすすめ資料 -
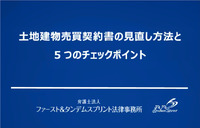
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

税務・会計業務で使える生成AI実践セミナー【セッション紹介】
ニュース -
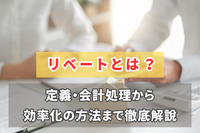
リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説
ニュース -

子どもが生まれた正社員に最大100万円を支給。大和ハウスグループの若松梱包運輸倉庫が「次世代育成一時金」を新設
ニュース -
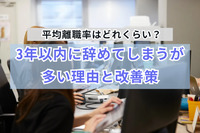
平均離職率はどれくらい?3年以内に辞めてしまう人が多い理由と改善策
ニュース -
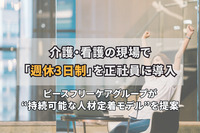
介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案
ニュース -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -
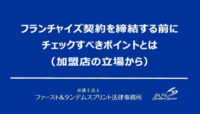
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
ニュース -
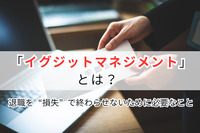
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと
ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
ニュース -
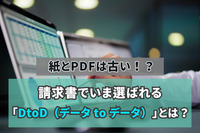
紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?
ニュース -

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ
ニュース