公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
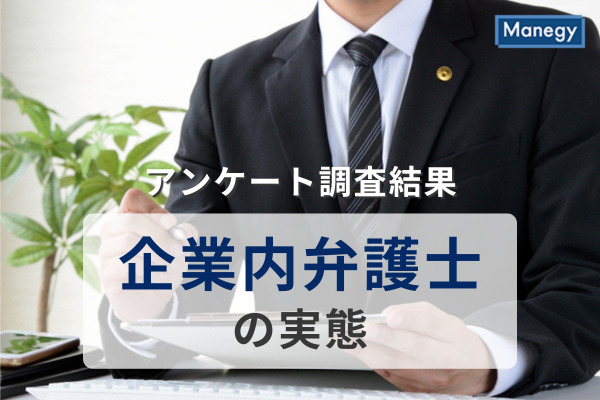
先日、日本組織内弁護士協会(JILA)が、企業内弁護士を対象とするアンケート調査の結果を発表しました(2024年3月15日~31日に実施、有効回答数は277人)。
引用元:企業内弁護士に関するアンケート調査集計結果(2024年3月実施)_日本組織内弁護士協会
企業内弁護士とは、国と自治体以外のあらゆる法人に従業員として勤務する弁護士のことです。具体的には民間企業、特殊法人、公益法人、事業組合、学校法人、国立大学法人等で雇用されている弁護士を指し、組織内弁護士とも呼ばれています。
弁護士と聞くと法律事務所で勤務する専門職とのイメージがもたれやすいですが、その勤務先は多岐にわたっているのが実情です。
今回は、組織内弁護士に関するアンケート調査の結果について深掘りします。
日本組織内弁護士協会が2023年7月に実施した調査によると、同時期の日本における登録弁護士数の合計は4万4,858名、そのうち企業内弁護士の数は3,184名のみです。割合としては7.1%ほどで、1割未満にすぎません。
では、なぜ企業内弁護士の道を選んだのでしょうか。今回発表されたアンケートでは、「あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか」の問いが含まれています(複数回答可)。それによると、最多回答は「ワークライフバランスを確保したかったから」で全体の62.1%も占めていました。
法律事務所の場合、成果を出せば収入は増えるものの残業がつづくこともあり、激務になりやすい傾向にあります。そうした職場ではなく、ワークライフバランスを重視した働き方をしたい人が、企業内弁護士の道を選択している傾向に見受けられます。一般企業では、昨今の働き方改革により過度な残業を強いられることは少なくなっているため、収入よりも働きやすさを重視している人が企業内弁護士に多いようです。
なお、この質問で2番目に多かったのが「現場に近いところで仕事がしたかったから」の49.8%、3番目が「その会社で働きたかったから」の33.2%と続いています。
個人受任とは、弁護士が自らの名前で個人的に事件を受けることを指します。事件を担当すれば報酬を得られるので、副業・兼業にもなりますが、個人受任ができるかどうかは所属する組織によって変わります。
今回のアンケート調査結果によると、「あなたの会社では個人受任の受任は認められていますか」との問いに対し、「認められていない」が60.3%を占め、「認められている」は39.7%でした。企業内弁護士の場合、個人受任が認められていないケースの方が多いです。
一方、「副業・兼業は認められていますか」との問いには、「認められていない」は38.6%で、残りの約6割は「認められている」との回答でした。認められている人のうち、実際に副業・兼業をしているのは20.9%となっています。
弁護士の副業としては、個人受任の他に講演や執筆業、裁判所の調停員などがあります。個人受任が認められていない会社でも、その他の副業・兼業は可能な場合もあります。約6割の所属先で副業・兼業OKなわけですから、収入アップの機会は得やすいともいえます。
企業内弁護士の年収については、今回のアンケート調査によると、最多回答だったのが「1,000~1,250万円未満」で23.5%、以下、「750~1,000万円」が19.9%、「1,250~1,500万円」が14.4%、「500~750万円」が13.7%と続いています。
年収1,000万円超えの企業内弁護士は、全体の65.4%を占めています。年収2,000万円以上は15.9%、年収5,000万円以上は2.5%でした。企業・法人で安定して勤務できる中で、高収入を得ているといえます。
また「弁護士会費は誰が負担していますか」との問いには、87.4%が「所属先」と回答しています。会費の負担がなく、しかも大手企業等では福利厚生も整っているため、総じて法律事務所よりも待遇面は良好といえるかもしれません。
1日の平均的な勤務時間についてのアンケートでは、最多回答が「8~9時間未満」の39.7%でした。次に多かったのが「9~10時間未満」の29.6%で、8~10時間未満に収まっている人が全体の7割近くを占めています。
高収入ながら激務の印象もある弁護士業務ですが、企業内弁護士の場合、それほど長時間にわたる残業もなく、ワークライフバランスを重視した働き方がしやすい結果といえるでしょう。
また「土日祝日に勤務することがありますか」との問いに対しては、78.3%が「ほとんどない」と回答し、「月1~2回程度」が16.6%でした。休日はしっかり休める職場が大半という結果です。
日本における企業内弁護士の数は、割合こそ少数ですが年々増え続けています。日本組織内弁護士協会の調査によると、2001年時点だと全国に66名しかいませんでしたが、2010年には428名、2015年には1,442名、2020年には2,629名、2023年には3,184名にまで増加しました。
企業内弁護士増加の要因は、司法試験制度の改革により弁護士の数が増えていることも影響していると考えられます。しかし今回のアンケート調査から明らかな通り、ワークライフバランスを重視した働き方ができることも大きな要因ではないでしょうか。近年では若者を中心に、かつてのような仕事中心のライフスタイルを見直す動きが強まっています。今後、企業内弁護士を目指す人はさらに増えていくとも予想されます。
引用元:企業内弁護士に関するアンケート調査集計結果(2024年3月実施)_日本組織内弁護士協会
■参考サイト
企業内弁護士の最新動向とは?年収相場や男女比について解説
企業内弁護士(インハウスローヤー)とは? 増加の背景や年収など
企業内弁護士(インハウスローヤー)への転職!面接で気を付けたいポイントとは?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
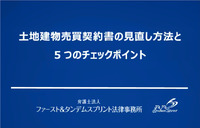
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

生成AI時代の新しい職場環境づくり
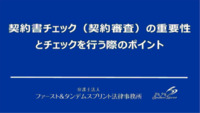
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

2026年の展望=2025年を振り返って(13)

雑収入とは?仕訳方法・具体例・税金の扱いをわかりやすく解説
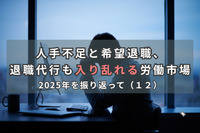
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)

決算書が赤字の時に見るべき場所とは?原因の読み解き方と改善策を徹底解説

令和7年度 法人税申告書の様式改正
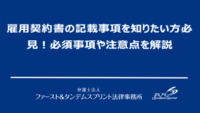
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
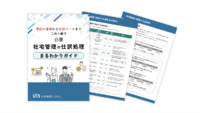
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド
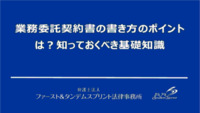
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
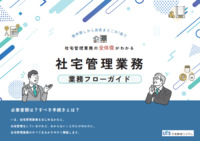
社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?

事業再生を取り巻く環境の変化=2025年を振り返って(11)
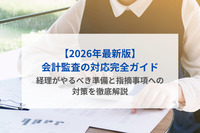
【2026年最新版】会計監査の対応完全ガイド|経理がやるべき準備と指摘事項への対策を徹底解説

年収の壁を起点に整理する!令和8年度税制改正 実務対応ガイド【セッション紹介】

外注と業務委託の違いとは?契約形態や活用シーンをわかりやすく解説
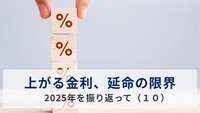
上がる金利、延命の限界=2025年を振り返って(10)
公開日 /-create_datetime-/