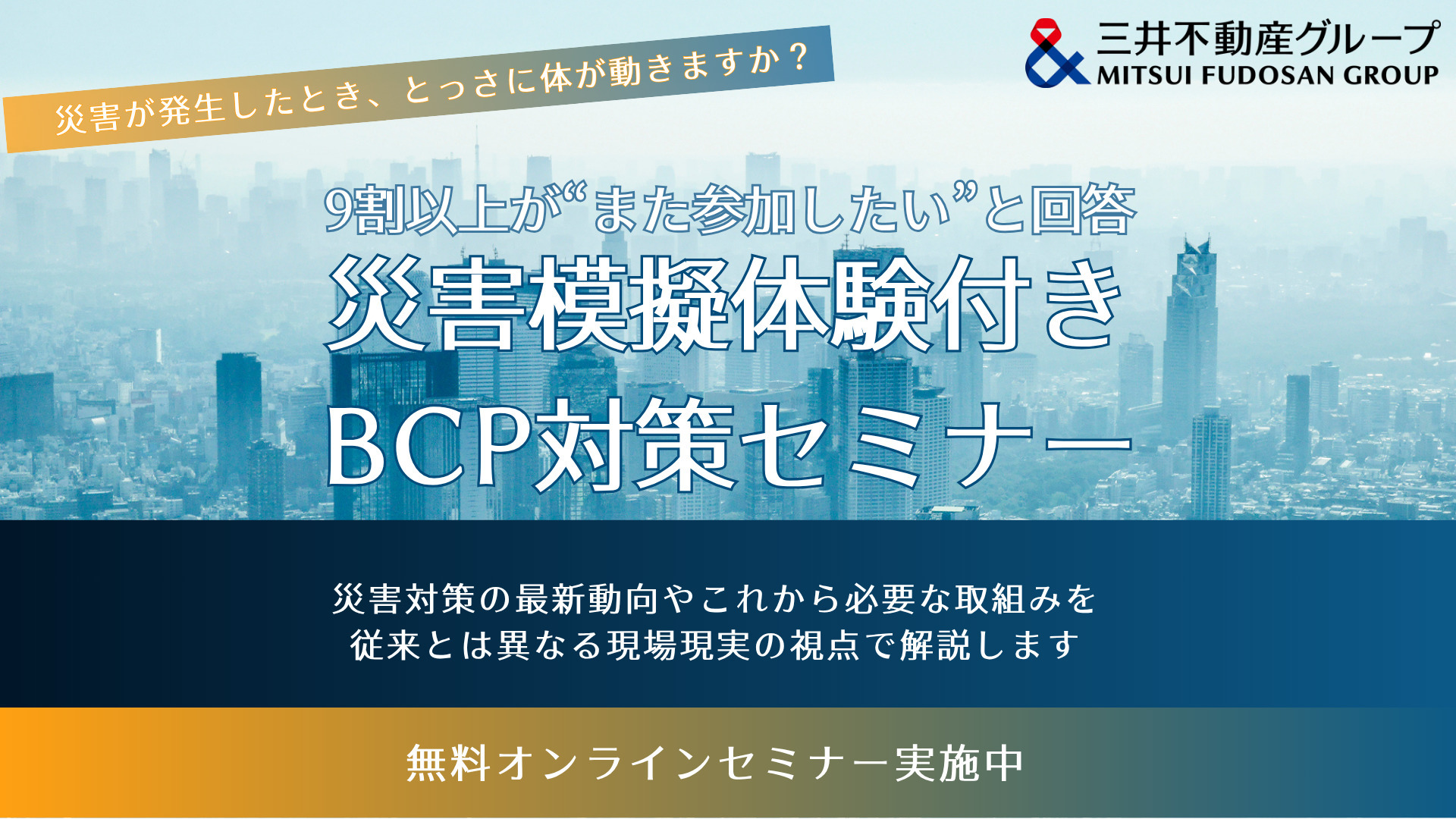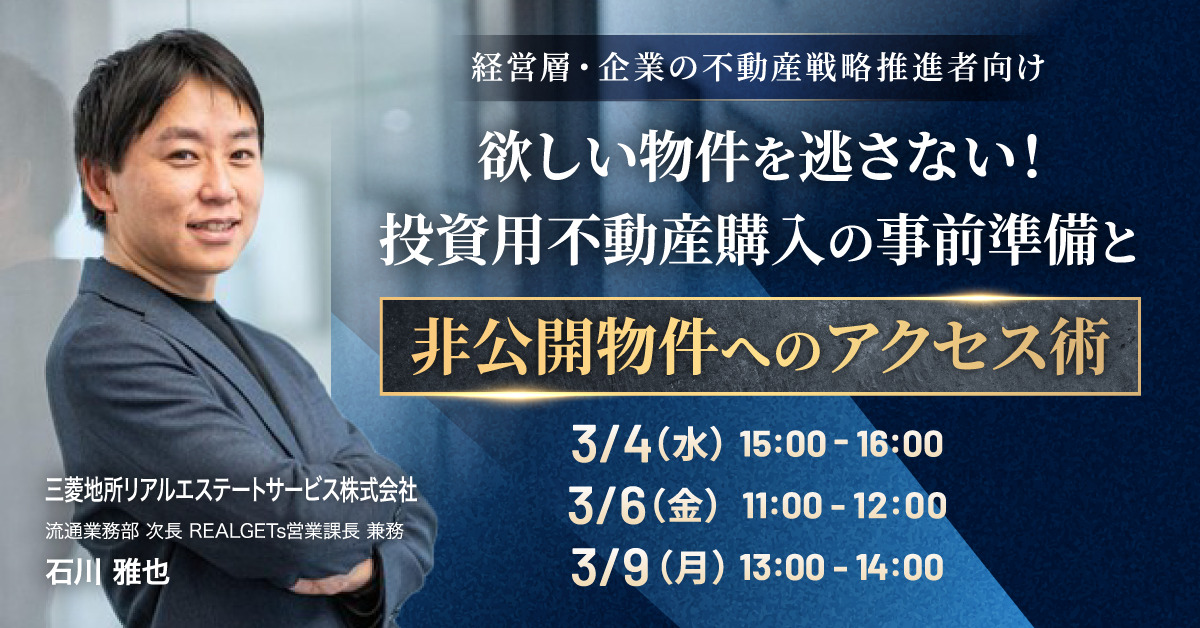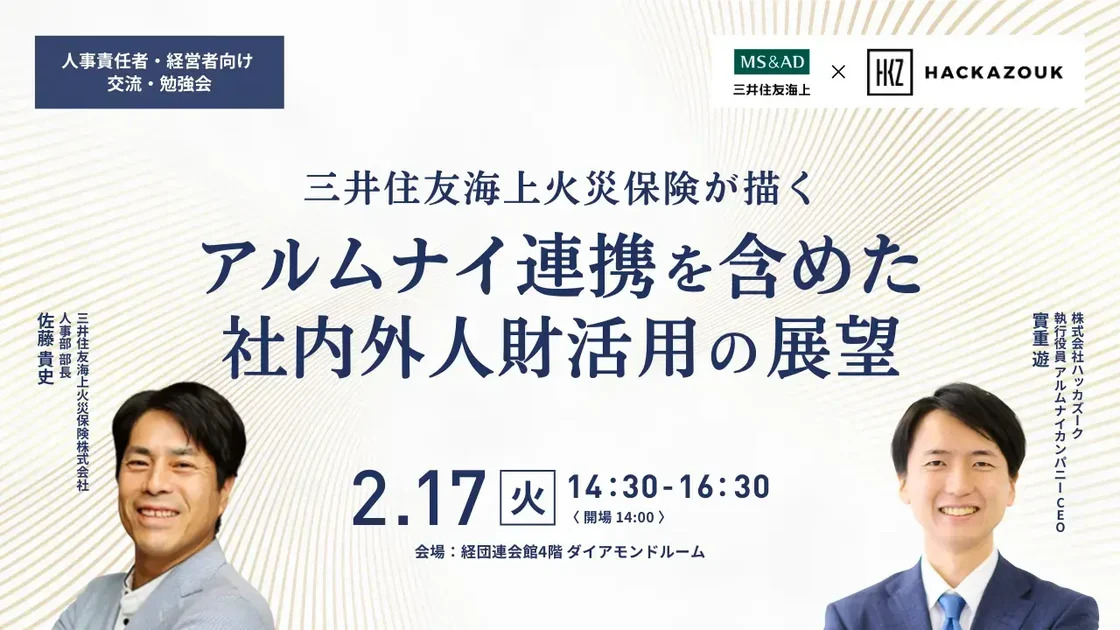公開日 /-create_datetime-/

現在では、国際化が進むにつれて海外勤務=大企業のみが行うことというイメージは古くなりつつあります。以前に比べると交通網も通信網も格段に便利になったことから、実際に日本のビジネスパーソンの、海外勤務の機会は多くなっているのではないでしょうか。
海外勤務となった場合、「税金はどうなるの?」という疑問は当然出てくるものでしょう。今回は、海外勤務の際の税金について紹介します。
目次【本記事の内容】
海外滞在が1年以上になる場合は「非居住者」に
海外勤務になった場合、日本に住んでいなくても日本人として、日本に税金を支払わなければならないのでしょうか。それを決めるのが「居住者」と「非居住者」の違いです。
「居住者」とは文字通り日本に住んでいる方のことで、「非居住者」とは「居住者」ではない人のことになります。居住者か非居住者かを決めるのは、日本に生活の本拠地を置いているか、または1年以上居住しているかです。もし海外に1年以上住むことが予測される勤務内容であった場合は、日本に住んでいない「非居住者」とみなされることになっています。非居住者になると、課税所得の範囲が限定されるようになります。
非居住者の課税所得
非居住者の課税所得は、原則上「国内源泉所得」のみに限られます。この「国内源泉所得」とは、簡単に言えば日本の内部で生じた所得という意味です。つまり、日本の内部で生じた所得でなければ、事実上課税されないことになります。このことは、たとえ国内に住んでいる家族にお金を送ったとしても、国内源泉所得に見合うものではない限り課税の対象にならないということを意味しています。
役員の国外勤務は例外的に国内勤務になるため外国税額控除の手続きをする
一般に役員の仕事やその結果は、勤務地ではなく法人に帰属すると考えられているため、国外で行う勤務も国内勤務に含まれることになります。そのため、国内でも報酬や給与に関しては約20%の源泉所得税がかかってしまいます。
しかし、この報酬に関しては勤務している外国の地でも税金の対象になるため、二重課税になってしまうといった事態が起きます。このような事態にならないよう、外国で確定申告をする際には日本に収める約20%の税金を差し引くことができる外国税額控除を受ける手続きを行うという方法があります。役員の方が海外勤務をする場合は、確認しておきましょう。
年末調整は出国前までの給与が対象に
年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収した所得税の合計額と本来収めるべき所得税の額に差額が出る場合があるため、その差額を求めて還付を受けたり、追加で支払ったりすることです。年末調整の対象となるのは出国する日までの給与や賞与であり、出国する前にしっかりと年末調整を行っておく必要があります。生命保険料や社会保険料の控除も、出国までに支払われたものだけが対象になる一方で、配偶者控除や扶養控除は1年分控除されるため、注意が必要です。
出国後も日本で収入が発生する場合は納税管理人の選定を
たとえば日本にある自宅を、海外赴任をしている間だけ賃貸するといった場合のように、出国後も日本国内で収入がある場合は、日本で確定申告をする必要があります。しかしその場合、1年以上海外で勤務する場合は出国と同時に「非居住者」となるため、代わりに税務を行ってくれる方を立てる必要が出てきます。代わりに税務を行ってくれる方を「納税管理人」といいます。
納税管理人の仕事は、一般に確定申告の提出など非居住者の納税義務を行うことです。この納税管理人を立てるときには「納税管理人の選任届」という書類を所轄の税務署に提出する必要があり、その後の税務関係の書類は、この納税管理人に郵送され手続きを取ることになります。もし納税管理人を定めなかった場合は、控除の判定などの際に不利になる可能性が出てきます。
細かいケースは国によっても違う
その他、現地で支払うことになる税金の種類や金額は、当然現地の法律によって異なってきます。たとえば日本の居住者については、収入の多寡によって所得税率が変化し、だいたい5~40%の累進課税になっています。例えば、台湾の所得税率の最高は日本と同じ40%ですが、韓国は38%、フィリピンで32%と異なっています。これらの数字だけを見ると日本と台湾が高いように思いますが、基準となる収入の額や物価が異なるため、結果的に日本よりも高額の納税を行うことになるという例も少なくありません。税金に関する細かい事柄に関しては、自分が行く先々の税金事情に詳しい人に聞くなり、調べたりすることが重要です。
まとめ
納税の金額に関しては行く先々で異なるため、個別のケースで調べることが大切です。国内の税金に関しては、1年以上海外に滞在することになる非居住者の場合、国内での収入がない限り特別かかるということはなさそうです。海外勤務を命じられたら、年末調整など国内で必要となる手続きを済ませ、現地の税金事情について調べてみましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

会社の存在理由から、法人の税金ルールを理解しよう
ニュース -
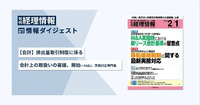
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -
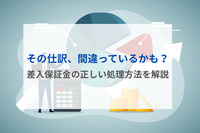
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース -

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース