公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
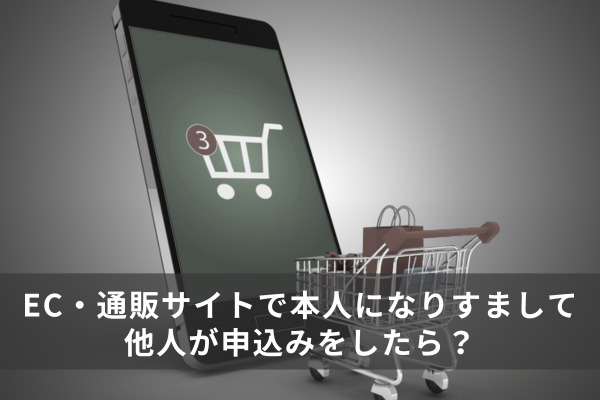
EC・通販サイトを運営していると、他人を装って商品の申込みがされる場合があります。このような「なりすまし」行為があった場合、契約上はどのような扱いになるのでしょうか。本稿では、「なりすまし」による不正注文の対策について解説します。
EC・通販サイトでの「なりすまし」による不正注文は、クレジットカード情報を悪用したものが中心です。クレジットカードの情報が不正に入手されるケースには、以下のようなものがあります。
・フィッシング
・スキミング
スキャナーを使ってクレジットカードの磁気データが読み取られ、カードの情報をコピーした偽造カードが作成されるケース
これらの手口で盗用したクレジットカード情報を使い、第三者がクレジットカード決済を行うことで、「なりすまし」による不正注文が行われる場合があります。
警察庁の発表によると、「なりすまし」による不正注文の被害は、年々増加しています。
また、新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業を自粛し、EC・通販サイトに切り替えた事業者も多いことが「なりすまし」による不正注文の増加に拍車をかけています。新たにEC・通販サイトに参入した事業者は、インターネット上での不正注文に対する対策が不十分な傾向にあり、不正注文の標的となりやすいのです。
契約は、当事者双方の意思表示が一致した場合に成立します。そのため、本人ではない他人が「なりすまし」によって申込みをしたとしても、申込者自身の意思表示はないため、原則として効力を持たず、契約は成立しません。つまり、EC・通販サイト運営者は、「なりすまし」の被害者である申込者本人に対して、その代金を請求することはできません。また、「なりすまし」によって契約を行った相手に対し、購入商品を送る必要もありません。
民法では、本人が意思表示をしていない場合にも、例外的に本人が契約に拘束される場合が定められています。これは、……
◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

令和7年度 税制改正のポイント

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
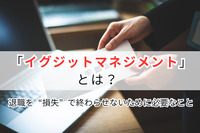
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
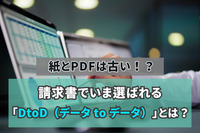
紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?
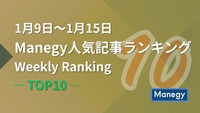
1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
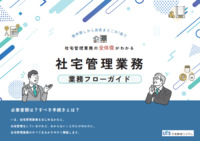
社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術
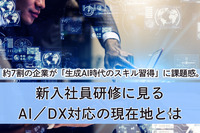
約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは
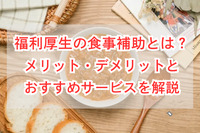
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

2026年の展望=2025年を振り返って(13)

「退職金制度」の導入・見直しタイミングを解説
公開日 /-create_datetime-/