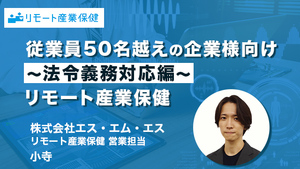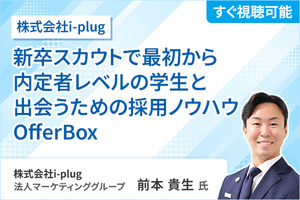公開日 /-create_datetime-/
【社労士執筆】高年齢者雇用安定法 経過措置の終了により65歳までの雇用確保が義務化(令和7年4月)

目次本記事の内容

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士
IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。
高年齢者雇用安定法とは
「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を前身とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」が昭和61年に制定されました。その後、改正が重ねられ、直近では令和3年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業確保措置が事業主の努力義務として設けられました。
lockこの記事は会員限定記事です(残り3936文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
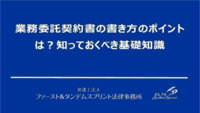
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -
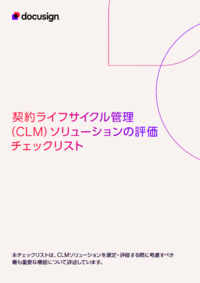
どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -
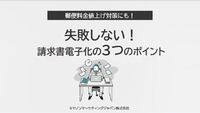
【郵便料金値上げ対策にも!】失敗しない!請求書電子化の3つのポイント
おすすめ資料 -

【大阪府堺市】省エネ・再エネ投資を最大90万円支援 事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金
ニュース -

資金繰りとは?会社経営で必須の知識を簡単に解説!悪化原因・改善方法・資金繰り表まで網羅
ニュース -

【最新版】2025年度の簿記2級 試験日程と試験概要まとめ
ニュース -

「個」が活きる組織をつくる──カオナビCPO平松氏に聞く、タレントマネジメントの現在とこれから
ニュース -

【おすすめセミナー】「クラウド会計ソフトが多すぎて導入が進まない…」比較セミナーで違いを知ることが導入への第一歩!
ニュース -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -
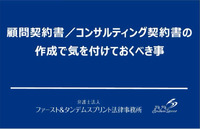
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -
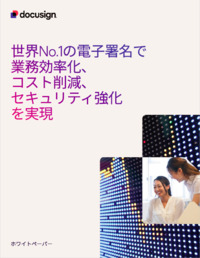
世界No.1の電子署名で業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化を実現
おすすめ資料 -
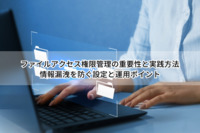
ファイルアクセス権限管理の重要性と実践方法|情報漏洩を防ぐ設定と運用ポイント
ニュース -
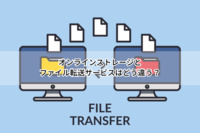
オンラインストレージとファイル転送サービスはどう違う?
ニュース -
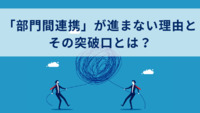
「部門間連携」が進まない理由と、その突破口とは?
ニュース -
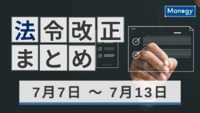
毎月勤労統計調査 令和7年5月分結果速報 など|7月7日~7月13日官公庁お知らせまとめ
ニュース -

【新入社員意識調査2025】卸・小売業の新人、「キャリア志向なし」が初めて1位
ニュース
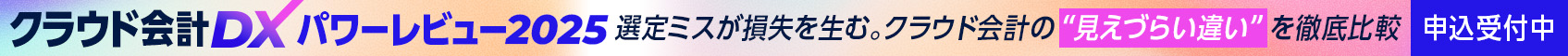









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました