公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

2024年4月に「労働基準法施行規則改正」が行われたことで、ビジネスシーンではあらためて労働法に対する理解の重要性に注目が集まっています。しかし営業やマーケティング、開発といった労働法との関係が薄い部署で働いている人にとっては、法律のことを聞かれても、いまいちよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ビジネスマンの基本知識ともいえる労働法について丁寧に解説します。
労働法とは、雇用する側の「使用者」と雇用される側の「労働者」の関係を規定する法律を総称したものです。法律としての目的は労働者側の保護にあり、労働法によって労働者は自身の権利を守れます。
労働者をより具体的に定義づけると、雇用する側である使用者の指揮命令の下で働く者です。
雇用する側の使用者が、雇用される側の労働者に対して指揮命令できる権利は、「労務指揮権」と呼ばれています。労働者は労働契約(雇用契約)を結ぶことにより、就労中は自らがもつ労働力の処分権を使用者側に委ねます。それによって使用者側には労働者に対する労務指揮権が生じ、この権利のもと、労働者側は使用者側が発する業務命令、配置転換命令などに従う必要性が生じるのです。
一方、使用者とは労働者を雇い入れる企業・法人を指し、労働契約法2条2項では「使用する労働者に対して賃金を払う者」と規定されています。また労働基準法10条では、経営者である「事業主」をはじめ、「事業の経営担当者」である役員や理事、「事業主のために行為をするすべての者」という表現で一定の権限をもつ管理職も、使用者側の存在として位置づけられています。
労働者に対して使用者が指揮命令権をもつという形となるので、労働者の立場はどうしても弱くなります。また労働者は生活収入を使用者が支払う給与に依存する形となり、日々の安定した暮らしを成り立たせるために、労働者は使用者の要求をできるだけ受け入れようとする傾向も生じ得ます。
こうした使用者・労働者間にある非対等な関係性により、労働者は使用者から劣悪な労働条件を強制され、自らがもつ労働力を搾取される危険性があります。そのため労働者の権利を保護し、使用者と労働者の関係をより適正なものに是正する役割を果たす「労働法」が必要になるのです。
「労働法」はあくまで総称であり、労働法という名前の法律があるわけではありません。労働法というとき、労務に関わる多数の法律が想定されていますが、その中でも中心的な法律として挙げられるのは以下の4つです。
労働基準法は、労働者の就労条件についての最低基準を規定した法律です。労働時間、休憩時間、休日、有給休暇などに関して、使用者側が最低限確保すべき条件が定められています。たとえば労働時間であれば1日8時間、週40時間が原則とされ、これ以上の長時間勤務を労働条件として定めることはできません。
日本国憲法28条において認められている労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を、具体的に保障する目的で定められたのが労働組合法です。 労働者の団結・団体行動を認め、使用者側と対等な立場で交渉できるようにするための法律です。
そもそも使用者側は企業・法人という「組織」であるのに対し、雇用される各労働者は「個人」です。労働者は個人で活動する限り、発言力・交渉力が使用者よりもどうしても劣ってしまいます。そこで賃金条件、労働条件などを巡って交渉する際に不利にならないように、労働組合法により団結・団体行動を取れる権利を認めているのです。
労働者側が使用側に対して起こすストライキ、それに対して使用側が事業所・工場を閉鎖して働けなくさせるロックアウトなどが起こると、労使関係は著しく悪化します。
こうした労使間の争いは労働争議と呼ばれ、その予防と解決を図るためのルールを規定したのが労働関係調整法です。労使間の争いを処理する行政機関である労働委員会における裁定の手続きや規則が定められています。
労働契約法は、使用者側が不当な解雇や懲戒処分をしたり、労働契約締結後に労働契約の内容を勝手に改ざんしたりしないようにし、労働者の地位を安定させるためのルールを定めた法律です。具体的には、労働契約締結に関する規則、労働契約の内容を変更する際の規則、労働契約の終了手続きに関する規則などが規定されています。
最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、職業安定法などが、労働法に含まれます。また労働者が関係する雇用保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、介護保険法といった各種社会保険の法律も、労働法の一種と考えられています。
企業の法務部は、契約書作成、社内規定の作成、知財管理、社内外のトラブル対応など、法律に関するあらゆる業務を扱う部署です。労働法は企業法務において、民法、商法、会社法、知的財産法などと並んで、熟知の必要のある法律といえます。
従業員の雇用、教育、配置などは人事部が行いますが、労使関係のトラブルにおいて法知識をもとに解決の中心役となるのは法務部です。基本的な労働法の知識はビジネスマンである限り抑えておきたいところですが、法務部に配属された場合、より深い法の理解と現実の問題への応用力が求められます。
労働者の保護を目的とした法律である労働法ですが、「労働者」に含まれる主体について、いくつか注意しておくべき点があります。まず、企業・法人と業務委託契約を締結して働くフリーランスは「労働者」ではないので、労働法の対象外です。また先に述べた通り、会社の役員は経営者ではありませんが、使用者側とされ労働者ではないので、労働法の適用外とされます。
さらに部長など管理職については、労務管理などにおいて大きな権限が与えられている場合は、労働基準法の定める管理監督者に該当するので使用者側とされ、労働基準法などは適用外です。しかし、労務管理において権限・責任のない部長職で、たとえばより上位の管理者の命令を伝達するのが主な業務といった場合は、部長職であっても使用者ではなく労働者とされます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
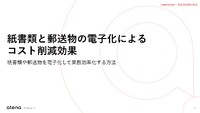
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
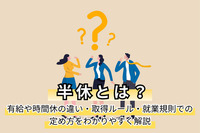
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
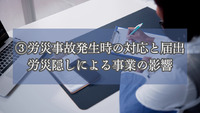
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
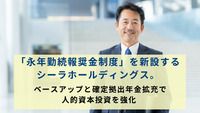
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
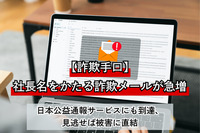
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い
公開日 /-create_datetime-/