公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
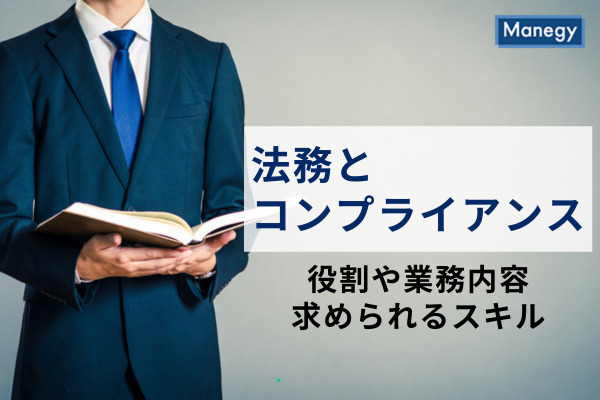
企業活動において、法務とコンプライアンスはリスク回避という点でどちらも必要不可欠です。対策を怠ると、売上・利益の低下といった事業面での要因ではなく、思わぬ形で足をすくわれ、最悪の場合はそのまま倒産・廃業にまで追い込まれます。企業にとって法務、コンプライアンスに注力することは、自社を守るという意味で極めて重要といえます。
そこで今回は、法務部門とコンプライアンス部門の役割と両者の相違点、それぞれの業務内容、仕事に従事する上で求められるスキルなどについて詳しく解説します。
法務とは、企業が直面する社内外の法的問題に対応することです。企業によって異なりますが、法務部門には弁護士・外国法弁護士の資格を持つ人も多く在籍し、社内の法律事務所のような役割を果たします。また外部の弁護士との窓口となる場合もあります。
一方、コンプライアンスとは、社内において法令・ルール違反が発生しないような仕組みづくりをすることです。法務ほど高度な法的な知識は求められないものの、コンプライアンス部門で勤務する場合も、労働法など関連する法律に通じていることは必要です。
法務とコンプライアンスはどちらも、法的な紛争を扱う仕事という点では類似しています。ただし、密接に法律に関わり、法的なトラブルに法律の専門家として予防・対応を行うのは法務部門の役割です。一方でコンプライアンス部門では、法令違反が生じないような規則・仕組みづくりを行うことで対応するのが主な役割であり、その点は異なります。
また、法務部門の仕事ではより高度な法律知識が求められます。それに対してコンプライアンス部門では法律の知識に加えて、業界のルールや企業独自の内部ポリシー、従業員が守るべき倫理とは何かといったことに関する幅広い知識が求められます。コンプライアンスは直訳すると「法令遵守」ですが、遵守すべきものの対象となるのは法律だけにとどまりません。従業員に対して業界ルール・社会的倫理などを守らせるにはどうするか、といったことも業務の範疇に入ります。
さらに歴史的経緯の点でも違いがあります。規模の大きな企業であれば、法務は資本主義社会の創成期から重視されてきた業務です。しかし、業務としてのコンプライアンスの重要性が指摘されるようになったのは比較的最近のことです。
とくに、1990年代以降、セクハラやパワハラをはじめとする企業の不祥事が多く発覚するようになり、その対策としてコンプライアンスが注目されるようになりました。各不祥事がマスコミで大々的に報じられることで、日本社会全体においてコンプライアンスに対する意識が高まり、その結果企業では「コンプライアンス部門」を設置する動きが生じたのです。この傾向は2024年現在も継続しているといえます。
法務部門とコンプライアンス部門の具体的な業務内容は以下の通りです。
法務部門の主な業務は、「商取引時の契約内容のチェック」「組織運営上の法的事項への対応」「法的紛争の対応」「経営陣・他部署への法的アドバイス」などです。
「商取引時の契約内容のチェック」とは、他企業と取引を行う際に取り交わす契約書の作成をはじめ、契約時の交渉・締結が適切に行われているかどうかを確かめる業務です。「組織運営上の法的事項への対応」は、株主総会・取締役会などの運営が法律に則って実施されるよう支援したり、策定されている社内ルールが法律に則っているかをチェックしたりする業務などが含まれます。
「法的紛争の対応」では、企業が直面する法的リスクの測定とその減少のための法的対策を行い、すでに生じている紛争に対する交渉、調停、訴訟などを行います。「経営陣・他部署への法的アドバイス」は、企業内部で生じたあらゆる法的問題への対応業務を指します。
コンプライアンス部門の主な業務は、「社内教育」と「法令・ルールを守らせるための規則づくり」です。
「社内教育」では従業員の不正・不適切行為を防ぐため、法令遵守すること、社会の倫理・ルールを厳守することの重要性、業界ルールの内容などについての研修を実施します。「法令・ルールを守らせるための規則づくり」では、行動規範・社内規範のマニュアル作成、法令・ルールを守れる組織・管理体制の整備などの業務を行います。
企業の法務部門やコンプライアンス部門で勤務する場合、以下のようなスキルが求められます。なお、法務部門とコンプライアンス部門が独立していたり、法務部門の中にコンプライアンスを扱う部署があったりと、企業によって組織形態は異なりますが、求められるスキルは業種・業界を問わずおおむね共通しています。
法務、コンプライアンスの業務を行う上で、法律の知識は欠かせません。とくに関わりが深い法律としては、労働法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、労働契約法、最低賃金法、男女雇用機会均等法など)、民法、会社法、商法、著作権法、特許法、商標法、独占禁止法などが挙げられます。
法律のすべてに目を通す必要はありませんが、自社が直面した過去の法的トラブルの内容、自社の商品・サービスなどに関連する法律知識は最低限理解しておきましょう。また法制度は定期的に改正が行われたり、新法が創設されたりもするため、法知識は絶えずアップデートが不可欠です。
また、アップデートの点ではとくにコンプライアンス部門の場合、社会通念上の倫理観・ルールも時代によって変わるため、その点にも敏感であることが求められます。他社で問題になった事例があれば調査・分析し、自社において問題が起こらないように対策を練る必要があります。
法務部門やコンプライアンス部門では、文書を作成する機会が多くあります。法務部門においては、契約書や官公庁に提出する書類の作成および内容のチェック業務を行います。コンプライアンス部門では、社内への通知文書の作成業務などを行います。法律・倫理に関わる文書の作成が多いため、あいまい・不適切な表現、誤った意図を伝えるような文言は厳禁です。
法務部門、コンプライアンス部門ともに、社内外の多くの人と頻繁にやり取りする必要があるため、スムーズにやり取りできるコミュニケーション能力が欠かせません。自社の経営陣や、社外の弁護士など専門家への連絡役になったり、社内で法律面の相談を受けたりすることもあります。相手の主張を理解し、的確なアドバイスができる能力は業務上不可欠です。
法務部門、コンプライアンス部門ともに、企業が直面する法的、社会的リスクを管理する上で重要な役割を果たします。法的リスクの管理とは文字通り法律上のトラブルへの予防と対処、社会的リスクの管理とは法律・社会的倫理に反することにより、企業の名声・評判が落ちることのないように予防・対処することです。最近ではAI(人工知能)技術を法務部門、コンプライアンス部門にも導入する動きがみられます。業務の遂行方法が今後大きく変わる可能性もありそうです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】
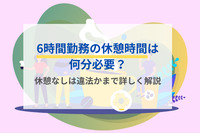
6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

オフィスステーション導入事例集

オフィスステーション年末調整

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
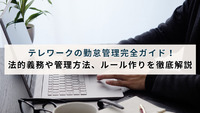
テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
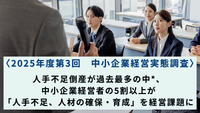
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
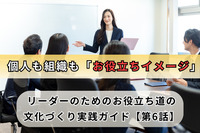
個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】
公開日 /-create_datetime-/