公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行が停止されます。今後はマイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)が基本となり、労務管理への影響も少なからず出るとみられています。
行政手続きのワンストップ化が進められるなか、人事労務担当者が知っておきたいのが「マイナポータル」の知識です。そこで本記事では、人事労務担当者が知るべき「マイナポータル」の基礎知識や労務管理への影響、マイナポータルの今後の動向について解説します。
日本では、国民皆保険制度にもとづいてすべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、保険証を提示することで医療サービスを受けてきました。しかし法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなります。
現在、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を、医療機関などで保険証として使用することが認められています。紙の保険証が実質廃止となり、今後はマイナ保険証を中心に手続きが進められるでしょう。
ここで重要なのは「新規発行ができなくなった」という点です。令和6年12月1日時点で手元にあり、なおかつ有効期限内の保険証であれば、今まで通り使用できます。ただしこれはいわゆる経過措置で、有効期限が切れるまでにマイナ保険証を用意しなければなりません。
マイナポータルは、政府提供のサービスで、行政手続きを一元管理できるプラットフォームです。税金や年金に関する情報、子育て支援情報など、自分に関する行政機関の情報や通知を確認できます。
各種の行政手続きをオンラインで申請できるのもマイナポータルの特徴です。税金の申告や各種給付金の申請など、従来オフラインで行っていた手続きがオンラインでも進められます。
現時点でもできることはさまざまですが、今後も多くのサービスを開発・提供し、行政手続きのワンストップ化を進める方針です。
マイナポータルが労務管理に与える影響について、まず考えられるのは労務管理の効率化です。従業員に関する各種手続きをオンラインで行えるようになり、紙の書類のやりとりや物理的な申請手続きを減らせます。とくに昨今では電子申請が浸透しつつあるため、将来的にはオンラインでの手続きが主流になると考えられます。
たとえば年末調整では、従来、従業員が保険料控除などの証明書を紙で提出していました。しかし、マイナポータルを活用することで、オンラインで証明書を受けとり、申告書を作成して会社へ提出できるようになります。従業員側は年末調整の一連の手続きをオンラインで実施でき、企業側も提出されたデータをシステムで処理できます。
また、マイナポータルの登場によって、コミュニケーション面での変化も顕著です。マイナポータルを通じて、従業員に重要な通知をスムーズに伝えたり、必要な手続きを忘れずに行うようリマインダーを送信したりできます。従業員自身がマイナポータルを通じて、自分の労務関連情報を確認・管理できるため、双方にとって利便性が向上するでしょう。
さらにマイナポータルは、法令遵守の面でも労務管理に大きな影響を与えます。たとえば新しい規制に関する通知を受けとり、必要な手続きをスムーズに行うなど、対応の柔軟性も格段に向上するでしょう。
マイナポータルは利便性が高い反面、いくつかの課題もあります。まず挙げられるのは、現時点で、マイナンバーカードの利用率が低いことです。政府や地方自治体は、カードの利便性を広く周知し、利用率を向上させる取り組みを進めています。また、カードを用いたサービスの拡充や、取得手続きの簡素化も実施しています。
もう1つ課題として考えられるのは、企業向けサービスの強化です。マイナポータルを業務に取り入れるためには、企業で利用している人事労務や給与システムが、API連携に対応していなければなりません。現状、マイナポータルの機能は主に個人ユーザー向けの仕組みが中心となっており、企業向けの手続きサービスの拡充が期待されています。
今後は、2019年(令和元年)12月に施行されたデジタルファースト法(デジタル手続法)を中心に、マイナポータルを業務に組み入れるための改革が進められると考えられます。大企業の電子申告義務化に続き、中小企業もITインフラの整備が急務となるでしょう。経費精算システムや電子契約システムの導入など、クラウド型サービスの活用も重要になります。
政府は行政手続きのオンライン化を推進しており、マイナポータルはその中心的な役割をはたしています。すでにマイナンバーカードを保険証として利用でき、さまざまな改革を進めていることもあり、今後は利用率の向上が期待されます。
企業として求められる対応は、大企業・中小企業に関係なく、さまざまな業務のデジタル化を進めることです。法改正の情報も適宜収集しておくとよいでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
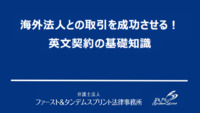
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

「インシビリティ」が組織を蝕む。“微細な非礼”の悪影響と防止法を解説

雑収入とは?仕訳方法・具体例・税金の扱いをわかりやすく解説
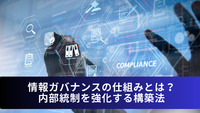
情報ガバナンスの仕組みとは?内部統制を強化する構築法
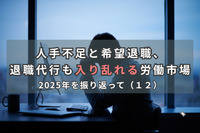
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)
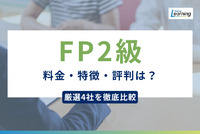
FP2級講座を厳選4社ご紹介|各講座の料金・特徴・評判を徹底調査

ラフールサーベイ導入事例集

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
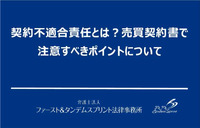
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

焼津市の建設会社・橋本組、「えるぼし認定」最上位に 女性活躍推進法に基づく全項目をクリア

決算書が赤字の時に見るべき場所とは?原因の読み解き方と改善策を徹底解説

専門人材向けに「ジョブ型人事制度」を本格導入した三井住友カード。“市場価値連動型”の評価・処遇でデジタル人材獲得へ

令和7年度 法人税申告書の様式改正

オフラインアクセスは危険?クラウドストレージの安全な活用
公開日 /-create_datetime-/