公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。
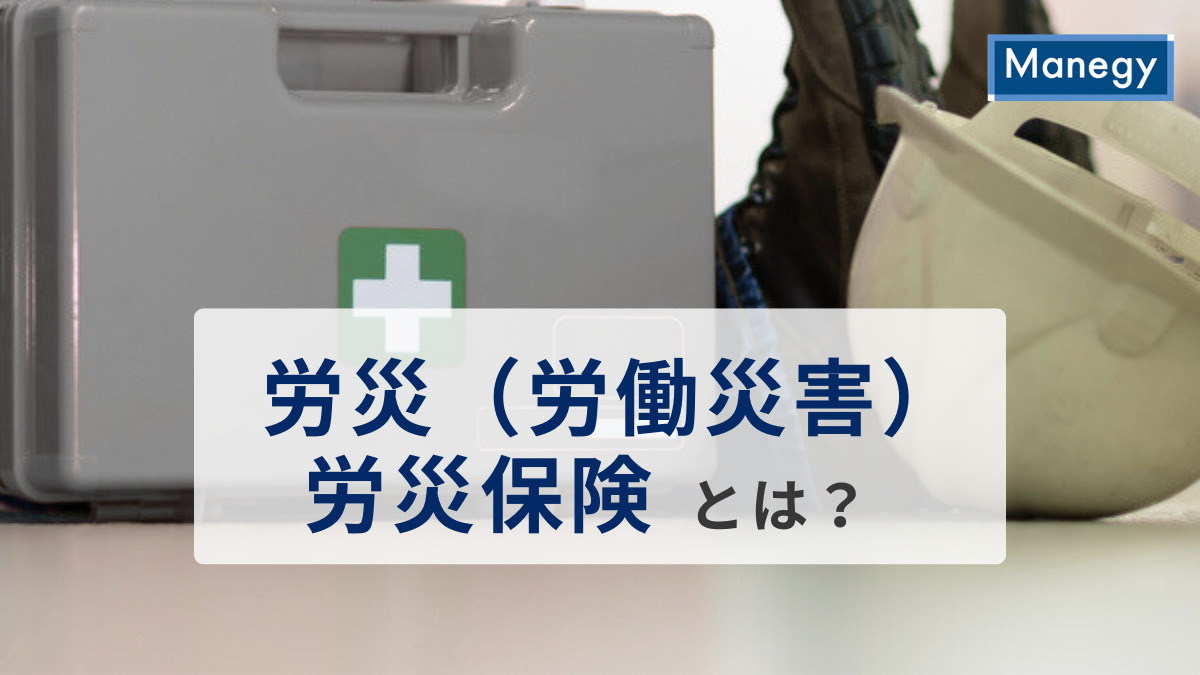
日々仕事をする中で、業種によっては労災(労働災害)に備えておく必要があります。労災に対して適切に対処することは事業主の義務であり、労災保険についても理解しておかなければなりません。この記事では、労災に関する基礎知識全般を解説します。概要を知るためのガイドとして役立ててください。
労災とは、業務にかかわることで従業員が負傷したり病気になったり、最悪の場合死亡に至ることです。労災は2つのケースに分類され、1つは就業中に発生した「業務災害」であり、もう1つが通勤中に発生した「通勤災害」です。
業務災害は就業中の事故による負傷や、業務が原因で生じた病気などが含まれ、精神的な疾患もその対象になります。一方で通勤中に事故にあった場合などは、業務に関連するものと見なされ通勤災害として扱われます。いずれの場合も、業務との因果関係が明確でなければなりません。
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中にケガや病気、障害、死亡などの災害に遭った場合に、必要な補償を行うための公的な保険制度です。労災保険法(正式名称:労働者災害補償保険法)に基づき、国が運営しています。
この制度は、労働者を雇用しているすべての事業主に加入義務があり、保険料は事業主が全額負担します。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず「労働者」として雇われていれば原則として労災保険の対象となります。
また、労災保険の仕組みは、企業が直接従業員に補償を行うのではなく、従業員が被災した際に国が給付を行うというものです。これにより、企業の負担を軽減しつつ、迅速かつ公平な補償を実現する仕組みとなっています。
なお、労災保険は雇用保険とあわせて「労働保険」と総称されますが、給付対象や仕組みはまったく異なります。労災保険は主に“万が一の災害への備え”として、すべての働く人を守るために設けられた制度です。
労災保険は、業種によって異なる保険料率で算出されます。実際に労災認定されると、主に以下のような補償が受けられます。
ほかにも労災とその後の状況によって、さまざまなタイプの補償が給付される場合があります。

労災保険は、労働者が業務中や通勤中に災害に遭った際に給付される制度ですが、その財源となるのが「労災保険料」です。ここでは、労災保険料のポイントをまとめます。
労災保険料は、次の計算式で求められます。
年間の労働者賃金総額 × 業種別保険料率(千分率)= 労災保険料
たとえば、賃金総額が2,000万円、保険料率が5.0/1000の場合、労災保険料は10万円となります。
労災保険料は、雇用保険とあわせて「労働保険」として一括で申告・納付します。 通常は、年度の開始時(毎年6月頃)に「概算保険料」を申告・納付し、翌年に「確定保険料」との差額を精算する仕組みです。保険料が高額になる場合は、分割(3期)での納付も可能です。
労災の対象は身体的な障害から、パワハラや過労による精神的疾患まで幅広く、認定の判断が難しい場合もあります。以下に労災が認められた過去の事例と、認定が難しいケースをそれぞれ紹介しましょう。
●労災認定された事例
・重量物を持ち上げて腰を痛め、椎間板ヘルニアと診断された
・空調機フィルター清掃中に熱中症になり休業31日以上
・ビルメンテナンス中に高所から落下して複雑骨折、91日以上の休業
・長時間労働でうつ病を発症し自殺、会社側が損害賠償1億6,800万円
・過重労働で心臓性突然死、損害賠償8,500万円
●労災認定されないケース
・故意に災害を引き起こした場合:業務遂行性が認められても、業務起因性がないため労災認定されません。
・自然災害による被災の場合:業務とは無関係に発生した自然災害では、業務起因性が認められないため労災認定されませんが、業務条件によっては例外があります。
・休憩時間中のけが:休憩時間中の行為が業務とは無関係であれば、労災認定されません。ただし、手待ち時間や特定の指示下での休憩の場合、認定される可能性があります。
・通勤中の私用の寄り道での事故:通勤災害とは認定されません。通勤の定義から外れるためです。
労災事故が発生した場合、被害者となる従業員も適切な対応を取ることで、スムーズに労災保険の給付を受けることができます。ここでは、被災直後から給付申請までの基本的な流れを解説します。
1. まずは安全確保と応急処置を最優先に
事故発生直後は、周囲に助けを求め、安全な場所へ移動します。必要に応じて救急車を呼び、医療機関で受診しましょう。初診時の診断書は、労災保険の申請にも使用される重要な書類です。
2. 会社へ事故の報告を行う
けがや事故が発生したことを、速やかに上司や人事担当者へ報告します。事故の状況や場所、時間などをできるだけ正確に伝えることが、労災の認定に役立ちます。
3. 労災保険の給付申請に向けて準備する
労災保険の給付を受けるためには、以下のような書類の提出が必要になります。申請にあたっては、会社側と協力して必要書類を整えましょう。
※ 申請は原則として労働基準監督署に提出します。
4. 給付決定を待つ・継続的な治療を受ける
申請後、労働基準監督署での審査を経て給付が決定されます。認定されれば、療養費や休業補償が支給されます。通院・治療の記録も必要となるため、医療機関での受診状況はしっかりと管理しておきましょう。
5. 職場復帰に向けて準備する
症状が回復してきたら、産業医や会社と相談のうえ、無理のない範囲で職場復帰の計画を立てます。復帰時には再発防止策や業務内容の調整も重要です。
労災事故の被害者となった場合、身体的な痛みだけでなく精神的にも不安を抱えることが多くなります。人事担当者は、申請のサポートだけでなく、被災者の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
労災事故が発生した際、企業側には迅速かつ適切な対応が求められます。対応が遅れたり不十分だったりすると、労働者との信頼関係が損なわれるだけでなく、行政処分や損害賠償、刑事責任に発展するケースもあります。以下では、労災事故発生時の基本的な対応フローを解説します。
1. 事故発生直後の初動対応をする
まずは、負傷者の救護と安全確保が最優先です。必要に応じて救急車を手配し、現場の危険を除去します。あわせて、事故の発生状況や関係者の証言などを記録しておくと、後の報告や証明に役立ちます。
2. 労働基準監督署へ報告する
労災事故によって労働者が死亡、または休業4日以上となった場合、会社は遅滞なく「労働者死傷病報告書」を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります(労働安全衛生規則第97条)。報告を怠ると、法令違反となるおそれがあります。
3. 労災保険給付の手続きサポートする
労働者本人が労災保険の給付申請を行う際、会社は所定の申請用紙への記入や証明欄の記載など、一定の協力が必要です。被災した従業員の負担を軽減するためにも、手続きについて丁寧に説明し、積極的にサポートすることが求められます。
4. 原因調査と再発防止策を実施する
事故後は、社内で事故原因の調査を行い、必要に応じて安全マニュアルの見直しや教育の強化、設備の改善などの再発防止策を講じます。労働者の安全配慮義務を果たすとともに、社内外への信頼維持にもつながります。
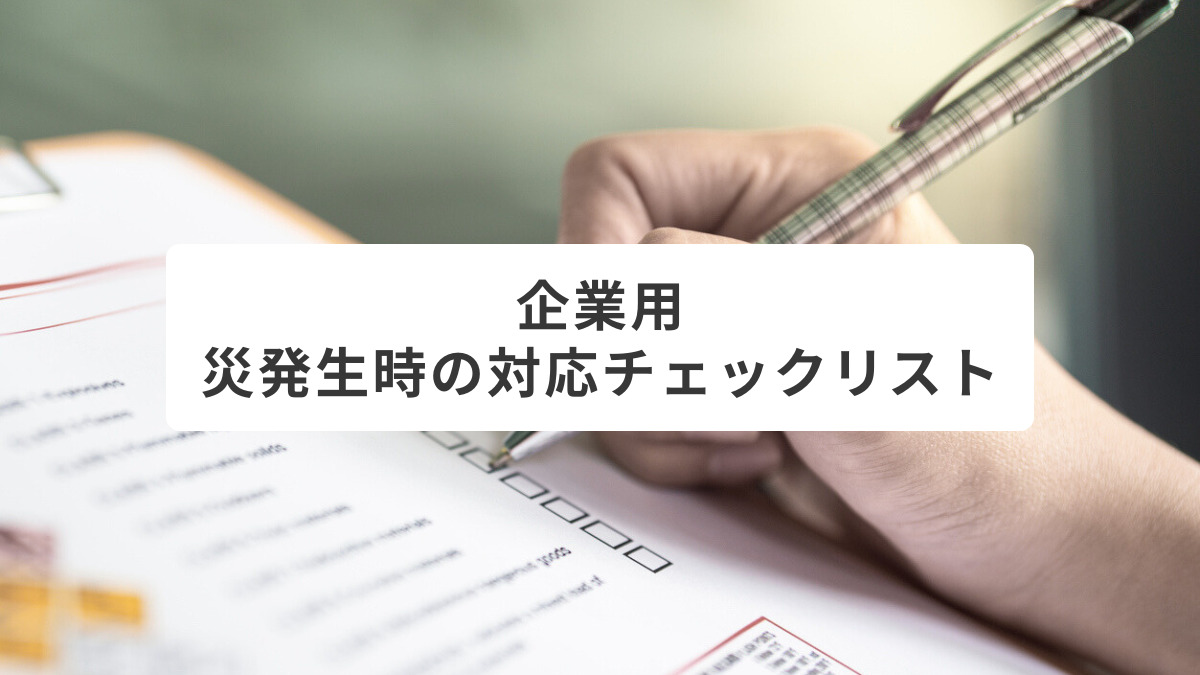
① 事故発生直後の初動対応
□負傷者の安全確保・応急処置を行う
□必要に応じて救急車を手配する
□ 現場の危険要因を除去する
□ 事故現場を記録(写真・動画・メモ)
□ 関係者からのヒアリングを実施
② 労働基準監督署への報告
□労働者死傷病報告書を作成(休業4日以上または死亡の場合)
□所轄の労働基準監督署に速やかに提出
□提出日や控えの保管を徹底
③ 労災保険申請のサポート
□被災者に必要書類を案内
□所定様式に会社記入欄・証明欄を記載
□労働基準監督署への提出サポート
□ 医師の診断書や治療記録の取得支援
□ 給付決定後の支給確認
④ 事故原因の調査と再発防止策
□ 事故原因のヒアリングと社内報告
□ 安全マニュアル・設備の見直し
□ 社内への注意喚起と再教育の実施
□ 改善策の実施・再発防止策の記録
⑤ 被災者フォローと復帰支援
□ 定期的な回復状況の確認
□ 復帰時の業務調整と面談実施
□ メンタルケアや産業医との連携
□ 復職後のフォローアップ体制構築
補足資料として備えておきたいもの
□ 労災保険の申請書式一覧
□ 過去の事故報告書の控え
□ 緊急連絡網・対応マニュアル
□ 社内の安全衛生管理計画
1.企業イメージが低下する
労災が発生すると、報道や口コミを通じて「安全管理が不十分な会社」と見なされ、企業の信頼性やブランドイメージが損なわれる可能性があります。特に死亡事故や重大な災害は社会的影響が大きいです。
2.行政指導・是正勧告の対象になる
労働基準監督署による調査が行われ、労働安全衛生法違反が見つかると是正勧告や指導が入る可能性があります。重大な違反があれば書類送検されるケースもあります。
3.労働環境改善に伴うコストが増える
労災をきっかけに、安全対策の見直しや設備投資、研修強化などが必要となり、費用負担が増加します。
4. 従業員の信頼喪失・職場環境の悪化につながる
安全が確保されていない職場では、従業員の不安が高まり、士気が下がったり、離職につながる恐れがあります。
5.生産性の低下や納期遅延が起きる
被災者が欠勤することで現場の人員体制が崩れたり、業務がストップすることで、取引先への納期遅延などが発生する可能性があります。
6. 労災隠しリスクと法的責任が生じる
労災を報告せず隠蔽すると、重大な法令違反となり、企業や責任者が刑事罰を受けるリスクもあります。
業務中や通勤中のけが・病気による休業時に、「労災保険の休業補償給付」と「健康保険の傷病手当金」のどちらが適用されるのか迷うケースがあります。両者は似ているようで仕組みが大きく異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
補償制度の違い
対象となる事由の違い
給付内容の違い
給付の併用について
原則として、同じ事由に対して労災保険と傷病手当金を併用することはできません。業務起因性が明確な場合は労災保険、それ以外は健康保険の傷病手当金というように、原因によって使い分けます。
労災事故は突然発生するものですが、いざという時に適切な対応をするためには、制度や運用面での正しい理解が不可欠です。ここでは、人事・労務担当者から特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 労災保険に会社が加入していない場合でも、従業員は補償を受けられますか?
A. はい、原則として補償されます。
事業主が加入義務を怠っていた場合でも、労働基準監督署への申請により労災保険の給付を受けることができます。ただし、会社には遡って保険料を納める義務が生じます。
Q2. 自転車通勤中に事故にあった場合、労災の対象になりますか?
A. 通勤経路上での事故であれば、通勤災害として認定される可能性があります。
ただし、私的な寄り道や逸脱があった場合は対象外となることもあるため、事前に通勤経路の申告を徹底しておくと安心です。
Q3. 労災申請に診断書は必要ですか?
A. はい、多くの申請において診断書の添付が必要です。
特に療養補償給付や休業補償給付を受ける際は、医師の診断書を添えて申請することが求められます。
労災に対する備えは、会社や職場が責任をもって実施すべきことです。会社に不備があり、その結果従業員が労災認定された場合、会社は賠償請求や行政処分の対象になることもあります。悪質と判断されたケースでは、業務上過失致傷や業務上過失致死などの刑事罰が科せられる場合もあります。
会社と従業員を守るためにも、労災対策の仕組みを整備することは重要です。しかし本来目指すべきなのは、災害が起きない職場づくりでしょう。労災を起こさないことこそ、最大の労災対策なのです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
公開日 /-create_datetime-/