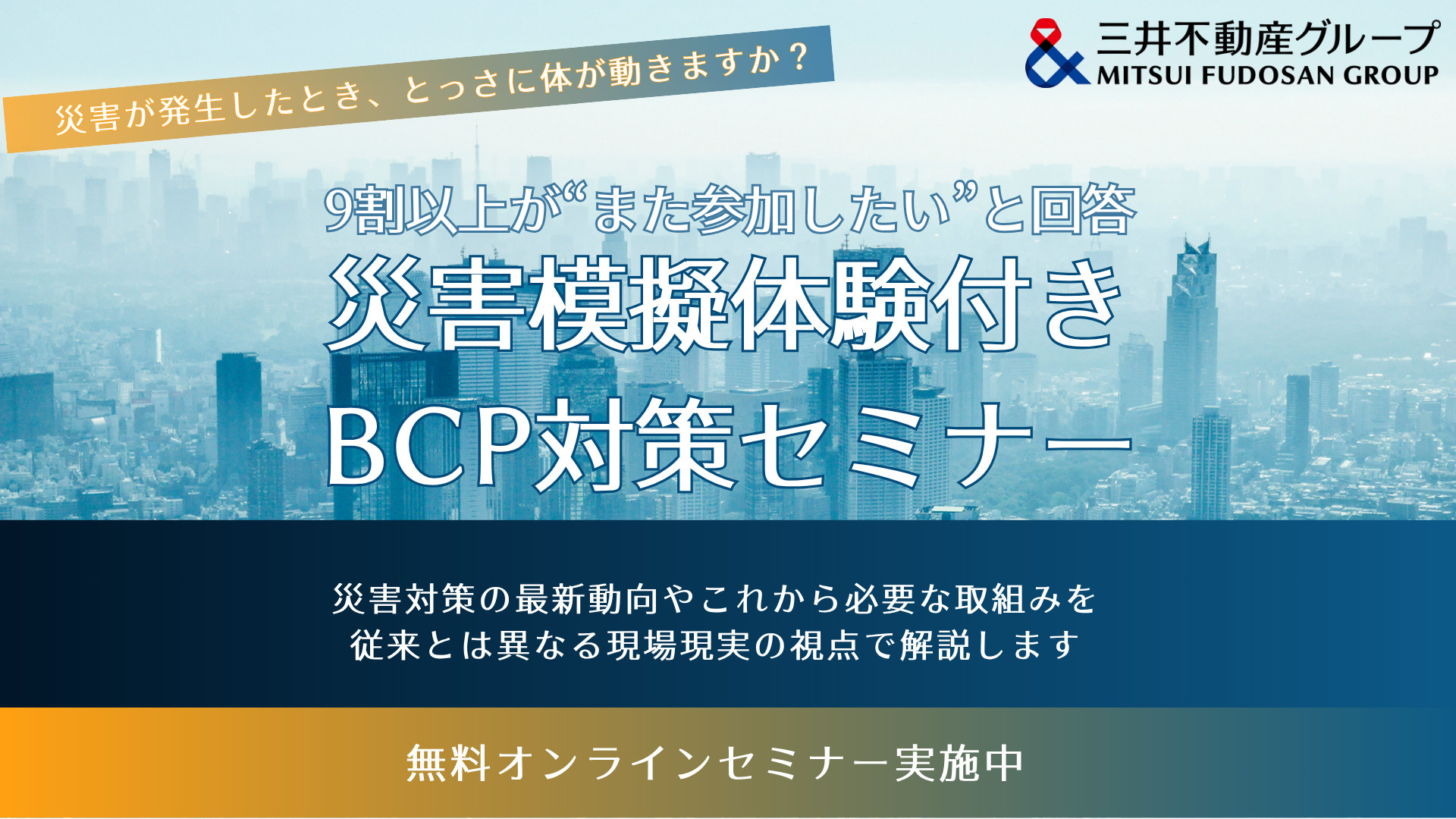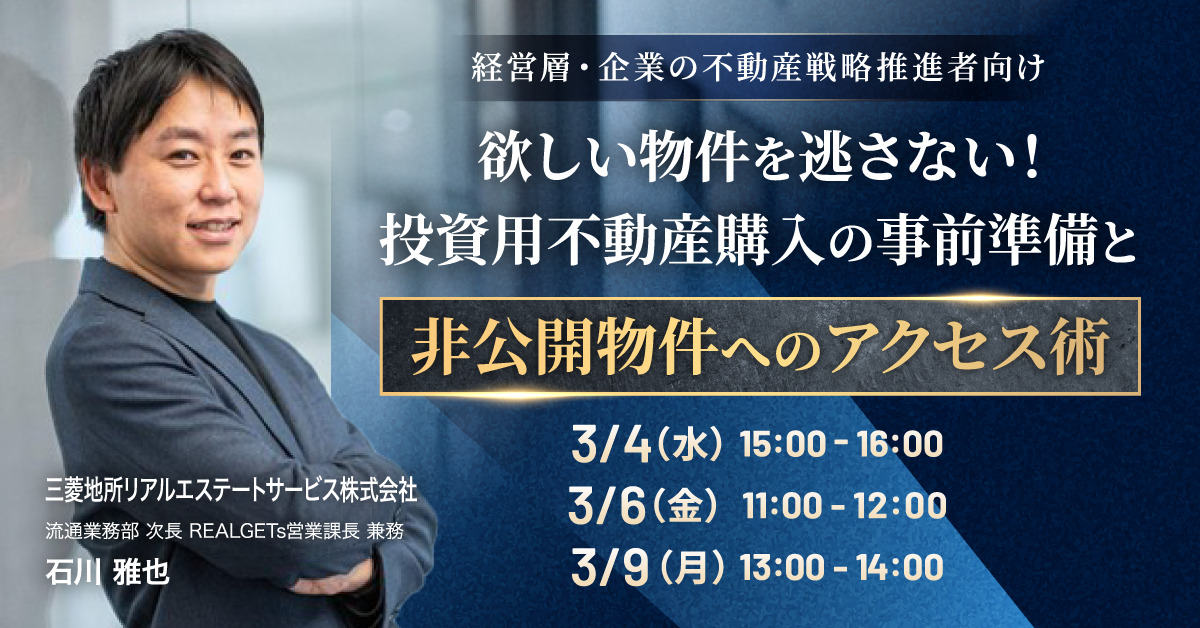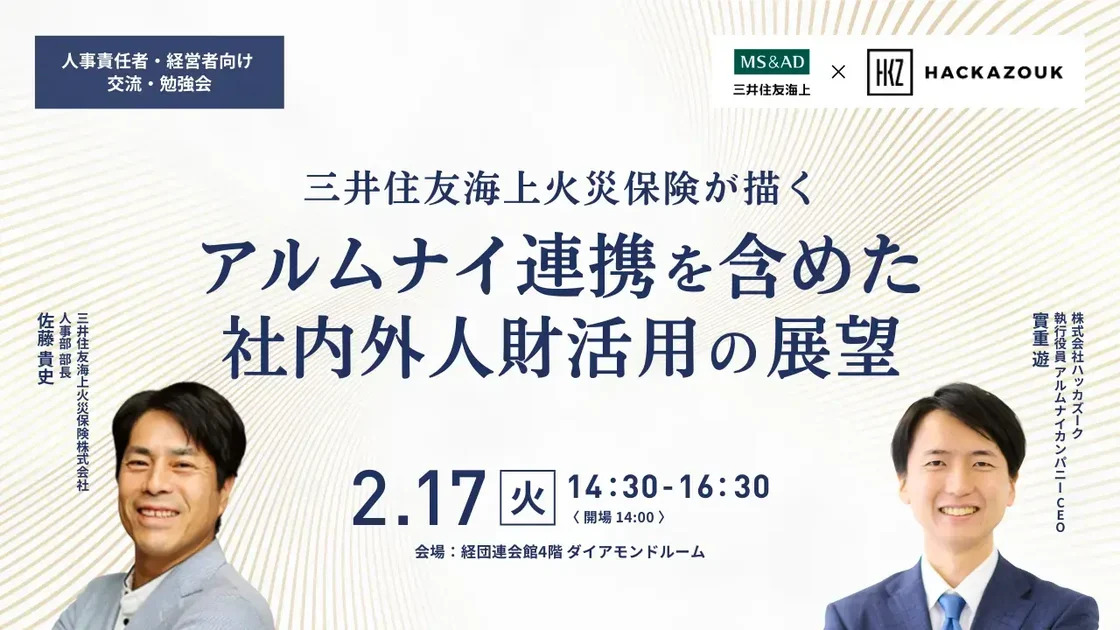公開日 /-create_datetime-/

社員に意欲を持って会社で働いてもらうために、会社が提供するサービス福利厚生。
福利厚生制度は社員が安心して働けるサービスを提供するだけでなく、節税としても有効的な仕組みです。
今回は節税として役立つ福利厚生を紹介します。
福利厚生で節税できる仕組みについて
福利厚生費とは「役員・従業員の福利厚生のために、給与、交際費以外に全員に平等に支出する費用」をいいます。
福利厚生費は税法上、原則経費として損金算入が認められており、課税対象の交際費などと比べると法人税を節税する効果があります。
参考例:損金算入
売上-費用(損金算入額)=利益
利益×法人税率=法人税
※費用(損金算入額)の額増えれば増えるほど、利益が圧縮されて納税する金額が減る
また、手当金と違い費用として現物で社員に支給されるため、社員は個人所得税が課税されず、さらに、社会保険料も負担する必要がありません。
そのため、「福利厚生費は節税効果がある」といわれるのです。
しかし、福利厚生費は実務上、区分が難しく「福利厚生費だと思っていても認定されない」場合があります。
福利厚生費として認定されない場合は、現物給与として社員に個人所得税が課され源泉徴収されるか、あるいは交際費として課税対象となります。
福利厚生として認められる費用とは
福利厚生費として認められるためには下記の条件を満たすことが必要です。
- 従業員等全員に支出されるものであること
- 社内規定で一定の基準が明記されていること
- 社会通念上、妥当な金額の範囲であること
まず、福利厚生費は、原則として従業員等全員に支出されるものでなければなりません。
例えば、一部の社員に対して功労賞などにより奨励金を付与した場合は、福利厚生費とは認められず、給与として個人所得税が課されます。
次に、福利厚生費についてあらかじめ社内規則で明記することが必要です。
福利厚生費は区分があいまいであることから、税務署から重点的にチェックされる勘定項目となります。
会社の福利厚生費であることを社内規則で記載し、社内で明文化・ルール化されていることで、税務署から経費否認される可能性が低くなるのです。
さらに、福利厚生費は社会通念上、妥当な金額の範囲である必要があります。
こちらは判断が非常に難しく、福利厚生費の区分のあいまいさで議論になるのは「社会通念上、妥当な金額の範囲」がどの程度かというところです。実務上判断が難しい部分が多いでしょう。
例えば、親睦会の開催が月に何度も実施されたり、残業時の食事代があまりに高額だったりといった場合は経費否認される可能性があるでしょう。
節税効果のある具体的な福利厚生を紹介
給与や交際費よりも福利厚生費として社員に還元されることで、会社も社員もうれしい福利厚生費。ここでは、実際の福利厚生費として認められる費用を紹介します。
社宅制度
会社から支給される住宅手当は給与とみなされ、社員は個人所得税を課税されます。同じ金額を会社が負担するとしても、手当ではなく社宅として社員に貸与する場合は、従業員が一定の賃料を負担している限り、会社が負担する賃料について課税されることはありません。
一定の賃料とは、国税局が定める「賃貸相当額」の50%以上のことを指し、社員が会社にこの金額を支払っている場合は、給与として課税されませんが、払っていない場合は現物支給の給与として課税されるので注意が必要です。
出張手当
社員が出張した際に、実費の旅費や交通費とは別に支給される日当が出張手当です。
出張手当は福利厚生費(または旅費交通費)として経費計上できます。
費用として認められるためには、出張旅費規定に役職ごとの妥当な日当金額が記載されていることが必要です。
出張の多い会社は大きな節税メリットを発揮できるでしょう。
忘年会・新年会
社内行事として福利厚生費となります。
ただし、一部の人だけで実施する場合には交際費等に計上されるので、全員参加することが必要です。
全員参加といっても、一度に全員が集まって忘年会や新年会を実施する必要はありません。
「全員が参加する権利がある」ことを前提に、部署ごとで開催しても福利厚生費として認められます。また、結果的に数人の社員が参加できなくなっても問題ありません。
あまりに豪華すぎる飲食や2次会の費用は、福利厚生費として認められないので注意しましょう。
社員旅行
社員旅行は旅行の日程が4泊5日以内で、参加人数が全体の人数の50%以上であれば福利厚生費として計上できます。
ただし、ビジネスクラスの使用など豪勢な旅行は経費として損金算入できません。最低限の金額を会社は負担するようにしましょう。
まとめ
福利厚生は社員のモチベーションアップや勤務上必要な出費をカバーする手段として活用できるだけでなく、給与支給などの手段と異なり税務上の負担を軽減してくれる側面を持ちます。
必要な費用で福利厚生として計上できる場合は、ぜひ節税のために活用してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -
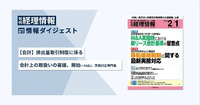
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース