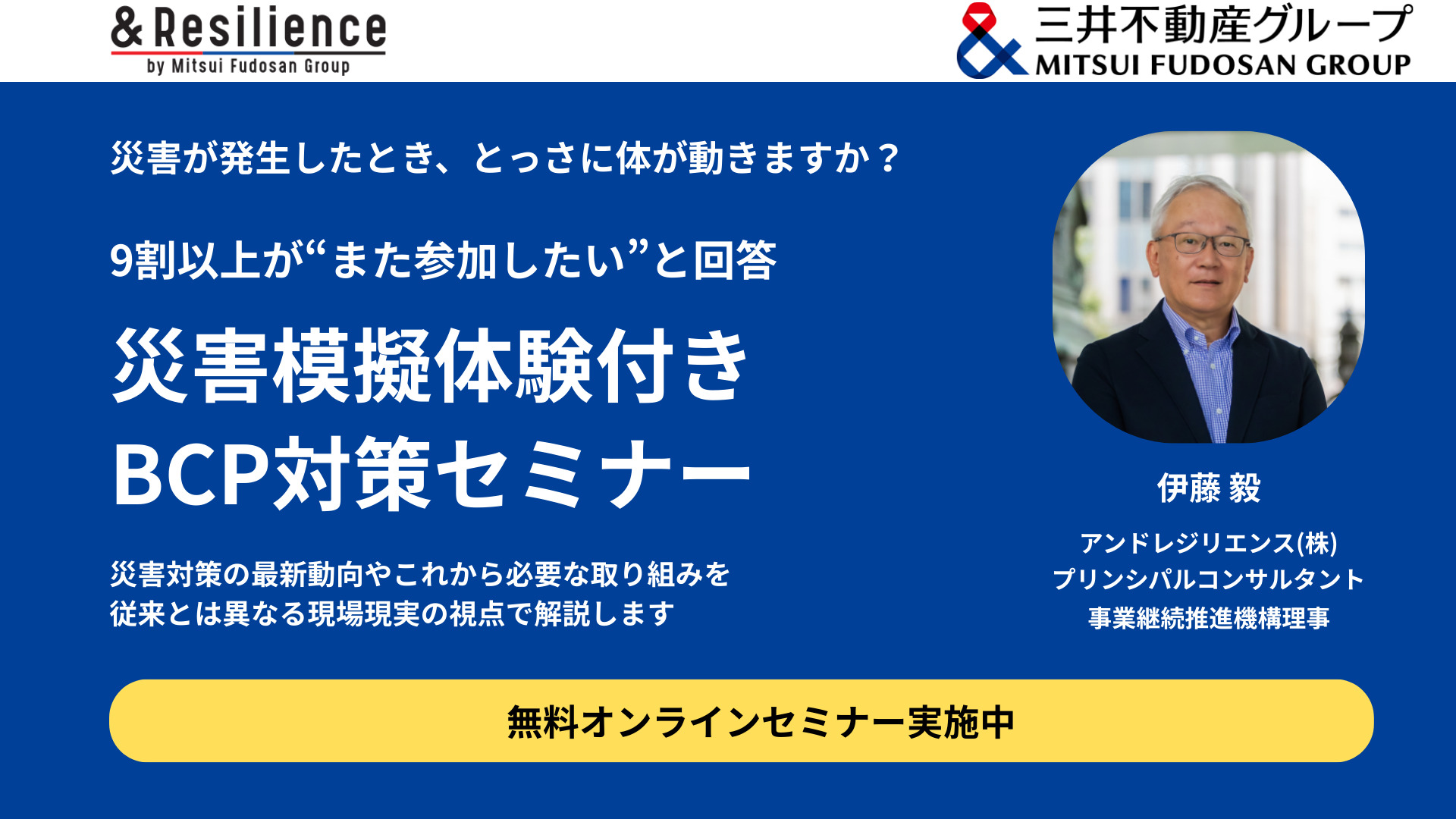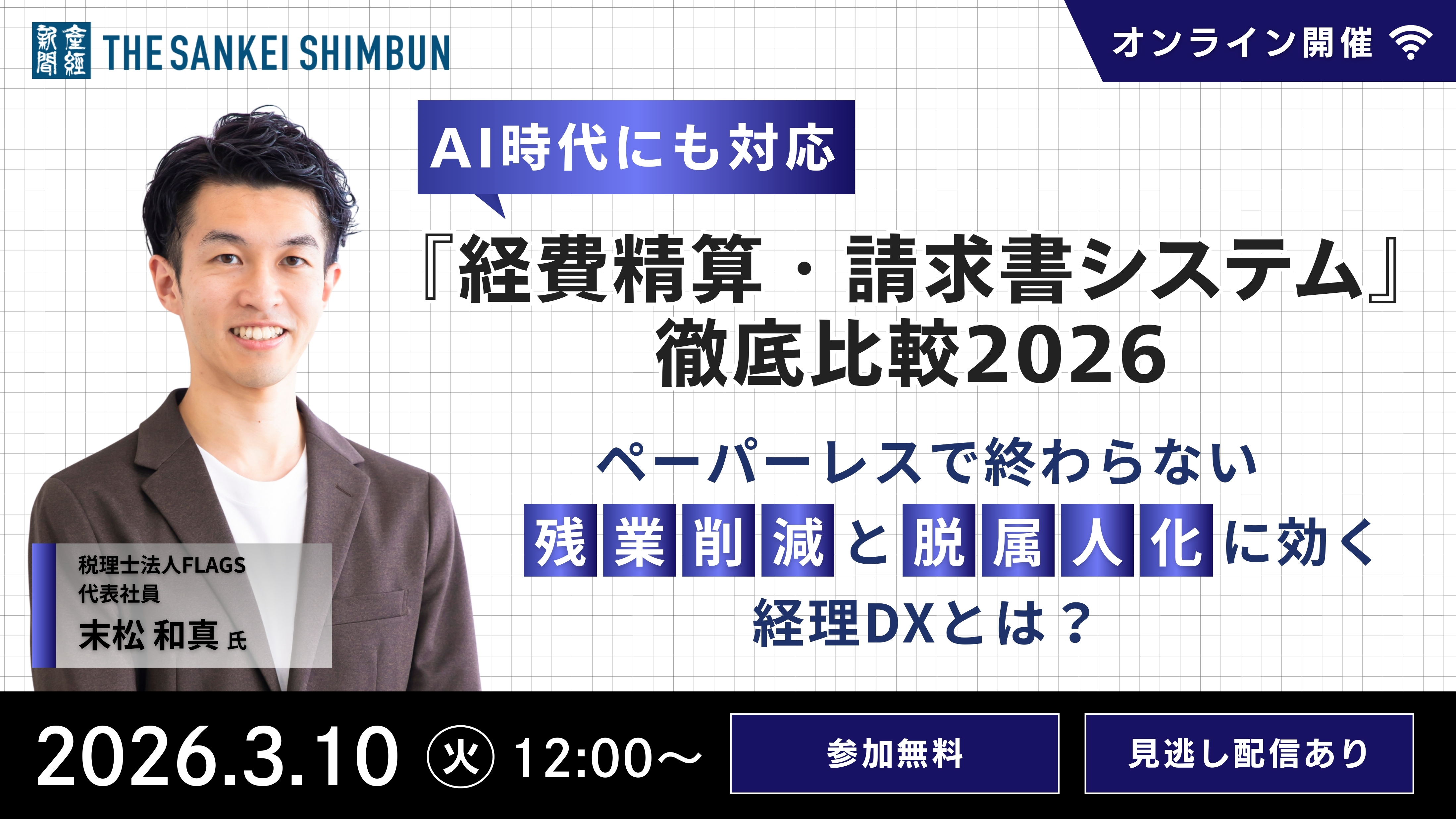公開日 /-create_datetime-/

あなたのまわりに休職している社員はいませんか。休職は、仕事を休んでいる状態ですが、風邪などをひいて熱を出して会社を休む「欠勤」とは異なるのでしょうか。休職に要する手続きには、どのようなものがあるのでしょう。
休職とは
休職とは、会社などの従業員が、ケガや病気などで仕事が難しくなるなど、自分の都合で仕事から離れることです。休職中の従業員は、労働する法的義務を負いません。
休職は「欠勤」や「休業」と区別されなければなりません。
欠勤は風邪などの体調不良などで、一時的に仕事を休むことです。半日ほど休む(遅刻・早退)こともあるでしょうし、連続して3日ぐらい自宅療養をすることもあります。ただし、休職とは異なり、その出勤日に働く法的義務は消えていません。それにもかかわらず、やむをえず仕事を休んでいる状態です。
もちろん、会社に届け出ない「無断欠勤」は、会社と従業員の間の信頼関係を壊しかねず、懲戒の対象となるおそれがあります。長期間の無断欠勤では、解雇(労働契約解除)の可能性もあります。
会社の許可を得て欠勤していても、欠勤中の期間は無給となります。「ノーワーク・ノーペイの原則」によって、労働が提供されない限り、会社は原則としてその対価を支払う義務がないのです。
また休業は、休職と異なり、業務用機器の大規模な故障など、会社の事情によって従業員に仕事をさせないことです。この場合は会社に責任があり、従業員側には責任がないのが一般的ですので、休業中の給与は例外的に支給されることが多いです。
休職中の給与
休職中の従業員は労働を提供していませんが、そもそも休職期間中は労働の義務を負っていませんので、「ノーワーク・ノーペイの原則」は当てはまりません。ただし、会社が特別に休職期間中にも、特別な手当を支給する場合があります。休職が始まってしばらくの間は満額の給与分の手当が支給されるものの、休職が長期間にわたると、手当が徐々に減額されたり、支給されなくなったりする場合があります。
休職中に手当が支給されない場合、保険協会・保険組合に申請することで、健康保険から「傷病手当金」が支給されることがあります。
休職期間中の取り扱いについては、従業員にとって一方的に不利なルールを定めない限り、会社が就業規則で自由に定められます。
なお、手当が出ないからといって、休職中に有給休暇を取得することは認められません。有給休暇の取得は、その従業員に労働義務が課されていることが前提だからです。
休職中の解雇
前述の通り、無断欠勤が続けば解雇の対象になりますが、重い病気やケガなど、やむを得ない事情がある場合には、欠勤ではなく休職として扱って、労働義務から解放しなければなりません。
もし、重い病気やケガが原因で欠勤が続いたとしても、そのことを理由にする解雇は裁判所によって認められない可能性が高いです。日本の労働法体系で、会社が従業員を解雇するハードルはかなり高く設定されており、それによって従業員が保護されています。
まずは、休職という取り扱いを挟んで様子を見て、その病気やケガの種類や程度によって、通常であれば仕事に戻れるまで回復してもしかるべき期間(数ヵ月から数年)を待っても、回復がみられない場合に、やむをえず解雇することは可能となります。
ただし、休職を決める前に、会社は任意に「自己都合退職」の意思を本人に確認したり、「退職勧奨」を行ったりする余地はあります。もし、従業員に復職の意思があれば、退職勧奨に応じる必要はありません。毅然とした態度で、休職の取り扱いを求めるようにしましょう。
復職(職場復帰)
休職は従業員の自己都合とはいえ、病気やケガなどやむを得ない事情があります。会社は可能な限り、その従業員がもともと勤めていた職場やセクションに戻れるよう、復職の努力をしなければなりません。休職を取得したことを理由として、配置転換や減給などを行えば、他の従業員が休職制度を使うことをためらってしまいます。
復職をきっかけとした配置転換や減給は、休職以外に何かやむを得ない事情がある場合に限られると考えるべきです。
休職が認められる事柄
病気やケガ
特に近年、問題となるのは、がんや鬱病です。
医療技術の進歩によって、がんが進行している患者も就労可能な状態になっている例が増えています。本人に働く意思がある限り、会社はその意思を最大限に尊重すべきです。働くことが生きる意欲に繋がる場合もありますので、がん患者だからといって業務量を減らしたりと手心を加えることは、かえって本人の自尊心を削いでしまいかねません。
がん患者は、体調が急変することもありますので、職場で働かせることに躊躇する企業の事情も理解できます。しかし、休職制度の採用も合わせて、がんを罹患したからといって安易に解雇しないようにしなければなりません。
鬱病などメンタルヘルスを損なった従業員の休職や復職については、会社が十分なケアを行う必要があります。鬱病の治癒には数ヵ月から数年の期間を要する場合があり、会社も粘り強く、治癒を待つべきです。
鬱病は、定時の仕事で毎日の生活リズムが整うことによって、回復しやすくなる場合も多いのです。また、メンタルヘルスを損なった従業員のケアで特に重要なのは、へたに復職させたために「再休職」してしまうリスクです。仕事内容にストレスの原因があると、労災認定されて会社の責任を問われかねません。言動に違和感があったり、突然連絡が取れなくなるなどの異変があれば、ご家族と連携を取り、病院の受診命令を出すように努めましょう。
逮捕・裁判
民事事件の被告として裁判に巻き込まれる場合がありますし、犯罪の容疑を掛けられて逮捕・勾留されることもあります。こうした司法手続きへの対応で仕事に就けない場合がありえますので、その場合は休職手続きを採りましょう。
「裁判沙汰」という言葉があるとおり、日本では裁判に巻き込まれている時点で、「面倒なことになっている」「何かやったに違いない」と色眼鏡でみられがちです。しかし、証拠に基づいて最終的な判断を出すのは裁判所です。刑事手続きなら有罪が確定するまで無愛が推定されていますので、本人が罪を認めていない以上は、休職で裁判の行方を見守るべきです。
留学・海外青年協力隊
自己研鑽や国際貢献のため、しばらく日本を離れるために休職することがありえます。多くの場合は期間が決まっているでしょうから、復職のときの問題も少ないはずです。
留学の場合は、海外に拠点がある企業であれば、そこで就労を続ける余地がありますし、リモートワークの可能性も検討すべきでしょう。
休職する際に必要な手続き
休職の手続きについては、会社ごとに対応が異なりますので、まずは就業規則を確認しましょう。そして、直属の上司に相談するようにします。休職の意思が受け入れられれば、その上司が社長や管理職などに伝えてくれます。
別に休職届などの作成や提出などの手続きが求められることも少なくありません。
確かに、休職は従業員の権利ですが、その権利を振りかざしたり、会社に対して不満を述べたりすることは避けましょう。会社や上司、同僚にとっても、引き継ぎなどの負担が増えることは間違いないのです。
休職を認めてもらえることに感謝の意思を表明し、復職の意思も伝えましょう。また、休職中も定期的に、直属の上司に連絡を入れるようにすると印象がいいです。このあたりの感情的なケアをおろそかにしていると、会社から退職勧奨を受けることもありえます。
まとめ
休職とは、会社の従業員という地位は維持しつつ、長期間にわたって労働義務を負わないことです。会社にとってその待遇や手続きはさまざまです。基本的には無給ですが、特別な手当が支払われる会社もあります。病気やケガからの復職では、会社の協力やケアも必要となります。このほか、裁判や留学などによる休職も認められます。
休職通知書 無料ダウンロードはこちらから!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
ニュース -

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査
ニュース -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
ニュース -

バリューチェーン分析を戦略に活かす方法
ニュース -

取引先とのファイル共有|メール添付をやめて「安全な場所」を作る方法
ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説
ニュース