公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。
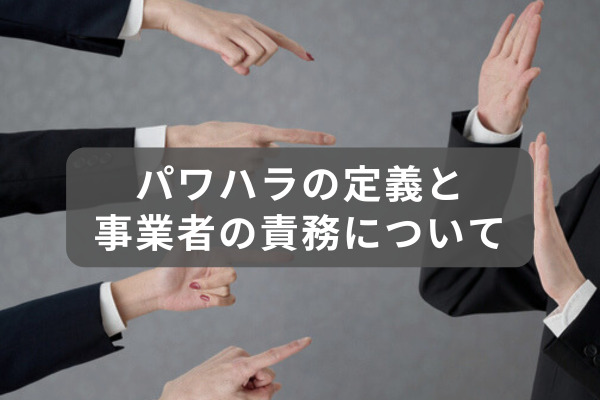
厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40975.html)によると、昨年度において仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害になり、労災と認められた人は883人と、過去最多となっています。その原因を詳しく見ると、「上司などからのパワハラ」が157人と最も多くなっております。
今回の記事ではパワハラの定義と、それについて課される事業者の責務についてご説明していきます。
直接的に「パワーハラスメント」という用語の定義を定めた法律や条文はないのですが、労働施策総合推進法第30条の2において、実質的なパワハラの定義が記載されております。それによれば、パワハラとは職場において行われる
以上3つの要件をすべて備えたものである、とされています。注意点としては、「職場」といってもいわゆるオフィスだけに限定されるものではなく、出張先なども該当しますし、「優越的な関係」とは必ずしも職位が上ということを意味せず、部下や同僚からの行為も該当可能性があります。
なお、厚生労働省が発表している『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』(以下『指針』)(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf)によれば、代表的なパワハラ言動として以下の6つが挙げられています。
殴打、足蹴りを行うこと、相手にものを投げつけることなどが該当します。
人格否定の言動や必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返し、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責の繰り返しなどが該当します。
自身の意に沿わない労働者に対して仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離したり自宅研修させることや、一人の労働者に対し同僚が集団で無視をすることなどが該当します。
記事提供元

企業経営並びに人事に関わる全てのみなさまへ
創業以来、お客様の右腕、そしてパートナーとして、発展の事業支援、事業創造のお手伝いをするとともに、
阻害するリスクに対してお客様とともに戦い、お客様の価値向上の環境づくりに邁進しております。
お客様の発展並びに価値向上のため、本業に専念できる環境を作ることで一緒に歩み価値を創造していく。これが当事務所の思いです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
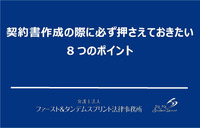
契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
公開日 /-create_datetime-/