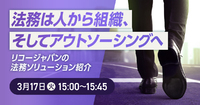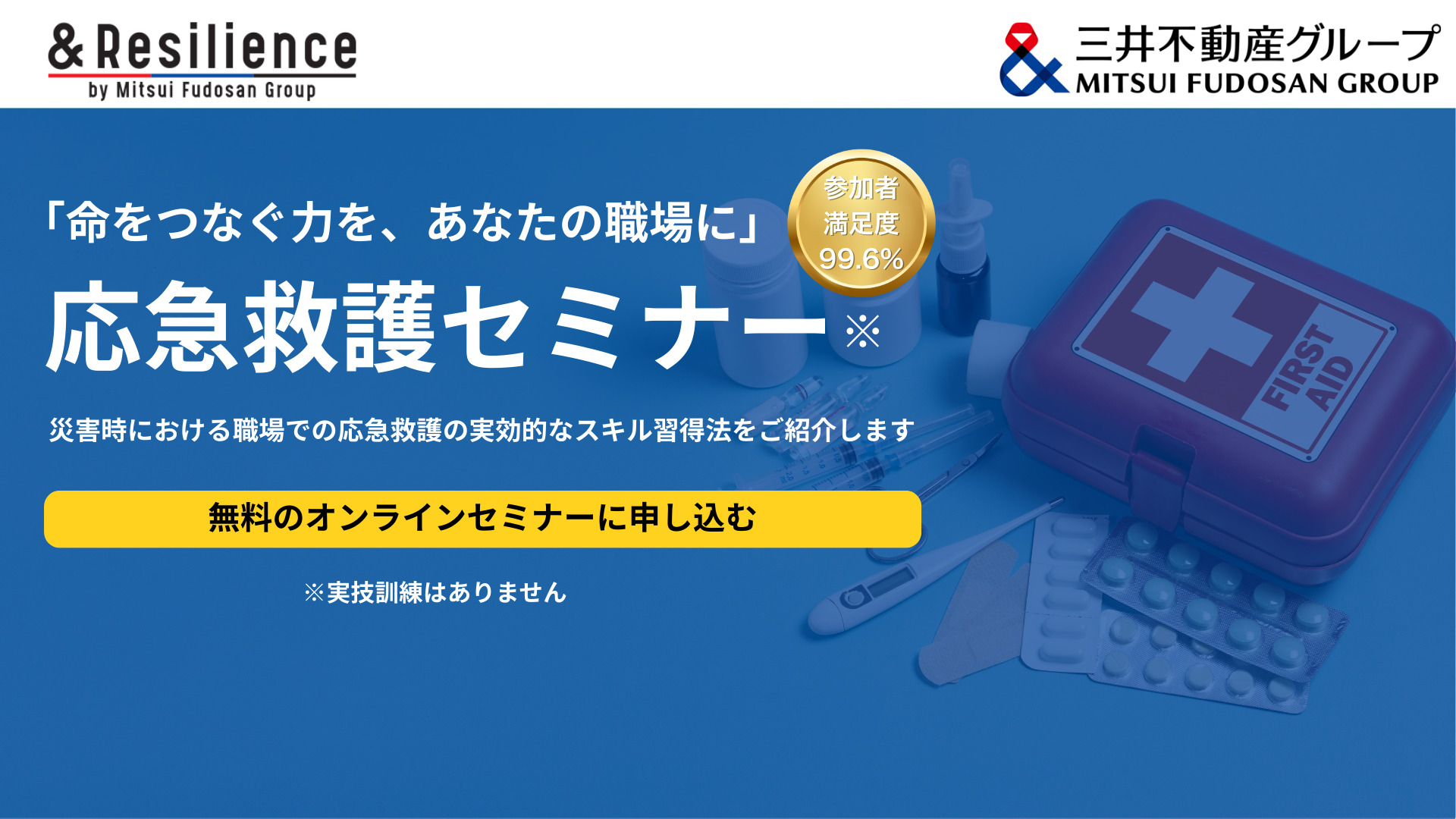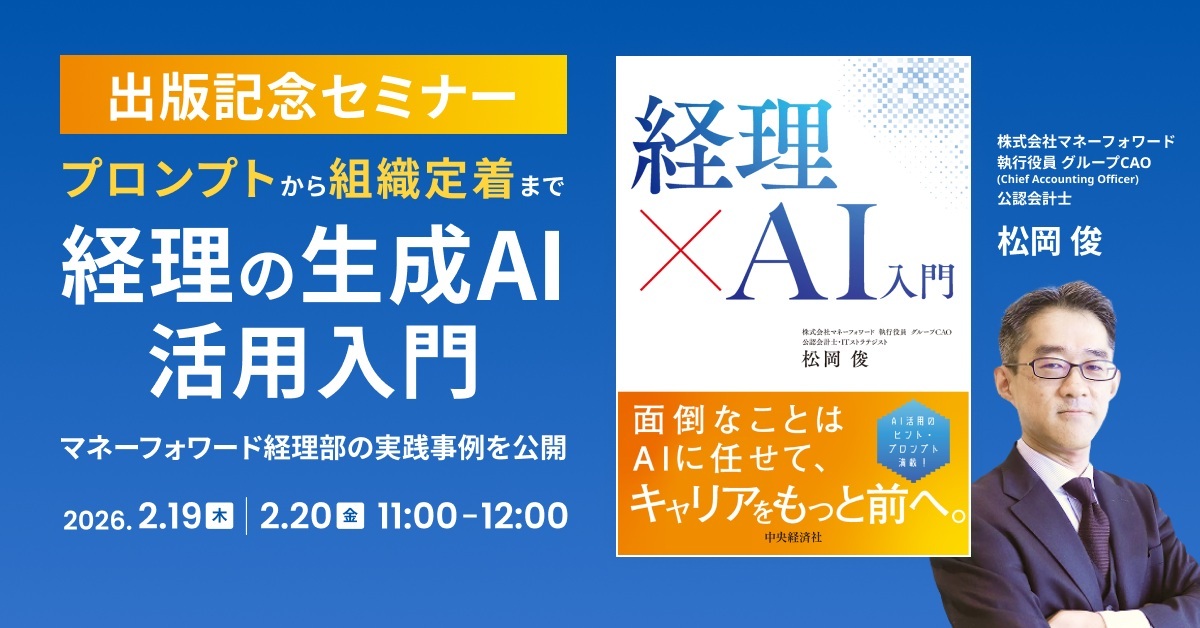公開日 /-create_datetime-/
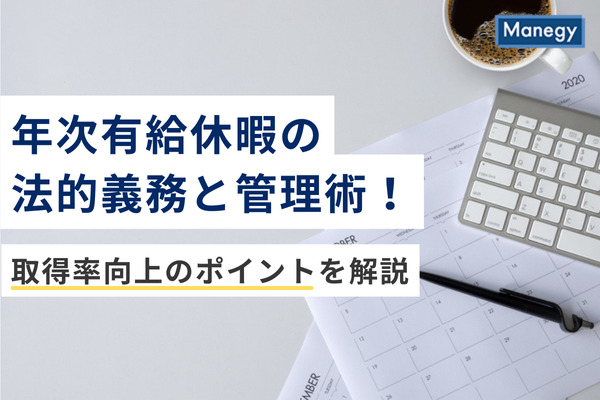
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
1. 年次有給休暇の法的義務と適切な管理方法
まず年次有給休暇の法的根拠について確認しておきましょう。年次有給休暇、いわゆる「有休」「年休」などと呼ばれているものですが、これは労基法第39条に規定されており、同条が定める条件を満たした労働者に対しては必ず付与しなければならないものとなっています。
その条件は二つあります。一つ目は「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務している」というものです。そのため継続6ヶ月勤務に満たない労働者には年次有給休暇を付与する法的義務はありません。この「継続勤務」とは労働契約の継続期間=在籍期間を指すので、例えば定年退職者を再雇用したときや休職者の復職、会社の合併、在籍型出向などの場合であっても、労働契約が実質的に継続していると認められるかぎり勤務年数を通算すべきとされております。
二つ目は「全労働日の8割以上出勤したこと」です。したがって全労働日の8割以上出勤していなければ、当該期間に対応した年次有給休暇を付与する法的義務はありません(この部分は2で詳述します)。ここでいう労働日とは、就業規則などにおいて当該労働者が就労すべきとされている日を指します。また外形的には就労していなくても、業務上の負傷・疾病のために休業した期間、産前産後の女性が労基法第65条(産前産後休業)の規定によって休業した期間、育児介護休業法第2条第1号・第2号の規定によって育児休業・介護休業を取得した期間については、出勤したものとみなさなくてはなりません。
なお、労働者から年次有給休暇取得の申出(時季指定)があった場合、時季指定があったその日に取得させることがあくまで基本となります。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は当該時季を変更して付与することができます(時季変更権の行使)が、これには様々な条件があり、例えば使用者が代替要員確保の努力など適切な配慮をせずに時季変更権を行使することは認められませんので注意しましょう。
次に年次有給休暇の適切な管理方法ですが、「年次有給休暇管理簿」を作成して3年間保存しておく法的義務(労基則第24条の7)があります。この管理簿に決まった書式はありませんが、労働者に年次有給休暇を与えた時(労働者による請求だけではなく、計画的付与・使用者からの時季指定による付与も含みます。計画的付与については3,使用者からの時季指定による付与については4で詳述します)に、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書面でなければなりません。なお、労働者名簿又は賃金台帳と併せて作成しておくことも可能です。
lockこの記事は会員限定記事です(残り6165文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
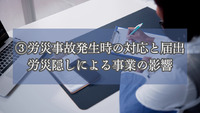
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
ニュース -

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
ニュース -

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得
ニュース -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース