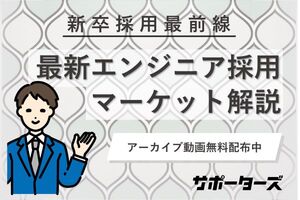公開日 /-create_datetime-/
充実した福利厚生とメンタルヘルス対策で組織力を高める重要性
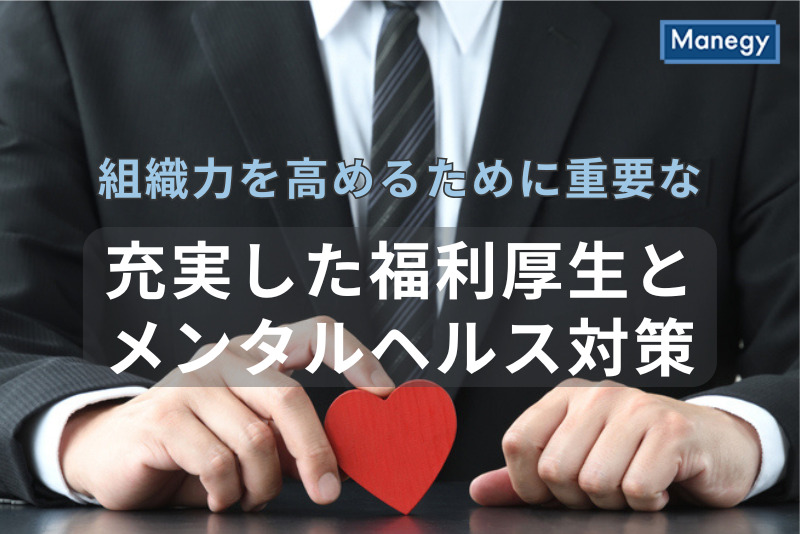
これまでは、人事制度の一部とされてきた「福利厚生」。財形貯蓄制度、通勤手当や家賃補助といった、従業員が働く上で必要な生活支援制度が多く存在しています。
しかし昨今では、働き方の多様化が進む中で、ライフステージやライフスタイルに合わせた「充実した福利厚生制度」を武器に、従業員の満足度向上や優秀な人材の確保・定着につながる「攻めの人事制度」を行う企業が増えています。
一方で、従業員が心身ともに健康で働ける環境を整えるために、昨今では「メンタルヘルス対策」に取り組む企業も増加しています。離職率の増加や生産性低下のリスクを防ぐ「守りの人事制度」として欠かせない要素です。この両輪をバランスよく推進することで、従業員のモチベーション向上や定着率の改善、そして組織力を高めることに寄与するでしょう。
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
堅田 康太(カタタ コウタ)
jinjer株式会社
PMM(プロダクトマーケティングマネージャー)/ ジンジャー人事DX総研フェロー
jinjer株式会社に入社後、事業開発部門にてLegalTechやFinTechなどの新規事業の立ち上げにおよび推進に従事。その後、プロダクト部門に異動しPMMとして、「ジンジャー」のタレントマネジメント製品(人事評価、人事データ分析、eラーニング、福利厚生)の構想から戦略立案・実行まで幅広く担当。
働き方改革関連法などの法改正に伴い、従業員のライフスタイルも変化
働き方改革関連法(※1)により有給休暇の取得が義務化されることや、労働基準法(※2)の改正で、時間外労働時間の上限が規制されました。また、育児・介護休業法の改正に伴い、男性の仕事と家庭の両立がより重要視されるようになり、従業員の働き方を見直す企業が増えています。
とくに長時間労働は、従業員の健康を害したり、仕事と家庭生活の両立を妨げ、女性のキャリア形成や男性の家庭参加を阻む原因となっています。
そのような背景から、法改正と併せて、従業員の健康増進やメンタルヘルス対策の推進に関しても、法的な指針が示されるようになりました。このように、法改正に伴う従業員のライフスタイルの変化により、企業が従業員をどのようにサポートしていくのかについて、より一層焦点が当てられるようになってきています。
lockこの記事は会員限定記事です(残り2274文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
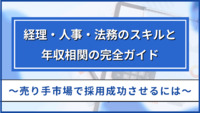
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -
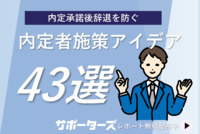
【内定者フォロー施策】内定承諾後辞退を防ぐ 内定者フォロー施策アイデア43選
おすすめ資料 -
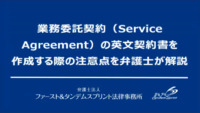
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
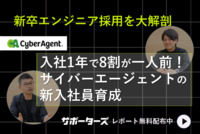
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成
おすすめ資料 -
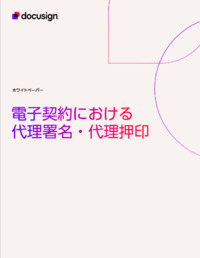
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

【2025年対応】日商簿記2級の出題範囲・学習法を一挙に紹介!
ニュース -

企業存続のカギを握る「事業承継」のコツ
ニュース -
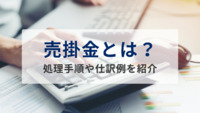
売掛金とは?処理手順や仕訳例を紹介
ニュース -

企業が知っておくべきサイバーセキュリティのベストプラクティス
ニュース -
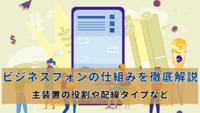
ビジネスフォンの仕組みを徹底解説|主装置の役割や配線タイプなど
ニュース -
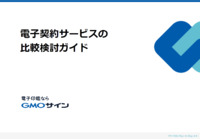
他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -
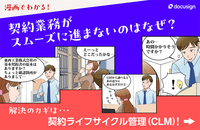
マンガでわかる!契約業務の課題と解決策 〜解決のカギはCLMにあり〜
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -
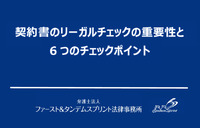
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
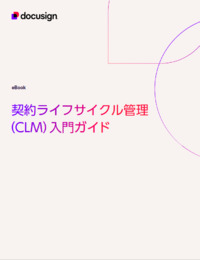
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -
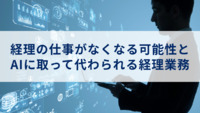
経理の仕事がなくなる可能性とAIに取って代わられる経理業務
ニュース -

【2025年改訂】健康経営戦略マップとは?変更ポイントと実務のヒント
ニュース -
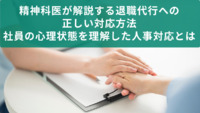
精神科医が解説する退職代行への正しい対応方法|社員の心理状態を理解した人事対応とは【医療法人社団惟心会/株式会社フェアワーク】
ニュース -
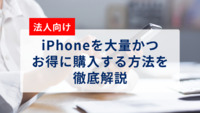
【法人向け】iPhoneを大量かつお得に購入する方法を徹底解説
ニュース -
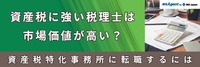
資産税に強い税理士は市場価値が高い?資産税特化事務所に転職するには
ニュース
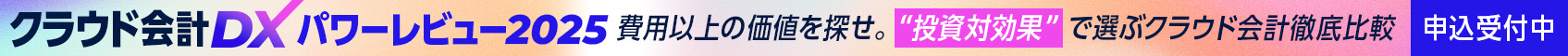









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました