公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
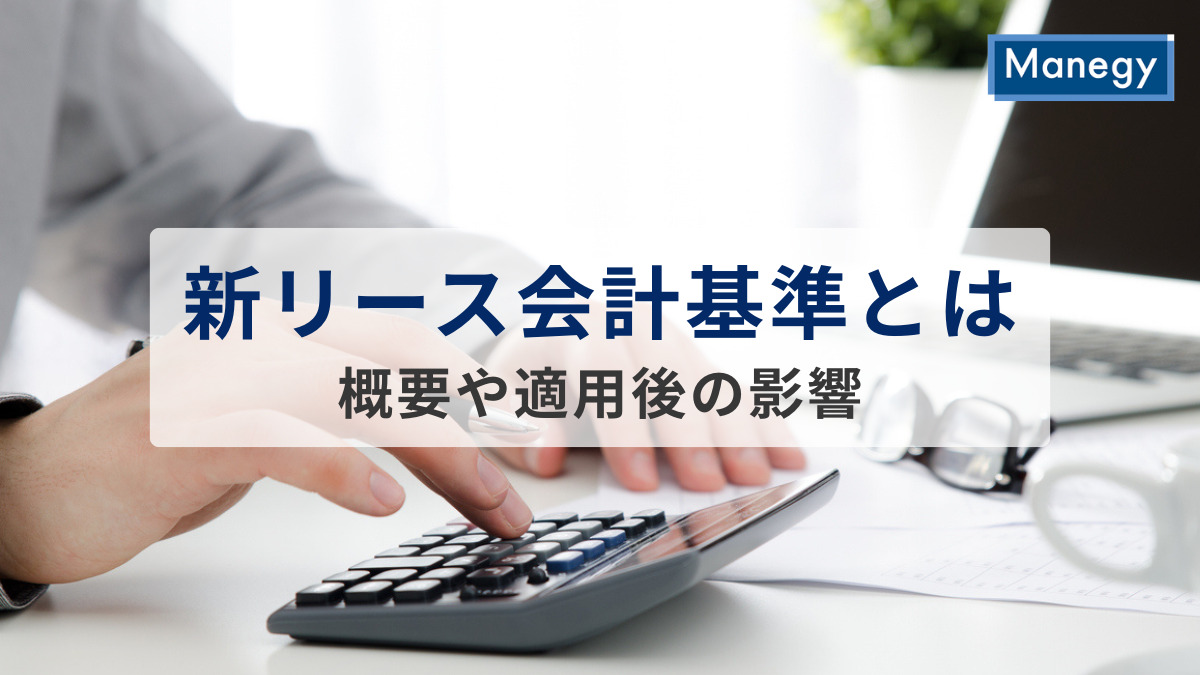
2027年4月1日以降、新リース会計基準が適用されます。借り手の会計処理が大幅に変更されるとともに、貸し手の会計実務にも影響がありそうです。本記事では、リースに関するどのようなルールが変わるか、解説していきます。
新リース会計基準は、2024年9月13日付で企業会計基準委員会(ASBJ)により公表された新たな会計基準です。この改正は、企業の財務情報の透明性向上や国際的な会計基準(IFRS)との整合性確保を目的としています。
従来のリース会計では、借手側がリース契約のうちオペレーティング・リースを貸借対照表に計上しないケースも多く、「実質的な債務が財務諸表に反映されない」という課題がありました。これを受け、改正では経済的実態に基づいた会計処理を促進する方針が示されています。
このような背景から、新リース会計基準は、リース取引の本質を捉え、企業の資産・負債状況をより正確に表す制度として位置づけられています。
新リース会計基準の適用開始日は2026年4月1日以後に開始する事業年度からとされており、それ以前からの早期適用も認められています。対象となるのは主に上場企業や会計監査を受ける大会社であり、すでに準備を進めている企業も見られます。
実務上の大きな変更点は、借手がすべてのリース契約について「使用権資産」と「リース債務」を計上する必要があるという点です。従来のように、オペレーティング・リースをオフバランス処理することはできなくなります。
これにより、企業の財務諸表にはリースに関する資産・負債が反映されるようになり、資産規模や自己資本比率、ROAといった財務指標に影響が及ぶ可能性があります。経営計画や資金調達戦略にも影響するため、早期の影響分析と準備が求められます。
なお、貸手の会計処理については、従来のルールが基本的に維持されますが、開示内容の強化など一部に変更が加わる見込みです。
新リース会計基準は、主に上場企業や大会社を対象としていますが、中小企業にも間接的な影響が及ぶ可能性があります。特に、上場企業のグループ会社として連結対象となっている中小企業や、取引先に上場企業を持つ企業では、リース契約に関する情報提供や会計方針の調整が求められる場合があります。
また、将来的には中小企業向けの会計基準(中小企業会計指針や中小企業の会計に関する基本要領)にも、本基準の考え方が一部反映される可能性があり、完全に無関係とは言い切れません。リース契約が多い業種では、制度の動向を把握しておくことが重要です。
さらに、金融機関とのやり取りにおいて、財務指標の変化が融資判断に影響を与えるケースもあるため、新基準が自社にどのような影響をもたらすかを早めに検討しておくことが望ましいでしょう。
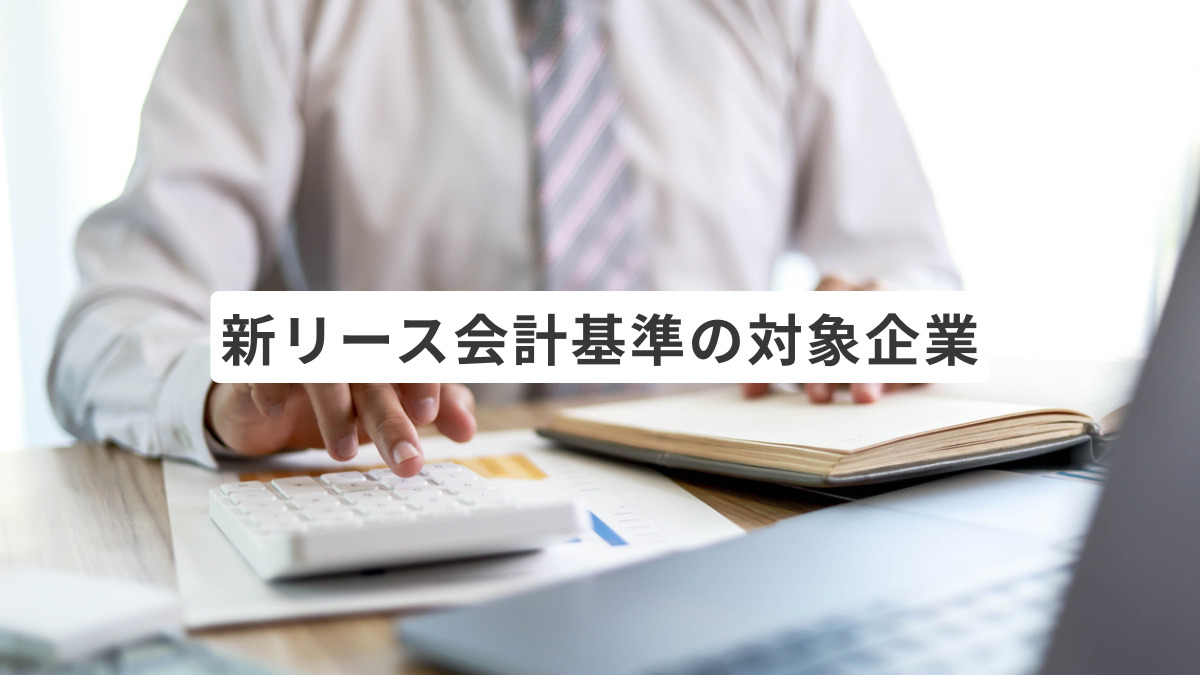
新リース会計基準の対象となるのは、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の提出義務がある企業や、会社法上の大会社に該当する企業です。具体的には、上場企業やその連結子会社、一定の規模を超える大企業が主な適用対象となります。
また、会計監査を受けている企業や、将来的にIPOを予定している企業も、早い段階での対応が望ましいとされています。特に上場準備企業においては、新基準への準拠が審査項目のひとつとなる可能性もあるため、事前の対応が不可欠です。
さらに、親会社が新リース会計基準を適用する場合には、連結対象の子会社や関連会社も基準を揃える必要が生じる可能性があります。そのため、非上場企業や中小企業であっても、グループ企業の方針に基づいて新基準への対応が求められるケースがあります。
このように、新リース会計基準は一部の大企業だけでなく、グループ会社全体に波及する可能性があるため、対象企業かどうかの確認と早期の準備が重要です。
新リース会計基準では、借手(リースを利用する側)と貸手(リースを提供する側)で、それぞれ会計処理に異なる変更が加えられています。とくに借手側の処理方法は、現行基準から大きく見直されています。
借手は、すべてのリース契約について、原則として「使用権資産」と「リース債務」を貸借対照表に計上する必要があります。これは、従来オペレーティング・リースとしてオフバランス処理されていた契約も含まれるため、実質的にすべてのリースがオンバランス化されるという点が大きな特徴です。
具体的には、リース契約開始時に、リース期間中に支払う総額(リース料)を現在価値に割り引いた金額を「リース債務」として負債計上し、対応する資産として「使用権資産」を計上します。その後、リース期間にわたり、利息費用と減価償却費として費用配分していく形となります。
一方、貸手の会計処理については、基本的に現行の区分(ファイナンス・リースとオペレーティング・リース)を維持する方向です。したがって、貸手は契約内容に応じて、資産計上または収益認識を継続して行うことになります。
ただし、新基準では貸手にもリースの分類基準や開示内容の見直しが求められています。たとえば、リース資産のリスク移転に関する情報や、契約条件に関する詳細な注記が必要となる場合があり、情報開示の強化が進められています。
新リース会計基準では、すべてのリース契約を原則として貸借対照表に計上することが求められていますが、実務上の負担を軽減するために一定の例外規定が設けられています。その代表例が、「少額リースの例外規定」です。
具体的には、リース資産の取得価額が300万円以下である場合、使用権資産およびリース負債の計上を省略し、従来どおり費用処理(賃借料処理)を行うことが可能です。これにより、IT機器や備品、車両などの少額なリース契約については、従来の実務を継続できるため、企業の経理処理の簡便化につながります。
ただし、この300万円という基準は、「リース1件ごとの取得価額」で判定する必要があり、複数契約を一括して評価することはできません。また、契約更新時やリース条件の変更があった場合には、再評価が必要となることもあります。
実務上は、以下のような対応が求められます。
・リース契約ごとの金額を確認し、少額リースに該当するか判定する
・社内で少額リースの定義や判断基準をマニュアル化し、統一的に運用する
・会計監査に備え、少額リースの判断根拠を文書化しておく
このように、例外規定を有効に活用することで、会計処理の負担を軽減しつつ、新基準への対応を進めることが可能です。ただし、判断ミスによる誤った処理を防ぐためにも、明確な社内ルールの整備が重要となります。
新リース会計基準の導入にあたっては、既存のリース契約を見直し、「リースに該当するかどうか」の識別を行うことが重要な実務対応のひとつとなります。とくに初年度の適用時には、すべてのリース契約について再評価を行い、新基準に基づいた会計処理へ移行する必要があります。
リースの識別とは?
「リースの識別」とは、契約において特定の資産の使用権が借手に移転しているか、つまり借手がその資産を指図・支配できる権利を有しているかを判断するプロセスです。新基準では、形式的な契約名ではなく、契約の実質に基づいてリースか否かを判断する必要があります。
具体的には、以下のような観点から判断します。
・契約に特定の資産(例:機械、車両など)が明示されているか
・借手がその資産を単独で使用・管理できるか
・借手が使用方法を決定し、経済的便益を享受できるか
これらの要素を満たす場合は、「リース契約」と識別され、使用権資産およびリース債務の計上対象となります。
実務上の見直しポイント
リースの識別と会計処理において、以下のような実務対応が求められます。
・契約書の内容を再確認し、リースかどうかを1件ずつ識別
・リース期間や延長オプションの有無、解約条件を精査
・「非リース要素(例:メンテナンス費用等)」との区分を明確化
・社内ルールやチェックリストを整備し、識別判断を標準化
また、ITシステムや契約管理台帳を活用して、識別の根拠を記録・保存しておくことも重要です。監査対応や将来的な契約変更への備えとして、契約管理の透明性が求められます。
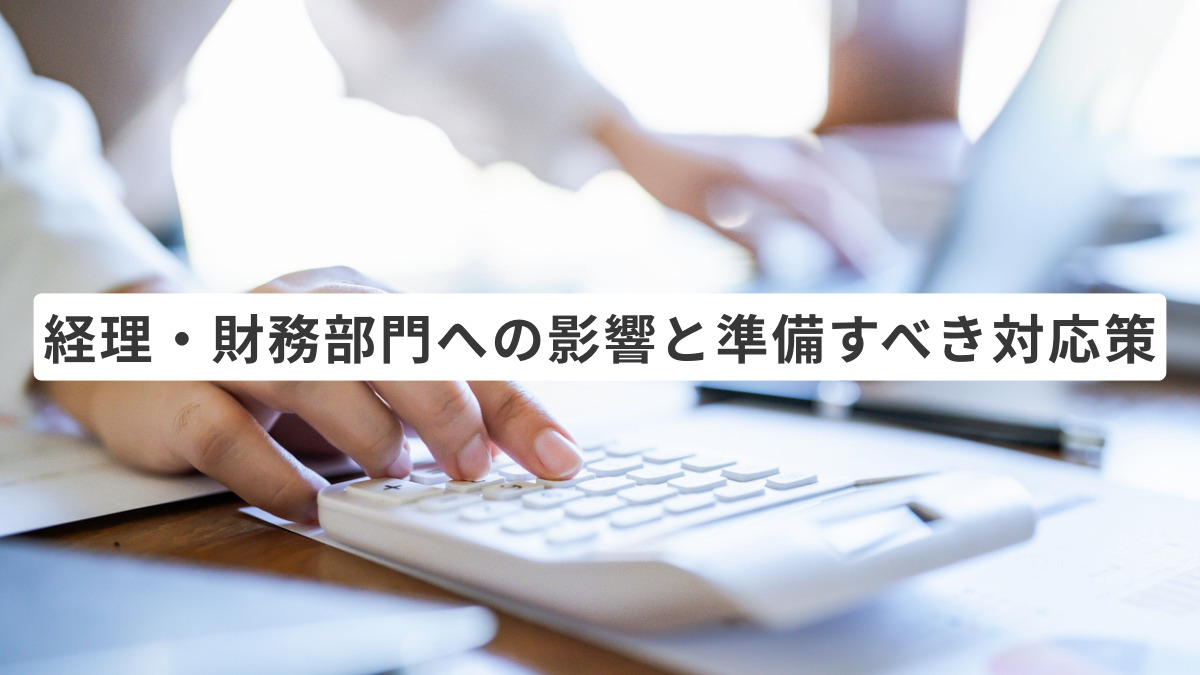
新リース会計基準の適用により、経理・財務部門には大きな影響が及ぶことが予想されます。とくに、すべてのリース契約を原則オンバランス処理とすることにより、業務負担の増加や財務数値への影響が懸念されます。
主な影響
まず、リース契約に関する情報を正確に把握し、使用権資産とリース債務の計上処理を行う必要があります。そのため、契約書の管理体制や内容の把握に時間と手間がかかるだけでなく、資産・負債の増加による財務指標の変動にも注意が必要です。
具体的には、以下のような影響が想定されます。
・ROAや自己資本比率などの財務指標が変化する
・決算業務の負担が増大する(契約内容の評価、計算処理など)
・会計システムやリース管理システムの見直しが必要となる
・経営陣や監査法人、金融機関への説明が求められる
準備すべき対応策
これらの影響に備えて、経理・財務部門では以下のような準備が求められます。
・既存のリース契約の棚卸しと識別作業
・契約情報の一元管理体制の構築(Excelや契約管理ツールの活用)
・新基準に対応した会計システムの導入または改修
・社内ルールやマニュアルの整備と運用フローの確立
・関連部門(法務・総務・購買など)との連携強化
・経営陣への定期的な報告と影響分析の実施
さらに、適用初年度に向けて、シミュレーションによる財務影響の事前把握や、外部の専門家や税理士・会計士との連携も重要です。
新リース会計基準の導入により、会計処理は大きく変化しますが、税務上の取扱いについては、会計と必ずしも一致するとは限りません。そのため、税務申告においてどのように取り扱うべきか、実務上の整理が必要となります。
現時点では、国税庁による正式な通達やガイドラインは公表されておらず、今後の動向が注目されています。ただし、過去の会計基準改正時の対応を踏まえると、税務上は現行のリース取引の取扱いを維持し、会計上との乖離に対して調整を行う方針になる可能性が高いと考えられています。
たとえば、会計上はリース債務として負債計上した金額についても、税務上は資産計上や損金算入のタイミングが異なる場合があり、別表調整等による処理が必要になるケースがあります。特に中小企業では、税務申告への影響を見落とさないよう注意が必要です。
また、「少額リースの例外規定(300万円以下)」についても、税務上は引き続き費用処理が可能とされる見込みですが、会計と税務の処理を一致させるかどうかは企業判断に委ねられる部分もあるため、社内の会計方針と整合を取った対応が求められます。
今後、国税庁から通達やFAQが発出される可能性があるため、最新情報の確認と、顧問税理士との連携が重要です。会計基準の改正に伴う税務リスクを未然に防ぐためにも、早期からの準備と方針決定が求められます。
国税庁|リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
| チェック項目 | 内容 | 対応状況 |
|---|---|---|
| ① リース契約の棚卸 | 現行の全リース契約を洗い出し、契約内容を一覧化しているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ② リース識別の実施 | 各契約がリースに該当するか、使用権の有無に基づき判定しているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ③ 少額リースの判定ルール策定 | 300万円基準をもとに、社内で明確な判断基準を設けているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ④ 契約書管理の整備 | リース契約書の保管・検索・更新体制を整えているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ⑤ 会計処理ルールの整備 | 使用権資産・リース債務の計上、減価償却・利息配分のルールを決定しているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ⑥ 会計システムの見直し | 新基準対応のため、会計・リース管理システムの改修を検討済みか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ⑦ 財務影響のシミュレーション | ROAや自己資本比率などの財務指標に与える影響を試算しているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ⑧ 経営層への説明 | 経営陣に対し、制度改正の概要と影響について説明しているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ⑨ 関係部門との連携体制 | 法務・総務・購買など、関連部門と情報連携の体制を築いているか | ☐ 済 ☐ 未 |
| ⑩ 税務影響と対応方針の確認 | 税務上の処理方針(別表調整など)を税理士と協議しているか | ☐ 済 ☐ 未 |
新リース会計基準の適用は財務諸表の記載内容が変更されることで、ROA(総資産利益率)などの数値基準が変わるため、会計処理のみならず、経営・財務関連指標にも多大な影響を及ぼすと見られます。多くの分野で早めに対策を立てて準備を進めていきましょう。
参考サイト)
KPMG|今知っておきたい「新リース会計基準」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

オフィスステーション年末調整

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
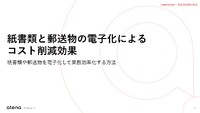
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】
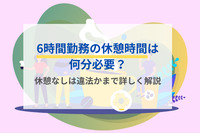
6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
公開日 /-create_datetime-/