公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。
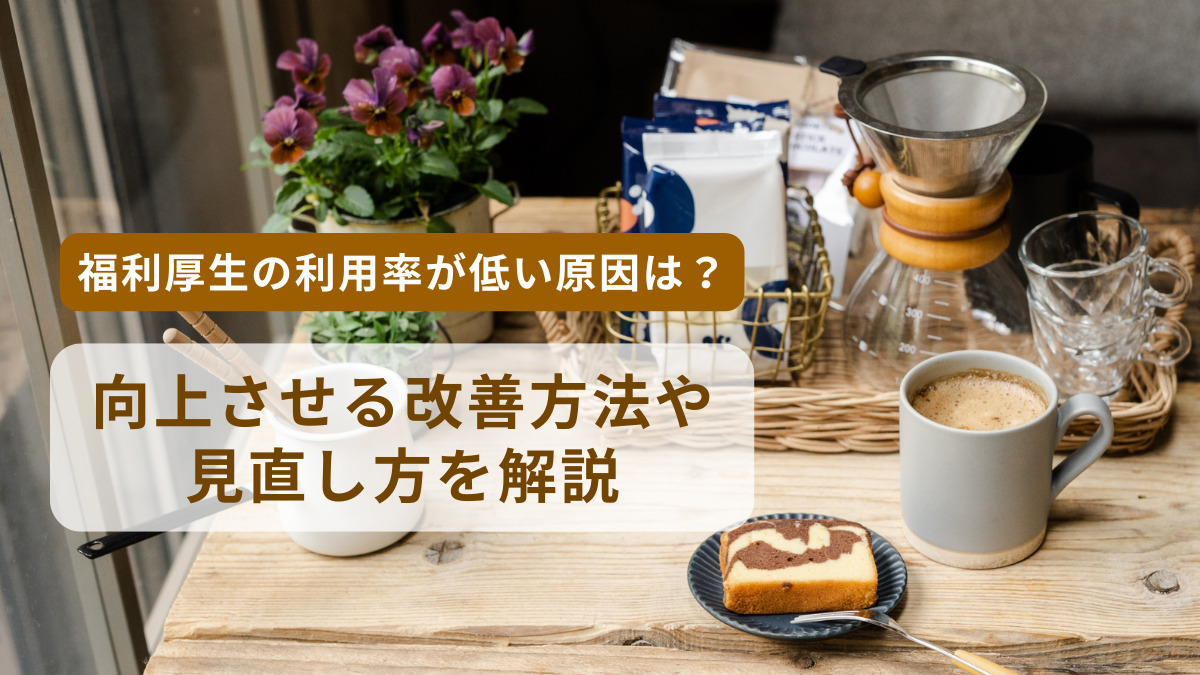
スキルアップ支援や食事補助、特別休暇など…従業員満足度向上や企業競争力強化につながるさまざまな福利厚生サービスが存在しますが、それらの肝心な利用率が思うように上がらずお悩みの企業さまも多いのではないでしょうか。導入に際してかかったコストや労力を無駄にせず少しでも有効活用することで、経費や人材リソースの浪費を防ぎながら、より効果的な労働環境改善につなげられます。
今回は福利厚生の利用率が低迷する根本的な原因を探り、具体的な改善策をいくつかご提案します。特にサービス内容に自社のニーズとのミスマッチがあった場合は、一日でも早くそのことに気づくことがカギといえます。制度の見直し方法や従業員フィードバックの重要性にも触れながら、持続可能な福利厚生制度の構築方法について理解を深めていきましょう。従業員へ手軽に活用価値を浸透させられる、健康的で上質なマルシェ置き菓子『snaq.me office (スナックミーオフィス)』の魅力についてもあわせてご覧ください。

企業が従業員のために用意した福利厚生サービス。その利用率が低迷してしまう背景にはさまざまな要因が絡み合っており、早期の発見および改善が欠かせません。まずは、多くの企業が直面している利用率低下の主な原因について深く掘り下げていきます。
福利厚生サービスの存在自体を知らない、あるいは詳細を理解していない従業員が多いことが利用率低下の大きな要因となっています。入社研修時、あるいはサービスの新規導入時に一度説明しただけでその後のフォローアップが不十分な場合や、社内の情報共有システムが効果的に活用されていない状況では、せっかくのサービスが埋もれてしまいます。
同時にサービスの内容が専門的であればあるほど、従業員は自分に関係のないものと誤解してしまう可能性もあります。特にライフステージに特化した福利厚生(託児施設・介護支援・マイホーム手当など)の場合、いざ必要になったタイミングでサポート制度の存在を把握していないと、活用チャンスの大きな損失につながりかねません。
従業員のニーズと提供されているサービスの内容が合致していないケースも少なくありません。たとえば、若手社員が多い企業で高齢者向けのサービスばかりが充実していたり、逆に中高年層が中心の職場で育児支援サービスに偏っていたりすると、利用率は自然と低下してしまいます。外出・出張が多い企業では社食の利用率が低くなるなどのケースも考えられます。
また、時代とともに変化する従業員のライフスタイルやワークスタイルに、福利厚生のアップデートが追いついていないことも考えられます。特に昨今のテレワークの普及や、ワークライフバランスへの意識の高まりを考慮すると、従来型のサービスでは対応しきれない部分が出てきているかもしれません。
そもそも福利厚生サービスを利用したくても、申請手続きが複雑で面倒だと感じてしまう従業員も多いようです。紙の申請書類や複数の部署を経由する承認プロセスなど、手続きに時間がかかるシステムでは、従業員の利用意欲を削いでしまう可能性があります。
さらに利用可能な条件や制限事項が細かく設定されている場合、それらを理解すること自体に労力がかかってしまい、結果として「面倒だから使わない」という選択につながることもあります。特に、急な必要性が生じた際にすぐに利用できないようなシステムでは、サービスの魅力が半減してしまいます。
たとえば書籍購入やセミナー受講、資格取得にかかる費用の企業負担といった福利厚生においては、長時間労働や残業があまりに常態化している職場環境の場合、自己研鑽に励む時間と心の余裕がなく利用を躊躇・敬遠してしまうケースもあることでしょう。
利用可能時間が著しく限定されている場合も利用率低下の一因となります。たとえば平日の営業時間内でしか利用できないサービスや、逆に休日のみ利用可能なサービスなどは、多くの従業員にとってアクセスしづらいものとなってしまいます。
福利厚生の利用に対する心理的な抵抗感も、利用率低下の重要な要因のひとつ。「利用すると周囲から何か言われるのではないか」「休暇を取ることで同僚に迷惑をかけてしまうのではないか」といった懸念から、利用を控える従業員も少なくありません。特に日本の企業文化においては、個人的な事情よりも組織の利益を優先する風潮が根強く残っている場合があります。このような環境下では、たとえ充実した福利厚生サービスが用意されていたとしても、それを積極的利用することに罪悪感を覚える従業員も存在するでしょう。
さらにプライバシーの観点により、自身の個人的な状況を会社に開示することへの抵抗感から利用を躊躇してしまう従業員もいます。たとえばメンタルヘルスケアや家族の介護支援などのサービスは、その性質上、利用することで自身の私生活の一部を会社に知られてしまうと考える人もいるでしょう。これらの心理的ハードルは、単に制度や仕組みを整えるだけでは解決が難しく、企業文化や職場の雰囲気を根本から変えていく必要がある複雑な課題といえます。
記事提供元

株式会社スナックミーでは、お菓子による複合的法人向けサポート『snaq.me office/スナックミーオフィス』を展開しています。福利厚生の無添加置き菓子・オフィスコーヒー・社食・オフィスコンビニ・コーポレートギフトなどのサービスを通じ、企業さまの健康経営やコミュニケーション活性化を、おいしくてギルトフリーな「おやつ体験」を通じて応援中。人事・総務ご担当者さまや経営者さまを助けるあらゆる情報を発信します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
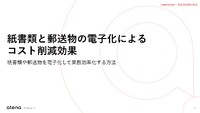
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

英文契約書のリーガルチェックについて

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

ESG・業種特化で差をつける!30代公認会計士が選ばれる理由(前編)

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方
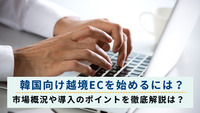
韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説
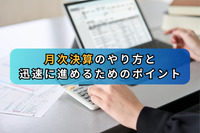
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
公開日 /-create_datetime-/