公開日 /-create_datetime-/
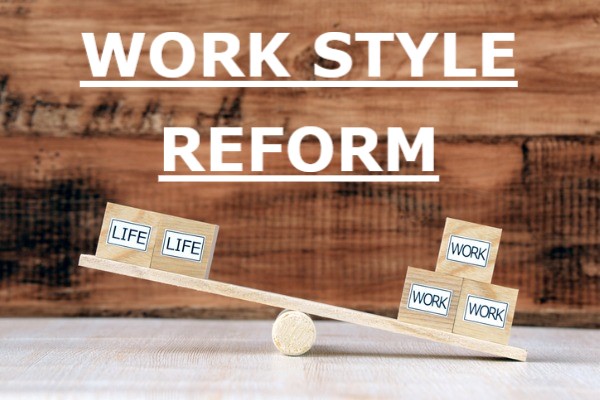
2019年4月1日、働き方改革関連法案が施行されました。これにより残業時間における上限規制や、従業員に年次有給休暇を年5日間取得してもらうことを義務付けるなど、就労に関する新たな規定の導入が始まっています。
これら一連の働き方改革はなぜ行われることになったのでしょうか。また、いつごろからこのような制度の改変が唱えられ始めたのでしょうか。
今回は働き方改革が行われた背景と歴史について紹介します。
目次【本記事の内容】
働き方改革とは何?就労環境を向上させ、労働生産性を高める取り組み
厚生労働省によると、働き方改革とは、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにする制度」(厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」より)とされています。特に重要な改革ポイントとされたのが、労働時間法制の見直しと、雇用形態に関係のない公正な待遇の確保です。
「労働法制の見直し」については、4月から「残業規制の上限規定(原則として月残業45時間、繁忙期などは例外として年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満)」や「勤務インターバル制度」、「高度プロフェッショナル制度」などが新たに導入されました。残業のし過ぎによる働き過ぎを防ぐことで、就労者の健康を守り、多様性のある「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)を実現するというのが法改正の目的です。
また、「雇用形態に関係のない公正な待遇」に関しては、同じ企業内において、正社員と非正規社員の間にある「あらゆる待遇差」に関して、不合理な待遇格差を設定することが関連法によって原則禁止されました。もし待遇差がある場合は、非正社員に対して待遇差の内容、理由について、事業主は説明する義務が生じます。
働き方改革が行われた背景①少子高齢化
ではなぜこのような働き方改革が行われたのでしょうか。その背景にあるのが、「少子高齢化」と「長時間労働を原因とする過労死」の問題です。
『平成30年版高齢社会白書』によれば日本は2010年を境に総人口が次第に減少しつつありますが、15~64歳の「生産年齢人口」については1995年から既に毎年減っているという状況にあります。労働力が減りつつある中でも、育児もしくは介護を理由として離職する必要がある人も多く、このままでは日本経済を支える労働力が将来的にどんどん縮小していくことになるわけです。
このような状況に対して政府は、元気な高齢者も働ける環境を整備すること、そして限りある労働人口でも高い成果を出せるように業務の効率化と生産性の向上を目指すことを、働き方改革によって実現するとしています。実際、公益財団法人「日本生産性本部」の「労働生産性の国際比較2018」によると、日本の時間当たりの労働生産性は47.5ドルで、OECD加盟国中36カ国中20位。この状況を改善したいというのが政府の狙いです。
働き方改革が行われた背景②長時間労働による過労死
また、働き方改革の背景には、日本で蔓延しているサービス残業などを含む長時間残業と、それによる過労死への国民的な関心の高まりもあります。近年、残業の強要によって過労死が起こる事件が相次いでおり、国民全体の中で日本企業における就労体制のあり方に疑問を投げかける意識が高まりつつありました。実際、厚生労働省『平成30年版過労死等防止対策白書』によると、労働者の「所定内労働時間」については年々減少しつつある一方で、残業などの「所定外労働時間」は2009年(平成21年)以降増加傾向にあります。
そうした中で政府は、働き方改革によって日本で蔓延している過度な残業を減らし、多様な働き方ができる就労環境の整備を目指したのです。
第三次安倍第二次改造内閣発足時に「働き方改革担当大臣」と「働き方改革実現会議」を設置
2016年の参議院選挙で自民党が勝利した後に行われた、第三次安部第二次改造内閣発足時、安倍総理は働き方改革に本格的に取り組んでいくために、「働き方改革担当大臣」という職を新たに設けると共に、「働き方改革実現会議」の開催することを明言しました。働き方改革担当大臣の初代大臣に任命されたのは加藤勝信氏で、2018年10月からは根本匠氏が厚生労働大臣と兼任する形で行っています。
働き方改革実現会議は、内閣総理大臣と働き方改革担当大臣を含む閣僚と、有識者15人(大学教授や財界関係者、さらにがんと闘った経験を持つ女優の生稲晃子さんなど)によって構成され、2016年9月26日に第1回会議が行われました。2017年3月まで合計10回にわたって会議が開催され、最終的に「罰則付き時間外労働の上限規制の導入」や「同一労働同一賃金の実効性を確保するための非正規雇用の処遇改善」を盛り込んだ「働き方改革実行計画」が策定されます。この計画書に基づいて、国会で各種法案の改正が行われていきました。
働き方改革関連法が成立
働き方改革実行計画に基づいて立案された働き方関連法案は、2018年6月に国会で可決され、2019年4月から順次施行されていきます。なお、「働き方改革関連法」とは1つの法律を指すのではなく、「労働基準法」や「労働安全衛生法」、「労働時間等設定」など合計で8つの法律改正を総称した言い方です。残業の上限規制や年5日の年次有給休暇を取得してもらうなどの規定は、守られていない場合は罰則が適用されるため、各企業には法に則った適正な対処が求められます。
まとめ
4月から施行が開始された働き方関連法ですが、2016年には制度形成に向けて具体的な動きが始まっていました。実際に改革の内容を詰めていくにあたっては、「働き方改革担当大臣」という新ポストを作成する、あるいは有識者を交えた「働き方改革実現会議」を計10回にわたって行うなど、改革実現に向けての体制がしっかりと作られていった過程があります。
ただ、働き方改革関連法の施行に対しては抜け道が存在し得るなど、その有効性を疑問視する声があるのも事実。どのような変化を経済界にもたらしていくのか、今後も注目を集めそうです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -
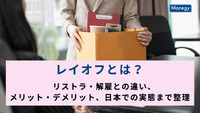
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較
ニュース -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -
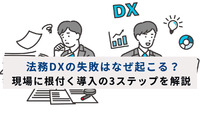
法務DXの失敗はなぜ起こる?現場に根付く導入の3ステップを解説
ニュース -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース




































