公開日 /-create_datetime-/
内部統制とは? 概要と強化するメリットについて詳しく解説
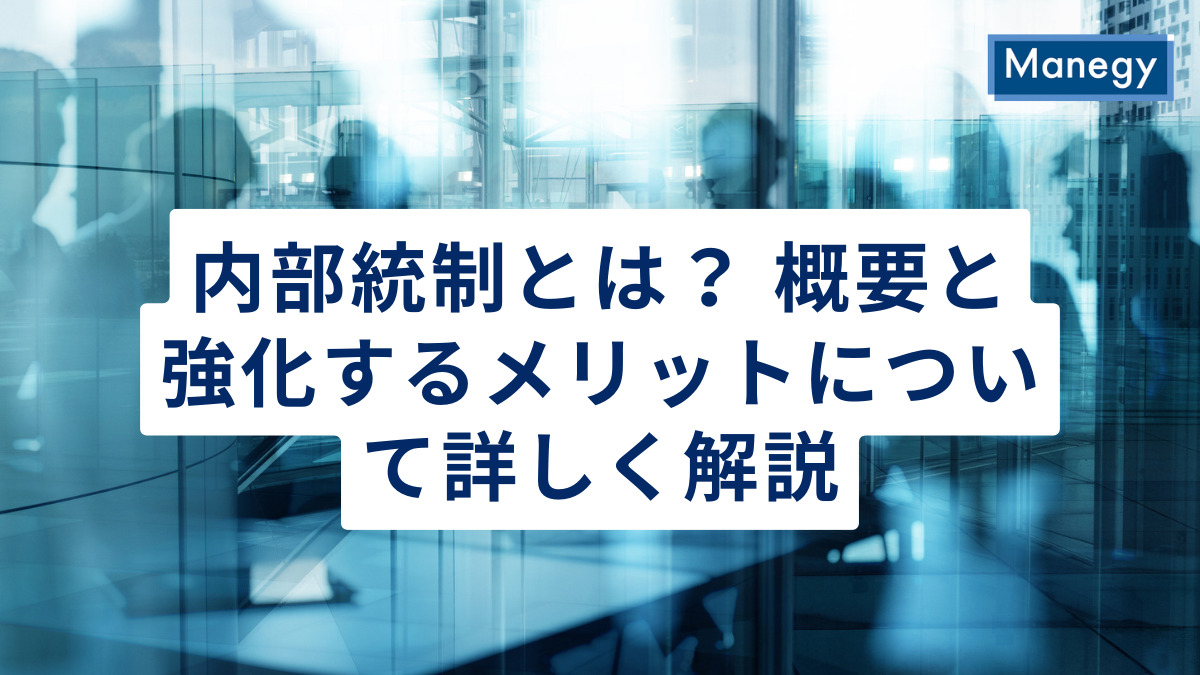
内部統制は企業が健全かつ効率的に企業経営を行っていく上で欠かせない取り組みといえます。社会全体でコンプライアンスに対する意識が高まりつつある現在、後に大きなトラブルを抱えないためにも、内部統制の概要や基本的な意味を押さえておくとよいでしょう。
そこで今回は、内部統制とは何かについて、4つの目的と6つの基本的構成要素を紹介しつつ、内部統制強化を行うメリットを紹介します。
内部統制とは
内部統制とは、企業が経営目標を実現するために、事業活動を健全、効率的に運営するための仕組みのことです。「健全」とは社内の不祥事・不正行為を防ぐこと、「効率的」とは業務効率化を実現して従業員の生産性を高めることを指します。
内部統制の仕組みは企業内で行われる日常業務の中に組み込まれ、組織内のすべての従業員・管理者によって遂行されなければなりません。そのためには内部統制の内容を体系化し、社内でルール化する作業が不可欠であり、実際に体系化・ルール化されたものは「内部統制システム」と呼ばれます。
内部統制と似た概念としてコーポレートガバナンスがありますが、こちらは株主など利害関係者側が、経営層に不正や独善的判断がないかを監視・統制する仕組みを指します。一方で内部統制は、経営層が企業組織を健全で効率的に統治するために必要となる仕組みのことです。監視・統制が誰から誰に行われるのかについて、両者は大きく異なるのです。
企業が健全に事業活動を行い、問題なく成長を続けていくには、内部統制システムの構築は重要なポイントになります。不祥事を多発させて社会的な信頼を失墜させていたり、客観的に見て明らかに非効率・非生産的な取り組みを続けていたりする企業だと、投資家も顧客も離れていってしまうからです。
とくに近年は、スマホ・SNSの普及で、企業に対してコンプライアンスを遵守しているかどうかの目が厳しく、もし反社会的な行動を繰り返していると、SNS上で炎上する恐れもあります。
現在、金融商品取引法の第24条では、上場企業を対象として、内部統制が適切に機能しているのかどうかを経営者が評価した書類である「内部統制報告書」の提出が義務付けられています。提出先は金融庁で、上場企業は有価証券報告書と合わせて提出が必要です。上場企業は内部統制報告書を提出する必要があるため、内部統制システムの確立は必須事項です。
しかし非上場企業、中小企業においても、内部統制によって不祥事を未然に防ぎ、業務の有効性や効率性を向上させることは重要といえます。つまり内部統制は、企業規模を問わず、日本企業全体で取り組むべき大きな課題であるといえるでしょう。
内部統制の目的と基本要素
内部統制報告書の提出先である金融庁は、内部統制を明確に定義づけています。それによると、内部統制は4つの目的と、6つの基本要素で構成されています。
内部統制の4つの目的
内部統制の4つの目的は以下の通りです。
・業務の有効性および効率性・・・企業組織が効率的に運営され、経営資源が効率的に活用されるようにする。
・財務報告の信頼性・・・財務諸表でのミスや不正を防いで財務報告の信頼性を確保して、企業に対する社会的な信用の維持・向上を図る。
・事業活動に関わる法令等の遵守・・・企業内で法令遵守を徹底することで、罰金・訴訟のリスクを最小限にする。
・資産の保全・・・企業の資産を不正使用、盗難から保護し、企業の財務上の安定性を確保する。
内部統制の6つの基本要素
以上4つの目的を実現するために必要な基本的要素として、以下の6つが挙げられています。
・統制環境・・・内部統制の土台となる経営陣の価値観・倫理観、組織の構造、組織風土など。
・リスクの評価と対応・・・企業が直面する潜在的な脅威を特定し、対策を行う。
・統制活動・・・企業組織として取り決めたことを、確実に実行に移せるようにする。職務の権限と責任の明確化、社内規定・業務マニュアルの整備など。
・情報と伝達・・・必要な情報を適切に処理して、組織内外の関係者に適切に伝達したり、正しく管理したりする。
・モニタリング・・・内部統制が機能しているかどうかを監視、改善する。
・IT(情報技術)への対応・・・企業内外のIT環境に適応し、セキュリティ問題などのITリスクに対応する。
内部統制の6つの基本的要素が組み込まれたプロセスを社内で整え、運用することで、4つの目的を達成できるのです。4つの目的が達成されれば、強固な内部統制システムが実現します。
内部統制強化のメリット
内部統制を強化することには、以下のようなメリットがあります。
・社会的信用の向上
内部統制強化を実現することで、財務状況の実態を可視化させると同時に従業員のコンプライアンスに対する意識を高められ、社会的信用の向上につながります。社会的信用が高まれば、資金調達や新たな取引先との契約、人材確保などの面でプラスの影響が期待できます。
・業務効率の向上
内部統制の基本的構成要素には、情報伝達やITへの対応など、業務の効率アップにつながる内容が含まれています。内部統制システムの確立を目指すことは、結果として企業組織全体の生産性向上につながります。
・社内ルールの整備・確立
内部統制を実現するルールを整備することで、組織内の業務プロセスの不透明さをなくし、業務を行う上での指針が明確になります。とくに、稟議の承認過程や予算の管理、報告の要件、職務の分離などに関するルールがきちんと定められ、周知されれば、各従業員はスムーズに業務を進められます。
内部統制強化の成功につながる経営分析ツール
内部統制の強化を進める際、経営分析ツールを活用することで課題の発見・解決をスムーズに行いやすくなります。また経営管理に関する膨大なデータをリアルタイムに集計して分析でき、短時間での分析内容のレポート提出が可能です。
まとめ
内部統制は上場企業のみならず、企業経営の健全化、効率化を実現できる点において、中小企業においても同様に重要です。とくに今後上場を目指す企業にとっては、準備プロセスの一環として内部統制を進める必要があります。内部統制の失敗によって不祥事などが起こってしまうと、企業価値の減少も招いてしまいます。内部統制の目的、基本的要素を押さえた上で、経営層が牽引役となって内部統制システムの確立を目指しましょう。
参考サイト
金融庁_コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方
金融庁_内部統制の基本的枠組み
電子手帳ナビ_内部統制とは?目的や強化方法、コーポレートガバナンスとの関係性を解説
Freee_内部統制とは?4つの目的と6つの基本的要素について分かりやすく解説
マネーフォワード_内部統制とは?内部統制の構築ポイントを解説
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -
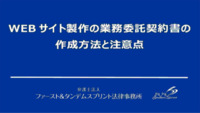
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -
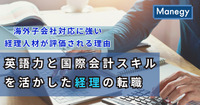
海外子会社対応に強い経理人材が評価される理由|英語力と国際会計スキルを活かした経理の転職(前編)
ニュース -

40年ぶりの労働基準法“大改正”はどうなる?議論中の見直しポイントと会社実務への影響を社労士が解説
ニュース -
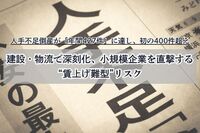
人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク
ニュース -
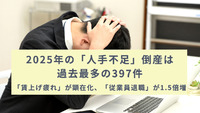
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増
ニュース -

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論
ニュース -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -
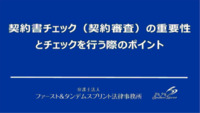
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
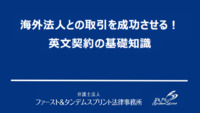
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

キャッシュフロー計算書を武器にする|資金繰りに強い経理が転職市場で評価される理由(前編)
ニュース -
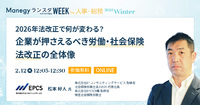
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年1月10日・20日合併号(通巻No.1765)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
ニュース -
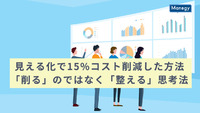
見える化で15%コスト削減した方法|「削る」のではなく「整える」思考法
ニュース
























