公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

企業の収益性を測る指標は数多くありますが、中でも「営業利益率」は、その企業が本業でどれだけ効率的に稼げているかを示す重要な指標です。
経営状況を把握し、改善策を検討する上で欠かせないこの指標について、定義から計算方法、分析・活用方法まで、経理・財務担当者として押さえておくべきポイントを網羅的に解説します。
営業利益率(Operating Profit Margin)は、売上高に対する営業利益の割合を示す指標です。
つまり、営業利益率は「本業の収益力」や「事業活動の効率性」を測るための指標と言えます。
金融収支(受取利息や支払利息など)や一時的な特別損益(固定資産売却益など)の影響を受けないため、純粋な事業のパフォーマンスを評価するのに適しています。
営業利益率は、以下のような理由から経営分析において非常に重要な指標とされています。
1. 本業の収益性の把握:
企業の核となる事業活動がどれだけ利益を生み出しているかを直接的に示します。
この数値を見ることで、事業の競争力や効率性を客観的に評価できます。
2. 経営効率の評価:
売上を上げるためにどれだけのコスト(売上原価+販管費)がかかっているかを示唆します。
営業利益率が高いほど、効率的な経営が行われていると判断できます。
3. 同業他社との比較:
業界平均や競合他社の営業利益率と比較することで、自社の収益性ポジションを把握し、課題発見につなげやすくなります。
上層部への報告資料作成において不可欠な視点です。
4. 収益構造の分析:
営業利益率の推移を時系列で追うことで、収益構造の変化や改善・悪化のトレンドを捉えることができます。
利益率改善策を立案する際の基礎データとなります。
5. 投資家からの評価:
投資家は企業の収益性や成長性を評価する際に営業利益率を重視します。
安定した高い営業利益率は、企業の持続的な成長期待を高め、企業価値向上に繋がります。

営業利益率の基本的な計算式と、具体的な数値例を用いた計算方法を確認しましょう。
部下への説明や、ご自身の理解を深めるためにも重要です。
営業利益率は、以下の計算式で求められます。
営業利益率(%) = 営業利益 ÷ 売上高 × 100
計算式の構成要素は以下の通りです。
つまり、営業利益率を高めるには、「営業利益を増やす」か「売上高を増やす(ただし、利益の増加率が売上高の増加率を上回る必要がある)」、あるいはその両方が必要になります。
具体的な数値を使って計算してみましょう。
例:A社の損益計算書(抜粋)
この場合のA社の営業利益率は、以下のようになります。
営業利益率 = 1億円 ÷ 10億円 × 100 = 10%
この計算により、A社は売上高の10%を本業の利益として確保できていることがわかります。
自社の営業利益率が高いのか低いのかを判断するには、業界の平均値や目安と比較することが有効です。
ここでは、公的データに基づいた平均値を見ていきましょう。
中小企業実態基本調査によると、2022年度の製造業の売上高営業利益率は5.1%でした。
業種によってビジネスモデルやコスト構造が大きく異なるため、営業利益率の水準も様々です。
例えば、一般的に以下のような傾向があります。
自社の属する業種の平均値を把握し、自社のポジションを確認することが、経営分析の第一歩となります。
製造業に属する場合、製造業全体の平均値だけでなく、より細分化された業種(例:輸送用機械器具製造業、電気機械器具製造業など)のデータも参考にすると、より精度の高い比較が可能です。
経済産業省が発表している企業活動基本調査によると、2022年度の全産業(金融業、保険業を除く)の売上高営業利益率は4.0%となっています。
前述の製造業の平均値(4.7%)と比較しても、大きな乖離はない水準です。
ただし、これはあくまで全体の平均であり、個別の企業状況は大きく異なります。
自社の営業利益率が業界平均と比較して「高い」または「低い」場合、単純に良し悪しを判断するだけでなく、その背景にある要因を探ることが重要です。
営業利益率が高い場合は、高いブランド力、技術的な優位性、効率的なコスト構造、優れた経営戦略などのポジティブな要因が考えられます。
一方で注意すべき要因もあります。過度なコスト削減による将来投資(研究開発費、人材育成費など)の抑制、市場での独占的な地位による価格設定(持続可能性に疑問符が付く場合も)、一時的な好況などが考えられます。
高すぎる利益率が、将来の成長機会を損なっていないか、という視点も必要です。
営業利益率が低い場合に考えられる要因としては、激しい価格競争、原材料費の高騰、販管費の増加、生産性の低さ、事業構造の問題などが挙げられます。
分析のポイントとしては、売上総利益率はどうか(原価に問題があるか)、販管費はどうか(コスト管理に問題があるか)、競合と比較してどうか、などを多角的に分析し、具体的な課題を特定する必要があります。
成長段階にある企業が意図的に投資を先行させ、一時的に利益率が低くなっているケースもあります。
経営層への報告においては、単に「高い」「低い」という結果だけでなく、その背景にある要因分析と、今後の見通しや対策を合わせて提示することが求められます。
営業利益率がマイナス、つまり営業赤字の状態は、企業にとって深刻な事態です。その原因と、放置した場合のリスク、そして黒字化に向けた考え方を理解しておきましょう。
営業利益がマイナスになる主な原因としては、以下の点が挙げられます。
1. 売上高の減少:
景気後退、競争激化、主力商品の陳腐化、顧客離れなどにより、売上が計画を下回り、固定費をカバーできなくなる。
2. 売上原価の上昇:
原材料費やエネルギー価格の高騰、為替変動(円安による輸入コスト増など)、歩留まりの悪化などにより、売上総利益が圧迫される。
特に製造業では大きな影響を受けやすい要因です。
3. 販売費及び一般管理費の増加:
過剰な広告宣伝費、人件費の増加(人員増や賃上げ)、新規事業への先行投資、非効率な業務プロセスによるコスト増などが考えられます。
4. 価格設定の誤り:
競合を意識しすぎるあまり、採算度外視の低価格設定を行ってしまう。
5. 新規事業の立ち上げ期:
新規事業が軌道に乗るまでは、売上が少ない一方で研究開発費やマーケティング費用が先行し、一時的に赤字になることがあります。
営業赤字が一時的なものではなく、継続してしまうと、以下のようなリスクが生じます。
対処法としては、まず赤字の原因を正確に特定することが最優先です。
その上で、短期的な資金繰り対策(不要資産の売却、借入条件の見直しなど)と並行して、中長期的な収益構造の改善策(後述)に早急に着手する必要があります。
営業赤字から脱却し、黒字化を目指すためには、収益構造の抜本的な見直しが必要です。以下のポイントを中心に検討を進めましょう。
営業利益率を高めることは、企業の持続的な成長に不可欠です。
ここでは、具体的な改善策を5つの視点から解説します。何から着手すべきか、優先順位を考えるヒントにしてください。
販管費は営業利益に直接影響するため、聖域なき見直しが求められます。項目例としては、人件費(残業代削減、適正な人員配置)、広告宣伝費(費用対効果の検証)、旅費交通費(Web会議の活用)、消耗品費、地代家賃(オフィススペースの見直し)、通信費などが挙げられます。
ポイントとしては、単なるコストカットではなく、業務効率化とセットで考えることが重要です。
効果の薄い経費を削減し、成長に必要な投資へ振り向ける視点も持ちましょう。全社的にコスト意識を高める取り組みも有効です。
すべての商品・サービスが同じ利益率ではありません。利益率の高い製品やサービスの販売比率を高めることで、全体の営業利益率を改善できます。
方法としては、ABC分析などを用いて製品・サービスごとの利益率を把握し、高収益製品の販売促進、低収益製品の値上げや終売、新製品開発による高付加価値化などを検討します。
製造業の視点では、部品構成の見直しによる原価低減と高機能化の両立、オプション販売の強化なども考えられます。
最も直接的に利益率改善に繋がる方法の一つですが、慎重な判断が必要です。検討ポイントとしては、製品・サービスの付加価値、競合の価格動向、顧客の価格弾力性(値上げによる販売数量への影響)などを総合的に判断します。
実施のコツとしては、値上げの根拠(品質向上、原材料高騰など)を明確に伝え、顧客の理解を得ることが重要です。
段階的な値上げや、付加価値を高めた上での値上げも有効な手段です。
売上高が増加すれば、固定費の割合が相対的に低下し、利益率向上に繋がる可能性があります(限界利益率がプラスの場合)。
施策例としては、新規顧客の開拓(新たな市場、ターゲット層)、既存顧客へのクロスセル・アップセル、販売チャネルの拡大(ECサイト、代理店活用など)、効果的なマーケティング・プロモーション活動が挙げられます。
注意点としては、単に販売数量を追うだけでなく、増加する変動費や、必要となる追加投資(設備、人員など)も考慮し、利益が伴う成長を目指す必要があります。
安易な値下げによる拡販は、利益率を悪化させる可能性があるので注意が必要です。
生産性の向上やコスト削減を通じて、売上原価や販管費を抑制します。業務効率化については、ITツールの導入(RPA、SFA/CRM、ERPなど)、業務プロセスの標準化・自動化、従業員のスキルアップ、情報共有の促進などが挙げられます。
原価管理については、仕入先の見直し・交渉、在庫管理の最適化(欠品防止と過剰在庫削減の両立)、生産プロセスの改善による歩留まり向上、品質管理の徹底による不良品削減などが重要です。
製造業においては特に重要な取り組みとなります。
これらの改善策は、単独で行うよりも複数を組み合わせて実施することで、より大きな効果が期待できます。
自社の状況に合わせて、優先順位をつけ、実行可能な計画に落とし込むことが重要です。

営業利益率は重要な指標ですが、その数値だけを見て判断するのは危険です。分析・活用する際には以下の点に注意しましょう。
営業利益率は、様々な要因で短期的に変動することがあります。
これらの変動要因を理解し、単月の数値だけでなく、複数期間のトレンドや移動平均を見るなど、長期的な視点で分析することが大切です。
同業他社や業界平均との比較は有効ですが、単純比較には注意が必要です。
比較する際は、これらの違いを念頭に置き、「なぜ自社と差があるのか」という背景まで考察することが重要です。
経営層へ報告する際には、単に数値を伝えるだけでなく、その数値が持つ意味や背景、そして今後のアクションに繋がる示唆を提供することが求められます。
企業の収益性を多角的に評価するためには、営業利益率だけでなく、他の利益指標との関係性を理解しておくことが重要です。
売上総利益率(粗利率) = 売上総利益(売上高 - 売上原価) ÷ 売上高 × 100
売上総利益率は、商品やサービスの基本的な収益力を示します。
売上原価(製造業なら材料費、労務費、製造経費など、小売業なら仕入原価)のみを考慮した利益率です。
営業利益率は、この売上総利益からさらに販管費を差し引いた後の利益率です。
したがって、売上総利益率は高いのに営業利益率が低い場合は、販管費(人件費、広告費など)がかかりすぎている可能性があります。
また、売上総利益率も営業利益率も低い場合は、原価が高いか、販売価格が低い、あるいはその両方の可能性があります。
このように、両者を比較することで、利益を圧迫している要因が原価側にあるのか、販管費側にあるのかを切り分けるヒントになります。
経常利益とは、営業利益に、営業外収益(受取利息、受取配当金など)を加え、営業外費用(支払利息、為替差損など)を差し引いた利益です。
これは企業の通常の活動全体から得られる利益を示します。
経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高 × 100
一方、税引前当期純利益は、経常利益に、特別利益(固定資産売却益など)を加え、特別損失(災害損失、リストラ費用など)を差し引いた利益です。
これは一時的な損益を含めた、税金支払い前の利益を示します。
税引前当期純利益率 = 税引前当期純利益 ÷ 売上高 × 100
営業利益率は本業の収益性を見ますが、経常利益率は財務活動なども含めた企業の総合的な収益力、税引前当期純利益率は一時的な損益も含めた最終的な利益の源泉を示します。これらの利益率も合わせて分析することで、企業の収益構造をより深く理解できます。例えば、営業利益率は高いのに経常利益率が低い場合は、借入金の支払利息負担が重いなどの財務的な課題が考えられます。
営業利益率だけでは見えない側面もあります。他の財務指標と組み合わせることで、より多角的な分析が可能になります。
これらの指標と営業利益率を組み合わせることで、例えば「営業利益率は高いが、ROAが低い」場合は、資産効率に課題がある可能性、「営業利益率は低いが、ROEが高い」場合は、財務レバレッジ(借入)を効かせている可能性などが推測できます。
最後に、営業利益率に関してよく聞かれる質問とその回答をまとめました。
A. 基本的には、営業利益率が高い方が本業で効率的に稼げていることを示すため、良い状態と言えます。しかし、必ずしも高ければ高いほど良いとは限りません。
例えば、将来の成長に必要な研究開発費や人材育成費、広告宣伝費などを過度に削減した結果、一時的に利益率が高くなっている場合、中長期的な競争力を失うリスクがあります。また、市場での独占的な地位を利用して不当に高い価格設定をしている場合なども、持続可能性や社会的な観点から問題視される可能性があります。
重要なのは、なぜ高いのか(低いのか)という背景を理解し、持続可能な範囲で適正な水準を目指すことです。
A. 一概に「最適な営業利益率」という万能な数値はありません。目指すべき営業利益率は、以下の要因によって大きく異なります。
自社の属する業界の平均値や競合の状況を参考にしつつ、自社の事業特性や経営戦略に基づいた目標となる営業利益率を設定し、その達成度を測っていくことが重要です。
A. 一時的、あるいは戦略的な理由で営業利益率が低い場合は、必ずしも問題とは言えません。具体的には以下のようなケースが考えられます。
ただし、これらのケースであっても、低利益率が常態化したり、資金繰りに影響が出たりする状況は問題です。なぜ低いのか、いつまでにどの水準まで回復させるのか、という計画とモニタリングが不可欠です。
営業利益率は、企業が本業でどれだけ効率的に稼いでいるかを示す、経営分析の根幹となる指標です。その定義や計算方法を正しく理解し、業界平均や他社と比較することで、自社の収益性ポジションを客観的に把握することができます。
営業利益率が低い場合やマイナスになっている場合は、その原因を深掘りし、コスト削減、販売構成の最適化、単価の見直し、販売数量の増加、業務効率化といった具体的な改善策に繋げることが重要です。
また、営業利益率を分析する際は、一時的な変動要因に注意し、売上総利益率や経常利益率など他の利益指標、ROAやROEといった財務指標と組み合わせて多角的に見ることが、より本質的な経営課題の発見に繋がります。
経営層へのレポーティングや社内での議論においては、単なる数値の報告にとどまらず、その背景にあるストーリーや今後の改善に向けた示唆を伝えることが、経理・財務担当者としての価値を高める鍵となります。
この記事が、日々の業務における営業利益率の分析・活用、そして企業の収益力向上の一助となれば幸いです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
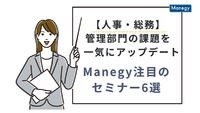
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選
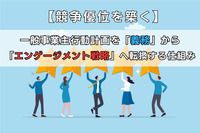
【競争優位を築く】一般事業主行動計画を「義務」から「エンゲージメント戦略」へ転換する仕組み
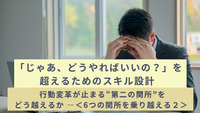
「じゃあ、どうやればいいの?」を超えるためのスキル設計― 行動変革が止まる“第二の関所”をどう越えるか ―<6つの関所を乗り越える2>

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応
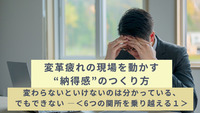
変革疲れの現場を動かす“納得感”のつくり方 ― 変わらないといけないのは分かっている、でもできない ―<6つの関所を乗り越える1>
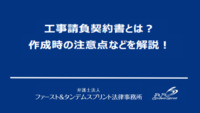
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
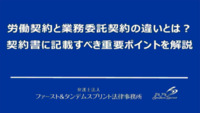
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

「一律50万円支給」の転勤支援金制度を新設。住友重機械工業、転勤を“前向きな挑戦”に変える人事施策を導入
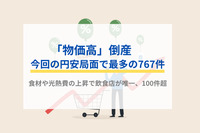
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
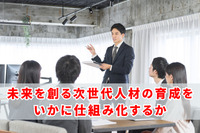
未来を創る次世代人材の育成をいかに仕組み化するか

「フリンジベネフィット」が映す企業文化とその戦略的価値とは
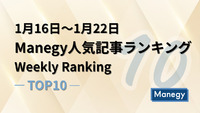
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
公開日 /-create_datetime-/