公開日 /-create_datetime-/

株主総会を開催する場合、定時・臨時に関わらず、事前に株主に招集通知を送る必要があります。
しかし、前もって送付すれば何でも良いわけではありません。招集通知を送る時期や送る方法などは、制度上厳密に規定されており、従わなかった場合は、法令を違反しているとして、株主総会における決議が取り消される場合もあります。
今回は、株主総会の収集通知にはどのような規定があるのかについて紹介します。
株主総会招集通知とは
招集通知を行う目的は、株主に対して株主総会が開催されることを事前に伝えることにより、総会に向けて準備を行う時間と、出席すべきか否かの判断の機会を提供することです。もし招集通知が株主に届けられなかった場合、あるいは通知内容に誤記があった場合は、法律上、総会決議取り消し事由(総会で決めたことが無効となる)に該当すると定められています。
総会決議取り消し事由とまではいかない軽度の誤りであっても、運営に問題が生じる恐れがあるので、通知の際は最大限の注意を払わなければなりません。
誤記が原因で株主総会が円滑に行えないとなると、会社の信用問題に関わります。
招集通知の発送元と発送先について
招集通知を誰が行うのかは、その会社が取締役会を設置しているか否かによって異なります。
取締役会を設置している会社の場合、取締役会で招集通知が決定され、その内容に基づいて代表取締役の名前で通知を発送するのが原則です。
一方、取締役会が設置されていない会社の場合は、各取締役が通知を行います。
招集通知を行う対象は、会社が定款の中で規定している基準日において、株主名簿に名前が記載されている株主です。なお、完全無議決株式(議決権がない株式)や議決権制限株式(議決権が制限された株式)、あるいは自己株式や相互保有株式等を持つ株主に対しては、招集通知は必要ありません。
会社法297条第1項では、「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6カ月前から引き続き有する株主」は、議決を行う事項と召集の理由を示すことで、取締役に対して株主総会の招集を請求できると定められています。企業側が株主に対して、一方的に招集をかけるだけでなく、例外的ではありますが、株主側もまた招集を要求できるのです。
株主総会招集通知は所定の発送期限までに送付する必要がある
株主総会の招集通知は、株主総会の直前ではなく、所定の期日前に通知を発送しなければなりません。いつまでに通知しなければならないかは、「公開会社」と「非公開会社」とで異なります。
公開会社とは、制限なく自由に譲渡できる株式を発行している会社のことです。
公開会社の場合、株主総会の14日前(発送する日を含めないので、正確には15日前)までに招集通知の発送手続きを終える必要があります。
一方、非公開会社とは、発行している株式の全てが譲渡において制限されている会社のことです。
非公開会社では、招集通知の発送期限は、株主総会の7日前(発送する日を含めないので、正確には8日前)までです。取締役会が非設置の非公開会社の場合は、定款の規定に基づき、1週間未満まで短くすることもできます。
なお、非公開会社で株主総会において書面投票制度あるいは電子投票制度を採用している場合は、2週間前までに通知を発送しなければなりません。
株主総会招集通知を行う方法
通知の方法は、取締役会が設置されているか否かによって異なります。取締役会が設置されている会社では、書面もしくは電子メール等(電磁的方法)による通知が必要です。
一方、取締役会が設置されていない会社では、書面による通知は不要で、口頭もしくは電話、電子メールで行うことができます。
先ほど、取締役会が非設置の非公開会社では、招集通知を株主総会開催の1週間前未満まで短縮できると述べましたが、このタイプの会社では書面による通知も必要ないので、場合によっては「株主総会の前日に、電話で招集通知を行える」わけです。
ただし、株主が株主総会を欠席しても「書面や電磁的方法で議決権の行使ができる」との定めがある会社の場合は、口頭もしくは電話での招集通知は行えません。
通知の中に記載されている事項
株主総会招集通知では、株主総会の開催日時、開催場所、議題などを記すのが原則です。
総会に欠席しても書面での投票ができることを定める場合は、所定事項を記載の上、必要な書類を同封します。議題の記載については、通知を受け取った株主がそれを見て、総会で決議される事柄がおおまかに分かるように書いてある必要がありますが、数値が多分に盛り込まれているような詳細な内容でなくてもかまいません。
ただし、重要事項については、議題に加えて「議案の要領」を記載する必要があります。
例えば「役員等などの選任」や「役員等の報酬」などについては、議題だけでなく議案の要領なども記載しなければなりません。
まとめ
株主総会は、株式会社における最高意思決定機関です。開催方法等に関しては法令による厳格な規定があり、株主に対して招集通知を送る場合も、何日前までに送付する必要があるのか、どのような場合に誰が送付するのかなど、細かく定められています。会社側として株主総会を滞りなく運営していくためにも、制度上の規定をよく理解して通知を実施することが重要です。また、株主の側も通知内容をしっかりと理解し、株主総会に向けて各自準備を進めておく必要があるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース -
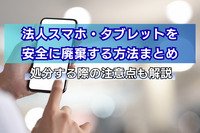
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由
ニュース -

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表
ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -

ファイル共有のセキュリティ対策と統制
ニュース -

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース




































