公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

前回のコラムでは、両親ともに育児休業をする場合の特例制度として「パパ・ママ育休プラス」制度について解説しました。
今回のコラムでは子育て支援規定事項の三つ目「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」について解説していきます。
出生時育児休業制度は2022年4月の「育児・介護休業法」の改正により創設され、2022年10月に施行されました。
この制度創設の背景としては、出産を経てからの女性の就業継続と、男性の育児への参加率の低さが課題となっていたこと(厚生労働省「雇用均等基本調査」:2021年時点で13.97%)が挙げられます。
そこで、既存の育休制度を活用した男性労働者の休業取得時期が「子の出生後8週間以内」に多いことから、既存の育休制度をさらに柔軟にし、出産直後の母親の身体的・精神的負担の軽減とともに男性労働者も必要な時期に育休を取得することで、父親の育児・家事参画を促進することを目標として、出生時育児休業制度が創設されました。
出生時育児休業は子の出産直後のサポートを目的とし、主に男性が取得することから、「産後パパ育休」とも呼ばれています。
出生時育児休業とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業を取得することができる制度です。
対象となる労働者は産後休業を取得していない労働者となるため、通常男性労働者(養子の場合は女性も取得可能)となります。
また、ほかの育休制度と異なり、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主間で合意した範囲内で就業できることが特徴となる制度です。
この記事を読んだ方にオススメ!
記事提供元

東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
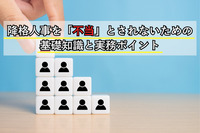
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
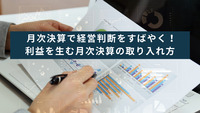
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
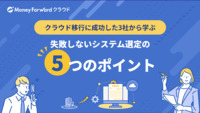
クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
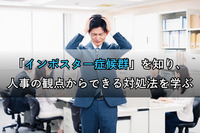
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
公開日 /-create_datetime-/