公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
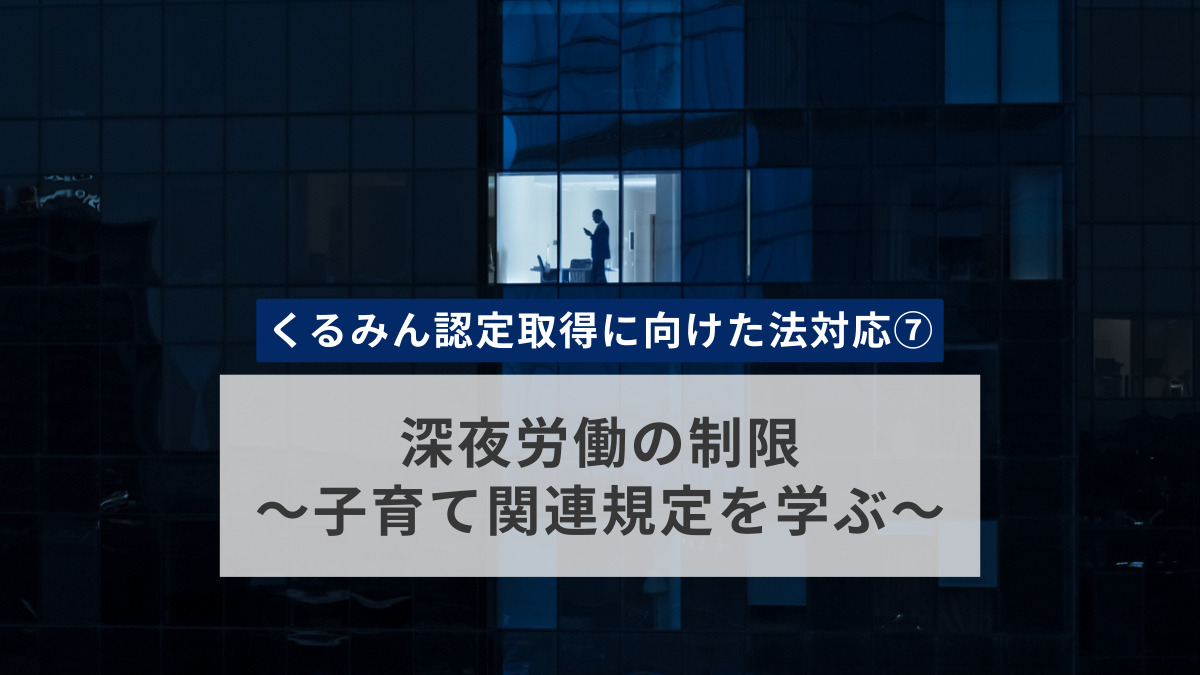
くるみん認定基準において「雇用する労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の時間数」の要件が記載されたように、「子育てサポート企業」の認定を受けるためには子育て世代に限らず、すべての労働者に対して残業を抑制する柔軟な働き方の整備が求められています。
また、その柔軟な働き方として、子育てをしながら働く労働者にとって、労働時間数の制限だけでなく、労働時間帯の制限も必要となります。
過去2回のコラムでは、子育てをしながら働く労働者に向けた仕事と家庭の両立を可能とするための柔軟な働き方のひとつである「所定外労働の制限」・「時間外労働の制限」について解説しました。
今回は子育て世代の労働者の労働時間帯の制限である「深夜労働の制限」制度について、制度成立までの歴史とそれに基づく法改正、その概要について解説します。
「深夜労働の制限」とは、労働基準法における深夜労働(22時から翌日5時まで)について、一定の条件を満たす労働者が希望(請求)すれば、事業主はその労働者に深夜労働をさせることができない制度です。
これは育児・介護休業法の第19条に定められています。
この請求によって、事業主は対象の労働者の深夜労働を制限しなければなりません。
ただし、この制限に例外があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」は労働者からの請求を拒むことができます。
なお、労働者が休むことで何らかの業務に支障が出ることが当然である状況下で、その担当者の業務内容や代替要員の配置可否なども事情を考慮したうえで「事業の正常な運営を妨げる」と客観的に判断すべきとしています。
そのため、事業主が代替要員を配置するなどで事業の正常な運営が客観的にできなかった場合が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、単に深夜業が事業の運営上必要という理由だけでは労働者の請求を拒むことはできません。
日々雇用される者を除く小学校就学前の子を養育する労働者が対象で、有期雇用者やパート・アルバイトも対象です。
しかし、以下に当てはまる労働者は対象外です。
この記事を読んだ方にオススメ!
記事提供元

東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
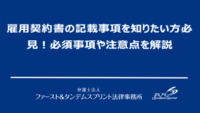
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
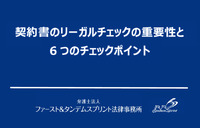
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
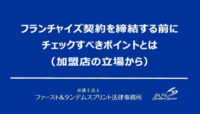
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
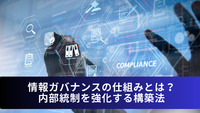
情報ガバナンスの仕組みとは?内部統制を強化する構築法
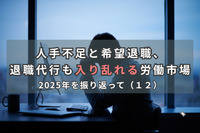
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)

焼津市の建設会社・橋本組、「えるぼし認定」最上位に 女性活躍推進法に基づく全項目をクリア

専門人材向けに「ジョブ型人事制度」を本格導入した三井住友カード。“市場価値連動型”の評価・処遇でデジタル人材獲得へ

オフラインアクセスは危険?クラウドストレージの安全な活用

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
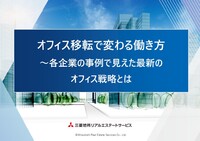
オフィス移転で変わる働き方

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

事業再生を取り巻く環境の変化=2025年を振り返って(11)
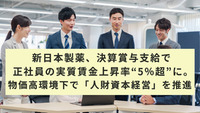
新日本製薬、決算賞与支給で正社員の実質賃金上昇率“5%超”に。物価高環境下で「人財資本経営」を推進

外注と業務委託の違いとは?契約形態や活用シーンをわかりやすく解説

社員同士の交流を促進する「まかないランチ会」開催 岐阜市のITベンチャーのユニークな支援策
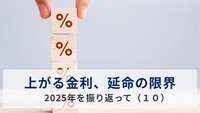
上がる金利、延命の限界=2025年を振り返って(10)
公開日 /-create_datetime-/