公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

厚生労働省は2025年5月、「労働基準法における『労働者』に関する研究会」において現在労働基準法において定義されている「労働者の判断基準」(労働者性)が働き方の変化や多様化に対応できていないとして、判断基準のあり方の見直しを図るために有識者会議を設置しました。
近年はプラットフォームワーカーの増加に伴い、現行の労働基準法で想定されていない働き方が増えてきたため、労働基準法の適用範囲や規制のありかたについて見直す必要性が高まっています。
実態としては企業の指揮命令を受けている業務委託契約者のケースや、企業が社会保険料などの負担を逃れるために、本来雇用すべき人を請負契約としているケースも問題点として浮かび上がっています。
なお、現在の労働者の判断基準は昭和60年の労働基準法研究会報告において整理されたものを元にしていますが、今回の検討に伴い労働者性の判断基準が変わる場合、約40年ぶりの見直しとなり、日本の労働市場において大きな影響を及ぼす可能性があります。
では、労働者性とはどのようにして定義されたのでしょうか。
根拠となる労働基準法をもとに背景を解説していきます。
また、これからの日本の労働者性はどのように再定義されていくのか、考察していきます。
労働者保護の法規の始まりは、世界各国の工場、鉱山労働者の保護の問題が取り上げられたことに起因します。
国際労働機関においても工場・鉱山労働の保護から始まり、そこから商業や事務労働者へと保護対象を広げ、広くあらゆる事業の労働者を保護することとなりました。
日本もそれにならい、鉱業法(明治38年)、工場法(明治44年)による特定の労働者の保護からはじまり、あらゆる事業の労働者を保護する労働基準法の制定へと至りました。
まず、そもそも労働者の定義はどのような基準にのっとっているのでしょう。
「労働者」の判定基準については労働基準法と労働組合法ではその法律の目的にのっとり異なっています。
例えば、……
この記事を読んだ方にオススメ!
記事提供元

「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

経理業務におけるスキャン代行活用事例
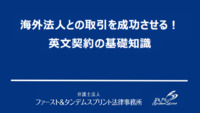
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
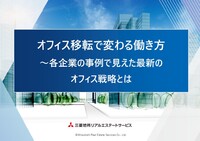
オフィス移転で変わる働き方

人的資本開示の動向と対策

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
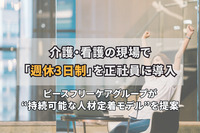
介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
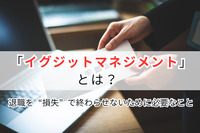
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
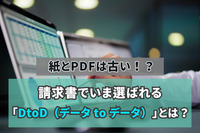
紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

オフィスステーション導入事例集

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
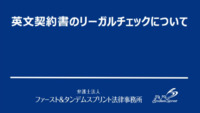
英文契約書のリーガルチェックについて

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術
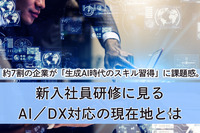
約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは
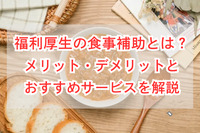
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

2026年の展望=2025年を振り返って(13)
公開日 /-create_datetime-/