公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。
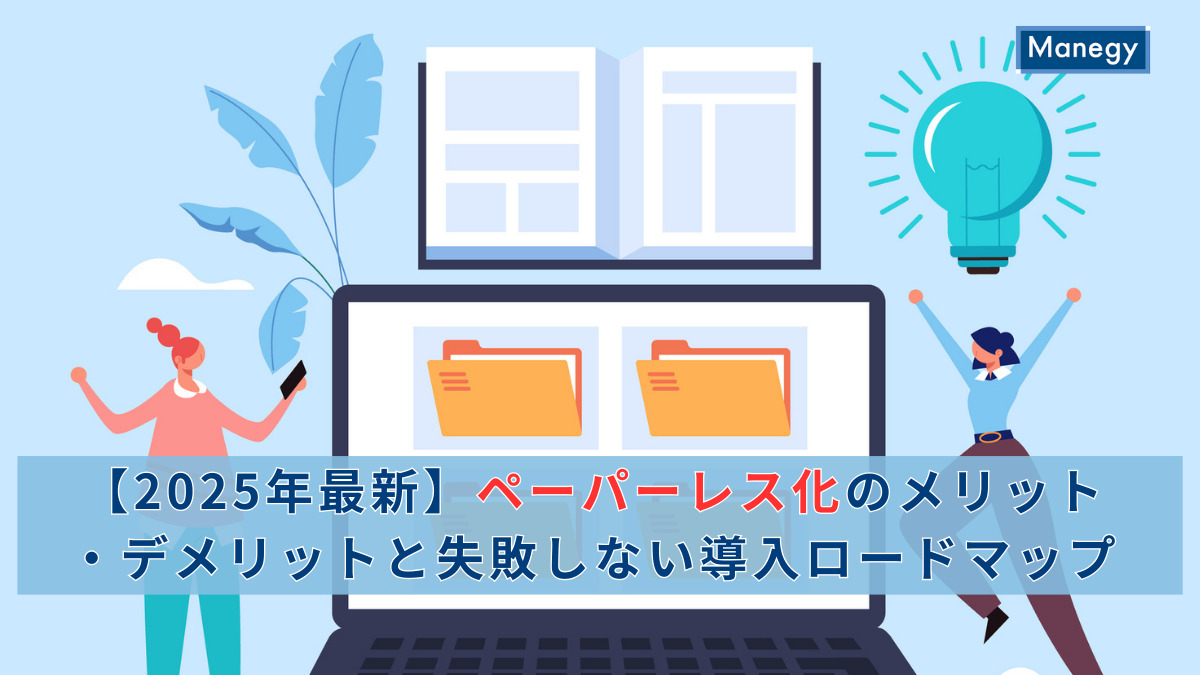
オフィスのキャビネットを占拠する紙書類、承認印をもらうためだけの出社、そして月末に山積みになる請求書処理──。こうした“紙中心”の業務は、管理部門にとって長年の課題でした。2025年現在、法改正やDX推進の流れを背景に、ペーパーレス化はもはや選択肢ではなく「待ったなし」の取り組みとなっています。
しかし導入のメリットが語られる一方で、初期コストや社内の抵抗感といったデメリットに頭を悩ませる担当者も少なくありません。
本記事では、ペーパーレス化の利点と注意点を整理したうえで、失敗しない導入ロードマップを提示します。まずは明日から取り組める一歩を一緒に見つけていきましょう。
ペーパーレス化は単なる業務効率化の手段ではなく、いまや「やらざるを得ない」状況に突入しています。その背景には、国の制度改革と働き方の変化という2つの大きな外部要因があります。どちらも管理部門の担当者に直結するテーマであり、対応の遅れは業務リスクや企業競争力の低下につながりかねません。ここでは、その具体的な理由を整理します。
まず大きな要因となっているのが、近年相次ぐ法改正です。2022年の改正電子帳簿保存法では、請求書や領収書などの国税関係書類を電子で保存することが正式に認められ、2024年以降は電子取引データの紙保存が原則禁止となりました。さらに2023年に始まったインボイス制度では、正確な取引情報をデータで管理・保存する必要性が一層高まっています。これらの制度は「努力義務」や「推奨」にとどまらず、実務担当者が遵守しなければならない法的要件へと変化しました。つまりペーパーレス化はコスト削減のための施策ではなく、コンプライアンス対応として必須の業務なのです。
もう一つの要因は、働き方の多様化です。リモートワークやハイブリッド勤務が当たり前となった今、「紙の書類のためにだけ出社する」ことは大きな非効率です。承認印を押すために稟議書を回す、経費精算の領収書を郵送する──こうした業務フローは、柔軟な働き方を阻害し、生産性低下につながります。一方、書類を電子化すれば、承認プロセスをオンラインで完結でき、在宅勤務でもスムーズに業務を進められます。また、企業全体でDXを推進するうえでも、ペーパーレス化は避けて通れない「第一歩」です。
ペーパーレス化は「便利そうだから導入する」という単純な話ではありません。実際に導入した企業では、コスト削減や業務効率化といった大きな成果を得られる一方で、初期投資や社内の抵抗感といった課題にも直面します。ここでは、代表的なメリットとデメリットを整理し、それぞれの対策もあわせて解説します。
①コスト削減につながる
紙の印刷費やインク代、郵送費、さらに倉庫やキャビネットにかかる保管スペースの賃料は意外と高額です。例えば従業員100名規模の企業で年間1万枚を印刷している場合、印刷費と紙代だけで数十万円に達することも珍しくありません。ペーパーレス化により、これらの固定的なコストを大幅に削減できます。
②業務効率化が図れる
紙の書類を探す時間や、承認のために物理的に回覧する手間は、積み重なると大きなロスです。電子化すればキーワード検索で瞬時に必要な書類を探せ、承認フローもオンラインで完結します。これにより、月末処理のスピードが格段に上がります。
③セキュリティ・内部統制が強化できる
紙の書類は紛失や持ち出しリスクが高く、誰が閲覧したのかも追跡できません。電子化すれば、アクセス権限の付与や閲覧履歴の記録が可能になり、情報漏洩リスクを減らせます。内部統制の観点からも、ペーパーレス化は有効な手段です。
④働き方改革・BCP対策ができる
リモートワークを進めるうえで「紙のために出社する」という非効率は大きな障壁です。電子化すれば在宅勤務でも業務を滞りなく進められ、災害時に紙の書類が失われるリスクも軽減できます。まさに生産性とリスク管理を両立する仕組みです。
①導入コストがかかる
スキャナやクラウドサービスなど、初期投資が必要になります。
改善策:国のIT導入補助金を活用したり、経費精算や稟議書などスモールスタートで導入範囲を絞ることで、コスト負担を抑えつつ着実に進められます。
②社内で反発が起こる場合がある
「紙の方が安心」「ITに不慣れで不安」という声は必ず出ます。
改善策:導入前に説明会を実施し、操作マニュアルや研修を用意することが重要です。特にITが苦手な社員への個別フォローを行うことで、定着率が大きく向上します。
③システム障害・災害時のリスクがある
サーバー障害やネットワークトラブルが発生すると、「書類が見られない」という事態が起こり得ます。
改善策:定期的なバックアップを行い、クラウドサービスを利用する場合は冗長化が整ったベンダーを選ぶことがポイントです。さらに、必要最低限の書類はオフラインでも閲覧できる仕組みを整えておくと安心です。
ペーパーレス化を検討する際に多くの担当者が悩むのは、「結局どの業務から着手すべきか」という点です。すべての書類を一度に電子化しようとすると社内の混乱を招き、コストや労力も膨らみます。無理なく成果を出すには、“取り組みやすい業務から段階的に広げる”のが鉄則です。ここでは、ペーパーレス化の実行難易度を3つのレベルに分け、優先順位を考えてみましょう。
まず最も取り組みやすいのが、社内だけで完結する書類です。稟議書や回覧文書、経費精算などは外部とのやり取りがなく、電子化のハードルが低い領域です。ワークフローシステムや経費精算ツールを導入すれば、申請から承認までをオンラインで完結でき、承認スピードの向上やペーパーレス化の効果を実感しやすくなります。小さな成功体験を積むことで、社内の理解や協力も得やすくなるでしょう。
次のステップは、社外とのやり取りが一部含まれる書類です。代表的なのは請求書や納品書、見積書など。取引先によってフォーマットが異なり、紙を前提とする企業も少なくありませんが、電子インボイス制度の普及により、電子データでのやり取りが急速に広がっています。この領域に着手する際は、自社のシステムだけでなく取引先の対応状況を確認し、段階的に電子化を進めることが成功のポイントです。
最後に取り組むべきは、契約書などの高度な社外連携が必要な書類です。法律要件や取引先との合意が不可欠で、導入には時間と調整が必要となります。ただし、電子契約サービスを活用すれば、締結スピードの向上や印紙税の削減など大きなメリットを享受できます。重要なのは、一気にすべての契約書を電子化しようとせず、新規契約や社内で合意を得やすい案件から導入し、徐々に対象範囲を拡大することです。
ペーパーレス化を成功させるには、「一気にすべてを変える」のではなく、段階を踏んで計画的に進めることが重要です。ここでは、現場の実務担当者がプロジェクトを円滑に進められるよう、5つのステップに整理しました。
最初の一歩は、現状の「紙依存度」を数値化することです。年間でどのくらい印刷しているか、どの業務で紙が多く使われているか、承認や保管にどの程度の工数を割いているかを棚卸しし、業務フローを図解すると、ペーパーレス化の効果が見える化できます。
「とにかくペーパーレス化する」では社内の合意は得られません。例えば、「請求書処理の時間を50%削減する」「保管コストを年間100万円削減する」といった具体的なKPI(数値目標)を設定することが重要です。目標を明確にすることで、成果を測定しやすくなり、社内の理解も得やすくなります。
次に、目的に合ったツールを選びます。ワークフローシステムや電子契約サービスなど、対象業務に応じて導入範囲を決めましょう。同時に、どの書類を電子化するか、保存フォルダやファイル名のルール、承認フローの設定といった社内ルールを整備し、混乱を防ぐことが欠かせません。
いきなり全社導入はリスクが高いため、まずは「経費精算」や「稟議書」など小規模な領域から始めます。成功体験を積んだら、その事例をもとに全社へ展開するのが理想です。また、従業員への教育と周知を丁寧に行うことが成功のカギです。特にITが苦手な社員へのフォローアップを用意することで、導入の抵抗感を最小化できます。
導入後は必ず効果を測定し、改善を繰り返します。紙の使用量がどれだけ減ったか、承認スピードは改善したか、コストは削減できたかといった指標を定期的にチェックし、改善点を洗い出します。そのうえで、次の対象業務へと範囲を拡大していくことで、無理なく全社規模のペーパーレス化へつなげられます。
ペーパーレス化を進める際、担当者から必ず出てくるのが「現場のリアルな疑問」です。ここでは、よく寄せられる質問に答えながら、不安を解消していきます。
Q. すべての書類を電子化しないといけませんか?
いいえ、すべてを一度に電子化する必要はありません。法的に電子保存が義務付けられているのは、電子帳簿保存法の対象となる取引データなど一部の書類です。それ以外については、自社の業務効率やコスト削減効果を考慮し、優先度の高いものから順に進めれば問題ありません。
Q. ITが苦手な従業員が多く、導入が進みません。
この課題は多くの企業で直面します。対策としては、操作がシンプルなツールを選ぶ、導入前に説明会やマニュアルを準備する、ITが苦手な社員には個別フォローを行うなどが効果的です。小さな成功体験を積ませることで、抵抗感は徐々に薄れていきます。
Q. 導入には、どのくらいの費用と期間がかかりますか?
導入規模によって異なりますが、スキャナやクラウドサービスを活用したスモールスタートなら、数十万円程度から始めることも可能です。また、国のIT導入補助金を活用すればコストを大幅に抑えられます。期間については、小規模な経費精算システムなら1〜3か月程度、大規模な文書管理システムの全社展開なら半年〜1年かかるケースもあります。
Q. 手書きのサインやハンコは、完全になくなりますか?
完全になくなるわけではありません。電子契約の普及により印紙税削減やスピード化のメリットは大きいですが、取引先の事情や社内規程によっては一部紙の運用が残る場合があります。現実的には「紙と電子のハイブリッド運用」から始め、徐々に電子契約を広げていくのが現実的な進め方です。
ペーパーレス化は、単に紙を減らすための施策ではありません。業務プロセスを根本から見直し、生産性を高め、企業の競争力を強化するための「デジタルトランスフォーメーション(DX)の第一歩」です。法改正や働き方の多様化といった外部要因に対応するだけでなく、コスト削減・業務効率化・セキュリティ強化・柔軟な働き方の実現など、多くのメリットを企業にもたらします。一方で、導入にはコストや社内の抵抗感といった課題も伴います。しかし、これらはスモールスタートや従業員教育、バックアップ体制の整備といった工夫で乗り越えることが可能です。大切なのは、完璧を目指して立ち止まるのではなく、まずは一つの業務、一枚の書類からでも電子化を始めることです。明日から取り組める小さな一歩が、やがて大きな変革につながります。ペーパーレス化をきっかけに、自社の「未来を創るDX」を今日から始めてみましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料
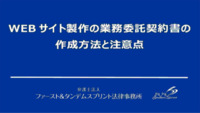
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
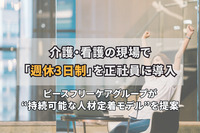
介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
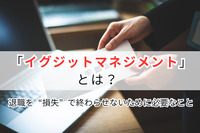
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
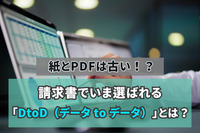
紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
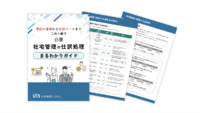
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
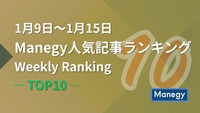
1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術
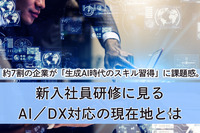
約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは
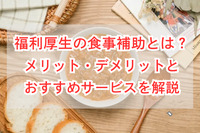
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説
公開日 /-create_datetime-/