公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
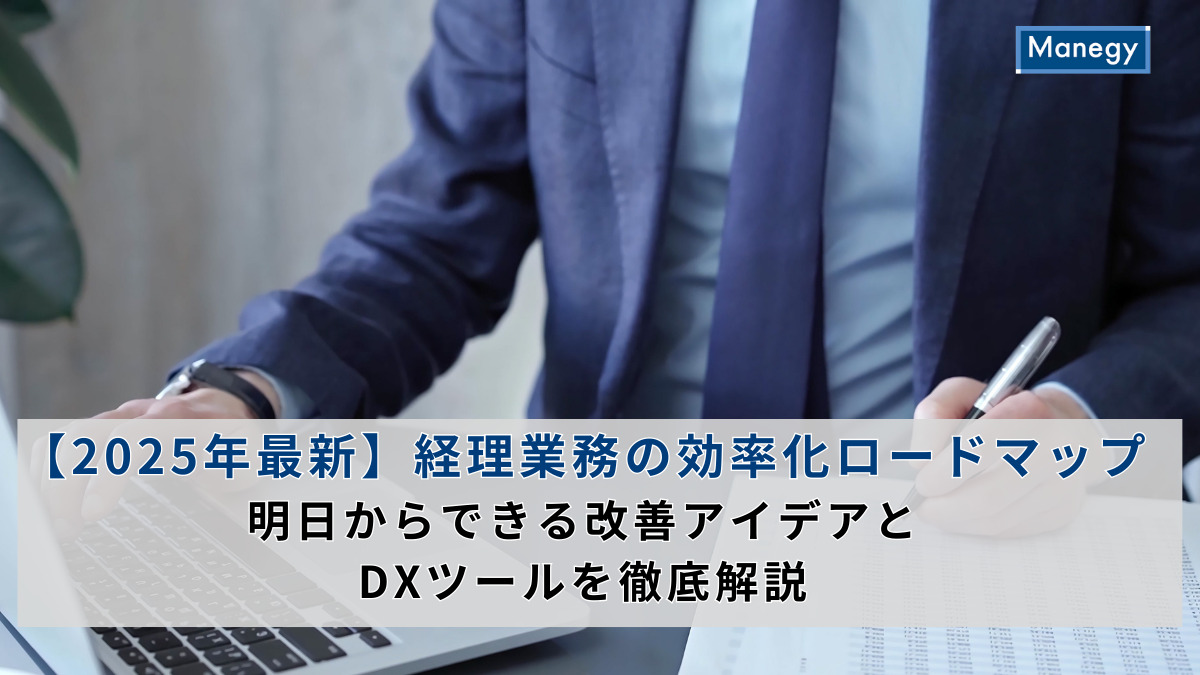
月末月初になると、請求書の処理や経費精算の確認、決算に向けた残高チェックなどに追われ、「経理業務はいつも時間に追われている」と感じる方は多いのではないでしょうか。こうした非効率は、担当者の残業やストレスを増やすだけでなく、ミスや不正、さらには経営判断の遅れにつながるリスクも抱えています。そこで注目されているのが「経理の効率化」です。
「毎月の締めが終わらない」「確認作業ばかりで本来の分析に手が回らない」──経理部門ではそんな声がよく聞かれます。多くの企業で経理業務が慢性的に忙しいのは、単なる人手不足だけが原因ではありません。実は、業務の仕組みに潜む“非効率の要因”こそが、経理担当者の負担を増大させています。ここでは、経理効率化を進める前に押さえておくべき典型的な原因を整理し、改善の出発点を見つけていきましょう。
経理部門の仕事は「正確さ」が最優先されるため、どうしても保守的になりがちです。その結果、非効率な仕組みが温存されやすい特徴があります。特に以下の4点は、多くの企業で共通する課題です。
①紙文化が残っている
いまだに請求書や領収書を紙でやり取りし、印刷・押印・郵送といったフローが残っているケースが多くあります。これが承認や保管の遅れを招き、業務効率を大きく低下させます。
②手作業が多い
Excelへの転記や目視によるチェックなど、人の手を介する作業が多いと入力ミスが避けられず、修正にさらに時間を取られる悪循環が発生します。
③属人化が進んでいる
「この作業はAさんしか分からない」といった業務の属人化は、担当者の不在時に業務が止まるリスクを生みます。教育や引き継ぎが十分でないと、効率化は進みません。
④やり取りが多いことによるタイムロス
申請書類の差し戻しや、確認のためのやり取りが多発することで、承認フロー全体が滞ります。特に部署間の連携不足は、経理効率化を阻害する大きな要因です。
これらの要因が積み重なると、経理業務は「常に終わらない仕事」になってしまいます。
非効率の温床を取り除き、経理の効率化を進めることで得られるメリットは、単なる業務改善にとどまりません。経営全体に影響を与えるインパクトは以下の3つです。
①コスト削減につながる
残業時間の削減や人的リソースの最適化につながり、人件費を抑制できます。さらに紙・印刷・郵送費用といった間接コストの削減効果も期待できます。
②スピードが向上する
月次決算や年次決算の早期化が可能になり、経営陣がより迅速に意思決定を行えるようになります。これは市場環境の変化に柔軟に対応するうえで欠かせません。
③品質が上がる
ツールや仕組みによる自動化・標準化でミスを減らし、内部統制の強化にもつながります。結果として、監査対応や法令遵守の精度も高まります。
経理効率化は「担当者の業務を楽にする」だけではなく、会社全体の競争力を高める戦略的な取り組みなのです。
経理効率化を進めるには「どの業務から改善するか」を明確にすることが重要です。単に「システムを導入すれば効率化できる」というものではなく、業務プロセスごとに課題を洗い出し、最適な改善アイデアとツールを組み合わせる必要があります。ここでは代表的な経理業務を4つ取り上げ、それぞれの課題と解決策を紹介します。
課題:請求書の作成・印刷・封入・郵送は手間がかかり、入金確認や消込作業も煩雑になりがちです。入金が遅れると資金繰りにも影響します。
アイデア:請求書を電子化することで、作成から送付までの工数を削減できます。また、入金サイクルを見直し、支払期日のルールを統一することで、回収リスクを低減できます。
有効なツール:請求書発行システム、ネットバンキングとの自動連携、RPAによる入金消込の自動処理。
課題:取引先から届く請求書の受領・保管や、支払依頼書の作成、振込処理は時間と手間がかかります。誤入力や支払漏れのリスクも発生しやすい業務です。
アイデア:支払プロセスを集約・標準化し、複数件の支払をまとめて処理できる「総合振込」を活用することで効率化が進みます。
有効なツール:AI-OCRで紙の請求書をデータ化する仕組み、支払管理システムによる承認フローの一元化、法人カードを活用した小口支払の集約。
課題:従業員が立替精算を行う場合、領収書の糊付けや紙の提出、承認リレーの遅延が発生しやすく、経理側もチェックや仕訳入力に追われます。
アイデア:キャッシュレス化を推進し、法人カードや交通系ICカードを利用することで、立替を最小化できます。さらに精算ルールを簡素化することで申請者・承認者双方の負担を軽減できます。
有効なツール:スマホから領収書を撮影して申請できる経費精算システム、交通系ICカードや法人カードとの自動連携。
課題:決算業務ではExcelでのデータ集計や証憑突合、残高確認に時間がかかり、担当者の大きな負担になっています。
アイデア:日次・週次の段階で早期に締め処理を進めておくことで、決算期末の負荷を分散できます。さらに「決算チェックリスト」を活用することで、抜け漏れを防止できます。
有効なツール:クラウド会計ソフトを活用した仕訳・残高の自動処理、BIツールによるデータの可視化・分析。
経理効率化は「ツールを導入すれば終わり」ではありません。現状把握から効果測定までの流れを設計し、段階的に進めることが成功のカギです。ここでは、失敗を避けるための4つのステップを紹介します。
最初にやるべきは、自社の経理業務を可視化することです。請求書処理、支払管理、経費精算、決算業務といった業務ごとに、
・どこに時間がかかっているか
・どの工程でミスや差し戻しが多いか
を整理します。
この時、課題はすべて一度に解決しようとせず、「業務量が多い領域」「影響が大きい領域」から優先度をつけることが重要です。
改善案を検討する際は、効果とコストを比較し「どの施策から始めるか」を見極めます。例えば、経費精算システム導入は初期コストが比較的低く、効果も分かりやすいため導入の第一歩に適しています。いきなり全社展開するのではなく、一部部署や特定業務でスモールスタートすることで、現場の抵抗感を抑えつつノウハウを蓄積できます。
ツール導入時の落とし穴は「現状の非効率な業務をそのままシステム化してしまう」ことです。これでは期待した効果が得られません。導入前に業務フローを見直し、不要な承認ステップや重複作業を削減したうえでシステムを適用することがポイントです。さらに、現場担当者へのトレーニングやマニュアル整備を行い、実務に定着させる工夫が必要です。
効率化は導入して終わりではなく、成果を測定して改善を続けることで定着します。
・削減できた工数
・エラー件数の減少
・決算早期化の達成度
といった数値を定期的に確認し、改善効果を「見える化」することが大切です。さらに、法改正や組織変更に合わせて業務フローをアップデートし続けることで、経理効率化を一過性で終わらせず、持続的な改革につなげることができます。
経理効率化を進める上で参考になるのが、実際に成果をあげた企業の取り組みです。ここでは、中小企業と中堅企業、それぞれの事例を紹介します。
ある従業員数50名規模の中小企業では、経費精算を紙の領収書提出とExcel入力で管理していました。経理担当者は毎月、領収書チェックや仕訳入力に膨大な時間を費やし、月末は残業が常態化していました。
そこで導入したのが経費精算システムです。従業員はスマホで領収書を撮影して申請でき、経理側は自動仕訳機能を活用してチェックに集中できるようになりました。さらに法人カードや交通系ICカードと連携させることで、立替精算自体を減らす仕組みを整備しました。
結果として、月50時間以上の工数削減に成功。経理担当者は請求書管理や決算準備など、より付加価値の高い業務に時間を充てられるようになりました。この事例は「小規模でもスモールスタートで成果を出せる」好例といえます。
従業員数500名規模の中堅企業では、毎月数千件に及ぶ請求書処理が経理部門の大きな負担となっていました。紙で届く請求書を人の手で入力し、入金消込まで目視で確認していたため、時間がかかるだけでなく入力ミスも多発していたのです。
同社はこの課題を解決するため、AI-OCRで請求書をデータ化し、RPAで会計システムに自動入力する仕組みを導入しました。これにより、担当者は内容確認と例外処理に専念できるようになり、定型作業はほぼ自動化されました。
導入後は、請求書処理にかかる時間が半分以下に短縮され、ヒューマンエラーも大幅に減少。業務品質の向上に加え、月次決算のスピードも向上し、経営陣がタイムリーに業績を把握できるようになりました。
経理効率化を進める際には、多くの担当者が似たような疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問にQ&A形式でお答えします。
A. 最も効果が出やすいのは 経費精算や請求書処理など、件数が多く反復的な業務 です。紙やExcelでの処理が残っているなら、まずはクラウド型の経費精算システムや請求書発行システムを導入するのがおすすめです。工数削減効果が目に見えやすく、現場の納得感も得やすいでしょう。
A. 抵抗をなくすには、「全員にメリットがある」ことを伝えるのが効果的です。例えば「立替精算が減って従業員の負担が軽くなる」「承認がスマホでできて管理職の負担も減る」といった具体的な利点を示しましょう。また、最初は小さなプロジェクトから始め、成功体験を積むことで自然に受け入れられるようになります。
A. クラウドサービスはセキュリティ対策が進んでおり、オンプレミス環境より安全性が高い場合も多いです。選定の際は、通信の暗号化、認証方式、データ保存場所、バックアップ体制などを確認しましょう。また、自社の情報管理ルールと照らし合わせ、利用権限の設定やアクセスログの管理を徹底することが重要です。
A. 効率化によって単純作業は減りますが、経理の仕事自体がなくなることはありません。むしろ、定型業務が減ることで、経営に貢献する分析や提案、内部統制の強化といった「付加価値の高い業務」にシフトできるのが大きなメリットです。効率化は「経理を不要にする」のではなく、「経理をより戦略的な役割に進化させる」取り組みなのです。
経理の効率化は、単なるコスト削減や残業削減のための取り組みではありません。紙や手作業を減らすことで ミスや不正を防ぎ、業務の透明性を高める ことができます。さらに、決算や月次処理のスピードが上がれば、経営層がリアルタイムで状況を把握でき、意思決定の精度とスピードが向上するでしょう。
また、効率化によって生まれた時間は、経理担当者が データ分析や経営支援といった付加価値の高い業務 にシフトするための大きな資源になります。つまり経理効率化は、組織を守るだけでなく、会社を成長へ導く「戦略的業務」なのです。
本記事で紹介したアイデアやツールは、どれも特別な企業だけが使えるものではありません。まずは自社の業務をひとつ選び、改善の「最初の一歩」を踏み出してみましょう。その小さな取り組みが積み重なれば、経理部門は会社の未来を創る強力なパートナーへと進化していきます。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

事業用不動産のコスト削減ガイド
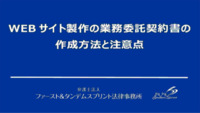
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
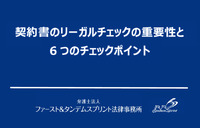
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
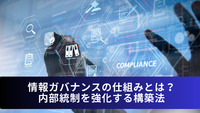
情報ガバナンスの仕組みとは?内部統制を強化する構築法
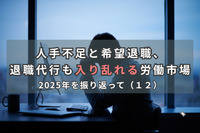
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)

焼津市の建設会社・橋本組、「えるぼし認定」最上位に 女性活躍推進法に基づく全項目をクリア

決算書が赤字の時に見るべき場所とは?原因の読み解き方と改善策を徹底解説

令和7年度 法人税申告書の様式改正
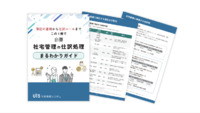
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

オフィスステーション導入事例集
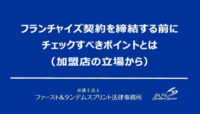
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

オフラインアクセスは危険?クラウドストレージの安全な活用

事業再生を取り巻く環境の変化=2025年を振り返って(11)
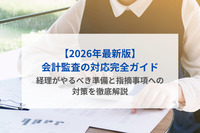
【2026年最新版】会計監査の対応完全ガイド|経理がやるべき準備と指摘事項への対策を徹底解説

年収の壁を起点に整理する!令和8年度税制改正 実務対応ガイド【セッション紹介】

外注と業務委託の違いとは?契約形態や活用シーンをわかりやすく解説
公開日 /-create_datetime-/