公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
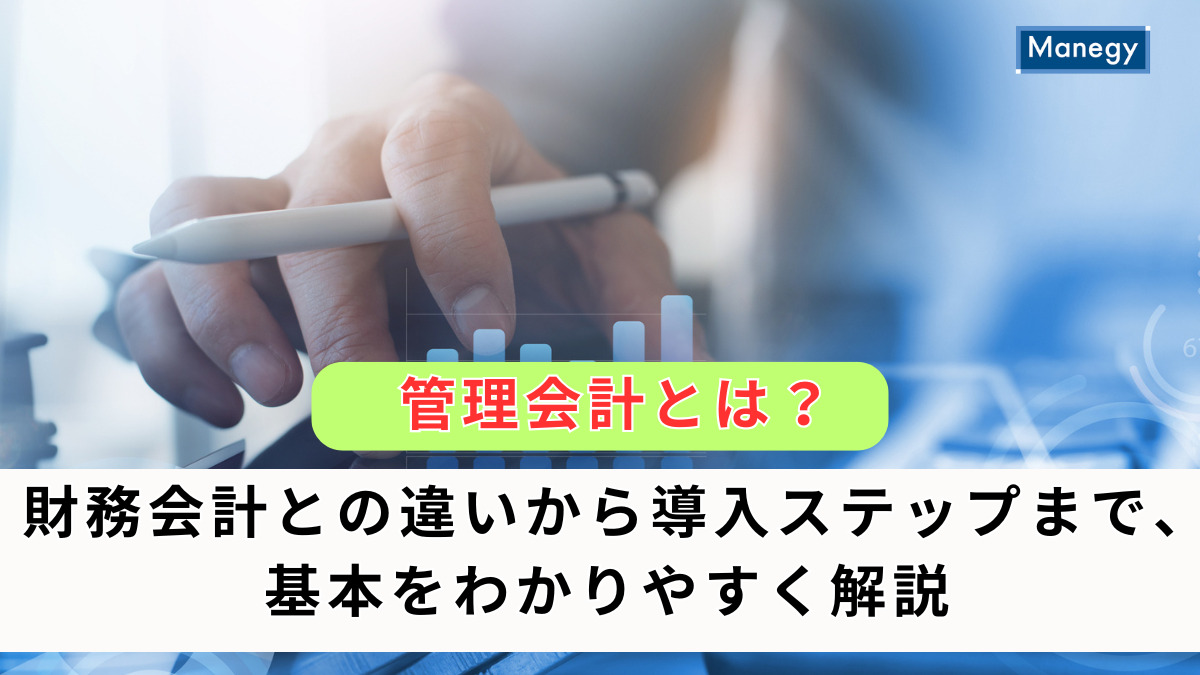
企業経営において、数字を正しく理解し、迅速かつ適切な意思決定を行うためには「管理会計」が欠かせません。
多くの企業では財務会計をもとに経営状況を把握していますが、財務会計は株主や税務当局など外部への報告が主目的であり、日々の経営判断には必ずしも十分ではありません。
一方、管理会計は社内の意思決定や業務改善を目的とし、経営陣や管理職が「次に何をすべきか」を判断するための情報を提供します。
市場環境の変化が激しい今、感覚や経験だけに頼った経営はリスクが高く、データに基づく経営判断が企業の生存戦略として求められています。
管理会計とは、経営陣や各部門の責任者が、事業の方向性や改善策を判断するために活用する会計手法です。
財務会計と異なり、法的な形式やルールは定められておらず、企業の実情に応じて自由に設計できます。
分析の対象は、製品別の利益率、部門別の収益性、プロジェクトごとのコスト構造など多岐にわたります。
目的は、将来の意思決定をサポートすることにあります。
たとえば、赤字の可能性がある事業を縮小したり、利益率の高い製品への投資を強化したりといった経営判断が可能になります。
情報は社内利用を前提としているため、速報性が重視され、月次や週次、場合によっては日次での分析が行われます。
一方、財務会計は企業の経営成績や財政状態を、株主、投資家、金融機関、税務当局など外部ステークホルダーに報告することを目的としています。
こちらは会社法や金融商品取引法、会計基準などの法的ルールに沿って作成する必要があり、記載内容や形式は厳格に定められています。
決算書や有価証券報告書が代表的なアウトプットであり、過去の取引実績を正確かつ網羅的に示すことが求められます。
財務会計の情報は客観性や比較可能性に優れますが、将来の意思決定や部門別の詳細分析には必ずしも適していません。
したがって、企業経営においては財務会計だけでなく、管理会計を併用することで、外部への信頼性確保と内部での迅速な意思決定の両立が可能になります。
管理会計と財務会計は、目的や利用者、ルールの有無など、複数の側面で異なります。
下表では7つの視点から両者を整理しました。
| 視点 | 管理会計 | 財務会計 |
|---|---|---|
| 目的 | 経営判断や業務改善のための情報提供 | 株主・投資家・税務当局など外部への報告 |
| 利用者 | 経営陣、管理職、現場部門 | 株主、投資家、金融機関、税務当局 |
| 対象期間 | 将来予測・計画を含む(予算・見込み) | 過去の実績(取引結果) |
| 法的ルール | なし(企業ごとに設計可能) | 会社法・会計基準などに準拠 |
| 形式 | 必要に応じた自由なフォーマット | 決算書など法定様式に基づく |
| 分析粒度 | 部門別・製品別・案件別など詳細分析 | 企業全体の財務状況を網羅的に表示 |
| 情報更新頻度 | 週次・月次・日次など柔軟 | 年次・四半期など法定タイミング |
この比較からも分かるように、財務会計は外部への信頼性の高い報告を目的とし、管理会計は社内の迅速な意思決定を支援するための柔軟な仕組みです。
企業が持続的に成長するためには、両者をうまく組み合わせて活用することが不可欠です。
管理会計では、会社の現状を正しく把握し、将来の戦略を立てるために様々な分析手法が用いられます。
ここでは代表的な4つを紹介します。
予実管理は、予算(予定)と実績を比較し、その差異の原因を分析する手法です。
売上やコストのどの部分が計画通りに進んでいないのかを明らかにし、改善策を検討します。
例えば、売上が予算を下回っている場合、その要因が販売数量の減少なのか、単価の下落なのかを特定し、対応策を立てます。
損益分岐点分析は、売上とコストの関係から、企業が利益を出すために必要な売上高(損益分岐点)を算出する方法です。
固定費・変動費の構造を把握し、黒字化に必要な販売量やサービス提供数を逆算できます。
販売戦略やコスト削減の優先順位を決めるうえで有効な手段です。
原価管理は、商品やサービスの提供にかかるコストを詳細に把握し、利益率を改善するための分析手法です。
直接原価(材料費・人件費など)だけでなく、間接費(管理部門費用・設備費など)も含めて集計することで、どの製品やサービスが利益を押し上げ、どれが足を引っ張っているのかを見極めます。
資金繰り管理は、入金と出金のタイミングを把握し、資金ショートを防ぐための管理手法です。
たとえ会計上は黒字でも、現金が不足すると倒産の危機に陥ります。
売掛金の回収期間短縮や在庫の適正化など、資金流動性の改善が重要なポイントです。
管理会計の導入は、会社全体の意思決定や業務改善を加速させますが、その恩恵は立場によって異なります。
ここでは、代表的な3つの立場と、それぞれのメリットを紹介します。
経営者にとって管理会計は、企業の現状を「数字」で可視化し、戦略を立てるための羅針盤となります。
部門別の収益性や事業ごとの採算性を把握することで、投資判断や撤退判断を迅速に行えます。
感覚や経験だけに頼らず、データに基づいた意思決定が可能になります。
管理職は、自部門の予算達成度やコスト構造を明確に把握できるため、日々のマネジメントに活かせます。
例えば、営業部門であれば商品ごとの利益率をもとに重点販売商品の選定が可能になります。
生産部門であれば、原価分析を通じて効率改善のポイントを特定できます。
現場レベルでも管理会計は有効です。
自分の作業が会社の利益やコスト構造にどのように影響しているかを理解できれば、業務改善やコスト削減の意識が高まります。
また、成果が数字で見えることで、モチベーションの向上にもつながります。
管理会計は大企業だけのものではありません。
中小企業でも、正しいステップを踏めば効果的に導入できます。
まずは管理会計を導入する目的を明確にします。
例えば「商品別の採算性を知りたい」「部門ごとの利益を把握したい」など、目的がはっきりしていれば、必要なデータや分析方法も定まりやすくなります。
最初から全ての分析を行おうとすると負担が大きくなります。
まずは予実管理や原価管理など、一つの分野から始めるのがおすすめです。
徐々に範囲を広げ、分析精度を高めていきます。
管理会計を機能させるには、データの一貫性と信頼性が欠かせません。
勘定科目の定義や収集方法を統一し、誰が見ても同じ結果が得られる仕組みを作ることが重要です。
最初はExcelでも始められますが、規模が大きくなると専用の会計ソフトやBI(ビジネスインテリジェンス)ツールの導入が有効です。
データ集計や分析が自動化され、意思決定のスピードが飛躍的に向上します。
基本的な分析は会計知識がなくても可能です。
まずは簡単な予実管理や損益分岐点分析から始め、必要に応じて専門家や会計ソフトのサポートを活用しましょう。
従業員数や売上規模に関係なく、意思決定のために経営数値を活用したい場合は導入を検討すべきです。
特に事業部や店舗が複数ある場合、部門別の収益管理は早い段階で必要になります。
実務者向けには「管理会計入門」や「原価計算基準」の解説書がおすすめです。
資格としては日商簿記2級以上や、中小企業診断士などが管理会計の理解に役立ちます。
管理会計は、財務会計のように法的な義務はありませんが、企業の意思決定や成長戦略に不可欠な存在です。
予実管理や原価管理、損益分岐点分析などの手法を活用すれば、会社の強みや課題を数値で明らかにできます。
導入にあたっては目的を明確にし、スモールスタートから始めることが成功の鍵です。
経営者、管理職、現場社員が共通の数字を基盤に動ける体制を作ることで、企業全体の方向性が一致し、持続的な成長につながります。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
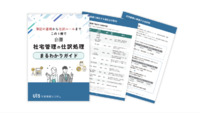
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
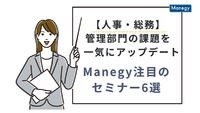
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選

クラウドストレージの安全な導入ガイド
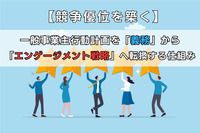
【競争優位を築く】一般事業主行動計画を「義務」から「エンゲージメント戦略」へ転換する仕組み
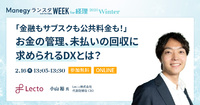
お金の回収を頑張らない時代へ!DXで変わる管理と回収の新常識【セッション紹介】
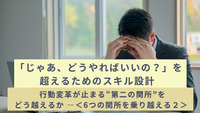
「じゃあ、どうやればいいの?」を超えるためのスキル設計― 行動変革が止まる“第二の関所”をどう越えるか ―<6つの関所を乗り越える2>

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応
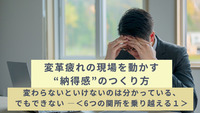
変革疲れの現場を動かす“納得感”のつくり方 ― 変わらないといけないのは分かっている、でもできない ―<6つの関所を乗り越える1>

「一律50万円支給」の転勤支援金制度を新設。住友重機械工業、転勤を“前向きな挑戦”に変える人事施策を導入
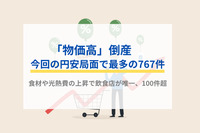
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
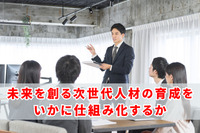
未来を創る次世代人材の育成をいかに仕組み化するか
公開日 /-create_datetime-/