公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
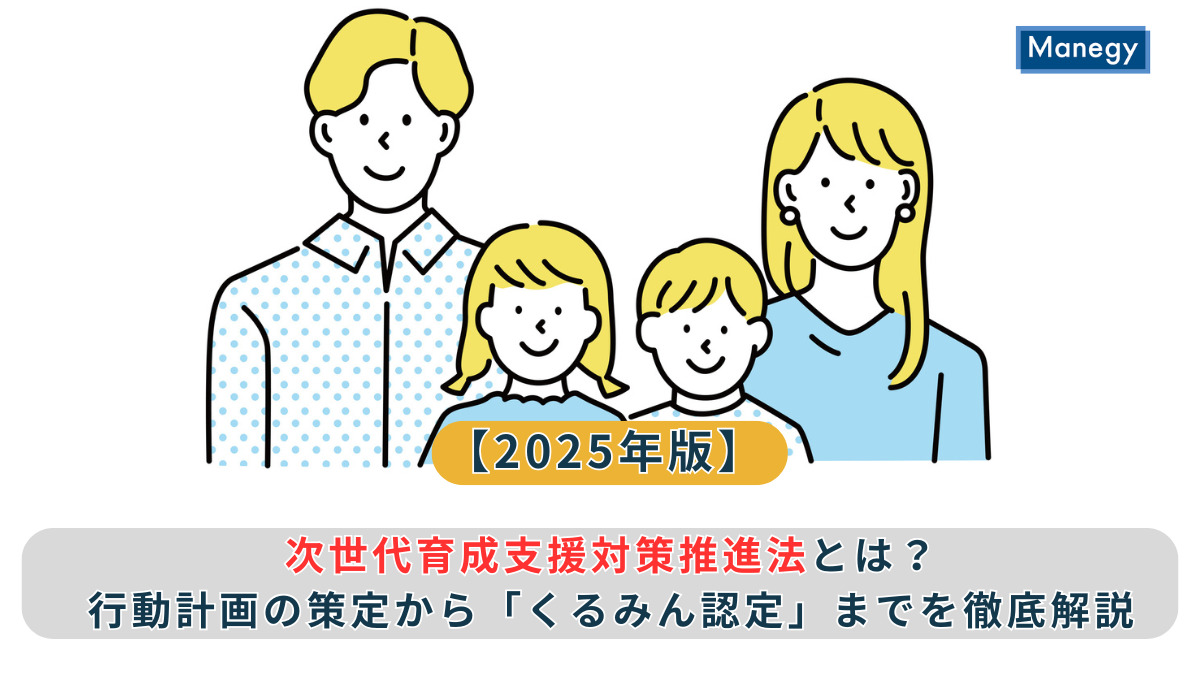
“次世代法”という言葉はよく聞くものの、自社で何をすべきか具体的にわからない…という担当者の悩みを耳にします。
次世代法が一定の企業に課している「一般事業主行動計画」は、企業にとっては単なる義務ではなく、人材確保や企業のイメージ向上に繋がる重要な経営戦略といえるでしょう。
また、計画を策定して一定の要件を満たした場合に取得できる「くるみん認定」は、人材の定着や税額控除などのメリットがあります。
そこでこの記事では、次世代法の計画策定から、くるみん認定の取得までを丸ごとナビゲートします。
企業にとってなぜ今、次世代育成支援への取り組みが重要なのかを、次世代法の目的やメリットとともに解説します。
次世代育成支援推進法(次世代法)の目的は、急速な少子高齢化、地域や家庭環境の変化などに対応しつつ、日本の次世代を担う子どもたちが健やかに成長できる社会を形成することです。
そして上記の目的を達成するために、次世代法は国・地方公共団体・企業等が負うべき義務を定めています。
次世代法が制定された背景は、少子高齢化の進行による労働力の減少や、共働き家庭の増加などによって、仕事と育児を無理なく両立できる環境を整えることが緊急の課題となったことなどです。
次世代法が定める企業の義務は、企業で働く労働者の仕事と子育てを両立させるために、「一般事業主行動計画」を策定することです。
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定して、管轄の労働局に届け出ることが義務とされています(100人以下の企業は努力義務です)。
一般事業主行動計画を策定することは、企業にとっては単なる義務ではなく、以下の3つの経営メリットを得ることができる、重要な経営戦略といえます。
一般事業主行動計画の策定から公表までの流れを、5ステップで解説します。
計画を策定するにあたって、まず自社の現状と従業員のニーズを把握する必要があります。
現状やニーズを把握することで、解決すべき課題や改善すべき点が見えてくるからです。
次に、労働者の育児休業等の取得状況と、労働時間の状況を把握することが重要です(法改正により、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、直近の事業年度における労働者の育児休業等の取得状況と、労働時間の状況を把握することが義務付けられています)。
計画期間は、各企業の実情に応じて、次世代育成支援対策を効果的かつ適切に実施できる期間を設定することが望ましいとされます。
次に、計画において達成すべき目標を設定します。なお、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、育児休業等の取得状況と労働時間の状況について、具体的な数値目標を設定しなければなりません。
たとえば、計画期間における男性労働者の平均育児休業取得率を〜%以上とするなど、具体的な数値を用いて目標を設定する必要があります。
目標を決めた後は、目標の達成に向けて実施する対策の具体的な内容を定めます。
内容を決めるにあたっては、自社の実情に見合った実効性のある対策を盛り込むことが重要です。
対策内容に実効性がある場合、行動計画の実施状況を適切に評価できるうえ、その結果を今後の計画に反映させやすいからです。
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3ヶ月以内に労働局へ届け出ます。
届け出の方法は、郵送・持参・電子申請の3種類です。
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3ヶ月以内に計画を社内に通知するとともに、社外に公表します。
社内に通知する方法としては、事業所の見やすい場所に掲示する、労働者へ配布する、電子メールで送付する、企業内ネットワークに掲載するなどがあります。
社外への公表方法は、自社のホームページへ掲載する、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」へ掲載する、事務所に備え付けるなどです。
行動計画を策定して一定の要件を満たした場合に受けることができる「くるみん認定」の種類と、くるみん認定を受けることによるメリットについて解説します。
| 認定の種類 | 認定の概要 | 認定のメリット |
|---|---|---|
| くるみん |
・行動計画を策定して一定の要件を満たした場合に、必要書類を添えて申請を行うことで、「子育てサポート企業」として認定を受けることができる ・認定を受けるには、全9項目の認定基準を全て満たす必要がある |
・くるみんマークを商品、広告、求人広告などに付けることができる ・公共調達の加点評価等を受けることができる |
| トライくるみん |
・3種類のくるみん認定の中では、比較的に認定を受けやすい ・認定を受けるには、全9項目の認定基準を全て満たす必要がある |
・トライくるみんマークを商品、広告、求人広告などに付けることができる ・公共調達の加点評価等を受けることができる(3種類の認定の中では、加点評価率が最も低い) |
| プラチナくるみん |
・3種類のくるみん認定の中では、認定を受ける難易度が最も高い ・認定を受けるには、事前にくるみん認定またはトライくるみん認定を受けたうえで、所定の要件を満たす必要がある |
・プラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などに付けることができる ・公共調達の加点評価等を受けることができる(3種類の認定の中では、加点評価率が最も高い) |
くるみん認定を受けると、認定を受けたことを証明するマークを商品や求人広告などに貼り付けることができるので、採用力の強化や企業イメージの向上につながります。
子育てを積極的にサポートする企業であることをアピールできるので、子育てと仕事の両立を重要視する人材を定着させたり、子育て世代の消費者から高評価を得たりなどのメリットが期待できます。
くるみん認定を受けた企業が一定の要件を満たした場合、税額控除率が5%上乗せされます。
上乗せを受けるための具体的な要件等は、以下のとおりです。
| どの企業向けか | 具体的な要件 | 必要なくるみん認定 |
|---|---|---|
| 全企業向け | 青色申告書を提出する全企業または個人事業主 | プラチナくるみん |
| 中堅企業向け | 青色申告書を提出する従業員数2000人以下の企業または個人事業主(一定の場合をのぞく) | プラチナくるみん |
| 中小企業向け | 青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)または従業員数1000人以下の個人事業主 | くるみんまたはプラチナくるみん |
次世代法に関するよくある質問について回答します。
常時雇用する労働者が100人以下の企業は、一般事業主行動計画を策定して届け出る必要はありません。
しかし、一般事業主行動計画は単なる義務ではなく、人材の確保や生産性の向上などのメリットがあるので、100人以下の企業も計画策定に積極的に取り組むべきといえるでしょう。
行動計画において定めた目標が未達成の場合でも、罰則などが課されるわけではありません。
ただし、目標を達成することはくるみん認定の要件の1つであるだけでなく、達成によって従業員のモチベーションを高めるなどのメリットがあるので、積極的に目標を達成することが望ましいといえます。
くるみん認定の申請は、認定要件を全て満たしたうえで、所定の申請書(基準適合一般事業主認定申請書)に必要書類を添付し、電子申請・郵送・持参のいずれかの方法で労働局に提出します。
くるみん認定は、次世代法に基づいて、子育てを積極的にサポートする企業であると評価された場合に認定を受けられます。
一方、えるぼし認定とは、女性活躍推進法に基づいて、女性の活躍を推進する取り組みなどが優良と評価された企業が認定される制度です。
くるみん認定は子育てについての認定制度であり、えるぼし認定は女性の活躍についての認定制度といえます。
次世代法に対応することは、企業にとっては単なる法令遵守の活動ではなく、従業員の働きやすさとエンゲージメントを高めることで、これからの時代に選ばれる企業になるための「未来への投資」といえるでしょう。
具体的には、次世代法が定める計画を策定したり、くるみんの認定を受けたりすることで、人材の定着や企業イメージの向上などの複数のメリットを得られます。
まずはこの記事のステップを参考にして、仕事と子育ての両立に関する自社の現状把握からスタートし、計画的かつ戦略的に取り組みを進めることが重要です。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説

契約書の表記ゆれチェック方法を解説|Wordと専用ツールの精度も比較

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
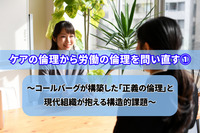
ケアの倫理から労働の倫理を問い直す①~コールバーグが構築した「正義の倫理」と現代組織が抱える構造的課題~

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
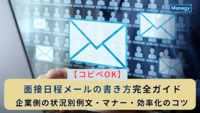
【コピペOK】面接日程メールの書き方完全ガイド|企業側の状況別例文・マナー・効率化のコツ
公開日 /-create_datetime-/