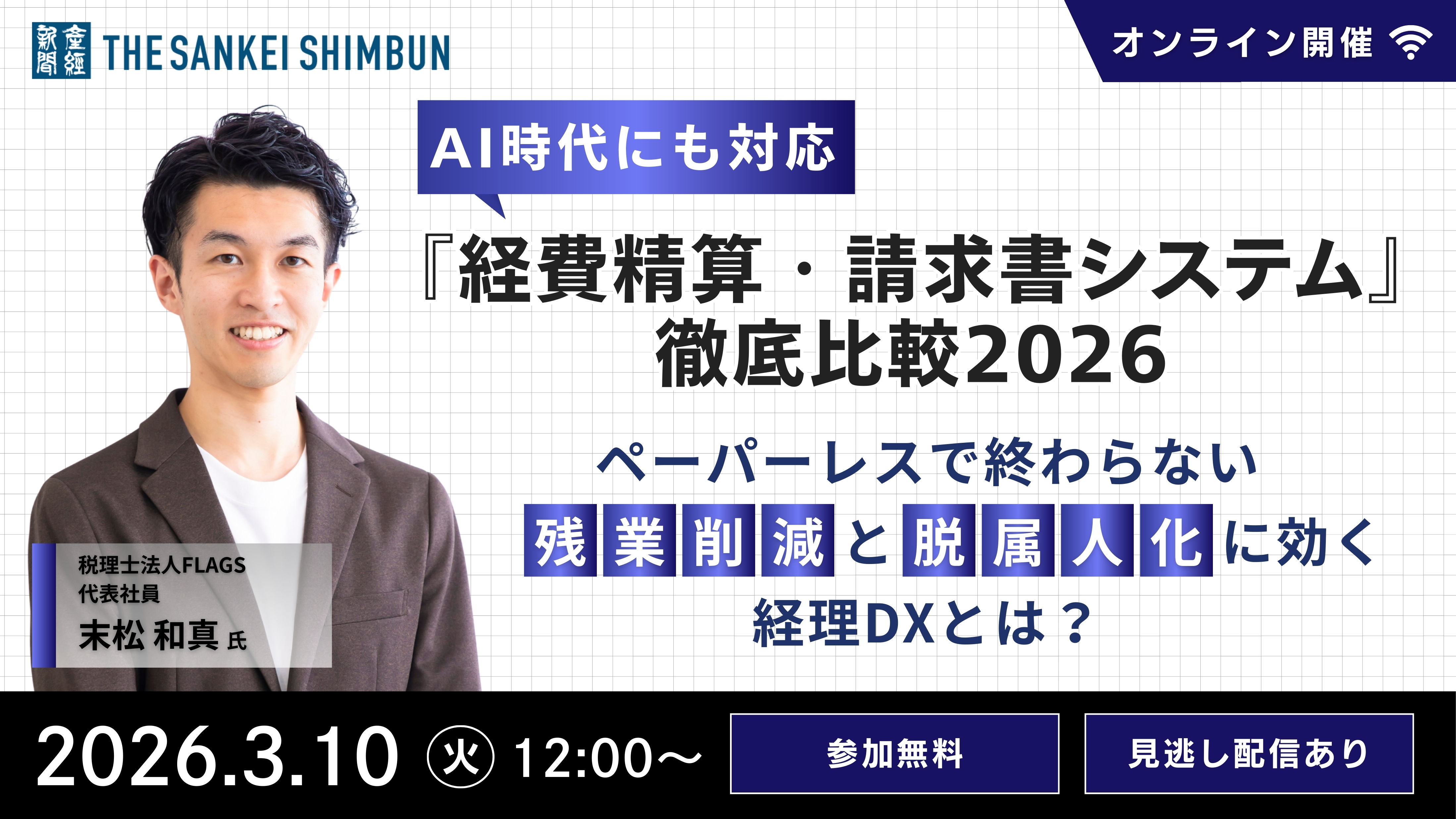公開日 /-create_datetime-/

「社員も経営者も懸命に働いているのに、利益が思うように出ない」──そんな悩みを抱える企業は少なくありません。
・残業が常態化し、社長自身も休みなく走り続けている
・広告や新サービスに投資しても成果につながらない
こうした状況の背景にあるのは、努力不足ではなく「利益構造がどこで崩れているのか」が見えていないことです。
本記事では、経営改善が進まない会社に共通する課題を整理し、数字をセグメント別に見える化して利益体質へ転換するための第一歩を解説します。
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
鍵政 達也
ExePro Partner
経営コンサルタント
ExePro Partner 代表 経営コンサルタント。経済産業省認定 認定経営革新等支援機関。
コンサルティング会社での経験と経営者としての事業再生の実務経験を活かし、経営における「数字の見える化」「やるべきことの言語化」をメインテーマに現場に即した経営支援を実施。
これまで100社超の支援に携わる。
なぜ「頑張っているのに苦しい」のか?
努力そのものは十分に行われているにもかかわらず、成果につながらないのはなぜでしょうか。
問題は、方向性が整理されないまま各部門が走り続け、組織全体が疲弊していることにあります。
さらに「収益構造の見えなさ」により、赤字要因が特定されず、打ち手が場当たり的になってしまうのです。
その結果、現場の頑張りが報われず、改善が進まない悪循環に陥ります。
lockこの記事は会員限定記事です(残り3459文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -
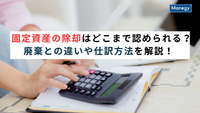
固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!
ニュース -
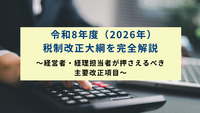
令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~
ニュース -

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説
ニュース -
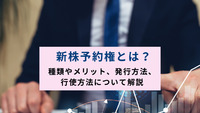
新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説
ニュース -
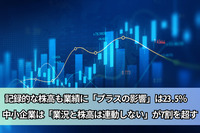
記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
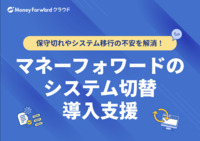
マネーフォワードのシステム切り替え導入支援
おすすめ資料 -

副業している社員から確定申告の相談!税務リスクを考えた対応方法とは
ニュース -
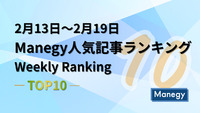
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -
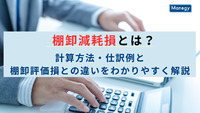
棚卸減耗損とは?計算方法・仕訳例と棚卸評価損との違いをわかりやすく解説
ニュース -
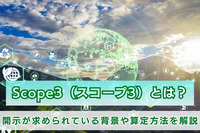
Scope3(スコープ3)とは?開示が求められている背景や算定方法を解説
ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説
ニュース