公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

外食関連企業や福利厚生サービス事業者などで構成される「食事補助上限枠緩和を促進する会」(幹事社:エデンレッドジャパン)は9月3日、経済産業省が8月29日に公表した2026年度税制改正要望において、食事補助制度に関する所得税非課税限度額の引き上げが明記されたことを発表した。
同会は、制度見直しに向けた政策的な動きが進んだものとして、「改正実現に向けた大きな前進」との見方を示している。
経済産業省の要望には、「足元の物価上昇の状況などを踏まえ、本制度の非課税限度額の引き上げを行う」と明記された。食事補助制度に関する非課税限度額の見直しが政府の税制改正要望に明記されたのは、今回が初めて。
企業が従業員に支給する食事補助については、一定の条件を満たす場合、所得税の非課税対象となる。現行制度では、会社が現物支給する食事について、従業員の自己負担が半額未満であり、かつ会社の負担額が月額3500円以下の場合は従業員には課税されない。企業側は福利厚生費として損金算入できる。
この非課税限度額は1984年に設定されたものであり、以降40年以上にわたり改定されていない。
「食事補助上限枠緩和を促進する会」は、飲食店、食事補助支給企業、福利厚生サービス事業者など1140者・社で構成される民間団体である。幹事社は、福利厚生食事券事業を手掛けるエデンレッドジャパン(東京都港区)。
同会は、設立以降、国会議員との勉強会や意見交換を重ねてきた。2025年5月には、小泉進次郎衆議院議員(当時)や古川康衆議院議員らに対し、非課税限度額を月額6000円に引き上げることを求める要望書を提出した。
こうした活動を受けて、同年6月に政府が閣議決定した「骨太の方針2025」および「新しい資本主義実行計画2025」において、物価上昇に対応できていない制度として、食事補助の非課税制度が明記された。
記事提供元

「月刊総務オンライン」は、総務部門の方々に向けて、実務情報や組織運営に役立つニュース・コラムなどの「読み物」を中心に、さまざまなサービスを提供する総合的支援プラットフォームです。
「eラーニング」「デジタルマガジン」「マーケット」、さらに有料会員向けサービス「プレミアム」が、日々の業務を強力に支援。会員向けメールマガジンも毎日配信しており、多くの方が情報収集に活用されています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

「叱る・注意する」が怖くなる前に ─ ハラスメントを防ぐ“信頼ベース”の関係づくり

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!

日本のダイバーシティの針はどちらに振れるのか ―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―
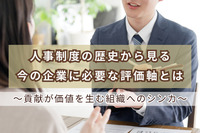
人事制度の歴史から見る今の企業に必要な評価軸とは ~貢献が価値を生む組織へのシンカ~
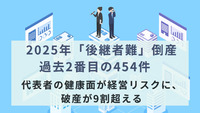
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

オフィスステーション年末調整

人的資本開示の動向と対策

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>
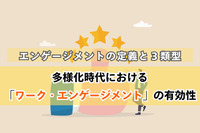
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
公開日 /-create_datetime-/