公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
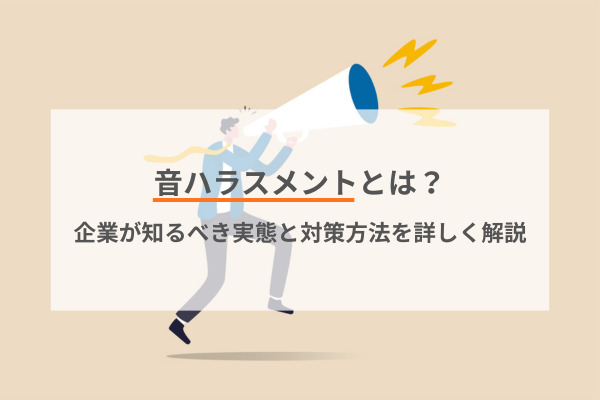
職場で「談笑する声」や「キーボードのタイピング音」など、他人の音に関するストレスを感じたことはありませんか。
近年、この職場での音に関する問題として、「音ハラスメント」が浮上しています。
本記事では、企業の人事担当者や管理職の方に向けて、音ハラスメントの実態と具体的な対策方法について詳しく解説します。
音ハラスメントとは、職場での不快な音や騒音によって周囲に精神的苦痛を与える行為を指します。
従来のハラスメント分類には含まれていませんでしたが、オープンオフィスの普及や働き方の多様化により、新たな職場問題として注目されています。
特徴は、加害者が無自覚であることが多い点です。
悪意がなくても、継続的な音が集中力を阻害し、業務効率の低下やストレスにつながります。
現時点で法令上の明確な定義はなく、通念上ハラスメントと認識されているにとどまります。
あわせて読みたい
職場での音ハラスメントは、日常的な行為が原因となることが多く、問題視されにくい傾向があります。
よくある音ハラスメントの事例を紹介します。
最も多く報告されるのが、強いタイピング音による迷惑行為です。
メカニカルキーボードを強く叩くことで生じる「カチャカチャ」という音が、周囲の集中を妨げるケースが多く報告されています。
在宅勤務からオフィス勤務に戻る際、自宅で使っていた音の大きなキーボードを持ち込むことで発生する場合もあります。
また、ストレスを感じて無意識に強く打鍵し、感情的な状態が音として周囲に伝わってしまう問題もあります。
営業職や顧客対応の部署では、電話中の大声や独り言が騒音問題となることがあります。
必要以上に大きな声での応対や、通話後に「疲れた」「面倒だ」などとつぶやくことで、周囲に不快感を与えるケースです。
オープンオフィスでは声が響きやすく、複数人が同時に電話をすると深刻化します。
また、Web会議の普及でマイク性能を理解せず、大声で話すケースも増えています。
不満やストレスを感じた際に、意図的にため息をついたり、舌打ちを繰り返したりする行為は、周囲の従業員に心理的圧迫感を与えます。
特に、上司が部下に対してこれらの行為を行う場合、パワーハラスメントの要素も含む複合的な問題となります。
また、花粉症や風邪などの体調不良による咳払いであっても、頻繁に続く場合は周囲に迷惑をかけることがあります。
あわせて読みたい
音ハラスメントが職場で頻発する背景には、複数の構造的な要因が存在します。
多くの音ハラスメントは、当事者が自分の行為に無自覚であることから発生します。
個人の感覚差により、自分にとって普通の音量であっても他人には不快に感じられることがあります。
特に、聴覚の感受性には個人差が大きく、同じ環境にいても音の感じ方は人それぞれです。
また、長時間同じ環境にいることで音に慣れてしまい、客観的な音量を判断できなくなる「順応現象」も原因の一つです。
現代のオフィス設計の主流であるオープンオフィスは、音ハラスメントが発生しやすい構造的な問題を抱えています。
個室や仕切りのない空間では音が響きやすく、わずかな物音でも周囲に影響を与えます。
本来はコミュニケーション促進や空間効率向上を目的に導入されましたが、音への対策は十分でない場合が多いのが実情です。
さらに、防音設備はコスト削減の対象となりやすく、問題を一層深刻化させています。
音ハラスメントは単なる職場の迷惑行為ではなく、従業員の心身の健康に深刻な影響を与える問題です。
企業は労働安全衛生法に基づき、従業員の健康を守る義務があるため、この問題を軽視することはできません。
継続的な騒音は認知機能に悪影響を与え、集中を要する作業の効率を大きく下げます。
文書作成や数値計算、プログラミングなどの知的業務では、わずかな音でも作業効率が低下しやすい傾向があります。
さらに、不規則な音や突発音は脳を緊張状態に置き、疲労の蓄積やミスの増加を招きます。
音ハラスメントは被害者に長期的なストレスを与え、イライラや不安感を増幅させます。
音に敏感な従業員にとっては出勤自体が苦痛となり、メンタル不調や離職につながることもあります。
さらに、問題が放置されると信頼関係やチームワークが損なわれ、生産性全体の低下を招きます。
企業にとっても大きな損失となるため、早期の対応が欠かせません。
音ハラスメントの対策には、従業員の意識改革と職場環境の整備の両面からの取り組みが欠かせません。
以下で、具体的な対策方法を解説します。
従業員への教育と意識付けが最も重要です。
新入社員研修や定期研修に「音への配慮」を組み込み、タイピングの強さや電話時の声量、体調不良時の配慮を指導します。
音に対する感受性の違いを理解させ、相互尊重の姿勢を浸透させることが欠かせません。
物理的な環境改善も重要です。
パーティションや仕切り板で音の伝播を遮断すれば、完全な個室化が難しくても一定の効果があります。
デスク周りに低いパーティションを設置するだけでも改善可能です。
また、防音カーペットや吸音材の活用も有効です。
さらに、電話専用ブースやWeb会議用スペースを設けることで、通話による騒音を抑えられます。
A.
花粉症や風邪などで出る音は故意ではありませんが、周囲への気遣いは大切です。
マスクの着用や治療で症状を軽くする工夫をしましょう。
症状が重いときは在宅勤務や休暇の利用も考えることが望ましいです。
会社側も、安心して休める制度や、加湿・換気などの環境改善に取り組むことで職場全体の健康を守れます。
音ハラスメントは、現代の職場で新たに浮上した課題であり、加害者が無自覚である点が特徴です。
そのため、従来の対策とは異なるアプローチが求められます。
企業は、従業員への意識啓発と職場環境の改善を両立させることが重要です。
研修によって予防効果を高めつつ、パーティション設置などの環境整備をすることで問題を構造的に防止できます。
人事担当者や管理職の方は、この問題を軽視せず、組織全体で取り組む姿勢を持つことが不可欠です。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
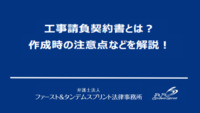
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
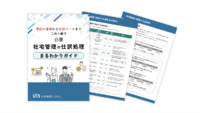
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
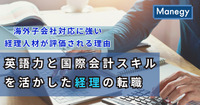
海外子会社対応に強い経理人材が評価される理由|英語力と国際会計スキルを活かした経理の転職(前編)

40年ぶりの労働基準法“大改正”はどうなる?議論中の見直しポイントと会社実務への影響を社労士が解説
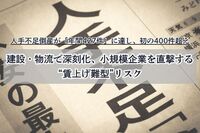
人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク
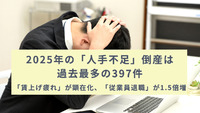
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論
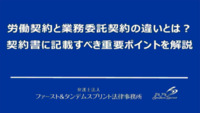
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
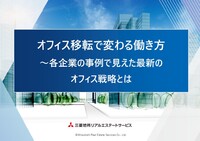
オフィス移転で変わる働き方

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

生成AI時代の新しい職場環境づくり

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
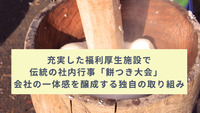
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み

キャッシュフロー計算書を武器にする|資金繰りに強い経理が転職市場で評価される理由(前編)
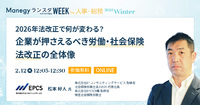
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】

旬刊『経理情報』2026年1月10日・20日合併号(通巻No.1765)情報ダイジェスト①/税務

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
公開日 /-create_datetime-/