公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

育児・介護休業法の改正で男性の育休取得が進む一方、男性育休の利用を妨げる「パタニティハラスメント(パタハラ)」も問題視されています。 パタハラとは、男性が育休や時短勤務などを利用する際に受ける嫌がらせや不利益な扱いのことです。
本記事では、パタハラの意味や事例、企業が取るべき防止策をわかりやすく解説します。
パタニティハラスメント(パタハラ)とは、男性が育児に関する制度を利用することに対して行われるハラスメントを指します。
「パタニティ(Paternity)」は「父性」を意味し、男性の育児参加を阻害する言動や行為全般が含まれます。
マタニティハラスメント(マタハラ)が妊娠・出産・育児を理由に女性が職場で不当な扱いを受けるのに対して、
パタハラは男性が育児制度を利用する際に受ける嫌がらせや不利益な扱いを指します。
男女雇用機会均等法第11条の3および
育児・介護休業法第25条において、
「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」として、企業には防止措置を講じる義務があります。
なお、法令や国の指針などでは「パタニティハラスメント」という用語は使用されず、
パタニティハラスメント・マタニティハラスメント・ケアハラスメントの3つをまとめて
「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」と呼んでいます。
具体的には、以下のような行為がパタハラに該当します。
参照:職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント|厚生労働省
ここでは、3つの観点からパタハラの具体的な事例を紹介します。
最も典型的なパタハラは、男性が育児関連制度を利用しようとした際に受ける妨害や圧力などです。
男性にも育児休業や時短勤務などの権利が保障されているにもかかわらず、男性育休の取得を拒否されたり、間接的に取得を妨害することがあります。
これらの行為は、育児・介護休業法第10条に違反する可能性が高く、企業は法的責任を問われる可能性があります。
申請があった場合は法的要件を満たしている限り、原則として承認しなければなりません。
育児休業や時短勤務から復帰した男性従業員に対する継続的な嫌がらせや差別的対応も深刻なパタハラです。
「育休ボケしているのではないか」といった揶揄的な発言や、昇進・昇格の機会を意図的に与えないなどの行為が該当します。
このような嫌がらせは、男性の育児参加を困難にし、組織全体の男性育児参加率向上の妨げとなります。
人事評価においては、育児制度利用を理由とした不利益取扱いは法的に禁止されているため、客観的で公正な評価基準の適用が必要です。
育児休業などを理由に、男性従業員に対する意図的な不利益配置や業務変更も重要なパタハラの形態です。
表面上は“配慮”として行われることもありますが、専門性を活かせない部署への異動や本人の意向を無視した一方的な配置決定は、これに該当します。
万が一配置変更が必要な場合は、十分な説明と本人の同意を得ることが重要です。
パタハラが社会問題として注目されるようになった背景には、社会的変化と制度改正の2つの側面があります。
少子高齢化が進むなか、政府は少子化対策の一環として「男性の育児参加」を重要な政策課題に掲げています。
内閣府の調査では、共働き世帯において夫の休日の家事・育児時間が長いほど、第2子以降の出生割合が高いことが明らかになりました。
こうしたデータからも、男性の育児参加が社会全体の課題として位置づけられていることがわかります。
さらに、働き方改革の進展により、ワークライフバランスや多様な働き方の実現が求められるようになりました。
これまでの「男性は仕事、女性は家庭」という性別役割分担の見直しが進み、男女問わず育児と仕事を両立できる社会への転換が進んでいます。
参照:第6回21世紀成年者縦断調査(夫の休日の家事・育児時間別にみた状況)|厚生労働省
あわせて読みたい
改正育児・介護休業法では、「出生時育児休業(産後パパ育休)」の新設(2022年10月施行)や、雇用環境整備の義務化などが行われました。
従業員1,000人超の企業には育児休業取得率の公表も義務付けられています(2023年4月施行)。
さらに、2025年4月からは従業員300人超の企業にも公表義務が拡大される予定です。
パタハラ防止と男性の育児参加促進には、
制度整備・意識改革・相談体制の3点を柱とした包括的な取り組みが必要です。
産後パパ育休を含む男性育児支援制度を整え、利用しやすい環境をつくることが基盤です。
給与保障を手厚くし、分割取得や時短勤務など柔軟な取得パターンを提供します。
さらに代替要員の確保や業務分散の仕組みを整え、職場全体の負担を軽減します。
管理職にはパタハラの法的リスクや適切なマネジメント方法を、
従業員には男性育児参加の意義や無意識の偏見を学ばせ、職場の理解を促進します。
実際に制度を利用した社員の体験談共有も、不安解消と利用促進に効果的です。
専門的な相談窓口を設け、社内外・匿名など複数のルートを用意することで相談しやすい環境を整備します。
相談員には専門研修を行い、公正で迅速な調査・対応体制を整えるとともに、不利益取扱いを防止します。
A. 原則として断ることはできません。
育児・介護休業法では、法定要件を満たす労働者の育児休業申請を事業主が拒否することを禁止しています。
「業務上の支障」は拒否理由として認められておらず、企業は代替要員の確保や業務調整により対応する義務があります。
ただし、労使協定により一定の労働者(入社1年未満の者、申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者、週の所定労働日数が2日以下の者)を対象外とすることは可能です。
A. このような発言は、直接的に育休を拒否しているわけではありませんが、
間接的に男性の育児制度利用を諦めさせる発言ととらえられることもあるため、パタハラに該当する可能性があります。
「慣例にない」ことを理由に利用を妨げることは法律違反となります。
企業は管理職に対する適切な研修を実施し、このような発言が行われないよう予防策を講じる必要があります。
A. 育児制度利用を理由とした不利益な評価は法的に禁止されています。
評価においては、育児休業期間中の不在や時短勤務を理由とした減点は行えません。
客観的な業務遂行能力や成果に基づく公正な評価を行い、育児と仕事の両立を支援する姿勢を示すことが重要です。
また、評価基準の明確化と評価者への研修実施により、公平な評価体制を構築することが求められます。
企業のバックオフィス担当者は、法的コンプライアンスの確保と職場風土の改善を両立させる視点で、
包括的なパタハラ防止体制を構築することが求められています。
男性の育児参加を支援する企業風土の醸成は、人材確保や企業イメージ向上の観点からも重要な経営課題となっています。
今後も制度改正や社会情勢の変化に応じて、継続的な取り組み強化が必要です。
パタハラのない職場環境を実現することで、性別に関わらずすべての従業員が安心して育児と仕事を両立できる組織作りを目指しましょう。
他にも知っておきたいハラスメント
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

ラフールサーベイ導入事例集

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
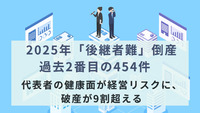
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
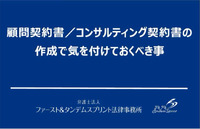
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
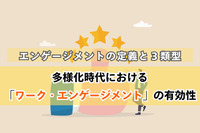
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
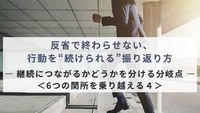
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
公開日 /-create_datetime-/