公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
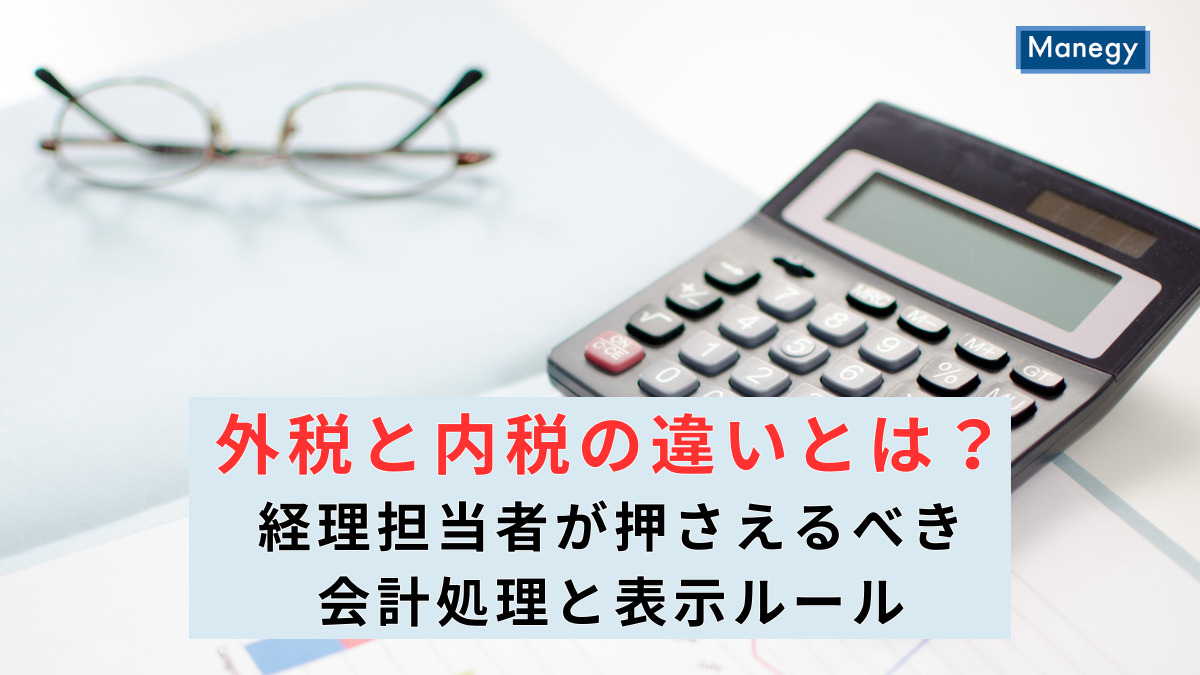
請求書や見積書を作成するとき、「外税(税抜)と内税(税込)のどちらで記載すべきか」迷うことはないでしょうか。
インボイス制度や総額表示義務の影響で、区分を誤ると金額認識のズレ・誤請求・会計処理の不整合が生じます。
この記事では、外税・内税の違い、請求書の正しい記載、総額表示義務・会計処理との関係を実務のコツとともに整理します。
商品やサービスの価格を表示・計算する際には、「外税(税抜)」と「内税(税込)」という2つの方法があります。どちらも消費税を考慮した価格の示し方ですが、税額を別に加算するか、あらかじめ含めて表示するかという点が大きな違いです。
経理・営業・総務いずれの部門でも、見積書・請求書の記載方法や会計処理に影響するため、正確に理解しましょう。
「外税(税抜)」とは、商品やサービスの価格を「税抜価格」として表示し、その金額に消費税額を別途加算する方法を指します。
たとえば、商品価格を「10,000円+税」や「10,000円(税抜)」と表示し、実際の支払額は税込で11,000円(消費税率10%の場合)となります。
「内税(税込)」とは、商品やサービスの価格に消費税を含めた総額で表示する方法を指します。
たとえば、「11,000円(税込)」や「11,000円(うち消費税1,000円)」のように、支払総額が一目でわかるように表示します。
外税・内税のどちらを採用するかは、取引相手・目的・経理処理の方針によって判断するのが基本です。
一般的に、企業間取引(BtoB)では外税(税抜)方式が適しており、消費者向け取引(BtoC)では内税(税込)方式が好まれます。
社内では会計処理と表示方法を統一し、取引先や顧客に誤解を与えない運用を徹底しましょう。
外税・内税の理解ができたら、次に押さえておきたいのが請求書や見積書への具体的な記載ルールです。
税区分を誤ると、取引先との金額認識のズレや、インボイス(適格請求書)発行事業者としての不備につながるおそれがあります。
ここでは、実務で注意すべき記載のポイントを整理します。
請求書の金額欄における「外税」「内税」の扱いは、税抜金額を明示して税額を別記するか、税込金額をまとめて記載するかの違いです。
どちらを採用する場合でも、取引先が一目で正確な金額を理解できるように、表記ルールを統一することが大切です。
外税の場合、税抜金額・消費税額・合計金額をそれぞれ明示します。
この方式は、インボイス制度における「税率ごとの消費税額」の記載にも対応しやすい形式です。
<記載例>
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 商品A (税抜) |
¥10,000 | 消費税10%対象 |
| 消費税(10%) | ¥1,000 | |
| 合計 | ¥11,000 |
税区分を明確にしておくことで、経理処理や消費税申告時の照合がスムーズになります。
内税の場合は、消費税を含めた総額を表示します。
ただし、インボイス制度の下では、税込総額の中に含まれる消費税額や税率を明記することが求められます。
<記載例>
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 商品A (税込) |
¥11,000 (うち消費税¥1,000) |
税率10% |
税込表示でも、税率や税額を補足することで、適格請求書の要件を満たせます。
実務の現場では、すべての取引項目が統一された税区分で処理されているとは限りません。
たとえば、商品販売は税抜(外税)で表示しながら、送料や手数料のみ税込(内税)で記載しているケースなど、一つの書類内で「混在表記」が発生することがあります。
一見すると大きな問題には見えませんが、混在表記にはいくつかのリスクが潜んでいます。
取引先が支払総額を誤って認識してしまうおそれがあるほか、消費税の集計やインボイス発行時に整合性が取れなくなるケースもあります。
また、税務調査の際に金額の根拠を説明する手間が増えるなど、後々の確認作業が煩雑になりやすい点にも注意が必要です。
こうしたトラブルを防ぐためには、同一書類内では可能な限り「外税」または「内税」のどちらかに統一することが基本です。
もしやむを得ず混在させる場合は、「※送料は税込価格です」などと明記し、税区分を明確に示すことが重要です。
また、社内の請求書や見積書のテンプレートを統一し、担当者間で表記ルールを共有しておくと、誤認やミスを防ぎやすくなります。
外税・内税の考え方は、請求書などの「取引書類」だけでなく、商品・サービスの価格表示(値札・ウェブサイト・広告など)にも関係します。特に注意したいのが、「総額表示義務」との関係です。両者は似ているようで目的が異なり、混同すると消費者への誤認表示につながるリスクがあります。
「総額表示義務」とは、消費者が支払う税込価格を分かりやすく表示するよう義務づけた制度です。消費税法第63条・施行令第29条に基づき、2004年から導入されています。
この制度の目的は、消費者が「実際に支払う金額」を一目で理解できるようにすることです。
たとえば、店頭やWebサイトで以下のように表記する必要があります。
<適正な総額表示の例>
<不適切な表示の例>
上記のように「税抜」「+税」といった外税表示のみでは、総額表示義務を満たさない点に注意が必要です。
総額表示義務はあくまで消費者向けの価格表示を対象とするルールです。
そのため、消費者取引に該当しない場合や、税込総額を即時に確定できない場合などには例外が認められます。主なケースは次のとおりです。
見積書・請求書・カタログなど、事業者間の表示は対象外。税抜表示や「+税」表記も可能です。
契約時に金額が確定しない場合は、見積段階で税抜表示をしても差し支えありません。
「本体価格○円+税」などの表現は、補足説明を併記すれば一時的に可。ただし最終段階では税込総額を明示することが必要です。
消費税の課税対象外となるため、総額表示義務の適用外です。
不動産・建設業界などで税抜・税込の併記が行われる場合もありますが、消費者が誤認しないよう最終的な税込総額を明確に示すことが前提です。
総額表示義務に違反した場合、景品表示法(不当表示)や消費税法の観点から行政指導や是正勧告の対象となる可能性があります。
法的な罰則は設けられていないものの、次のようなリスクが発生する点には注意が必要です。
特に、チラシやパンフレット、ECサイトなど複数の媒体で価格を掲示している場合は、表示内容の統一と定期的な点検を行うことが重要です。
外税・内税の違いは、請求書の記載方法だけでなく、会計処理の方法(経理方式)にも影響します。
企業の経理処理では、消費税をどのように扱うかによって「税抜経理方式」と「税込経理方式」に分かれ、それぞれで仕訳や損益の計算方法が異なります。
税抜経理方式とは、消費税を損益から切り離して処理する方法です。
売上や仕入は税抜金額で記帳し、消費税部分は「仮受消費税」「仮払消費税」として別勘定で管理します。
消費税は、企業が一時的に預かって国に納めるものであり、会社の収益や費用ではありません。
このため、税抜経理方式では純粋な損益を正確に把握できるという特徴があります。
<仕訳例(税抜経理方式)>
■商品販売(税抜100,000円・税10%)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 110,000円 | 売上 | 100,000円 |
| 仮受消費税 | 10,000円 | ||
■ 商品仕入(税抜50,000円・税10%)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 50,000円 | 買掛金 | 55,000円 |
| 仮払消費税 | 5,000円 | ||
期末には、仮受消費税と仮払消費税の差額を集計し、納付額(または還付額)として処理します。
<期末調整の仕訳例>
仮受消費税10,000円 − 仮払消費税5,000円 = 納付消費税5,000円
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | 10,000円 | 仮払消費税 | 5,000円 |
| 未払消費税 | 5,000円 | ||
税込経理方式とは、消費税を含めた金額で売上や仕入を記帳する方法です。
取引全体を「税込金額」で処理するため、消費税を個別に区分しません。
■ 商品販売(税抜100,000円・税10%)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 110,000円 | 売上 | 110,000円 |
■ 商品仕入(税抜50,000円・税10%)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入 | 55,000円 | 買掛金 | 55,000円 |
どの経理方式(税抜経理・税込経理)を採用している場合でも、期末には消費税の区分経理と納税額の確定を行う必要があります。
特に税抜経理方式では、取引ごとに「仮受消費税」や「仮払消費税」を計上しているため、月次・四半期・期末ごとにこれらの残高を照合し、正確な納税額を算出することが重要です。
期末調整の主な流れは次のとおりです。
<期末調整仕訳例>
■ 消費税納付額の確定
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | 10,000円 | 仮受消費税 | 5,000円 |
| 未払消費税 | 5,000円 | ||
あわせて読みたい
外税・内税の扱いは、請求書表記や会計処理の整合性に直結します。
外税は税額区分が明確で利益管理に優れ、BtoBに適合。内税は総額がわかりやすく、BtoCや総額表示義務に向きます。
採用方式にかかわらず、会計ソフトの税処理設定(税抜/税込)と請求書テンプレートの統一が必須です。
また、インボイス要件(税率ごとの課税標準額・消費税額等)の抜け漏れを防ぎ、媒体別価格表示も定期点検を行いましょう。
まずは、自社の取引形態と会計方式の整合確認から始めてください。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
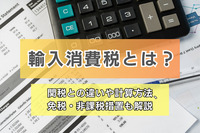
輸入消費税とは?関税との違いや計算方法、免税・非課税措置も解説
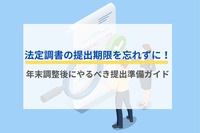
法定調書の提出期限を忘れずに!年末調整後にやるべき提出準備ガイド

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

ラフールサーベイ導入事例集
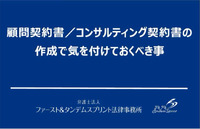
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
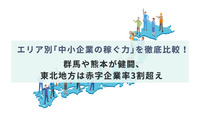
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
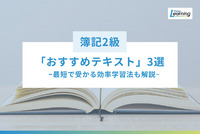
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説

レンタル料の勘定科目の考え方|賃借料・地代家賃・雑費の使い分けと仕訳例

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
公開日 /-create_datetime-/