公開日 /-create_datetime-/
総務のお役立ち資料をまとめて紹介
総務の「業務のノウハウ」「課題解決のヒント」など業務に役立つ資料を集めました!すべて無料でダウンロードできます。

女性が活躍できる職場づくりは、現代の人事戦略において不可欠なテーマです。
一方で、現場では女性社員が安心して働き続けられる環境づくりに課題を抱える企業も少なくありません。
本記事では、制度を形骸化させないための福利厚生設計のポイントを整理し、自社の制度を見直すヒントを紹介します。
女性のための福利厚生は、単に「女性向け制度を増やす」ことが目的ではなく、ライフステージの変化に合わせてキャリアを継続できる環境を整えることが本質的な狙いです。
たとえば、出産・育児・介護などのライフイベントに柔軟に対応できる休暇制度や在宅勤務制度の整備はもちろん、復職支援やキャリア形成を後押しする学習支援制度などが挙げられます。
女性従業員に人気のある福利厚生の具体例としては、以下のような制度が挙げられます。
産前産後休暇や育児休業、保育補助など、ライフイベントに合わせた支援制度。
生理休暇や更年期休暇、婦人科検診補助など、女性特有の健康課題に対応した取り組み。
テレワークやフレックスタイム、時短勤務など、家庭と仕事の両立を支援する制度。
eラーニングや資格取得補助、メンター制度など、長期的なキャリア形成をサポートする仕組み。
家賃補助や住宅手当、貯蓄支援など、生活の安定を支える制度。
カウンセリングや健康アプリとの連携など、心身の健康を支援する仕組み。
カフェテリアプランやポイント制福利厚生など、自身のニーズに合わせて選べる制度。
近年、企業には“女性が働き続けられる環境整備”を、定量的な目標だけでなく実際の取り組み内容として具体的に示すことが求められています。
これは、女性活躍推進法や人的資本開示の流れを背景に、「どのような制度や支援策によって実現しているのか」を可視化・説明する責任が強まっているためです。
その象徴が、女性活躍推進法や人的資本開示の義務化です。
女性活躍推進法では、従業員101人以上の事業主に対し、女性活躍に関する行動計画(数値目標を含む)の策定・届出・公表が義務化されています(※“女性管理職比率の公表”そのものを一律義務化しているわけではなく、行動計画に関する公表義務が拡大されています)。
また、従業員301人以上の事業主は「男女の賃金の差異(いわゆる賃金格差)」の公表が義務です。 さらに金融庁は2023年1月の開示府令改正により、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄を新設。女性管理職比率・男性の育休取得率・男女間賃金格差などの多様性指標を求めています。
こうした非財務情報の開示が進む中で、「制度を整えている企業=人的資本を重視している企業」と見なされる傾向が強まり、女性向け福利厚生の整備が注目されています。
もう一つの要因は、女性社員自身の働き方に対する価値観の変化です。
若年層では、単に時短勤務ができることよりも、「自分らしく働けるか」「柔軟にキャリアを描けるか」といった要素が重視されています。
ヒューマンホールディングスの調査では「週休3日」「副業・兼業」「フレックスタイム」などへの期待が高いことがわかります。
こうした価値観に応えるために、企業は柔軟な勤務制度やリスキリング支援、心理的安全性を支える福利厚生を整備する必要があり、“選ばれる職場づくり”の一環として女性向け制度が注目されているのです。
さらに、採用・定着の観点からも、女性向け福利厚生の重要性が高まっています。日本では第1子出産前後の就業継続率は改善傾向にある一方で、一定の離職・非正規化が依然として存在します。
制度があっても「使いにくい」「評価に響くのでは」といった懸念がある職場では、制度の定着・活用が進まず、エンゲージメント低下や離職につながります。
このため、“制度を作るだけで終わらせず、使われる仕組みを設計すること”が、人的資本経営を進める企業にとっての重要テーマとなっています。
女性社員の働き方ニーズは、ライフイベントや世代によって多様化しています。
ここでは、管理部門が押さえておくべき3つの主要テーマを通じて、最近の傾向を整理します。
出産・育児・介護・不妊治療といったライフイベントへの対応は、女性が働き続けるうえで重要なポイントです。
例えば「育児休業制度を利用しなかった理由 」は厚生労働省の調査によると、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」 でした。
そのため、制度を整備し利用しやすい組織風土の確立が求められているといえるでしょう。
出産や育児などでキャリアが一時中断される可能性がある女性にとって、学び直し(リスキリング)や社内メンター制度・ロールモデルの提示は、キャリア不安を和らげる重要な支援策となります。
また、特に若年層(Z世代)の女性社員においては、 「自分の市場価値を高めたい」「自分らしく働き続けたい」という意識が高く、キャリアを諦めずに働ける環境への期待が強まっています。
さらに、これら制度を有効に機能させるためには、上司との定期的な1on1や、育児・介護中社員へのフォロー体制といった “対話を通じたキャリア支援” の仕組みが欠かせません。
心身の健康を支える福利厚生は、もはや“働きやすさ”だけでなく“働き続けられる職場”の象徴です。特に女性特有の健康課題として、月経困難症・PMS・更年期症状、不妊治療などへの配慮が進んでおり、企業による対応が広がっています。
また、メンタルヘルス研修やハラスメント防止教育を定期的に実施することで、心理的安全性を高めることも重要です。健康課題をオープンに話せる風土が整えば、従業員満足度だけでなく、職場全体の生産性向上にもつながるでしょう。
女性活躍を支える福利厚生を実効性のある仕組みにするには、人事制度との連動、公平な運用、そして社内への浸透が欠かせません。
以下では、女性が長く活躍できる職場を実現するための3つの設計視点を解説します。
福利厚生を採用・評価・育成などの人事制度と切り離すと、形だけの制度になりがちです。
たとえば「育児短時間勤務」制度があっても、評価制度が成果主義一辺倒では利用しにくくなります。
柔軟な勤務形態を評価・昇給制度に反映させたり、復職後の学び直し支援を評価体系と連動させたりすることで、制度を活用しながらキャリアを続けやすい環境が整うでしょう。
福利厚生を運用するうえで、性別や立場に関わらず誰もが利用できる「機会の公平性」を保つことが重要です。
アンケートや人事データを活用して利用率を把握し、課題を分析しましょう。
また、男性の育休取得や介護支援の利用も促すことで、互いに支え合う職場文化が育ちます。
制度を定着させるには、社内コミュニケーションが欠かせません。
社内ポータルで「利用者の声」や「上司からのメッセージ」を紹介するほか、管理職向け研修で制度の趣旨を共有すると効果的です。
“使っても評価に影響しない”という安心感が広がれば、心理的安全性と制度の定着が両立します。
福利厚生の整備で重要なのは、制度を活用しやすい心理的安全性のある環境と、マネジメント層を巻き込んだ職場文化の変革です。
ここでは、人事・管理部門が取り組むべき3つのアプローチを紹介します。
人事が意識すべきは、「福利厚生=コスト」ではなく“人的資本を高める施策”という位置づけです。
そのためには利用率・満足度・離職率の変化など福利厚生のKPIを測定したり、利用者のフィードバックを元に制度を改善するなど、導入後のアップデートも求められます。
「目的・効果・改善」をセットで回すことで、福利厚生を組織の成果創出につなげることができます。
女性特有の事情に関わる制度(不妊治療・更年期・月経休暇など)は、職場で話題にしづらいテーマであるため、心理的安全性の確保が不可欠です。
人事・管理部門が実践できる工夫としては、ハラスメント・無理解を防ぐための啓発研修を定期的に実施する、管理職・同僚が安心して相談を受けられるような支援マニュアルを整備するなどが挙げられます。
社員が「制度を使っても評価に影響しない」「サポートを受けても居づらくならない」と感じられることが、真の働きやすさにつながります。
女性が働き続けられる職場を実現するには、制度の理念だけでなく、現場で実際に活用される仕組みづくりが欠かせません。
他社の取り組みや人気の福利厚生サービスを参考に、自社の制度をアップデートするヒントを得てみましょう。
Manegyでは、働く環境の改善や従業員エンゲージメントの向上に役立つ福利厚生をまとめた「【2025年版】おすすめの福利厚生14選」 を公開しています。
この記事では、
・法定・法定外福利厚生の基礎知識
・導入によるメリット(採用・定着・モチベーション向上など)
・最新の福利厚生サービス14選(健康支援・キャリア支援・家族支援など)
・自社に合う制度を選ぶポイント
といった内容をわかりやすく解説しています。
女性活躍を支える制度設計を検討する人事・管理部門の方にとって、「自社の福利厚生をどう進化させるか」を考える実務ガイドとして最適です。
具体的なサービス事例や導入のヒントを知りたい方は、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。
女性が活躍できる職場づくりには、制度の数よりも「活用され、成果につながる仕組み」が重要です。
ライフイベント・キャリア・健康を支える福利厚生を人事制度と一体化し、心理的安全性と上司の理解を育むことで、女性が自分らしく働き続けられる環境が生まれます。
まずは現状の制度運用を見直し、“使われる福利厚生”への改善から始めましょう。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

人的資本開示の動向と対策

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート

OEM契約とは?メリット・デメリットからOEM契約書の重要条項まで整理

「一律50万円支給」の転勤支援金制度を新設。住友重機械工業、転勤を“前向きな挑戦”に変える人事施策を導入
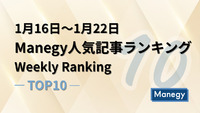
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

SOMPOホールディングス、国内社員約3万人にAIエージェントを導入。業務プロセスを再構築し、生産性向上とビジネスモデル変革を加速
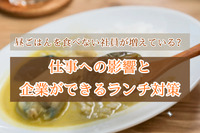
昼ごはんを食べない社員が増えている?仕事への影響と企業ができるランチ対策

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
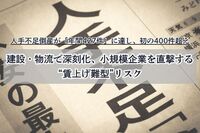
人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク
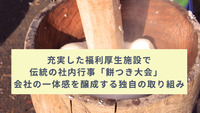
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み

子どもが生まれた正社員に最大100万円を支給。大和ハウスグループの若松梱包運輸倉庫が「次世代育成一時金」を新設
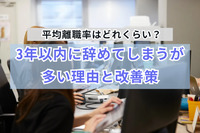
平均離職率はどれくらい?3年以内に辞めてしまう人が多い理由と改善策
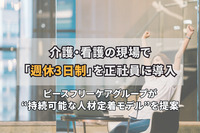
介護・看護の現場で「週休3日制」を正社員に導入。ピースフリーケアグループが“持続可能な人材定着モデル”を提案
公開日 /-create_datetime-/