公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
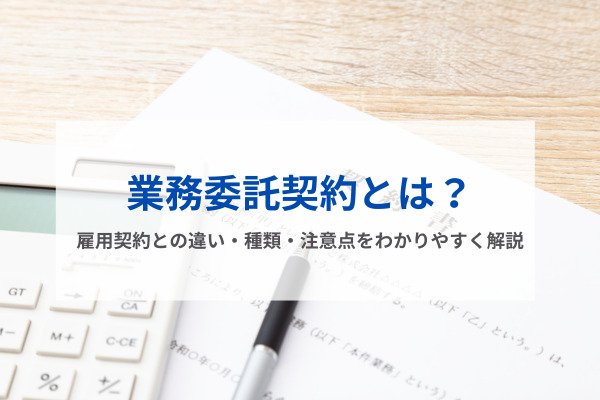
企業が外部の専門家や事業者に業務を任せるケースが増える中、「業務委託契約」はますます身近な契約形態となっています。
しかし、「雇用契約との違いが分かりにくい」「偽装請負になるのでは」といった疑問も多く、法務・総務担当者が注意すべき点が多い契約形態です。
この記事では、業務委託契約の基本から、種類・メリット・注意点までをわかりやすく解説します。
業務委託契約とは、企業や個人が特定の業務を他者に依頼し、その成果または遂行に対して報酬を支払う契約形態です。
法律上の名称は「請負契約」または「委任(準委任)契約」に分類され、民法に基づいて成立します。
この契約の特徴は、雇用契約のような「指揮命令関係」が発生しない点にあります。
受託者は成果や遂行内容に責任を持ちますが、労働基準法や社会保険の保護対象にはなりません。
雇用契約や派遣契約と業務委託契約は、指揮命令関係や法的保護の有無が異なります。
混同すると違法リスクもあるため、明確な線引きが重要です。
雇用契約は、労働者が会社の指揮命令下で働く関係であり、労働基準法
や労災保険、社会保険などの保護が適用されます。
一方、業務委託では、依頼者が指示を出さず、受託者が独立して成果を提供します。
たとえば、勤務時間の指定や勤怠管理を行えば、それは実質的に雇用関係とみなされる可能性があり、「偽装請負」と判断されるリスクがあります。
契約内容だけでなく、実際の運用で指揮命令がないよう注意が必要です。
派遣契約は、派遣元企業が雇用した労働者を派遣先に送って働かせる契約であり、労働者派遣法の適用を受けます。
これに対し、業務委託では委託先が自らの責任で業務を完遂します。
派遣と請負を混同すると、労働者保護を欠く形での契約(違法派遣)に該当する可能性があるため、業務の実施主体を明確にすることが不可欠です。
フリーランスは企業に雇用されず、自らのスキルをもとに案件ごとに契約を結ぶ独立事業主です。
契約形態の多くは業務委託契約にあたります。
2024年11月1日に「フリーランス新法
(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行され、
発注者に対して契約書面の交付義務や報酬支払期日の設定などが求められるようになりました。
企業側も法令遵守の意識を高める必要があります。
業務委託契約には主に「請負契約」と「委任・準委任契約」の2種類があります。
業務内容によってどちらが適切かを見極めなければ、後々の紛争原因になりかねません。
請負契約は、成果物の完成をもって報酬が発生する契約です。
ウェブサイト制作やアプリ開発、建設工事など、具体的なアウトプットがある業務で用いられます。
請負の場合、完成物の品質保証や修正対応といった「成果責任」が発生します。
契約時には納品・検収条件、成果物の所有権や知的財産権の帰属などを明確化することが重要です。
委任・準委任契約は、業務の遂行そのものを目的にする契約であり、成果物の完成を義務づけるものではありません。
会計士や弁護士、システム運用、コンサルティングなど、継続的・知的な業務がこれに該当します。
善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を果たすことが中心となり、結果よりも遂行過程の誠実性が求められます。
あわせて読みたい
業務委託契約は、企業にとって柔軟な外部活用手段ですが、品質管理や契約更新などのリスクも伴います。
双方の利点と注意点を理解しましょう。
メリットとして、必要な時期に専門スキルを活用できる柔軟さが挙げられます。
自社雇用に比べ採用・教育コストを抑えられる一方、契約終了も容易で組織効率を高めやすい点が魅力です。
ただし、発注者は受託者に業務指示を行えないため、進捗や品質を直接コントロールしにくいデメリットもあります。
契約段階で成果条件や納期、検収方法を定義しておくことが欠かせません。
受託者にとっては、働く場所や時間を自由に選べる柔軟性があり、複数案件を受注することで収入を増やせる可能性もあります。
一方で、契約期間が短く更新リスクがある、報酬が業績連動で不安定、社会保険非加入などの課題も伴います。
安定した業務を継続するためには、契約内容の理解とリスク分散が必要です。
業務実績、専門スキル、法令遵守体制の有無などを総合的にチェックします。
過去の契約トラブルや偽装請負事例を把握し、リスクのある委託構造を避けることが大切です。
業務範囲、報酬金額、納期、再委託の可否、契約解除条件など、紛争リスクの高い項目を明文化します。
報酬支払いの基準を「納品完了」「作業時間」などどちらにするかも重要な判断ポイントです。
契約内容を文書化し、両者が署名・押印または電子署名を行います。
近年は電子契約システムを活用する企業が増えており、印紙税を節約できる、契約管理が容易といったメリットがあります。
総務や法務部門は、過去契約との整合性や法改正対応をチェックする責務があります。
業務委託契約では、業務範囲や報酬、知的財産権などを明確に定めておくことが重要です。
契約内容が曖昧だと、成果物の責任や支払い条件を巡るトラブルにつながるため、必須項目を正しく盛り込みましょう。
これらの項目を明確にしないと、報酬トラブルや成果物の権利問題が発生しやすくなります。
特に知的財産権の帰属先を未定義のまま進めると、後に大きな紛争を招く恐れがあります。
外部委託であっても、実態として受託者が指揮命令を受け、勤務時間や業務内容を細かく管理されている場合、偽装請負とみなされるリスクがあります。
違法と判断されると、労働者派遣法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金、労働基準法違反(中間搾取)として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、厚生労働省から是正指導や業務改善命令を受けることもあります。
業務の進め方を含め、現場レベルで独立性を確保する体制を築くことが必要です。
書面で契約を結ぶ場合、契約金額に応じて印紙
税が必要になります。
たとえば、請負契約において契約金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合は2万円の印紙税が発生します。
一方、電子契約であれば印紙税が不要になるため、経費削減の観点から電子契約化を進める企業が増えています。
報酬単価、納期、契約期間などの数字の誤記は重大なトラブルに発展します。
社内ではチェックリスト方式や、AI契約書レビュー、法務担当によるダブルチェックを導入して精度管理を強化しましょう。
柔軟に外部リソースを活用できる一方、雇用関係がないため品質管理や継続性に課題があります。
指揮命令関係を生じさせないこと、契約内容を明確に書面化すること、印紙税・電子契約対応を確認することです。
受託者が継続的に報酬を得る場合、原則として個人事業主(開業届要)として扱われます。
アルバイトは雇用契約に基づき勤務時間や労務管理が発生しますが、業務委託は独立した事業契約であり、労働法の保護対象外です。
業務委託契約は、外部の専門リソースを活用するための有効な手段です。
しかし、雇用契約や派遣契約との線引きを誤ると、偽装請負など法令違反のリスクが生じます。
契約時には「指揮命令関係の不存在」「契約条件の明確化」「法改正(特にフリーランス新法)への対応」を意識することが不可欠です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

オフィスステーション導入事例集
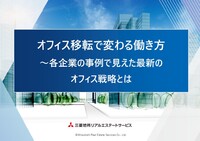
オフィス移転で変わる働き方

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
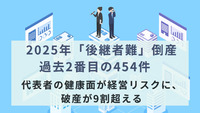
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
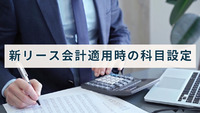
新リース会計適用時の科目設定

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

サーベイツールを徹底比較!

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>
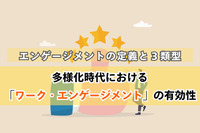
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
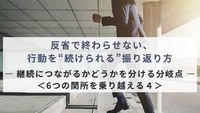
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>
公開日 /-create_datetime-/