公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
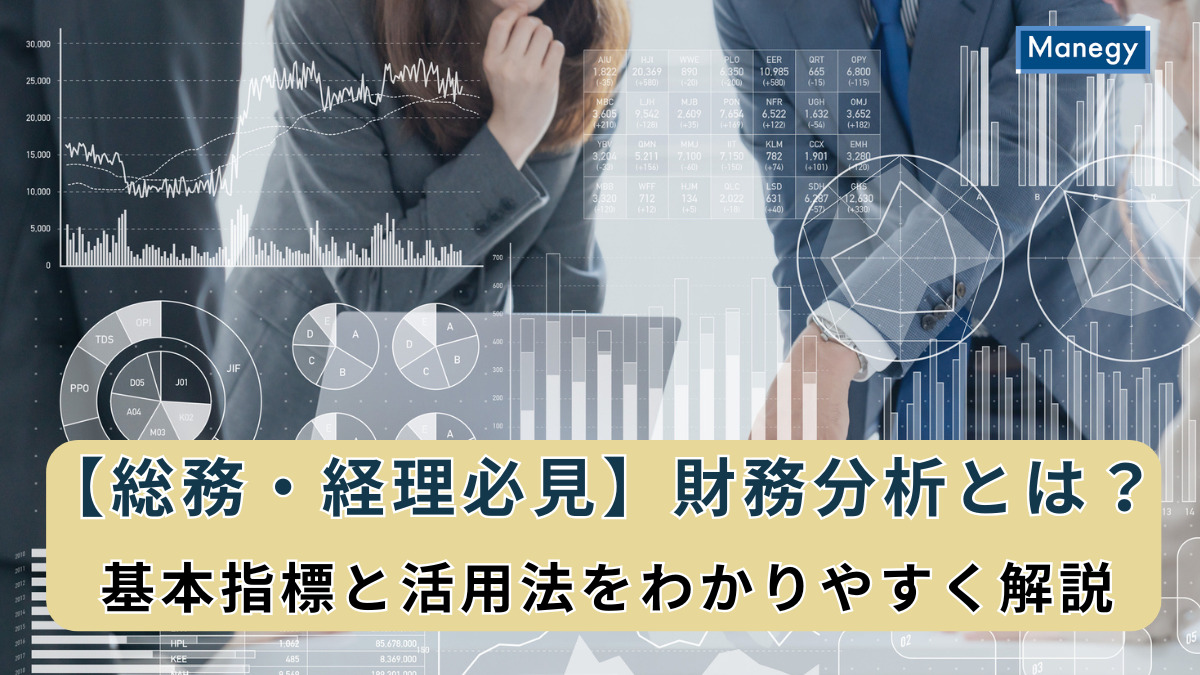
企業の経営状況を正しく把握するために欠かせないのが「財務分析」です。
損益計算書や貸借対照表を眺めても、数字の意味やつながりがわからなければ、経営改善や報告資料に活かすことはできません。
とりわけ総務・経理・経営企画といった管理部門では、財務データを読み解き、経営層や現場にわかりやすく伝える力が求められています。
ここではまず、財務分析の基本的な定義や管理部門が学ぶ意義、さらに財務三表との関係性を整理していきましょう。
財務分析とは、企業の決算書(財務諸表)に記載された数値をもとに、経営状況や財務体質を評価する手法のことです。
単なる数字の羅列を「利益が出ているか」「資金繰りは健全か」といった視点で整理・比較することで、企業の現状を客観的に把握できます。
例えば、売上高だけを見ても成長性は判断できません。
利益率や資産効率とあわせて分析することで、はじめて「本当に健全な成長かどうか」を判断できるのです。
この記事を読んだ方にオススメ!
財務分析は経営層だけでなく、総務・経理・経営企画など管理部門の実務担当者にとっても重要なスキルです。
このように、分析の基礎を押さえるだけでも日常業務の質は大きく変わるのです。
財務分析は「財務三表」を材料に行います。
三表はそれぞれ役割が異なり、相互に補完し合う関係にあります。
これらを組み合わせて初めて、企業の「収益性」「安全性」「効率性」「成長性」を多角的に捉えることが可能になります。
この記事を読んだ方にオススメ!
財務分析は目的に応じて複数の切り口があります。
たとえば「会社が安全に存続できるか」を見るのと「どれだけ効率よく利益を出しているか」を見るのでは、注目すべき指標が異なります。
ここでは代表的な4つの視点 ― 安全性・収益性・効率性・成長性 ― を中心に確認していきましょう。
管理部門が資金繰りをチェックする際、まず押さえておきたいのがこの安全性分析です。
安全性分析は、企業が短期・長期の支払いに耐えられるかどうかを評価するもので、倒産リスクや資金ショートの可能性を早期に把握できます。
経営会議や役員説明では、この収益性指標が「企業の稼ぐ力」を示す裏付けになります。
収益性分析は、企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示すものです。
この記事を読んだ方にオススメ!
管理部門では、売掛金の回収や在庫管理といった日常業務の効率化につながります。
効率性分析は、持っている資産をどれだけ有効に使えているかを測るものです。
成長性は単独の指標ではなく、安全性や収益性とあわせてバランスよく分析するのが実務のコツです。
成長性分析は、企業が将来に向けてどの程度拡大しているかを測るものです。
管理部門で財務分析を行う際は、これらの指標を単独で見るのではなく、複数の視点を組み合わせて総合的に判断することが重要です。
管理部門の担当者がすぐに使えるように、代表的な財務分析指標の一覧(指標名・計算式・意味・目安)をまとめました。実務の参考として、ぜひご活用ください。
計算式:流動資産 ÷ 流動負債 ×100
意味:1年以内の支払能力を示す指標。
一般的な目安:100%以上(200%が望ましい)
計算式:当座資産 ÷ 流動負債 ×100
意味:現金性の高い資産による支払能力を示す。
一般的な目安:80%以上
計算式:自己資本 ÷ 総資産 ×100
意味:借入に頼らず、自社資本で経営を支える安定性を表す。
一般的な目安:30%以上(上場企業は40%以上)
計算式:営業利益 ÷ 売上高 ×100
意味:本業の収益力を示す。
一般的な目安:業界平均を基準に比較。
計算式:経常利益 ÷ 売上高 ×100
意味:本業+財務活動を含む収益力を表す。
一般的な目安:5〜10%以上が目安。
計算式:当期純利益 ÷ 自己資本 ×100
意味:株主資本をどれだけ効率的に増やしているかを示す。
一般的な目安:8〜10%以上。
計算式:当期純利益 ÷ 総資産 ×100
意味:総資産全体の収益性を示す。
一般的な目安:5%以上。
計算式:売上高 ÷ 総資産
意味:保有資産をどれだけ効率的に売上に変えているかを示す。
一般的な目安:1回以上。
計算式:売上高 ÷ 売掛金残高
意味:売掛金の回収スピードを示す。
一般的な目安:年6回以上(約2か月で回収)。
計算式:売上高 ÷ 在庫残高
意味:在庫をどれだけ効率的に活用しているかを示す。
一般的な目安:業種によるが、高いほど良い。
計算式:(当期売上高 − 前期売上高) ÷ 前期売上高 ×100
意味:売上の増加スピードを示す。
一般的な目安:プラス成長が望ましい。
計算式:(当期利益 − 前期利益) ÷ 前期利益 ×100
意味:利益の増加スピードを示す。
一般的な目安:プラス成長が望ましい。
財務分析は、ただ指標を並べるだけでは意味がありません。
必要な資料をそろえ、主要指標を計算し、最後にその結果をどう業務や経営判断に活かすか──この一連の流れを押さえておくことで、初めて実務で効果を発揮します。
ここでは、管理部門の担当者が実際に取り組む際のステップを解説します。
財務分析の第一歩は「正しいデータを集めること」です。
※ポイントは「最新かつ正確なデータをそろえる」こと。古いデータや未確定値では誤った判断につながります。
資料がそろったら、次は主要指標の計算です。
指標ごとの計算式(例:流動比率=流動資産 ÷ 流動負債 ×100)を表にして、必要な数値を入力すれば自動計算できます。
近年の会計ソフトには、流動比率やROEなどを自動で計算する機能が搭載されているケースも多くあります。
たとえば「流動比率が低下した理由」を掘り下げれば、
売掛金の回収遅延や短期借入の増加といった具体的な課題に気づくことができます。
財務分析の目的は「数字を見ること」ではなく、「改善につなげること」です。
※実務では「分析して終わり」ではなく、課題の仮説立て → 改善提案 → 実行 → 再分析 のサイクルを回すことが重要です。
財務分析は経理部門だけのものではありません。
総務や経営企画、人事総務などの管理部門にとっても、日常業務や経営サポートに直結する強力なツールとなります。
ここでは、代表的な活用シーンを3つ紹介します。
資金ショートは企業にとって致命的なリスクです。
財務分析を通じて定期的にモニタリングを行うことで、問題の早期発見と対策が可能になります。
※ 実務では「月次での資金繰りモニタリング表」を作成し、経営層に報告するのが効果的です。
財務分析を行うことで、コスト構造や業務効率の課題が浮き彫りになります。
※ 管理部門が「どの費用を削れば最も効果的か」を数値で示すと、経営層への説得力が格段に高まります。
経営会議では「勘や経験」ではなく、「データに基づく説明」が求められます。
財務分析を活用した数値資料は、会議の意思決定を支える武器になります。
※ 総務・経理担当者が「見やすく、経営判断に直結する資料」を準備できれば、経営層の信頼度も大きく高まります。
財務分析は指標の計算や資料作成に時間がかかりがちです。
特に管理部門では、限られたリソースの中で定期的な分析と報告を行う必要があります。
ここでは、実務を効率化する代表的なツールとテンプレート活用の方法を紹介します。
Excelは最も手軽に始められる分析ツールです。
※ 初心者は「流動比率」「ROE」など主要な5指標程度から始めるのがおすすめです。
近年のクラウド会計ソフトには、財務分析機能が標準搭載されているケースが増えています。
※ 「毎月の試算表チェックに追われている」という管理部門には特に有効です。
財務分析の成果を活かすには、経営層や現場部門への「伝え方」も重要です。
※ 「見やすく、理解しやすく、行動につながる資料」を意識することで、財務分析は経営改善に直結します。
財務分析に初めて取り組む際には、多くの疑問や不安が出てきます。
ここでは、管理部門の実務担当者からよく寄せられる質問に答えていきます。
※ 自社分析では「社内の会計ソフトや顧問税理士から最新データを入手する」のが第一歩です。
※ 「業界平均」は基準のひとつですが、自社の過去推移との比較も同じくらい重要です。
※ 初学者はまず簿記や財務三表の基礎本から入り、実務と並行して理解を深めるのが効率的です。
はい、むしろ赤字企業こそ財務分析が重要です。
※ 赤字=分析不要ではなく、赤字だからこそ「どこを直すべきか」を示すために有効です。
財務分析は、決算書に並ぶ数字を「経営に役立つ情報」に変えるための基本スキルです。
安全性・収益性・効率性・成長性といった指標を組み合わせて読み解くことで、資金繰りの改善やコスト削減、経営判断のサポートなど、管理部門の業務に直結した活用が可能になります。
また、Excelやクラウド会計ソフトを活用すれば、分析や資料作成の負担を大幅に軽減でき、経営層や現場へのわかりやすい共有にもつながります。
大切なのは「完璧な分析を一度で行うこと」ではなく、小さな一歩から継続することです。
まずは流動比率や営業利益率といった基本指標を確認することから始め、徐々に自社に合った分析手法を取り入れてみましょう。
今日からの業務に「財務分析」を取り入れ、管理部門として経営に一層貢献できる力を磨いてみてください。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

事業用不動産のコスト削減ガイド

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
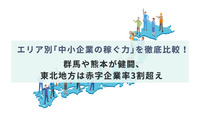
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
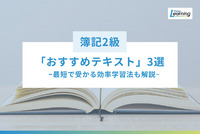
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説

レンタル料の勘定科目の考え方|賃借料・地代家賃・雑費の使い分けと仕訳例

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
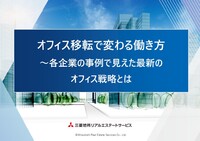
オフィス移転で変わる働き方

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

生成AI時代の新しい職場環境づくり

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
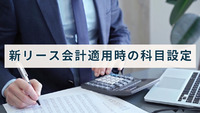
新リース会計適用時の科目設定

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
公開日 /-create_datetime-/