公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
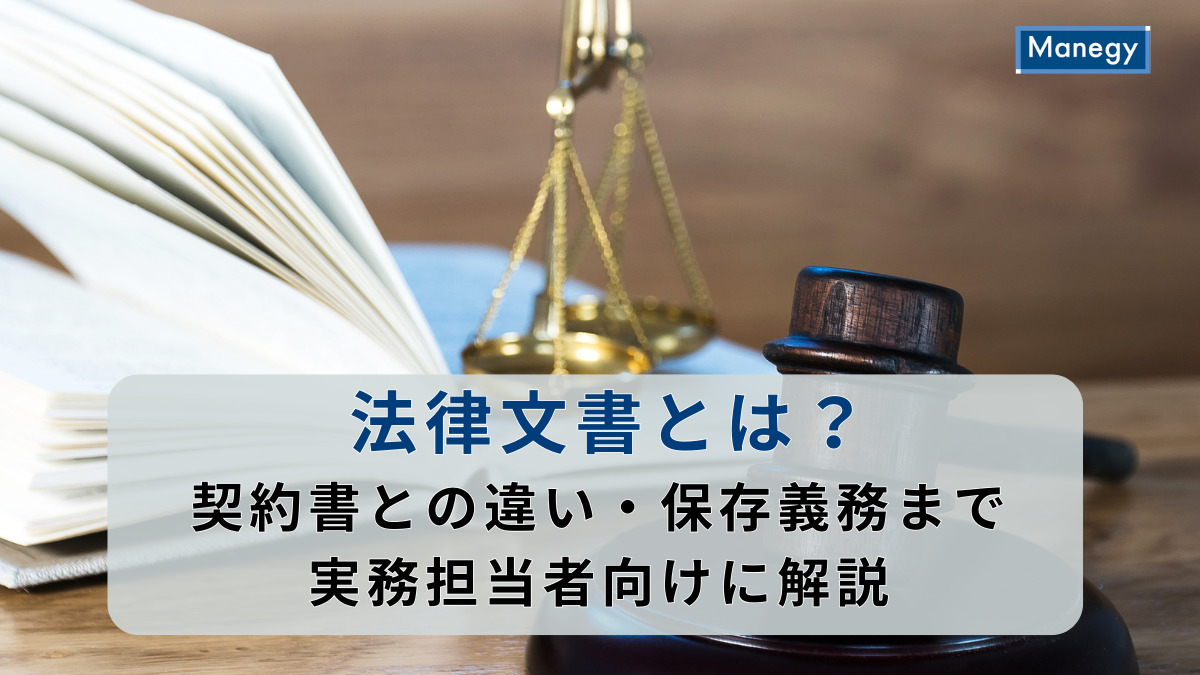
企業の取引やガバナンスを支えるうえで、「法律文書」は非常に重要な役割を担っています。
しかし、その定義や保存ルールを誤ると、法令違反や監査での指摘、トラブル発生時の証拠不足などにより、企業の信用や利益を損なうおそれがあります。
本記事では、管理部門の担当者の方に向けて、法律文書の役割や種類、保存義務、電子化の注意点までを整理し、日常業務に直結する実務ポイントをわかりやすく解説します。
企業活動では、契約の締結や取引条件の確認、人事労務の合意事項などを記録するために、さまざまな文書が作成されます。
その中でも法的な効力を持ち、権利義務の有無を証明できる書類が「法律文書」です。
法律文書は、単なる業務メモや社内報告とは異なり、以下のような役割を果たします。
適切に作成・管理された法律文書は、企業の信頼性とリスク管理を支える“盾”のような存在です。
企業が日常的に扱う法律文書には、契約に関わるものから社内規程、行政手続き用まで幅広い種類があります。
ここでは、管理部門が押さえておきたい代表的な法律文書を紹介します。
契約書:取引や業務委託、人材雇用などの合意内容を明文化し、双方の権利義務を確定させる文書です。
同意書:特定の行為や取り決めに対して、同意の意思を示すための文書です。
誓約書:秘密保持や安全管理など、特定事項を遵守することを誓う文書です。
覚書:契約書の補足や暫定的な合意内容を簡潔に記載した文書です。
利用規約・約款:サービス提供者がユーザーに対して定める取引条件をまとめた文書です。
通知書:契約解除や条件変更など、相手方へ正式に意思を伝えるための文書です。
内容証明郵便:郵便局が送付内容と日付を証明する仕組みで、トラブル時の証拠として活用される文書です。
議事録:取締役会や株主総会などの会議内容を記録し、会社法に基づいて保存する文書です。
社内規程:就業規則や給与規程など、従業員の権利や義務を定める社内ルールをまとめた文書です。
公正証書:公証人が作成する文書で、契約や遺言などの内容を公的に証明するものです。
訴状・陳述書:訴訟や裁判での主張や事実関係を正式に記録する文書です。
あわせて読みたい
法律文書は作成したら終わりではなく、法令に基づいた保存と適切な管理が欠かせません。
保存方法を誤ると、税務調査・監査・訴訟などの場面で証拠能力を失い、企業に不利益が及ぶおそれがあります。
ここでは、必ず押さえておきたいポイントを整理します。
法律文書の多くは、会社法・税法・労働法などの法令で一定期間の保存義務が定められています。
保存期間内に廃棄した場合、法令違反として罰則や追徴課税の対象になることもあります。
以下は、代表的な保存期間の例です。
| 文書 | 根拠法令 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 株主総会 議事録 |
会社法318条 (および定款・施行規則) |
10年 |
| 取締役会 議事録 |
会社法369条3・4項 施行規則98条 |
10年 |
| 会計帳簿・ 決算書類 |
会社法432条 435条 |
10年 |
| 契約書 (取引関係) |
法人税法・消費税法 会社法上の「重要書類」に関する見解 |
7年 (消費税関係は10年) |
| 労働者名簿・ 賃金台帳など |
労働基準法109条 | 5年 (当分の間は3年も可) |
ペーパーレス化の推進により、契約書や領収書などを電子データとして保存するケースが増えています。
ただし、電子帳簿保存法などの要件を満たさずに保存すると、法令違反となるおそれがあり、紙の書面と同等の証拠力を持たなくなる可能性があります。
特に電子化を行う際は、以下のような点に注意が必要です。
保存期間を過ぎた文書を廃棄する場合でも、情報漏えいや不適切な廃棄方法、訴訟リスクに十分注意する必要があります。
特に、紛争が継続中の契約書や議事録などは、保存期間を過ぎても廃棄せず、一定期間保管を延長することが望ましいです。
また、廃棄を行う際は、次のような点を守りましょう。
個人情報を含む文書を不用意に処分すると、個人情報保護法に違反し、罰則や損害賠償のリスクが発生するおそれがあります。
法律文書は、単に文章を作ればよいわけではなく、法的効力を確保するための書式・文言・手順を守ることが重要です。
ここでは、管理部門担当者が押さえておくべき基本的な作成の流れと注意点を解説します。
法律文書には、一定の体裁と必須項目があります。これらを欠くと、後に効力が争われたり、契約自体が無効と判断される可能性があります。
主な記載事項の例:
表題(タイトル):契約の種類を明確に示す(例:業務委託契約書、秘密保持契約書など)
前文:契約の目的・背景・当事者の合意意思を簡潔に記載する
本文(条項):権利義務、履行条件、支払条件、契約期間、解除条項、損害賠償責任などを具体的に定める
作成日:契約や合意が成立した日付を明記する(効力発生日と一致させるのが原則)
署名・押印(または電子署名):当事者双方が記載し、本人確認と同意を示す
法律文書では、解釈に幅が生じるような表現や、重要な条項の抜け漏れは避けなければなりません。
不明確な文言が含まれていると、契約の解釈をめぐって争いが発生し、裁判で契約自体が無効と判断されたり、不利な結論を下されたりする可能性があります。
そのため、「できる限り」「なるべく」といった抽象的な表現は使わず、数量・期限・条件などを具体的に示すことが重要です。
また、当事者それぞれの責任範囲や、違約が発生した場合の対応方法を明確に定めておく必要があります。
さらに、消費者契約法や下請法、労働基準法など、関連する法律に抵触しないかを確認することも欠かせません。
外国語で契約を締結する場合は、日本語版と照らし合わせ、内容や意味に相違がないか慎重に確認しましょう。
A. 結論から言えば、一定の条件を満たせばメールやPDFも法律文書として扱われます。
契約や合意内容が明確に示され、当事者間で同意の意思が確認できれば、紙の書面と同等の証拠力を持つ場合があります。
ただし、前述のとおり電子契約の場合は電子署名やタイムスタンプなど、本人確認と改ざん防止の要件を満たすことが重要です。単なる添付PDFやメール本文だけでは証明力が弱まる可能性があります。
A. 法律文書を紛失すると、契約内容を証明できなくなり、トラブル発生時に不利な立場に立たされるおそれがあります。
特に契約書や議事録のように法定保存期間が定められている文書を紛失すると、法令違反や監査上の指摘につながる可能性があります。
契約書の場合、相手方が写しを保管していれば再発行やコピーの取得が可能ですが、その際には双方で内容を確認し、再度署名が必要になる場合があります。
また、株主総会議事録や登記関連書類などについては、法務局や公証役場で閲覧や再交付の手続きを行えるケースもあります。
A. 弁護士に法律文書の作成を依頼する最大のメリットは、専門家によるリーガルチェックによって抜け漏れやリスクを防止できる点です。
契約条件や条項の妥当性を法的観点から精査してもらえるほか、最新の法改正や判例を踏まえた適切な文言に調整してもらうことができます。
また、紛争の予防や訴訟時の証拠として有効性の高い文書を作成できるため、企業のリスクマネジメントにも大きく寄与します。
重要な契約や高額な取引、あるいはリスクの大きい案件では、弁護士に依頼することが結果的に企業防衛につながります。
A. 議事録は法律文書に含まれますが、すべての議事録が「法律文書」になるわけではありません。
例えば稟議書や社内通知は原則として法律文書には該当しません。
文書の用途と法令上の保存義務があるかどうかで、法律文書に該当するかを判断しましょう。
法律文書は、企業の信用・コンプライアンス・リスク管理を支える重要な基盤です。
契約書や議事録、社内規程などは、それぞれに定められた保存義務や形式要件を理解し、適切に管理しましょう。
近年は電子化が進み、電子署名や電子帳簿保存法への対応が実務上の大きな課題となっています。
法令要件を満たしたうえで、紙とデジタルを併用した安全な運用ルールを整備することが、トラブルを未然に防ぐポイントとなります。
まずは、自社の法律文書を棚卸しし、部門横断でルールを見直すことから始めましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

経理業務におけるスキャン代行活用事例

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
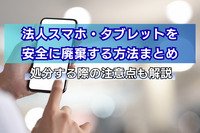
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説
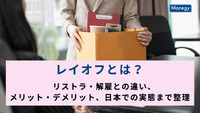
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
公開日 /-create_datetime-/