公開日 /-create_datetime-/
管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!
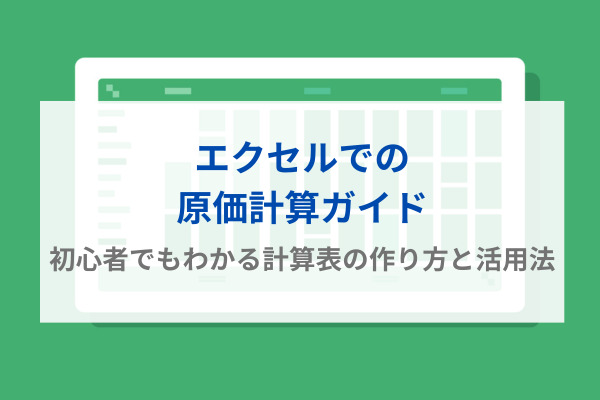
「利益が思うように出ていないのは、もしかして原価計算が正しくできていないからでは?」。
経営者や管理部門の担当者であれば、一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか。原価を正しく把握できなければ、価格設定や利益管理も感覚頼りになり、気づかないうちに経営を圧迫してしまう危険があります。
そこで本記事では、特別な会計ソフトがなくても、誰でも使い慣れている「エクセル」を使って実践できる原価計算の方法を解説します。
原価計算とは、商品やサービスを提供するためにどのくらいのコストがかかっているかを明らかにする仕組みです。
代表的な要素は「材料費」「労務費」「経費」の3つに分けられます。
材料費は原材料や仕入品の購入にかかる費用、労務費は従業員の人件費や作業時間に基づくコスト、経費は光熱費や家賃などの間接費用を指します。
これらを正しく把握することで、価格設定や利益率の見直しにつながり、経営判断の精度を高めることができます。
逆に、原価を曖昧なままにしてしまうと、気づかぬうちに赤字を抱え込む危険性もあるため、重要性は非常に高いといえます。
原価計算を始めるにあたって、専用システムや高価な会計ソフトを導入する方法もありますが、初めの一歩としてはエクセルが最適です。
新たな投資が不要で、ほとんどの企業ですでに利用環境が整っているため、すぐに取り組むことができます。
また、業種や自社の業態に合わせて自由に設計・修正できる柔軟性も大きな強みです。
従業員にとっても日常的に使い慣れているツールであるため、教育コストがかからず導入が容易です。
こうした点から、エクセルは「原価計算の仕組みづくりの入口」として非常に実用的だといえます。
ただし、エクセルには明確な限界もあります。最も大きな課題は、手作業による入力ミスが発生しやすい点です。
さらに、ファイルをメールや共有フォルダでやり取りすると、最新版の管理が難しくなり、情報が分散しやすくなります。
また、リアルタイムでの自動集計や更新には対応できないため、経営判断に必要なスピード感を確保することが難しくなる場合があります。
こうした弱点は、事業規模の拡大や製品数の増加に伴って顕在化しやすいため、まずはエクセルで全体像をつかみ、一定の規模に達した段階でシステム化を検討する流れが望ましいといえるでしょう。
まず最初に取りかかるのは、製品ごとに必要な材料のコストを管理するシートです。
表には「材料名」「単価」「使用量」の3つの基本項目を入力できるようにします。
たとえば飲食店であれば「小麦粉」「卵」「バター」といった食材と、その仕入単価・使用量を記載します。
エクセルのSUMPRODUCT関数を使えば、「単価 × 使用量」を自動的に計算し、製品ごとの合計材料費を一瞬で算出できます。
このシートを作ることで、材料ごとのコスト構造が見える化され、無駄な仕入や過剰在庫のチェックにもつながります。
次に必要なのが、従業員の人件費を反映させる「労務費シート」です。
ここでは「従業員名」「作業時間」「時給(または月給換算額)」を入力する形式にします。
さらに、どの製品やサービスにどれだけの作業時間を割いたのかを記録すれば、製品別の労務費を算出できます。
例えば、A製品の組立に社員が延べ20時間かかった場合、時給1,200円なら労務費は24,000円と算出可能です。
このようにして人件費を正確に振り分けることで、どの商品に人手がかかりすぎているかを把握でき、業務効率化のヒントを得られます。
原価計算では、家賃や水道光熱費、通信費といった間接的なコストも無視できません。
これらを管理するのが「経費シート」です。
ポイントは、経費をどの基準で製品に割り振るかという配賦の考え方です。
例えば、工場の電気代であれば「作業時間」に応じて按分する方法、オフィスの家賃であれば「使用面積」で按分する方法が考えられます。
実際には、企業規模や業種によって適切な基準は異なりますが、まずは大まかな基準で割り振ることから始めると十分です。
このシートを整備することで、間接費を見落とさない原価計算が可能になります。
最後に、「材料費」「労務費」「経費」の3つのシートをまとめて集計するサマリーシートを作成します。
ここには「製品名」「材料費」「労務費」「経費」「総原価」「売上」「利益」といった項目を並べます。
各シートからリンクさせることで、自動的にデータが反映され、製品ごとの収益構造を一覧で把握できます。
売上と総原価を比較すれば利益額や利益率も計算でき、赤字の商品や高収益の商品がひと目でわかります。
このサマリーを活用すれば、経営判断に直結する「数字に基づいた分析」が可能になります。
原価計算表を作成した後、そのデータを分析する際に非常に役立つのがピボットテーブルです。
製品別や部門別に原価を集計すれば、どの商品が高コスト体質なのか、どの部門が利益率を押し下げているのかを瞬時に把握できます。
例えば、製品ごとに「材料費・労務費・経費」の内訳を出せば、コストの偏りや改善すべき項目が一目で見えるようになります。
特に管理部門では、経営層への報告資料としても活用しやすく、意思決定のスピードアップにつながります。
数字だけの表では、担当者以外には直感的に理解しづらいケースも多いでしょう。
そこで役立つのがエクセルのグラフ機能です。
円グラフを使えば、材料費・労務費・経費の割合が一目で把握でき、棒グラフを使えば複数の製品のコスト構成を比較することが可能です。
色分けや凡例を工夫することで、非専門家にもわかりやすい資料に仕上げることができます。
視覚的に整理された情報は、経営会議や部門会議での説得力を高め、施策の合意形成をスムーズにします。
日々の業務の中で、担当者が常に原価率をチェックするのは手間がかかります。
その解決策のひとつが、IF関数を用いたアラート設定です。
例えば、「原価率が70%を超えたらセルを赤く表示する」といった条件付き書式を設定すれば、異常値を自動で知らせてくれます。
これにより、問題の早期発見が可能となり、経費削減や価格設定の見直しに素早く対応できます。
単なる数値管理から一歩進んだ「自動監視機能」として取り入れることで、エクセルがより強力な経営管理ツールに変わります。
間接費の配賦には「作業時間」「面積」「売上高」など、いくつかの基準があります。
どの基準が最適かは業種や業務の性質によって異なります。
例えば、工場の電気代は作業時間に比例するため「稼働時間」で配賦するのが妥当です。
一方、オフィスの家賃は部門ごとの使用スペースに応じて「面積」で配賦する方法がよく使われます。
大切なのは「誰が見ても合理的で納得できる基準」を選ぶことです。
複数の基準を組み合わせて運用するのも有効です。
最も基本的なのは、作業日報やタイムシートを用いた記録です。
小規模であればエクセルに作業内容と時間を入力するだけでも十分ですが、従業員数が増えると入力ミスや記録漏れが問題になりやすくなります。
その場合は、勤怠管理システムやプロジェクト管理ツールを併用すると精度が上がります。
また、時間だけでなく「どの製品や案件にどれくらい関わったか」を残すことで、労務費の割り振りがより正確になります。
エクセルファイルが重くなる主な原因は、複雑な数式やシートの増加、不要な書式設定などです。対策としては以下が有効です。
定期的にファイルを整理することで、作業効率が格段に向上します。
どうしても扱いにくい場合は、Accessなどのデータベースやクラウド型のシステムを併用する方法もあります。
目安となるのは「扱う製品や案件が増え、エクセルでの管理に時間がかかりすぎている」と感じた時点です。
例えば、製品数が数十を超え、毎月のデータ更新に数日かかるようであれば、システム導入を検討すべき段階といえます。
また、複数の担当者で同時に作業する必要がある場合も、エクセルでは限界があります。
専用システムはコストがかかりますが、データの信頼性や効率性を大きく向上させるため、中長期的な投資として検討する価値があります。
正確な原価計算は、勘や経験に頼った経営から脱却し、数字に基づいた意思決定を行うための出発点です。
材料費・労務費・経費を整理するだけで、どの製品が利益を生み、どのサービスがコストを圧迫しているのかが見えてきます。
これは、価格設定の改善やコスト削減、さらには新規投資の判断にまで直結する重要な指標となります。
高価な会計システムを導入しなくても、身近なエクセルを使えば誰でも今日から原価管理を始めることができます。
本記事で紹介した手順や無料テンプレートを活用すれば、特別な知識がなくても十分に実務に役立つ原価計算表を作成できるはずです。
まずは、自社の主力製品やサービスの原価をひとつ算出してみてください。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
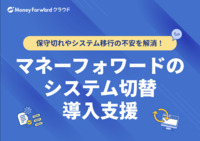
マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

経理業務におけるスキャン代行活用事例

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
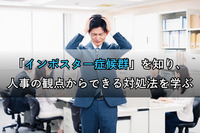
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
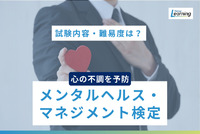
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?
公開日 /-create_datetime-/